�H�i���E�����Z�p������(�l�q�b)25�N�̂���݁\���W�ҁ\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�i���E�����Z�p������@��@
�n�ӓ֕v�i�_�w���m�j
�A����F��332-0015�@����s���1-1-3-3211
e-mail�Fmack80wata@uu.em-net.ne.jp
�P�D�͂��߂�
1989�N�i�������N�j�ɐݗ����ꂽ�H�i���Z�p���k��i�l�q�b�j�͔��W�I�ɐH�i���E�����Z�p������i�l�q�b�j�Ɩ��̕ύX���A�{�N�Őݗ�25�N���}���܂����B�����̂����Ɏl�����I���̒����ɂ킽�茤��������p������Ă������Ƃ�����̕��X�ƂƂ��Ɍc�т����Ƒ����܂��B���̊ԁA�l�q�b���x�������ĉ��������l�q�b�����E���s�ψ��Ȃ�тɉ���e�ʁA����ɐH�i���E�����Z�p�Ɍg���l�q�b�̊����ɒg������x�������������X�A�M�d�Ȃ��u����Ղ����u�t�̐搶���Ɍ������\���グ�܂��B
�M�҂́A�ݗ��������\�����A����\�����A����A�����Č��݂͉�Ƃ��āA���E�Y�E�w�Ɨ����ς��Ȃ�����l�q�b�̊�����ʂ��ĐH�i�Y�Ƃɂ����閌�E�����Z�p�̔��W�ߒ����Ԃ��Ɍ��Ă��܂����B�����ŁA�ݗ�25�N���L�O���ĐH�i���E�����Z�p������W�̗��j�����ǂ�Ȃ���A����̖��E�����Z�p�̌����E�J���������F�l�Ƌ��ɍl���Ă݂����Ǝv���܂��B
�Q�D�䂪���̐H�i���E�����Z�p���W�̗��j
2.1�@���E�����Z�p���t�����@
�킪���̐H�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p�́A1970�N�ɓ��{�H�i�H�Ɗw��̃V���|�W�E���̈�̃e�[�}�Ƃ��ċt�Z���i�q�n�j�����グ���Ĉȗ��A�_���ȐH�i���ʋǂ̊O�s�c�̂ł���H�i�Y�ƃZ���^�[�i�ȉ��A�H�Y�Z���^�[�Ƃ���j�Ɣ_���ȐH�i�����������i�ȉ��A�H�����Ƃ���j�������J�������[�h���Ă��܂����B��B��w�E�_�@�쑺�j���搶�����͓I�ɐH�i�E�o�C�I����ł̖��Z�p�̌����Ɏ��g��ł����܂����B�M�҂́A���̌�A�卸�쑺�搶�A����⫓��L�搶�Ə�c���V���搶�̐R�����w�ʂ����^����Ă��܂��B�����A�H�����E�H�i�H�w�����ł������ؑ��i�搶�ɘA����āA�H�Y�Z���^�[�ł̖��Z�p�Ɋւ����c�ɏo�Ȃ��A����E�H�@�ؑ����j�搶����{�^��i���j�ɂ���ꂽ���{���ꂳ�̎Y�ƊE�̊e���̘b���ȂǁA�H�i�Y�ƊE�ł̖��Z�p�̊J������������邱�Ƃ��ł��܂����B�����̌����ɂ��ẮA�H�Y�Z���^�[�Z�p�����̓��W�u�����Z�p�v�P�j�ɂ܂Ƃ߂��Ă���̂ł����������B
�@�d�C���͂ɂ��ẮA1963�N�����玙�p�����̒E���Ɋւ��錤�����J�n�Q�j����Ă���̂ŁA�H�i����ł̖��Z�p�͂��̎���܂ők��ׂ���������܂��A�����ł͈��͂��쓮�͂Ƃ��閌�Z�p�𒆐S�ɏq�ׂ�̂ŏ�L�̂悤�ɍl���Ă����܂��B�T���g���[�́A1967�N�ɐ�����ߋZ�p�𗘗p�����r�l���r�[���w�����x��{���H��Ő����A�������Ă��܂��B�M�҂́A���̔N�����_�H��w��w�@�C�m�ے��ɍ݊w���Ă���A�w��3�N�̍H�ꌩ�w�ɓ��s�������Ő�[�̕r�l���r�[���w�����x�����܂��Ē����܂����B���̎��́A�����A�Љ�ɏo�Ă��疌�Z�p����Ƃ��錤���҂ɂȂ낤�Ƃ͗\�����Ă��܂���ł����B
�H�Y�Z���^�[�̌�������݂�ƁA�哤�^���p�N�̖������C�t�Z���i�q�n�j�ɂ��ʏ`�̔Z�k�Ɨp�������A�b���������ւ̖��Z�p�̗��p�A�b������ё哤���H�r������̗L����������Ȃǂ̌����Ɏ����ŁA�u���̕ێ�Ǘ��Ɋւ��錤���v��1970�N��ɍs���Ă��܂��B���̌����͓���E�H�@�ؑ��������ŕM�҂���ƂȂ�s�������̂ł��B���̓����͐|�_�Z�����[�X�������J������Ă��炸�A�M�E�ۂ≖�f�܂ɂ����E�ۂ��s����A�܂������W���[����u�̃T�j�^���[���Ɋւ���v���[���łȂ��A�����u�̉q���Ǘ����s�\���ɂȂ�₷���H�i�i���ɑ傫�Ȗ����c���ł����B
�]�k�ł����A���̎��A�̂��ɓ��勳���ƂȂ�ꂽ�����^��搶�i���E�H�w�@�勳���j�͖ؑ��������̏C�m�ے��ɍݐЂ��Ă���ꖌ�̍����������Ē����܂����B�܂��A��L�̎����Ŏg�p���������W���[���͐|�_�Z�����[�X���A�Z�g���ɗn�����K���X�ǂ̓��ʂɊǏ�ɐ���������A�ǏW���[�����A�M�����������ōs�������̂ł����B
2.2�@���Z�p���p���ɂ�����͍���
���E�G���W�j�A�����O��Ђ͐F�X�ȕ���ɖ��Z�p�����p���Ă݂����̂́A�H�i�͑������n�t�ł��薌�ʂɃt�@�E�����O���N�����₷���A��ʂɁA�H�i���H���u�͂P���P����E�ۂ��Ȃ���ΐH�i�i�����ቺ���Ă��܂����Ƃ��\���������ĂȂ��������߁A�����u�̕ێ�E�q���Ǘ����[���ɂł������p�����i�ݓ�Ȃ������߈�[���݂Ƃǂ܂�A���E�E�ۂɊւ����b�I������i�߂���Ȃ��Ȃ�܂����B
�@���̂��Ƃ������ЂƂ̗�Ƃ��āA1974�N���ɁA�x�r�[�t�[�h�����Ă����L���̉�Ђ���A�W���[�X�ނ̔Z�k�ɂq�n�������ꂽ���������������W���[�����ő��B���Ă��܂����i�i�����������ቺ���Ă��܂��̂ʼn����ǂ��Ȃ����낤���Ɖ]�����k�������Ƃ�����܂��B�䂪���ɂ����Ă悤�₭�����̏��ɕt�����ƍl���Ă����q�n�������\���������\���ɂ���Ȃ��܂܁A�Z�p�I�ɂ��\���Ǝv���Ȃ������K�͂̉�ЂɎ��p�K�͂̑��u�����ɓ�������Ă��邱�Ƃɋ����܂����B���̉�Ђ͂��̌�A�x�r�[�t�[�h�������ƋU����ː��E�ۂ����Ă������Ƃ����o���Љ�I�����N�������ƋL�����Ă��܂��B
�����u���̉q����Ԃ�ǍD�Ɉێ����邽�߂ɂ́A���u���ł̔������̑��B��j�~�R�j���邱�Ƃ��K�v�ł���A�f�b�h�X�y�[�X���̐H�i�����Ɩ��̃t�@�E�����O�����̏����A�X�ɖ����u���̎E�ۂ��s�����Ƃ��K�v�ł��B�܂��A�t�@�E�����O�����̏����͖��@�\�̈ێ��̖ʂ�����K�v�ł���A���\�ʂ���ѓ����̐��̌����Ɠ����Ƀt�@�E�����O�@�\�𖾂̌����S�j�T�j���K�v�ł���Ƌ����F�������悤�ɂȂ�܂����B
�����u���̕ێ�E�q���Ǘ��̏d�v���́A���ł́A���𗘗p����ꍇ�̏펯�ł����A�����́A���E�G���W�j�A�����O��Ђ͐H�i��m�炸�A�H�i��Ђ͖���m��Ȃ��ł���A���҂̗������i��ł�����Ȃ��ł����s�����Ȃ���̌����J���ł������悤�Ɋ����Ă��܂����B�����ŁA�H�i��Ђ������w�сA���E�G���W�j�A�����O��Ђ��H�i���w�Ԍ�����K�v�ƍl���A����̖ؑ��搶�ɑ��k���`�����X���L��Ζ��Z�p�Ɋւ��錤�����ݗ����鏳�����Ă��܂����B
�������Ȃ���A1982�N�ɔ_���ȗ��ʋǂ̏����ŐH�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g���i�ȉ��A�������g���Ƃ���j���ݗ����ꂽ���߁A�M�҂��`���Ă���������̐ݗ����������A�����g���̊������I������܂ő҂��Ƃɂ��܂����B�Ȃ��Ȃ�A�_���Ȃ̐H�����Ɨ��ʋǂƂ����Z�p�J���Ɋւ��錤����ƃv���W�F�N�g����s���ē������ẮA�֘A���閯�Ԋ�ƁE��w�ɂƂ��Ė��f�ł���Љ�I�ɂ����������ƍl��������ł��B
�H�i����ł̖��Z�p�̎��p�����n�܂����̂́A1982�N�ɐݗ����ꂽ�������g���̊����ɂ��Ƃ��镶�����݂邱�Ƃ�����܂����A���ۂ́A�������g���ݗ��܂łɂ������̐�i�I��Ђ́A�傫�ȍ�������z���Ď��p���ɂ��������Ă��܂����B�䂪���Ŗ��Z�p�Ɋւ��錤�����n�܂��Ă���A�������g���̐ݗ��܂łɂ́A10�N�ȏ�̔N��������܂��B�e�ГƎ��̋Z�p�J���ɂ����p���Ɩ����u���̐��E�E�ۂ̌�����m�E�n�E�̒~�ς����X�ɂł͂���܂����i�݁A���̖ʂł̔F�������܂����܂����B�_���Ȃł��A���ʌ������^�ʘg�����Ƃ��Ė��Z�p�����グ�A��w���Q�������v���W�F�N�g���i�߂��Ă���A�H�����A�H�Y�Z���^�[�A��w�̋��͂ɂ���b������i�ߐ�i�I��Ђ̋Z�p�J�����o�b�N�A�b�v���Ă��܂����B
�ڋ߂ȗ�����A�M�҂�1973�N�����疌�Z�p�����ɒ��肵�1976�N4������͐H�i�Y�ƃZ���^�[����̗v���Őv���������W���[���̐��������u�𓌑�̖ؑ��������Ɏ������܂��Ă����������\�m�F�̌������s���A���̔N��11������͕č��_���Ȑ����������̂lorgan�����̂��ƂɉȊw�Z�p�������݊O�������Ƃ��Ė��Z�p�����̂��ߗ��w���A�A�����1977�N����J�n���ꂽ���B�݂���W���[�X�̂q�n�Z�k�Ɋւ�����ʌ�����S�����铙�̌������s���Ă��܂��B������������̒��ŁA1982�N�ɂ͊w�ʎ擾�A1985�N�ɂ͓��{�H�i�H�Ɗw��i���E�H�i�Ȋw�H�w��j�̌�������܂���܂����đՂ����x�̋Ɛт��グ�Ă��܂����̂ŁA���Z�p�͂�����x�Y�ƊE�ł��F�m������p�����i��ł��܂����B���Z�p���t�����E�͍����ɁA�g���C�A���h�G���[�̌J��Ԃ��̒��Ő�i�I�Z�p�J�����s�����p�C�I�j�A�̕��X�́A���̋�J�̊��ɂ͕���Ă��Ȃ������A�����̕��X�Ɍh�ӂ�\���Ӗ����炠���Ē��ӂ����N���Ă��������Ǝv���܂��B
2.3�@�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g���̐ݗ�
�@1982�N�ɔ_���Ȃ̏����Őݗ����ꂽ�������g���́A�����u�̃��[�U�[�Ƃ��Ă̐H�i��Ђƃ��[�J�[�Ƃ��Ă̖��E�G���W�j�A�����O��Ђ����݂ɑ���Ȃ��_��₢�����Ȃ��猤���J����i�߂���悤�A���҂��`�[����g�݁A�e�X�̌����e�[�}�Ɏ��g�߂�悤�ɂ��܂����B���̍l���́A�������g���Ƃ͑S���ʂ̃��[�c����������ł���l�q�b�Ɉ����p����Ă��܂��B�\�P�ɂ͐H�i�����ɂ����閌���p�Z�p�U�j�Ƃ���1985�N�܂ł̂R�N�Ԃɍs��ꂽ�����ۑ�ƎQ����Ɩ��A�\�Q��1985�N����3�N�Ԑ������Z�p�V�j�ւ̉��p�Ƃ��čs��ꂽ�����ۑ�ƎQ����Ɩ��������܂����B
�������g���̊������J�n���ꂽ���A�����Z�p�ɂ��傫�Ȑi���������A����������������n�߁A����ɁA�ߋ�10�N�ȏ�ɂ킽�鎸�s�Ɛ����̌o������m�E�n�E�̐ςݏd�˂�����A�ȑO���ꡂ��ɕێ�E�q���Ǘ��ɑ���F�������܂�A���̖ʂł̋Z�p���オ������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������A���݂ł��C�����u�̕ێ�E�q���Ǘ��ɖ�肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A���ɁA�q�n�ɂ����ẮA�܂����̑ϔM���Ƒϖ�i���ɖ�肪����A����Ȃ���ǂ����߂��Ă��邱�Ƃɕς��͂���܂���B
�@�t�����ɂ́A���̑ϔM���E�ϖ�i���A�X�ɑ��u�v�̃m�E�n�E�s���Ȃǂ̗��R�ɂ����L�єY�݂̒i�K�ł���܂������A���Ɏ��p���ɂ��������Ă����J�S�����������̉�Ђ͖������g���ɎQ�����ĂȂ��Ƃ��������܂��B�������A�������g���͖��Z�p�̔��W�ɑ傫�ȍv�����ʂ���6�N�Ԃ̊������I�����܂����B
2.4�@�H�i�Y�ƃn�C�Z�p���[�V�����E�V�X�e���Z�p�����g���̐ݗ�
�@�������g���̊������I�����鎞�_�ŁA���̌����g�����ǂ�������悢���낤���Ƃ̑��k��H�i���ʋǂ���܂����B�܊p�i��ł������Z�p�������U���N�Œ��f���邱�ƂȂ�����������p���`���K�v�ł��邱�ƁA�܂��o�C�I�Z�p��H�i�̐������������i�@�\�������j�����̔��W�̒��ŕK�v���̍��܂������������Z�p�̌��������킹�Č����g������낤�Ɖ]�����ƂɂȂ�A���������̂��H�i�Y�ƃn�C�Z�p���[�V�����E�V�X�e���Z�p�����g���W�j�i�ȉ��A�n�C�Z�p�����g���Ƃ���j�łS���N�Ԋ������s���܂����B
�\�R�Ƀn�C�Z�p�����g���̌����ۑ�ƎQ����Ɩ��������܂����B�n�C�Z�p�����g���ł͖��Z�p�ɉ����A���ՊE���̒��o�Z�p�A���͋Z�p��N���}�g�O���t�B�[����X�̕����Z�p�Ɋւ��錤�����s���Ă��܂��B�������A���̌����g���̌������ʂ́A���e���[�����Ă���ɂ�������炸���܂�m���Ă��Ȃ����������Ă��܂��B�������e�͋@�\�������̕����ɉ����āA�p��������̗L�������̕��������܂܂�Ă���A�n�������␢�E�I���������l�����ŎQ�l�ɂȂ���e�ł���A���������x���ʂ��m�F���������Ǝv���܂��B���ʂ��\���L��Ă��Ȃ����ɂ́A���́A�n�C�Z�p�����g�����s���Ă���1991�N�S���Ɏ��������@��i���j����̋��߂ɉ����ĐH�����𗣂�Ă��܂������Ƃ������ƂȂ��Ă���̂łȂ����Ɛ\����Ȃ��v���Ă��܂����A����͍l���߂��ł��傤���B
�@�@�@�\�P�D�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g�������ۑ�i�H�i�����ɂ����閌���p�Z�p�j
|
�Ǝ� |
���������ۑ� |
��Ɩ� |
|
�����H�Ɋւ��錤�� |
���O�h�ߖ@�ɂ��S���y�ђE�����̔Z�k |
�������i���j |
|
�t�Z���@�ɂ��z�G�C�̔Z�k�@ |
�X�i���Ɓi���j |
|
|
�J�b�e�[�W�`�[�Y�z�G�[�̌��O�h�� |
���������i���j |
|
|
���y������̓��_�̑I��I���� |
���������i���j |
|
|
���y�������ɂ�����Z�k |
�S�����_�Ƌ����g���A���� |
|
|
���@�ɂ�錴�����̔Z�k |
���{���_�����i���j |
|
|
�ʎ����H�Ɋւ��錤�� |
���k�ʎ��̓����������� |
���Q���ʔ_�Ƌ����g���A���� |
|
�H�i���H�H�����ւ̖����p�Z�p�̓K�p |
���ʋl�i���j |
|
|
������ʏ`�ƔZ�k�ʏ`�̐��� |
�������H�i�i���j |
|
|
�����`���Ɋւ��錤�� |
�Ǐ���O�h�ߖ��ɂ�闑���̔Z�k |
�L���[�s�[�i���j |
|
�H���`���̕����Z�k |
�ɓ��n���i���j |
|
|
�p�����̐����ƒE�F |
�I���G���^���y��H�Ɓi���j |
|
|
�y�f����哤�`���̂Q�i���� |
�X�i�����i���j |
|
|
�哤�`���Ɋւ��錤�� |
HVP �����t�̒E�F |
���̑f�i���j |
|
�����q���ɂ�铤���̔Z�k |
�i���j�I�� |
|
|
�������̕s�������̏��� |
�����H���i���j |
|
|
���g�ݖ��h�߂ɂ����閌���p�Z�p |
�T���r�V�i���j |
|
|
���@�ɂ��Γ���ݖ��h�� |
���c�ݖ��i���j |
�\�Q�D�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g�������ۑ�i�Ő�[�������Z�p�ւ̉��p�j
|
���� |
���������ۑ� |
��Ɩ� |
|
�Y������ |
�b�����H�Ƃ̊Ð��̗L�����p |
�T���G�C�����i���j |
|
�R�[���Z�Љt����̂���ς������̉�� |
���q�R�[���X�^�[�`�i���j |
|
|
�������̐���v���Z�X�̊J�� |
�䓜�i���j |
|
|
�C�[�X�g�����r���̒E�F�Ɛ��̏z���p�V�X�e���̊J�� |
�I���G���^���y��H�Ɓi���j |
|
|
������Ƃɂ����鏬�^�������V�X�e���̊J�� |
�~�����p���i���j |
|
|
�`���� |
�H�����H�H��������̂���ς������̉�� |
�ɓ��n���i���j |
|
�h�z���t����̃A�~�m�_�̉�� |
���c�ݖ��i���j |
|
|
���Y���H�H��������̂���ς������̉���Ɛ��̍ė��p |
���{���Y�i���j |
|
|
�����r���̌��C�������Z�p�̊J�� |
���������i���j |
|
|
�Z���~�b�N���ɂ�鑍���������V�X�e���̊J�� |
�X�i���Ɓi���j |
�\�R�D�H�i�Y�ƃn�C�Z�p���[�V�����E�V�X�e���Z�p�����g�������ۑ�
�i�@�\���H�i�f�ނ̍��x�����E�����ƊJ���j
|
�O���[�v�� |
���������ۑ� |
��Ɩ� |
|
���� |
�I���S���̐V��������E�����Z�p�̊J�� |
���������i���j |
|
�Ԃǂ�������уI���S���̕��� |
���a�Y�Ɓi���j |
|
|
�����ӂ��ܓ�����������ނ̕����E���� |
���������i���j |
|
|
�T�C�N���f�L�X�g�����|���}�[�̊J���Ɖ��p |
�����`�����i���j |
|
|
�^���p�N�� |
�����z�G�C���f�������̕������� |
���������i���j |
|
�j�{�����i�����j����̌��t�^���p�N���̕����E���� |
�������H�Ɓi���j |
|
|
�������̐��������^���p�N���̕����E���� |
�G�[�U�C�i���j |
|
|
�哤�z�G�C���̐������������̕��� |
�s���i���j |
|
|
���l��������̗L�p�����̕����E�����Z�p�̊m�� |
��i���j |
|
|
���� |
�A����������̍��x�s�O�a���b�_�̕����Z�k |
���̑f�i���j |
|
�V�R�R�_���܂̕����E�����V�X�e���̊J�� |
���{�����Y�Ɓi���j |
|
|
�����z�H�X�t�@�`�W���R�����̕��������V�X�e���̊J�� |
�L���[�s�[�i���j |
|
|
���������x�s�O�a���b�_�̑�ʕ����E���� |
�T���g���[�i���j |
|
|
���[�O���i����̗L�p�����̕����E���� |
�������i���j |
|
|
��������̍��x�s�O�a���b�_�̔Z�k�E���� |
���d���H���i���j |
|
|
�哤���V�`���̃z�H�X�t�@�`�W���C�m�V�g�[���̕����E���� |
���������i���j |
|
|
�q�}������q�������p�V�X�e���̊J�� |
�������i���j |
|
|
�������� |
���k�ނ���̗L�p�����̌n���I�����V�X�e���̊m�� |
��ˉ��w�i���j |
|
�A�����ՊE�b�n�Q���o�@�ɂ��ݖ��̍��t�����l���Z�p�̊J�� |
�L�b�R�[�}���i���j |
|
|
�R�_���\��L���郁���m�C�W���̕������� |
���{�����i���j |
|
|
�n�`�~�c�Ȃǖ��I���Y������̓��萬���̃n�C�Z�p���[�V�����E�V�X�e���̊J�� |
�i���j�������I���{�� |
|
|
���J�e�L���̌o�ϓI���o�E�����E�����V�X�e���̊J�� |
�i���j�ɓ��� |
2.5�@�H�i���Z�p���k��i�l�q�b�j�̐ݗ�
�H�i�̂悤�ɐ��������G�ŔS�����������s�E�ώ����₷���t�̂���������Ŗ��Z�p�����p�����邽�߂ɂ́A���E�G���W�j�A�����O��ЂƐH�i��Ђ̋��͂����������K�v�ł���A�܂��A�n��Y�Ɛ��̍����H�i��Ђɐ�[�I���Z�p�y������ɂ͓s���{���̌��������@�ւ̋��͂��K�v�ł���ƍl���Ă��܂����B�����ŁA�������g���̉���ɔ���ꂸ���L�����Ԋ�Ƃ��Q���ł��A��w�A�����E���������@�ւ̎Q���ł��錤�����ݗ��������ƍl���A�Y���w�̗L�u�ɂ��ݗ����ꂽ�̂��l�q�b�ł��B
�������g���̊�����1988�N3���ɏI�������Ƃ͂������̂̌������ʂ�{�Ƃ��Ď��܂Ƃߌ��J���邱�Ƃ�w�����Y�̊Ǘ����̎c�����������邽�߁A�������g���͑g�D�Ƃ��đ��݂��Ă��܂����B�����ɁA�V���ɎY���w�̋��͑̂Ƃ��Ăl�q�b���ݗ�����A�������J�n�����̂Ŗ��g���̎����ǁi�n�b�L�������A�������g�����������Ă������ʋǂ̋Z�p���j�͒�R�������Ă��܂����B�w�H�i��Ƃ𑩂˂�i���˂�Ƃ������t�͖����ł悭�g���錾�t�̂悤�ł��j���Ƃ͉����ւł���̂ŁA�������ł͂��Ă����ȁx�Ƃ������Ƃł����B�������g������͖������g���Ƃ��ĎQ���������Ƃ̐\���o������܂������A�l�q�b�͊e��Ƃ����R�ӎu�ŎQ�����ĖႤ���Ƃ������Ƃ���̂ŁA���̐\���o�͔F�߂��܂���ł����B�Ȃ��Ȃ�A�l�q�b�͉���̑P�ӂʼn^�c������ł���A����A���ɖ��Ԋ�Ɖ���ւ̏����ŗD�悷��^�c�����邱�Ƃɂ�蒷�������ł�����̂ł��邪�A�����ɖ����̗��v�i�����ɂȂ��Ă���V���蓙�j���������܂�ẮA�R�X�g��������Ɠ����ɉ^�c���X�g���[�g�ɍs������₱�����Ȃ�A�l�q�b�{���̊����̖ړI����͂���Ă��܂��ƍl����ꂽ���߂ł��B
�]���āA�l�q�b�͖������g���ɎQ�����Ă�����Ƃ��Q�����Ă��܂����A�������g���Ƃ͑S���ʂ̑g�D�Ƃ��đ��݂��Ă�����̂ł���A���̋@�ւɍS������邱�ƂȂ��A������Ƃ��Ă̗��O���n�b�L���������Ǝ��̉^�c�����Ă������Ƃ�2�T�N�Ԃ̒����ɂ킽��������x�����ꑱ���Ă����傫�ȗ��R�ł��낤�ƍl���Ă��܂��B
�ݗ�������135�Ђ��z���閯�Ԋ�Ƃ��Q�����Ă��܂������A���݂͖�R���̂P���x�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���ꂾ�������̖��ԉ�Ђ��Q�����錤����͐��̕W�����炷��Α匤����ł���A25�N�Ԃ̒����ɓn��A���ꂾ���x�����ꑱ���Ă����H�i�����Z�p�֘A�̌�����͋H�ł���A����̉^�c�ɑ���ӔC�������Ă��܂��B
���\�ɓ��{���w��Ɠ��{�\����������ŊJ�Â��Ă����j���[�����u�����e�N�m���W�[�V���|�W���[����1990�N����2000�N�ɂ킽��H�i�Y�ƕ���ɂ����閌�Z�p�ɑ���Q���Ґ��Ƒ��̕���̎Q���Ґ��̕ϑJ�������܂����B
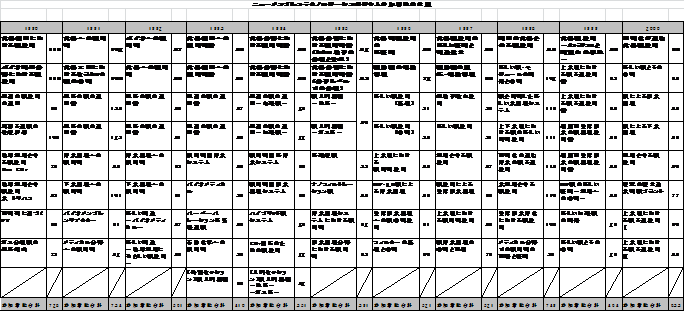
1990�N�̏��߂͈��|�I�ɐH�i�o�C�I����ւ̊S���������Ƃ��킩��܂��B1990�N��I���ɂȂ�Ɩ��̒l�i���ቺ����������E����ɂ����y���L����n�߂܂����B�H�i�����2000�N�������ăj���[�����u�����e�N���W�[�V���|�W�E������p���������ƂɂȂ�A���݂Ɏ����Ă��܂��B
���̗�ŕ�����悤�ɁA���Z�p�����y�n�߂������͕t�����l�̍����H�i��ΏۂƂ��Ė��Z�p�����W���A�H�i�Y�Ƃ͐��i�͂Ƃ��đ傫���v�����܂������A���Z�p�����y�����̒l�i���ቺ���t�����l�̒Ⴂ��������ő�ʂ̖����g����悤�ɂȂ�ƁA���֘A�Z�p�҂̊S�͑����E����Ɉڂ�H�i�Y�Ƃ͎��c�����`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
������������͌o�ϓ����̓����ɂ�鎩�R�Ȃ��̂ŁA�Ȋw�Z�p�̎��h���ł���ƍl�����܂��B�������A�H�i�Y�Ƃɂ����ẮA��^���u�͗��p����Ȃ��ł������̒����̐H�i��ЂŖ��𗘗p����܂łɔ��W���Ă���ȏ�A�H�i��Ђɑ��閌�Z�p�̌����J���ɂ�������M�A�܂��H�i��Ђ̖��Z�p�Ɋ֘A�����������Ђ�G���W�j�A�����O��Ђ֏�M����K�v������ƍl�����܂��B�l�q�b�͂��̖�����25�N�ԉʂ��������Ă��܂��������ꂩ����ʂ����Ă����\��ɂ��Ă��܂��B
2.5.1�@�t�G�ƏH�G�A�N�Q��̌������̊J��
�l�q�b�͔N��2��̌������ƔN��2��̂l�q�b�j���[�X�̔��s���傽��Ɩ��Ƃ��Ă��܂����B�t�G�������͓����ߕӂŔ����̍u������s���A�H�G�������͂P���Q���̃X�P�W���[���Ŗk�͎D�y�s�����͎������s�܂ŁA�S���e�n�ŊJ�Â����Ē����Ă��܂����B�e�n�ŊJ�Â����Ē������̂́A�H�i�Y�Ƃ��x����n��Y�Ƃɐ�[�I���Z�p�y�����邱�Ƃ�ړI�ɂ������߂ŁA��Ƃ��Č��̎�����̌䋦�͂�Ղ��s���Ă������̂ł��B�V�N�O�A�M�҂��V����w��ފ���������1��2���̏H�G�������̊J�Â�ύX���܂����B
�\�S�ɂl�q�b�̌������J�Ïꏊ�ƎQ���l���̕ϑJ�������܂����B�H�G�������́A����s�ł̂P���Ԃ̌������ɂ��Ă���Q���Ґ����������Ă��܂��܂����B�����ߍx�ȊO�Ō��w�������ĊJ�Â��ė~�����Ƃ̊�]������܂����̐������������_�ł����������݂����Ă݂����ƍl���Ă��܂��B
�\�S�@�l�q�b�̌������J�Ïꏊ�ƎQ���l���̕ϑJ(���Q���ҁ@4324��)
|
�ݗ� |
�t�G�������J�Ïꏊ |
�Q���� |
�H�G�������J�Òn |
�Q���� |
|
�P�N�� |
�|����� |
�P�R�O�� |
�@�}�g�R |
�P�Q�O�� |
|
�Q |
�@�B�U�� |
�P�S�S |
�@�@��� |
�P�Q�R |
|
�R |
�H�Ɖ�� |
�P�S�U |
�@�@�D�y |
�P�S�W |
|
�S |
�H�Ƌ�y |
�P�O�W |
�@�@���q |
�P�R�S |
|
�T |
�@�@�@���� |
�@�W�Q |
�@�@��� |
�P�O�X |
|
�U |
���ۉ�� |
�@�X�S |
�@���� |
�P�V�W |
|
�V |
�@�@�@���� |
�@�V�U |
�@�@���s |
�P�R�X |
|
�W |
�@�@���� |
�@�@�V�V |
�@�@�@���l |
�P�Q�V |
|
�X |
���i���w��ƍ����j |
�P�V�T |
�@�@�@��� |
�P�Q�R |
|
�P�O |
���ۉ�فi�P�O���N�L�O�j |
�@�@�W�X |
�@�@�@�V�� |
�P�R�P |
|
�P�P |
�S�і��� |
�@�@�U�V |
�@�@������ |
�P�O�R |
|
�P�Q |
���� |
�@�@�T�W |
�@�@�@��{ |
�P�P�R |
|
�P�R |
���� |
�T�T |
�@�@�@���R |
�P�P�O |
|
�P�S |
���� |
�@�@�T�P |
�@�@�@�V�� |
�P�O�W |
|
�P�T |
�@�@�@���� |
�@�T�X |
�@�@�� |
�P�Q�W |
|
�P�U |
�@�@�@���� |
�@�T�Q |
�@�@�{�� |
�V�Q |
|
�P�V |
�@�@�@���� |
�@�S�W |
�@�C��� |
�P�O�X |
|
�P�W |
�@�@�@���� |
�@�T�U |
�@�@�V�� |
�P�O�R |
|
�P�X |
���ۉ�فi��ފ��L�O�ƍ����j |
�@�W�R |
��������A |
�R�U |
|
�Q�O |
��������A�i�Q�O���N�L�O�j |
�@�T�P |
��������A |
�S�Q |
|
�Q�P |
�@�@�@��������A |
�@�S�T |
�@��������A |
�R�Q |
|
�Q�Q |
�@�@�@��������A |
�@�R�V |
�@��������A |
�@�Q�W |
|
�Q�R |
�@�@�@��������A |
�@�Q�W |
�@��������A |
�@�Q�Q |
|
�Q�S |
��������A |
�@�Q�Q |
�V�����f�z�e�� |
�X�P |
|
�Q�T |
��������A |
�@�R�Q |
��������A |
�R�O |
�@�@�@���j��10��14��18��24��H�G�������͐V�����H�i�Z�p������Ƌ����J��
2.5.2�@�l�q�b�j���[�X�̔��s�@50�����^�b�c�̔��s�̗\��
�l�q�b�j���[�X��2013�N��12���܂ł�50���̔��s���s���Ă��܂��B����ɁA�c�ӑ�\����(����)���ݗ�20���N���L�O����39���܂ł��b�c�Ɏ��^���A�w���^�\�H�i���E�����Z�p�x���쐬���Ă���܂����B����́A�l�q�b�ւ̍v���x�ɉ����đ��悠�邢�͔̔�����Ă��܂��B
�ݗ�25�N�L�O���A50���܂ł̂l�q�b�j���[�X���b�c�Ɏ��^���{�N�x���ɂ͔������A���̂b�c�͂l�q�b�ւ̍v���x�ɉ����đ��悠�邢�͔̔�����\��ł��B
2.5.3�@�H�i���Z�p�u�K��̊J��
2004�N���疌�E�����Z�p�Ɋ֘A����Z�p�҂̈琬�ƋZ�p�̌p����ړI�Ɂw�H�i���Z�p�u�K��x���W����2���ԊJ�Â��Ă��܂��B���̍u�K��ł͑S���̏����҂Ƃ��Ȃ薌�Z�p�ɐ��ʂ��Ă�����X�����݂��Ď�u����Ă��銴�����܂����̂ŁA���݂͂W���ɂ́w���Z�p�u�K��x�Ƃ��Ď�Ƃ��Ē��E�㋉�҂�Ώۂɂ����u�K��A1���Ɂw�����҂̂��߂̖��Z�p�u�K��x���J�Â��Ă��܂��B
���Z�p�u�K��(���o�ȎҐ�152��)
|
|
�u�K��� |
�Q���Ґ� |
|
��1��(2004�N�x�j |
�����_�H��w�H�w�� |
17�� |
|
��2��(2005�N�x�j |
�����_�H��w�H�w�� |
26�� |
|
��3��(2006�N�x) |
�����_�H��w�H�w�� |
13�� |
|
��4��i2007�N�x) |
��������A |
22�� |
|
��5��(2008�N�x�j |
��������A |
18�� |
|
��6��(2009�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
18�� |
|
��7��(2010�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
6�� |
|
��8��(2011�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
9�� |
|
��9��(2012�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
13�� |
|
��10��(2013�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
10�� |
�����҂̂��߂̖��Z�p�u�K��(���o�ȎҐ�81��)
|
|
�u�K��� |
�Q���Ґ� |
|
��1��(2008�N�x) |
��������A |
16�� |
|
��2��(2009�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
15�� |
|
��3��(2010�N�x�j |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
14�� |
|
��4��(2011�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
15�� |
|
��5��(2012�N�x) |
(��)���{�H�i���̓Z���^�[ |
21�� |
2.5.4�@�H�i�����E��Z�p�u�K��̊J��
2008�N���w�H�i�����Z�p�u�K��x2009�N���w�����E��Z�p�u�K��x�Ƃ��ĂQ���Ԃ̍u�K��ɕύX���āA���Z�p�҂̈琬���͂����ĎQ��܂������A���݂͒��~���Ă��܂��B
�R�D�l�q�b�j���[�X�ƌ�������茩���l�q�b�̕��݂Ɩ��Z�p�J���̓���
�l�q�b�ݗ���|�Ɖ^�c���j�A����ɐݗ��ɂ܂���X�̓����Ȃǂɂ��Ă͂l�q�b�j���[�X�P������тQ�P�����ɏq�ׂĂ���̂ŎQ�l�ɂ��Ă������������ƍl���܂��B�����ł́A�l�q�b�����̋L�^�Ƃ��ĔN�㏇�ɂ��̔N�̏Ƃl�q�b�j���[�X����ь������̓��e���Ɋւ��ĕM�҂̎v���������Ƃ��q�ׂČ��܂��B�o���I�ɋL�q���܂������A�r�����猤�����̍u�����e���l�q�b�j���[�X�Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ�܂����B�������A�������̓��e��������₷���悤�ɁA���̕������o���������Ƃ����e�L�X�g�{�b�N�X���ɋL�ڂ��܂����B�l�q�b�j���[�X�̓��e���R�����Ȃ����킯�ł͂Ȃ����Ƃ��������������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�ؑ���i1989�N2���`1997�N�S���j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
3.1�@1989�N�x
�@�Q���P�S���ɔ��N�l����J�Â��A��̖��́A��{���j�A��A�����������߁A���̌�A���Ԋ�ƁA�����������@�ցA��w���ɌĂт������s���A�l�q�b�̑g�D�ł߂����܂����B�t�G�������́A�ʏ�ł���T���ɊJ�Â��邱�Ƃɂ��Ă��܂������A���̔N�͂T���ɃP�����ŊJ�Â��ꂽ�w���ېH�i�H�w��c�x�ɏo�Ȃ���\��ɂ��Ă������߁A�ݗ�����Ƒ�P��t�G���������U���R�O���ɊJ�Â��邱�Ƃɂ��܂����B���ۉ�c�̏I����A�M�҂������߂Ă����v���Z�X�H�w�������̎����ł������������i���݁A�}�g��w�����j���X�C�X�ɗ��w���Ă����̂ŁA��l�Ńh�C�c�̖�����𐔃J�����w���܂������A���s���ɁA�l�q�b�j���[�X�P���Ɍf�ڂ����^�c���j�����M���܂����B�V���^�b�g�K���g�ŁA�X�i���Ƃ̓c�����B�ɂ��ڂɂ�����[�H���ꏏ�ɂ����Ă��������l�q�b�̉^�c���j���Ɋւ���l�������b�����A�܂���]���̈ӌ������Ă��������܂����B
�A�����Ă���͐ݗ�����̏����Ƃl�q�b�j���[�X�P���̏o�œ��ŋɂ߂đ��Z�ł������A���E�����E�����e�����͂��߂Ƃ�������̕��X���i���J�Ɍ��߂ĉ�����A�����̓X���[�Y�ȉ^�c���ł��܂����B�ݗ�����ɂ͂P�R�R���̕��X�ɎQ�����Ă����������Z�p�Ɋւ���S�̍����Ƃl�q�b�̊����Ɋւ�����҂��������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@��P��H�G�������́A�}�g�R�̎R�[�ɂ���؉����قŊJ�Â��܂����B�؉��͐H�����Ƃ��ĉ��x�����p�������Ƃ��������̂ł����A������������J�Â���i�ɂȂ�ݔ����m�F�����Ƃ���A�ړ����̏����ȃX�N���[�������Ȃ��f�ʂ���X���C�h�����Â炢�Ɗ������܂����B�����ŁA�e�[�u���N���X��V�䂩��݂艺���A��^�̃X�N���[���Ƃ��Ďg�p����Ȃǖ����e�ʂ̂����͂Ŗ����J�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�H�G�������͂P���Q���ōs���܂����A�����̌𗬉�i�[�H��j�̌�ɕ��ȉ���J�Â��Ė{���̋c�_���d�˂Ă����̂́A�����d�H�ɂ���ꂽ��莁�́w�������͉�Ђ̌��C����݂̌��������K�v�ł���x�Ƃ̈ӌ��ɏ]�������̂ł��B�܂��A���ȉ�I��������̉��y��(�J���I�P)�͐X�i���Ƃ̓c������̔��z�ɂ��`�����������̂ŁAMembrane
Research Circle�i�l�q�b�j����ɂȂ�Ɓ@Music Research�@Club�i�����l�q�b�ł����j�ɕω����邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�l�q�b�j���[�X�Ɋւ��ẮA�����������@�ւ������f�ڂ��Ă��܂��B�H�����̃v���Z�X�H�w�������Ɍ������������猤�C�ɗ��Ă������X�𒆐S�Ɏ��M���Ă��������܂����B�����������ł����Z�p�ɑ傫�Ȋ��҂������Ă��邱�Ƃ�������܂��B
�l�q�b�j���[�X�P������A�����Ă��������������@�ւ���肪�P�X���̐H�����������ďI�����Ă��܂��B���M�������������́A�P���E���R���H�ƋZ�p�Z���^�[�E���ѓ��v���A���������_�Y�����H�����w���Z���^�[�E�n�ꓧ���A���������莁�A�Q���E�X�����Y�����H�������E���c�T���A��ʌ��H�i�H�Ǝ�����E����m�����A�R�����H�ƋZ�p�Z���^�[�E����q���A�S���E���m���H�i�H�ƋZ�p�Z���^�[�E�ēc���l���A���쌧���y�H�i������E��茫��A�T���E�É����É��H�ƋZ�p�Z���^�[�E���{�@�L�A�{�茧�H�Ǝ�����E�������v�E���������A�V���E�Q�n���_�Y���H�w���Z���^�[�E�ؑ��ߕ�����A�k�C�������H���Y������E��x���u�A傒J�K�i�A�������v�e���A�W���E�x�R���H�i�������E��������E���� ���e���A���挧�H�i���H�������E������E�H�c�K��E���J
�K�q�E�e�R ���e���A�X���E�������n�C�e�N�v���U��Îᏼ�Z�p�x���Z���^�[�E�ē� �E�j���A�F�{���H�ƋZ�p�Z���^�[�|�E���V�� ��q���A�P�P���E���H�ƋZ�p�Z���^�[�E���J�������A�P�R���E�����s���H�i�Z�p�Z���^�[�@�O�}�O�玁�A�P�S���E�a�̎R���H�ƋZ�p�Z���^�[�E�����������A�P�T���E���쌧���y�H�i������E�����ېm���A�P�U���E��ʌ��H�i�H�Ǝ�����E����m�����A�P�V���E�É������Ǝ�����E���ї������A�P�W���E���R���H�ƋZ�p�Z���^�[�E�Y�씎�����A�P�X���E�H�i�����������E�������q�E��J�_�u�e���ł��B
�k�́A�k�C���E�X�����͎������E�{��E�F�{�܂ő����̌��̕��X�Ɏ��M���������Ă��܂��B�s���{���̐H�i�������̌����҂͐��������Ă���A�������_�|���w�o�g�҂Ő�߂��Ă��邽�ߍH�w�I���������ɂ��Ă��邱�Ƃ��l����A���Z�p�͌����x���܂ŗ������Ă����������p���L�������ƍl���ėǂ��悤�Ɏv���܂��B����������ɖ�����������Ɍ����J���ƕ��y�ɗ͂�s�����Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�ݗ������́A�N�ɂR��l�q�b�j���[�X�s����\��ɂ��Ă��܂����̂ŁA�ݗ����N�ɂR���s���Ă��܂��B���̌�A�N�R��̔��s�͎����ǂ̕��S���傫���Ȃ肷����̂ŔN�Q��ɕύX���܂����B�R�����u���E���W���[�����W���v�́A���������X�C�X���w����A�����A�����W���[�����W�����쐬�������̂ł�点�ė~�����Ƃ̐\���o���琶�܂ꂽ���̂ŁA40�Ђ̖����[�J�[�����M���Ă��܂��B�e��Ђ̖����Ƃɑ���ӋC���݂���������e�ł����A25�N�o�������݂́A���ɖ����Ƃ���P�ނ��Ă��܂�����Ђ��܂܂�Ă��܂��B��J�E��J���ɉ����A���������A���������Ƃɂ��l�q�b�j���[�X���A���E�ʋ��ɏ[�����ݗ��P�N�ڂɂ��Ăقڊ�b���m���������̂ƍl�����܂��B�@
MRC News No. 1
�@ 1989�N6�����s
�u�H�i���Z�p���k��̐ݗ��ɍۂ��āv �l�q�b��A������w�E�ؑ����j�j�u�H�i���Z�p���k��ݗ��܂ł̌o�߂Ɖ^�c���j�v�i�l�q�b��\�����A�H�i�����������E�n�ӓ֕v�j
�����������@�ւ���� �i���R���H�ƋZ�p�Z���^�[�E���ѓ��v�j�i���������_�Y�����H�����w���Z���^�[�E����������A�n��@���j
����u�H�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p�p�����v �i�H�i�����������E�n�ӓ֕v�j �u�H�i�Y�Ɩ��Z�p�p��v�i�����j �i�H�i�����������E�n�ӓ֕v�A�����d�C�H�ƁE���r�j�j
�u�e��_�C�i�~�b�N������і��@�ގ����Ƃ��̉��p�v �i�H�i�����������E��J�q�Y�j
|
MRC�ݗ�����@1989�N6���@�|����ف@�@�Q����133�� �@�@MRC�ݗ���|�@�@�@�@�@��@�@�@�ؑ����j�i������w�E�����j �@�AMRC�̉^�c���j�@�@�@�@��\�����@�n�ӓ֕v�i�H�i�����������E�����j ��P��t�G�������@ �@���Z�p�̓W�]�@�@�@�@�@�@�@�@�ؑ����j�i������w�E�����j �A�����@�\�Ɩ���������@�@�@�@���c�h�O�i���s��w�E�����j �B�H�i�J���ɂ����閌�Z�p�̖��́u����ɖ��Z�p�W�����邽�߂ɂ́v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�ӓ֕v�i�_���ȐH�����E�����j |
MRC News No. 2
1989�N9�����s
�������u�H�i���Z�p���k��ւ̊��ҁv �i������w�E���r���j
���������������@�ւ���� �i�X�����Y�����H�������E���c�@�T�j�i��ʌ��H�i�H�Ǝ�����E����m���j �i�R�����H�ƋZ�p�Z���^�[�H�i�������E����@�q�j
����u�������̕W�����Ɖۑ�v �i���l������E���F�j�u���Ƃւ̖����p�v �i�X�i���Ƈ��E�c���g���j�u�o�C�I�e�N�m���W�[�ւ̖��Z�p�̉��p�v �i������w�E�쏟�F���E�����^��j
|
��P��H�G�������@1989�N11�� ���ΎR�A�؉��@�Q���҂P�Q�O�� �@
�������q�i�_���ȐH�����j�|���[���b�p�ɂ����郁���u�����o�C�I���A�N�^�[�J���̓����|
�A�R��Ɂi�����@�퇊�j�|�Z���~�b�N���̐H�i�ւ̉��p�| �B�����ەF�i�_�C�Z�����w�H�Ƈ��j�|�t�e�����ɂ�鐴���ʏ`�̐����|�C���F�i���l������w�j�|���O�h�ߖ��̕]���@�ɂ��ā|
�D�c���g���i�X�i���Ƈ��j�|���Ƃɂ����閌���p�̓����|�E�c�Ӓ��T�i�w���P���������j�|���̐��|�F���R���Y�i�������j�|�A�~�m�_���̂q�n�ɂ�镪���Z�k�|�G���r�j�i�����d�H���j�|���[�Y�q�n���ɂ�钲���t�����| �[�H��19:30~21:30���ȉ�i��茤������̒�āu��Ђ̌��C����݂̌������ł��v�j�E���ȉ�I�����Music�@Research�@Club�@�ɕϐg�i��E�c���g���j |
MRC News No. 3�@1989�N12�����s
�������u���E���W���[�����W���v�̊��s�ɂ������� �i�l�q�b��@������w�E�ؑ����j�j
1�A���t�@�E���o����2�������H�Ƈ�
3���Ɏq�� 4�L���m�� 5�_�C�Z�����w�H�Ƈ� 6�_�E�P�~�J�����{��7�t�W�t�B���^�[�H�Ƈ� 8�x�m�ʐ^�t�C������ 9�Q���}���T�C�G���X�W���p���� 10�O���[�X�W���p����
11���C�Y�~�t�[�h�}�V�i�� PCI 12�I�c�H�Ƈ� 13�O��Ζ����w�H�Ƈ� Phone-Poulenc, Tech-Sep14�O�䓌���@�H�� DDS 15�O�䑢�D��
GFT 16�O�H���C������17�O�H���C�����E�G���W�j�A�����O�� 18�X�i�G���W�j�A�����O�� Osmonics 19���{�A�u�R�[�� 20���{�Z�����g�� 21���{�K�C�V��
22���{�����e�b�N�� 23���{�~���|�A���~�e�b�h�� 24���{�|�[���� 25�����d�H�� 26 �m�n�j�� 27�I���K�m�� Romicon 28���O�W����
Desalination, Film Tech 29�Z�F�x�[�N���C�g�� 30�Z�F�d�C�H�Ƈ� 31�Z�F�d�@�B��G���o�C���e�b�N�� Tech-Sep 32�s�c�j��
33������ 34���R���B�� 35���ŃZ���~�b�N�X�� SCT 36�����@�퇊 37���m�a�ч� 38���m�h���� 39�F�����Y�� 40����d�r�� Ionics �iABC���j
3.2
1990�N�x
��Q��t�G�������́A�H�i�ƊE�ɂ�����i�m�h�߂̏������ɒ��ڂ��V���|�W�E���`���̍u������J�Â��Ă��܂��B�܂��A��P��H�G�������ł͐�莁���A���[�Y�q�n���ɂ�钲���t�����Ɋւ���u�����s���Ă��܂��B�����́A�܂��i�m�h�߂Ƃ������t���Ȃ��A���[�Y�q�n�Ƃ��A��j�~���t�Z���Ƃ��]���Ă�������ł����B�l�q�b�ł́w�t�Z���ƌ��O�h�߂̒��ԗ̈�ɂ����鍂�x�����Z�p�x�ƃe�[�}��ݒ肵�Ă��܂��B�M�ғ��́A��j�~���t�Z�����̗L�����ɂ����������ڂ��A�������قƋ����Ńt���N�g�I���S���̕���Ɋւ��錤�����s���Ă��܂����B
��Q��H�G�������͊֓��𗣂ꖌ���[�J�[�������{�Ђ��\������n��ł�낤�Ɖ]�����ƂɂȂ�A�_�C�Z���̒������A�����d�H�̐�莁�A���s���H�ƌ������̏��R�����̂����͂������������ŊJ�Â���Ă��܂��B�������ɁA�����̖ڕW�ʂ�S���e�n�ŏH�G���������J�Â��邱�ƂɂȂ�܂����B
���̔N�̂S���A�M�҂͐H�i�Y�ƕ���ɂ����閌�Z�p�����̐��ʂƖ������g�����ł̌��т��F�߂��A�u�H�i���H�p�����p�Z�p�̊J���v�Ƃ��āw�Ȋw�Z�p�������܉Ȋw�Z�p���J�ҕ\���x����܂����Ă��������܂����B
2003�N�ɂ͓c���g����(�X�i���Ƈ�)�Ɛ��K�Y��(�J�S����)���A�e�X�u���N�g�t�F�����̍H�ƓI�Ȑ����@�̊J���v�Ɓu�g�}�g�W���[�X�q�n�Z�k�Z�p�̌����J���Ǝ��p���v�̌��тŁw�����Ȋw��b�܉Ȋw�Z�p���J�ҕ\���x����܂���Ă����܂��B��܋L�O�_���͂l�q�b�j���[�XNo.31�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
|
��)�@�Ȋw�Z�p���ł�,�䂪���̉Ȋw�Z�p�Ɋւ��ŋߌ����Ȍ��т��グ���҂��Ȋw�Z�p���J�҂Ƃ��ĕ\������ق�,�D�ꂽ�������ʂ��グ�������҂��������ю҂Ƃ���,�D�ꂽ�n�ӍH�v�ɂ���Ċe�E��ɂ�����Ȋw�Z�p�̍l��,���Ǔ��ɍv�������ΘJ�҂�n�ӍH�v���J�҂Ƃ���(����)�Ȋw�Z�p�Ɋւ��ėD�ꂽ�U����̋Ɛт��グ���҂��Ȋw�Z�p�U�����ю҂Ƃ���,�Ȋw�Z�p�̕��y�[���ɐs�͂��D�ꂽ���ʂ��グ���҂��Ȋw�Z�p���y�[�����ю҂Ƃ���(����)�\�����Ă���B |
MRC News No. 4�@1990�N4�����s
�������u���������H�i�̐����Ɩ����p�Z�p�v �i��B��w�E⫓��@�L�j
���������������@�ւ�����@ �i���m���H�i�H�ƋZ�p�Z���^�[�E�ēc���l�j�i���쌧���y�H�i������E��茫��j
����@�u�t�Z�����v (�������E�I���@�D�j �u���[�Y�q�n���ɂ�钲���������v �i�����d�H���E���r�j�j �u���ۉ�c�Ɍ��閌�̃t�@�E�����O�Ɛ��̌����̓����v �i�Q�n��w�H�w���E�������O�j
�u���[���b�p�ɂ����閌�̃o�C�I���A�N�^�[�Z�p�̌����J�������v�i�_���ȐH�i�����������E�������q�j
|
��Q��t�G�������@1990�N5�� �����A�@�B�U����ف@�Q����144�� �t�Z���ƌ��O�h�߂̒��ԗ̈�ɂ����鍂�x�����Z�p �@�����^��i������w�j�t�Z���A���O�h�ߒ��ԗ̈�ɂ�����Z�p�J���̓W�] �A�Љ���Y�i���̑f���j��j�~���t�Z�����ɂ�钲�����̐����B��˗���i�������ه��j�E�n�ӓ֕v�i�_���ȐH�����j�t���N�g�I���S���̍��x�����C���㏟�u�i�I���G���^���y�ꇊ�j�����𗘗p�������y�p�t�̒E�F |
MRC News No. 5�@1990�N9�����s
�H�i���Z�p���k��ږ�A �쑺�j���搶�i���E��B��w�_�w�������j�̂������𓉂� �@�i�H�i�����������E�n�ӓ֕v�A�����d�H�i���j�E�ˑ�C���j
�������u���n�C�u���b�h�v���Z�X�̌o�ϐ��v �i����w��b�H�w�����w�H�w�ȁE�����ߎ��j
���������������@�ւ�����@�u���ƃo�C�I���A�N�^�[�v�@�É����É��H�ƋZ�p�Z���^�[�E���{�@�L�j�@�u���E���K���X�̓����Z�p�ւ̉��p�v�i�{�茧�H�Ǝ�����E�������v�E���������j
�����@�u�H�i���H����ɂ����閌���p�Z�p�v �i�_�C�Z�����w�H�Ɓi���j�E�����ˍW�j �@�u�p�����𗘗p�������y�p�t�̒E�F�v �i�I���G���^���y��H�Ɓi���j�E���㏟�u�j
���ۉ�c���@�u���ۖ��@����c�ɂ݂�H�i�E�o�C�I����̌��������v�i�_���ȐH�i�����������E�������q�j
���������@�u�H�i���Z�p���k��(�l�q�b)��Q��t�G�������|�[�g�i�t�Z���ƌ��O�h�ߒ��ԗ̈�ɂ����鍂�x�����Z�p�j�v�i�_���ȐH�i�����������E�n�ӓ֕v�j
|
��Q��H�G�������@1990�N11�� ��ナ�o�[�T�C�h�z�e���@�Q����123�� �@���엲��i���s��w�j�|�o�C�I�v���_�N�g�̖������|�A�n�ӓ֕v�i�_���ȐH�����j�|�t�Z���@�ɂ�鍂�Z�x�Z�k�|
�B���J��G�i���{�V�q���j�|�Z���~�b�N�l�e�E�t�e���̐H�i����ւ̉��p�| �C���J��W�T�i�_�|�p���e�b�N���j�|�����p���O�h�ߑ��u�ɂ��ā| �D�n��@���i�����������H���Z���^�[�j�|���������ɂ����閌�Z�p���p�����̌���|
�E��茫��i���쌧�H�i������j�|���쌧�ɂ����閌���p�Z�p�̌���| �F����@���i���挧�H�i���H�������j�|���挧�ɂ����鐅�Y���𒆐S�Ƃ��������p�Z�p�̌���ɂ��ā|
�G���c�`�Y�i�L�����H�i�H�ƃZ���^�[�j |
MRC News No. 6�@1991�N1�����s
�������u���������p�����u���W���v�̊��s�ɂ������āv �i�l�q�b��@������w�E�ؑ����j�j
1 �A���t�@�E���o�� �� �@2 ���Ɏq �� �@3 �������H�� ���@�@�\���Z�p�� �@4 �������H�� ���@���������ƕ� 5 �L���m ��
6 �_�C�Z�����w�H�� �� 7 �x�m�ʐ^�t�B���� �� 8 �O���[�X�W���p�� ��
9 �����v�����g���� �� 10 �� �C�Y�~�t�[�h�}�V�i�� 11 �O������w�H�� ��
12 �O�䓌���@�H �� 13 �O�䑢�D �� 14 �O�H���C���� ��
15 �O�H���C�����E�G���W�j�A�����O �� 16 ���{�K�C�V �� 17 ���{�����e�b�N��
18 ���{�~���|�A 19 ���{�|�[�� �� 20 �����d�H �� 21 �I���K�m ��
22 �Z�F�x�[�N���C�g �� 23 �Z�F�d�@�B�G���o�C���e�b�N �� 24 ���R���B ��
25 ���� 26 ���m�h�� �� 27 �U���g���E�X ��
��Q��H�G�������ȉ�i���s�j�@(1990�N11��30���`12��1��)
�u���̑������p�v A-1-1�@�i�����d�H���E�������j�j A-1-2 �i���挧�H�i���H�������E����@���j �u�q�n����у��[�Y�q�n�̗��p�v�i���������_�Y�����H�����w���Z���^�[�E����������j
�u�t�e�E�l�e�̗��p�ɂ��āv �i�i�c�����@�B���E�ɓ��G���j �u�H�i�Y�Ƃ̐V�������̊J���ɖ]�ށv�i�����d�H���E�g��_�u�j�u�o�C�I�ɂ����閌�Z�p�̐V�������p�v�i���{�K�C�V���E�x�k�O�V�j
3.3 1991�N�x
�@���̔N�A�M�҂͓����@�킩��̋��߂ɉ����āA�H������ސE�������@��ɈڐЂ��܂����B�ڐЂɍۂ��ẮA�����̒����A��J�����ɑ��k���A�����ڐЂ��Ă��������������ǂ��v���Z�X�H�w�������ň����Ă���邱�ƁA�܂��A�����@��ɂ͉�v�Ɩ��𓌓��@��ň����l�q�b���T�|�[�g���Ă����m���ꖱ�����������ڐЂ��邱�Ƃɂ��܂����B�������A��Ђł̎d�����O���ɏ��A����Ԃɂ܂�����悤�ɂȂ�ƕM�҂ւ̏��`�B���x���Ȃ�i�Г��ɂ͑�����������l�������悤�ł��j�A�M�҂̒m��Ȃ��Ԃɖ��j���Ă��܂����悤�ł��B
�M�҂̖��ԉ�Ђւ̈ڐЂɍ��킹�āA������w�̖��搶�̋�����\�������쌤�����̏������ł������{�e���ɂ��肢���邱�Ƃɂ��܂����B�M�҂́A�ړ]��̓����̋����A����\�����Ƃ��ċ{�e�����T�|�[�g���l�q�b���]���ʂ�~���ɉ^�c���Ă������Ƃɂ��܂����B
�@��R��H�G�������̓o�C�I�Y�Ƃւ̓����ɔM�ӂ������đΉ����Ă����k�C����s�̉��쎁�̗v��������A�i���j�k�C����s������Ɛl�ފ���Ƃ̋��Âɂ���D�y�s�̃v�����X�z�e���ŊJ�Â����đՂ��܂����B�����́A�o�u���o�ς̏I���ł͂���܂������A��s�����̗T�����Ɋ��S������ꂽ���̂ł��B
|
��R��t�G�������@1991�N5�� �����A�H�Ɖ�ف@�Q����146�� �@���������i���{�~���|�A���~�e�b�h���j�|�č��ɂ����閌���p�Z�p�̌���|�A��J�q�Y�i�_���ȐH�����j�|���[���b�p�ɂ����閌���p�Z�p�|
�B�ɓ��V���i���������I���{�܁j�|�n�`�~�c�����������ɂ����閌�Z�p�| |
MRC News No. 7�@1991�N7�����s
�������u���A�H�i�����Ė��v
�i������w�E�{�e�@���l�j
���������������@�ւ�����@�u���O�h�߂ɂ��K���ʏ`�̐������v �i�Q�n���_�Y���H�w���Z���^�[�E�ؑ��ߕ���j �u�����A�N�^�[�Z�p�ɂ�邢�킵�Ϗ`����̓V�R�����������v
�i�k�C�������H���Y������E��x���u�A傒J�K�i�A�������v�j
����@�u�n�`�~�c�����������ɂ����閌�Z�p�v �i���������I���{�܁E�ɓ��V���j�@�u�����A�N�^�[�ɂ��V�������X�����v
�i���l������w�E���{�����j �u�t�Z���A���O�h�ߒ��ԗ̈�ɂ����鍂�x�����Z�p�J���̓W�]�v�i������w�E�����^��j�u�o�C�I�v���_�N�g�̖������v�i���s��w�E���엲��j �u�����H�Ƃւ̖����p�v�i�����������Ǝ�����E�]���p�Y�A�H�i�����������E�������q�j �u�����H�Ƃւ̖����p�v �i���d���H�Ƈ��E���r�����A�H�i�����������E�������q�j
�C�O���@�u���[���b�p�ɂ����閌����ѕ\�ʕ��͌����̌���v �i�H�i�����������E��J�q�Y�j�u�A�����J�H�i�H�ƊE�ɂ����閌�����̌���v�i�~���|�A�R�[�|���[�V�����E���������j
��c�� �u�h�b�n�l90�ɂ݂�H�i�E�o�C�I����ɂ����閌�Z�p�����̌���v�i�H�i�����������E�������q�j
|
��R��H�G�������@1991�N10�� �D�y�v�����X�z�e���@�Q����148�� �@�~�ю��Lj�i�������j�|�q�n���̋Z�p���W�̊T�v�|�A�v�ۓc���i�������H�Ƈ��j�|�t�e���̌���ƍ���̓W�J�|�B�����@�Ɂi�x�m�ʐ^�t�C�������j�|�l�e���̌����ƍ���̓����|�C�����N���i�����@�퇊�j�|�Z���~�b�N���̌���ƓW�]�|
�D�s�D�A�{�b�g�i�č��_���Ȗk���������j�|New Crops and Membrane application�|
�E�O���u�i��t���Ƈ��j�|�����H�ɂ����閌���p�| �F���ˌ���i�T�b�|���r�[�����j�|�r�[�������ɂ������h�ߋZ�p�| �G�|�{�Y�O�i������ި�����жٽއ��j�|�H�Ɨp�y�f�̐��Y�Ɩ����p�|
|
MRC News No. 8�@1992�N1�����s
�������u���A�G�ρv�@�i���k��w�E�V��@�M�v�j
���������������@�ւ���� �u���Z�k�ʏ`�������Ƃ������C���̐����v�i�x�R���H�i�������@��������E����
���j �u�����p�ɂ��J�j�Ϗ`�Z�k�G�L�X�̐����v�i���挧�H�i���H�������@������E�H�c�K��E���J �K�q�E�e�R ���j
���Z�p���Ӌ@����W�@1.�H�i�p�|���v �O�Y�H�Ƈ� ���_������ �X�^���v�|���v��
����@���H�Ƈ� �@2.���͌v ���v��H�Ƈ� �����a�d�� ������v�퐻�쏊
���{�x�[���[�� ���I���G���e�b�N �����H�Ƈ� ���G�X�E�e�[������
�L�c�H�@�� 3.���ʌv ���{�t���[�Z���� �������H�� �O���p�C�I�e�N�� 4.���x�v ���v��H�Ƈ�5.�Z�x�v ���A�^�S �d�C���w�v�퇊
���I�[�g�}�`�b�N �V�X�e�� ���T�[�`�i�G�[�G�X�A�[���j ���s�d�q�H�Ƈ� �Z���g�����Ȋw�� �X�Y�L�� �����Ƈ�
6.�M�������A�z�Ǎޓ� ���C�Y�~�t�[�h�}�V�i�� �����㐻�쏊
�����@�u���ލH�Ƃւ̖����p�v�i���������_�Ǝ�����_�Y�����H�����w���Z���^�[�E����������A�_���ȐH�i�����������E�����@���q�j
���ۉ�c���u���ېH�i�Ȋw�Z�p��c�ɂ݂閌�Z�p�̓����v�i�_���ȐH�i�����������@���� ���q�j
�H�G�������ȉ�@A-1 �u�o�C�I����ւ̖����p(1)�v A-2 �u�o�C�I����ւ̖����p(2)�v
B �u�Z���~�b�N���̗��p�v C �u�t�e���̗��p�v D �u�e�����[�J�[�̃��[�U�[�ւ̑Ή��v E �u�l�e���̗��p�v F �u�q�n���̗��p�v
3.4�@1992�N�x
�@��S��H�G�������́A�M�҂��k��B�s�œ����@��̊�b�������������Ă������Ƃ����q�ŊJ�Â��邱�Ƃɂ��܂����B�J�Âɓ������āA���������̌ߑO���ɖ�������J�Â���̂ƕ��s���Ēn���̕��X�ɖ����Ŗ��Z�p���Ղ���������Ċ�b�͂�t���Ă�����������A�������ɎQ�����Ă��������悤�ɁA��b�u���F�u�����p�Z�p�̊�b�Ɖ��p�v�̍u�����J�Â��邱�Ƃɂ��܂����B��P��͕M�҂Ƒ�J�����u�t�������܂������A�M�҂��u�`�����Ă���Ɩ�������J�Âł��Ȃ��̂ŁA������n�܂�܂ł�30���Ԃ̍u�`���s���A��͑�J���ɂ��肢������܂���ł����B
|
��S��t�G�������@1992�N6�� ��������{�H�Ƌ�y����ف@�Q����108�� �@�u�H�i�Y�Ƃ̏����ƌ����g�������v�i�H�i�������������{ �����j�A�u�������Z�p�̍��x�����ւ̉��p�v
�i������w�{�e ���l�j�B�u���������̖�����v�i�X�i����(��)�c��
�g���j�C�u�����ނ̌��O�h�߂ɂ�铧�ߗ����ቺ�ɂ��āv�i������(��)�@�_��
���M�j |
MRC News No. 9�@1992�N8�����s
�������u�����̂��߂̍ŏ��G�l���M�[�Ǝ��ۂɕK�v�ȃG�l���M�[�v�i���s��w ����@����j
���������������@�ւ�����@�u��j�~�t�Z������p���������y�є��y�������̊J���v�i�������n�C�e�N�v���U��Îᏼ�Z�p�x���Z���^�[�@�ē�
�E�j�j�@�u�������ɂ��ʎ��A��̐���������єZ�k�����v �i�F�{���H�ƋZ�p�Z���^�[�|�@���V�� ��q�j
�����@�u�l�e���̌���ƍ���̓����v�i�x�m�ʐ^�t�B����(��)���� �Ɂj �u�����E���ٍH�Ƃւ̖����p�v�i�������ه� ����k����H�i����������
�������q�j
���ۉ�c�� �u��T�� �k�Ė��w��ɎQ�����āv�i������w �R�� �҉��j
|
��S��H�G�������i���q�s�j1992�N12�� ��B�����N����� �Q����134�� �@��b�u���F��P��u�����p�Z�p�̊�b�Ɖ��p�v�n�ӓ֕v�E��J�q�Y �@�u��j�~���t�Z�������p�ɂ�鍂�Z�x�Z�k�ƃI���S���ނ̕����v�i�H�i�����������@��J�_�u�j�A�u�������ۑ̔|�{�t�̃N���X�t���[�h�߁v�i���R��w�@������O�E�c���F���j�B�u�Éĉʏ`�̖��ɂ�鐴��������ђE�_�v�i�F�{���H�ƋZ�p�Z���^�[
���V���q�j�C�u�T�c�}�C���A���g�V�A�j���F�f�̔Z�k�E�����v�i���������_�Y�����H�����w���Z���^�[�@����������j�D�u���Z�p�𗘗p�������x�s�O�a���b�_�̕����E�����v�i�����d�H��
�����T�q�j�E�u�Z���~�b�N���ɂ�����h�߁v�i���{�~���|�A���~�e�b�h�� �M�ؓO�j�F�u�H�i�����p���G�������g�̏Љ�v�i�������@�R���O�V�j�G�u�A���R�[�����������ւ̖����p�v�i�����I���K�m�������@�����u�Y�j�H�u�ʏ`�H�Ƃւ̖����p�v�i�_�C�Z�����w�H�Ƈ��@�Ɋ֗T�i�j |
MRC News No. 10�@1993�N1�����s
���W �|������S���ŐV�@�\���E���W���[���|
1.�n�}�n���@1.1 ���� �i������w�����^��j 1.2 �e�Ђ̖� ���{�~���|�A�� �����d�H�� �����Y�Ƈ�(Sepracor)
2.�דd��2.1 ���� �i�Z�F�x�[�N���C�g�� �ɓ��_�u �j�i�����d�H�� �r�c���� �j 2.2 �e�Ђ̖� �����d�H �� �Z�F�x�[�N���C�g��
�����@�퇊 3.�A�t�B�j�e�B�[�� ���{�~���|�A���@4.��]�^���E���W���[��4.1 ����i�I���K�m�_�ۏ��K�j 4.2 �e�Ђ̖�
�����v�����g���݇� ���{�K�C�V�� �I���K�m�� �_�|�p���e�b�N�� ���j�e�b�N��
ABB Water Filtration Aqua
Technology 5.�p�[�x�[�p���[�V������5.1 ���� �i�_�C�Z�����w �Ã��J�m�j 5.2 �e�Ђ̖� �_�C�Z�����w�H�Ƈ� ���N���� ���R���B�� �F�����Y��6.�����E�Z�Ќ^���E���W���[��6.1 ���� �i�����d�H���r�j�j
6.2 �e�Ђ̖� �v�ۓc�� �O�H���C������7�D�E�C���E���W���[�� 7.1 ���� �i�O�Y�H�Ɩ{�c���v�j
7.2 �e�Ђ̖� �_�C�Z�����w�H�Ƈ� �O�Y�H�Ƈ� ������ 8.�זE�|�{���E���W���[��8.1 ���� �i�}�g�叼�������j 8.2 �e�Ђ̖�
�����f�B�J���� ���Z���g�����Ȋw�f��
����A���R�|���s�n���Ō`������@�ɂ�铧���ʏ`�̕]�� �i�Ó썁���� ��� �݁j
3.5�@1993�N�x
�@��T��t�G�������́A�l�q�b�ݗ��T���N���L�O���ĕč��C���m�C��w�̃`�F���A�����ƃX�F�[�f���������g��w�̃f�W�}�b�N�������҂����L�Ɏ������u������s���܂����B�l�q�b��ݗ����������l�q�b�ɂS�O�Ђ��Q�����Ă����ΐH�����Ɏ���������l�ق����Ƃ�����^�c���Ă�����ł��낤�A�܂��A���Ȃ��Ƃ��l�q�b�j���[�X����i�P�O���j�܂ŏo�ł��悤�Ɩ�����Řb�������Ĕ��������l�q�b�������̂����ɂT���N�܂ʼn^�c�ł������Ƃ��ϊ����������܂����B
�@��T��̏H�G�������͓��k��w�̐V�䎁�A�Ė{������ы{�錧�H�ƋZ�p�Z���^�[�̗�؎��̂��s�͂ɂ����ŊJ�Â����Ă��������܂����B���k�n���̑����̌��ɋ��^���������A�n���̑����̕��̎Q����Ղ��܂����B
�l�q�b�j���[�X�Ɋւ��ẮA�P�P�����猤�����̍u���v�|�ɉ��M�C���������A�������ɎQ���ł��Ȃ��������X�ւ̏��ƍu�����e���L�^�Ɏc�����Ƃ�ړI�ɂl�q�b�j���[�X�Ɍf�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B�]���āA�{�e�ł͌������̔��\���ڂɂ��Ė{���͂l�q�b�j���[�X�Ɍf�ڂ���Ă��鍀�ڂ��A�e�L�X�g�{�b�N�X���̌������Ɉڂ��Ă��܂��Ă��镔�������邱�Ƃ��������������������ƍl���܂��B
|
��T��t�G�������@1993�N5�� �����A���{�H�Ƌ�y����� �Q����82�� �@ �ؑ����j�i������w�j�|Progress of Membranes and Membrane Processes�| �A�n�ӓ֕v�i�����@�퇊�j�|Membrane Applications in Japanese Food Industry �BProf. M.Cheryan�iUniv. of Illinois �č��j�|Corn Refining in USA �CProf. P.Dejmek�iLund Univ. ������݁j�|Food application of
membrane technology in Europe�| |
MRC News No. 11�@1993�N8�����s
�������u���H�Ɖ�̐ݗ���]�ށv
�i���l������w�H�w�������H�w�ȑ��F�j
���������������@�ւ�����u���O��ߖ��ɂ�鐶���̏����v�i���H�ƋZ�p�Z���^�[���J�����j
|
��T��H�G�������i���s�j1993�N11�� ܼ�����ف@�Q����109�� ���ÁF�i���j���k�Y�ƋZ�p�J������E���k�n�扻�w�H�w���b�� ���^�F�{�錧�H�i�H�Ƌ��c��E�������H�i�U���v���U�E��茧�H�i���H������E�������H�i���c�� �㉇�F�{�錧���x�Z�p�U�����c�@ �@�u�`���������o�C�I���A�N�^�[�ɂ����閌���p�v�i���k��w�_�w���R�����j�j�A�u�哤�z�G�[����̃��A�~���[�[�̉���v�i���a�Y�Ƈ��쑺��Y�j�B�u�Z���~�b�N�h�ނ�p�����ݖ��̌]���y�h�߁v(���m���H�i�H�ƋZ�p�Z���^�[ �ēc���l�j�C�u�ʏ`�H�Ƃɂ����閌���p�v�i�J�S�����R�c�N���j�D�u���Ƃɂ����閌�h�߁v �i�č��Filtration Engineering Co., Inc Todd Nelson�j�E�u���k�r�h�����ɂ�����E���g���N���[���Z�p�Ɩ������Z�p�̖����v�i���k��w�H�w���匩���O�j�F�u�o�C�I�v���_�N�g����̒E���v�i���k��w�H�w�������a�v�j�G�u���Y���H�ɂ����閌���p�v�i���n�`�e�C���c�q�v�j�H�u�����Z�p�ƒ��ՊE���̋Z�p�v�i���k��w�H�w���V��M�v�j |
MRC News No. 12�@1994�N1�����s
�������u���E���W���[�����W�������̊��s�ɂ������āv�i�H�i���Z�p���k���\�����@������w�_�w���E�{�e���l�j
1���Ɏq��2�������H�Ƈ� 3�_�C�Z�����w�H�Ƈ� 4���C�Y�~�t�[�h�}�V�i�� 5�x�m�t�B���^�[�H�Ƈ� 6�x�m�ʐ^�t�C������ 7�Q���}���T�C�G���X�W���p���� 8�N������
9�O��Ζ����w�H�Ƈ� 10�O�䓌���@�H�� 11�O�H���C������ 12�X�i�G���W�j�A�����O�� 13�����d�H�� 14���{�K�C�V�� 15���{������16���{�~���|�A���~�e�b�h��17�O�H���C�����E�G���W�j�A�����O��18�I���K�m��19�����@�퇊20���m�a�ч�
21���m�h���� 22������ 23���R���B�� 24�F�����Y��25���A�T�E�R�[�|���[�V������
3.6�@1994�N�x
�@���Z�p�𗘗p�����V�H�i�����X�Ɣ������ꂽ���Ƃ��A�l�q�b�j���[�X�P�S���ł͖����g�������i���W���g�܂�Ă��܂��B��U��H�G�������́A���m���̌������ɂ���ꂽ�ēc���A���É���̔��ː搶��̂��s�͂ɂ�薼�É��s�ŊJ�Â����Ă��������P�V�W���̎Q���邱�Ƃ��ł��܂����B���̎Q���ҋL�^���l�q�b�̌������ł͍ō��L�^�ƂȂ��Ă��܂��B
|
��U��t�G�������@�@1994�N5���@�����A���ۉ�� �Q����94�� �@�u���@�\�̌���ƓW�]�|���@���ɂ��t�̕����𒆐S�Ƃ��āv�i������w�H�w���s�������j�A�u�H�i���H�ɂ����閌�����Z�p�̌���ƓW�]�v�i�X�i���Ƈ����S�O�j�B�u�n�C�u���b�h���v���Z�X�̌���ƓW�]�v�i���l������w�H�w�����{�����j�C�u�H�i�H�Ƃɂ����閌���p�̌���ƓW�]�v�i�L�b�R�[�}�����Ð�r�v�j
|
MRC News No. 13�@1994�N9�����s
������ �u�����p�̍L����ւ̊��ҁv
�i������w�_�w���@�������O�j
���������������@�ւ�����@ �u�������ɂ��E�X�^�[�\�[�X�̓����������v�i�����s���H�i�Z�p�Z���^�[�@�O�}�O��j
���ۉ�c���u��U��k�Ė��w��ɎQ�����āv�i�_���� �H�i�����������@�쏟�F���j
�����@�u�H�i���H�ɂ����閌�Z�p�v�i������w�_�w�� �{�e���l�E�_���ȐH�i���������� �������q�j�u���@�������ɂ��t�̌n�����̌���v�i�_���Ȕ_�ƍH�w������
��J�q�Y�j
|
��U��H�G�������i���É��s�j1994�N12�� ���É��A���m�����N����� �Q����178�� �@�u�z���[�t�@�C�o�[���p�ɂ��|�_���y�̌������v�i������w���q�זE�����w������
�˓c�@���j�A�u�~�N�������H�̔����H�ƌ��t�זE���̒ʉ߂̉����ƌv���v�i�_���ȐH�i�����������@�e�r�S��j�B�u���h�߂ɂ������h�߃P�[�N�̖����v �i���É���w�H�w���@���J�p�i�j�C�u�H�i����ɂ�����Z���~�b�N���̉��p�v
�i�m�f�j�t�B���e�b�N���e�c���G�j�D�u�哤�I���S�������ɂ����閌���p�̎��ہv�i�J���s�X�H�i�H�Ƈ����z���j�E�u���Ƃւ̃i�m�h�ߋZ�p�̉��p�v�i�������Ƈ��v�Đm�i�j�F�u�������̔|�{�Ɩ������v�i���É���w�H�w�����іҁj�G�u���^�o�C�I���A�N�^�[�ɂ��y�f�̐��Y�v�i
�É����É��H�ƋZ�p�Z���^�[���{�L�j�H�u�ݖ��̖��h�߂̎��ہv�i�������������c���v�A�X���N�j |
MRC News No. 14�@1995�N2�����s
�������u�؍����w��ɎQ�����Ďv�����Ɓv
�i���l������w�H�w�����{�����j
�����W�@�|�����g�������i�|�@�i�\�����j �P�D���̑f�������
�Q�D�J�S��������� �R�D������Љ������I���{�� �S�D�������Ɗ������ �T�D�_�C�Z���E�����u�����E�V�X�e���Y������� �U�D��a����������� �V�D�X�i���Ɗ������
�W�D�����Ɗ������ �X�D�l�q�b�ҏW��
���������������@�ւ�����@�u�d�C���͂ɂ�邵�炷�Ϗ`�E�~�������p�t����̗L�������̉���v�i�a�̎R���H�ƋZ�p�Z���^�[���������j
3.7�@1995�N�x
�@��Q��t�G�������ɂ����ẮA�t�Z���E���O�h�ߒ��ԗ̈�Ƃ���Ă�������͈͂́A��V��ł̓i�m�t�B���g���[�V�����Ƃ���A�i�m�h�߁iNF�j�Ƃ������t����ʓI�ɗ��p�����悤�ɂȂ��Ă������Ƃ�������܂��B
��V��H�G�������́A�L�b�R�[�}���̌Ð쎁�̂��s�͂ɂ���c�s�̗�����i�����Y�ƌ�������{�ő勉�̐�j�߂��̃z�e���ŊJ�Â���A�L�b�R�[�}���̎Ј��̕��X�̗]������������ςɂ��₩�Ȍ��������J�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B�@
�@��������������������~�l�����������Ɉ�ʓI�ɗ��p�����悤�ɂȂ�AMRC�j���[�X�P�U���ł͖��Ɛ��Ƃ������W���g�܂�Ă��܂��B
|
��V��t�G�������@�@1995�N5���@
�����A���ۉ�ف@�Q����76���@�@ �@�u���Z�p�̗��j�I���ڂƍ���̌����J���̂�����v�i����w��b�H�w���ؑ����j�j�A�u�T�C�N���f�L�X�g�����Ɩ������i�����_�H��w�H�w������F�Y�A�c���\�j�j�B�u�������𗘗p�������o�Z���T�[�̐H�i�Y�Ƃւ̉��p�v�i��B��w�H�w���s�b���j�C�u�i�m�t�B���g���[�V�����̐H�i�����ւ̉��p�v
�i�����Ƈ��_�����M�j |
MRC News No. 15�@1995�N8�����s
������ �u�����������ƋZ�p�ɂ��Ďv�����Ɓv�i�����H�Ƒ�w�������H�w���@�C�씣�j
���������������@�ւ�����@�@�u���������H�����畛������哤�Ϗ`���̃I���S���̋t�Z���Z�k�v�i���쌧���y�H�i������@�����ېm�j
���ۉ�c���@�u��V��k�Ė��w��ɎQ�����āv�i�_���ȐH�i�����������@�쏟�F���j
���� �u�؍��ɂ����閌����v�i���l������w�H�w���@���{�����A�\�E����w�V�R�@�ۊw�ȑ�ו��j
|
��V��H�G�������i���s�j1995�N11���@��c�s�A�`�T���z�e���嗘���@�Q����139���@ �@�u�H�i����ɂ�����P�����g���b�N�X��@�̉��p�v�����c�Y�i�L�b�R�[�}�����j�A�u���ɂ��^���p�N���̍��x�����v�֓�����i��t��w�H�w���j�B�u�ʏ`�Y�Ƃɂ�����d�C���͖@�̉��p�v���c�p���i�����w����w��w�@�h�{�Ȋw�����ȁj�C�u���ɂ��_�Y���̍��t�����l���v��J�_�u�i�_���ȐH�i�����������j�D�u�g���n���[�X�����A�����ɂ����閌���p�v
�g�샆�~�i���l������w�H�w���j�E�u�t�e���ɂ��H�i�H�ƌ������̐����v������N�i�������H�Ƈ��j�F�u�H�i�Y�Ƃŗp�����閌���u�̐��ƎE�ہv�c�Ӓ��T�i�w���P���������j�G�u���Z�p�J���̍Ő�[�v
�a������i�H�Z�@�����H�w�H�ƋZ�p�������j�H�u�Z���~�b�N���ɂ��ݖ��Γ���I�������v�c��G�j�i�q�Q�^�ݖ����j�I �u���ɂ��W�F�E�X�^�[�\�[�X�̐����v �O�}�O��i�����s���H�i�Z�p�Z���^�[�j |
MRC News No. 16�@1996�N1�����s
������ �u���̌����̃O���[�o���ȓW�J�Ɋ��҂���v�i������w�H�w�n�����ȌÍ�V���Y�j
���ۉ�c�� �u���B���w��(95)�ɎQ�����āv�i�_���ȐH�i�����������@�쏟�F���j
���������������@�ւ�����u���O��ߖ@��p�����ĕ����������t�̐����v�i��ʌ��H�i�H�Ǝ����ꉜ��m���j
���𗘗p�������������W �u���Ɛ��v �u�`�����������������v�i���G���W�j�A�����O���j �u�����p�^�V�Z�p�̊J���v�i�������O�q���@ ����͈�E������E�ɓ����j �u�����p�����W���[���y�уV�X�e���̊J���v �i�_�C�Z���E�����u�����E�V�X�e���Y���j�u�����p�^�������u�v�i�f�B�b�N�f�O���������j�u�����������Ɏg�p����閌�G�������g�v�i�����������u�������ƕ��j
�u�����ƒ�p��g�g���r�[�m�h�v�i�������g���r�[�m���ƕ��j �u���ሳ�q�n�����e�X�g�@�F�d-100�v�i�����d�H���j �u�������������u�g�l�h�k�k�h�@�q�w�h�v�i���{�~���|�A���j�u�H�i�H��r���̍ė��p�V�X�e���v�i���{�B�����j�u�~�l�����E�H�[�^�[�����ւ̐����h�ߖ��̉��p�v�i�n�E�X�H�i�H�Ƈ��j
�u�����������̉Ȋw�v�i�L���d�@��w���X�،��j�u�H�i�����p�E�C���u�w�y�O�B�W�B�x�v�i���O�Y�������j �u�t�Z�����𗘗p�����C���W�����ݔ��v �i�O�H�d�H�Ƈ��j�u�H�i�H����A�������V�X�e���ɂ��āv�i�O�H���C�������j�u�t�Z������p���������������@�v�i�X�i�G���W�j�A�����O���j
3.8�@1996�N�x
�@1996�N4���ɕM�҂͐V����w����̗v���ɉ����āA����w��w�@���R�Ȋw�����Ȃ̋����Ƃ��ĐV���ɕ��C���܂����B�����ɂ����Ă̓Z���~�b�N�����W���[�������i�����A����ɖ����p�^���̌����J���������ɐi�ߐ������Ɛ��i���𗧂��グ�啪���ŏ��̌���̔����n�߂�ȂǁA�قڎ��̂���ׂ����Ƃ��I������i�K�ƍl���Ă��܂����̂Ŏ��ɂƂ��Ă͑�ϗǂ��^�C�~���O�ł������ƍl���Ă��܂��B���{�̉�Ђł͈�ʓI�Ȃ̂�������܂��A�V�K���ƂɊւ��Ă͐��i�h�Ɣ��Δh������A������Ō��肵���͂��̂��Ƃ��b������ƕ�����邱�Ƃ��x�X�Ŏ��ƈꏏ�Ɏd�������Ă���Ă����l�ɂ͎��̑ގЂŗ͊W���ω����Ă��܂����f�������Ă��܂����̂ł͂Ȃ����ƌ��O���Ă��܂��B
�l�q�b��W��H�G�������͂Q�N�����̊֓��ł̊J�ÂƂȂ�܂������A���l������̏��{���Ɖ������I���̈ɓ����̂��s�͂ɂ�艡�l�s�ŊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@MRC�j���[�X18���������u�̃����e�i���X�Ɋւ�����W���g�܂�Ă���A�H�i�Y�Ƃł̖����p�ɂ�����傫�ȏ�Q�ƂȂ��Ă������u���̉q���Ǘ��Ɋւ��ėL���ȉ�^�������̂ƍl���Ă��܂��B
|
��W��t�G��������@1996�N5���@�����A���ۉ�ف@�Q����77�� �@�u���E�̍ŐV������ƍ���̖������J���̓W�J�v�����^��i������w�H�w�n�����ȁj�A�u���͂Ɩ������v�ѐA�G���i�c��`�m��w���H�w���j�B�u�������Z�p�ƐH�i�G�}���V�����ւ̉��p�v
��؊���i�L����w�������Y�w���j�C�u�r�W�l�X���猩�����Z�p�̔��W�v �͑��a�F�i�O�W����j |
MRC News No. 17�@1996�N7�����s
�������u���@�\�Ɛ����v ���c�ĎO�i���m�H�Ƒ�w��b����n�����H�w�j 1
���������������@�ւ���� �u�Β��̋t�Z���Z�k�v ���ї����i�É������Ǝ�����j
�����@�u�o�C�I�Z�p���[�V�����ɂ����閌�����v �@���{�����i���l������w�H�w���j �Ę^�@�u��y�f�̍Đ��������u�����o�C�I���A�N�^�[�v�{�e���l�i������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȁj
���ۖ���c(ICOM'96)�v���r���[
�������q�i�_���ȐH�i�����������j
|
��W��H�G������� �i���l�s�j1996�N11�����l�A�z���f�B�E�C�����l�Q����127���@ �@�u���͉������Ă����A���ꂩ�牽������̂��v ���F�i���l������w�j�A�u���Ƃւ̖����p�v�y�c�@��i�X�i���Ƈ��j�B�u�P�C�\�E�y�h�߂ƍ���̓W�J�v�p�����i���a���w�H�Ƈ��j�C�u���ɂ��^���p�N�����݂̍��x�����v�M�ؓO�i���{�~���|�A���j�D�u�������v���Z�X�̉^�]�Ǘ��v���{�����i���l������w�j�E�u�H�i���H�̖����Ɩ��̖����v��J�V��i����w�j�F�u�����p�V�X�e���̎��p���̔錍�v�ɓ��V���i���������I���{�܁j�G�u�t�Z���@�ɂ���ʏ`�̔Z�k�v
�|�����F�i(��)���쌧�_���H�ƌ������j�H�u���y�H�i�����ɂ����閌���p�ɂ��āv����m���i��ʌ��H�i�H�Ǝ�����j�I �u�p�[���J���`���}�C�N���J�v�Z���̊J���Ɠ����v�ԏ���i���C�I�����j |
MRC News No. 18�@1997�N2�����s
�������@�u���Z�p�Ƃ̐G�ꍇ���Ƃl�q�b�ւ̊��ҁv�ؑ�
�i�i�i�Ёj���{�p���Z�p�������j
�h�b�n�l�f�X�U�� �쏟�F���i���k��w�j
���������������@�֕ւ��u�L�N�C���I���S���̃i�m�t�B���g���[�V�����v �Y�씎���i���R���H�ƋZ�p�Z���^�[�j
�|���W�u�����u�̃����e�i���X�v�|�u�����u�̃t�@�E�����O�̃��J�j�Y���Ɛ��̊�b�v
������O�E��R�����i���R��j�u�����u�̃����e�i���X�v�|�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g�����ʘ_���W�ɂ݂�|�_�����M�i�R��������w�j�u�������u�̐��ƎE�ۂɊւ���l�@�v�c�Ӓ��T�i�w���P���W���p�����j�u�������W���[���̖���ߗ����ێ��Ɩ�i���v�F���a�v�i�_�C�Z���E�����u�����E�V�X�e���Y���j�u�H�i�p���������u�̐v�ƊǗ��v���쎟�Y�i�������H�Ƈ��j�u�����u�̃����e�i���X�v���c�����i�����d�H���j�u�����u�̃����e�i���X�v�M�ؓO�i���{�~���|�A���j�u�����̋t�Z�����G�������g�Ɩ����u�̃g���u���V���[�e�B���O�v
�|���O�i�������j�u������p�����h�ߋZ�p�y�і��E�����u�̎�舵���ɂ��āv���X�Ď��i���N�����j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\����i1997�N5���`20001�N�S���j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
3.9�@1997�N�x
�ؑ����j�搶������w���N�ފ��ɂȂ邱�Ƃ��ĉ��l������̑��F�搶����ɏA�C����܂����B
��X��t�G�������͖��w��Ƃ̋����J�Â̌`��������̂ŁA�Q���҂�175���Ɩ��É��̑�U��H�G�������ɔ��鐔�ɂȂ��Ă��܂����A���w��ƐH�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p���p�Ƃ̐ړ_�͋ɂ߂ď��Ȃ��w��Ƃ̋����J�Â��ǂ�قǂ̈Ӗ������������̕]���͓���Ƃ���ł��B�l�q�b�͊w��Ƃ͈�����悷������ł�����p�Z�p�Ƃ��Ă̌����J���A���y���ړI�ł��̂ŕ������܂�g���Ă͂����Ȃ����A�^�c�͂Ȃ��Ȃ�����Ƃ���ł��B
��X��H�G�������́A����ɈڐЂ���Ă�������l�q�b��̖ؑ��搶�̒�N�ފ�
�Ƃ̊W������A���n��̖����[�J�[�ł���_�C�Z���̒������A�����d�H�̐�莁�̌䋦�͂ő��ŊJ�Â����Ă��������܂����B���ł̊J�Â͂��ꂪ�Q��ڂł��B�ؑ��搶�͎�����蓖���u���ɗ����Ȃ������̂ŁA�ؑ��搶�̋����q�ł������̉@���i�C�m�ے��j������ɍu�����܂������A���̍u���́A���e�͖ܘ_�Ƃ��đ�ϗ������������h�Ȃ��̂ł����B
|
��X��t�G�������@1997�N5�� ���A�H�Z�@�}�g�����Z���^�[���p�u���Q���ҁ@175���@�@�@���{���w��Ƃ̋����J���i�u�����e�͖��w��Ɍf�ځj �@�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j�|���Z�p�J���ɂ�����Y�E���E�w�̓����Ɩ����|�A�Ð�r�v�i�L�b�R�[�}�����j�|�����Ƃւ̖������Z�p�̓W�J�|�B��J�_�u�i�_���ȐH�����j�|�����\�ւ̃t�@�E�����O�����ƐZ�����̉e���|�C���r�j�i�����d�H���j�|�œK�H�i���V�X�e���u�Ő�[�̒��ሳ�q�n���ƃ��W���[���̌���|�D�_�����M�i�R��������w�j�|�����u�̉^�]�Ǘ��V�X�e���| |
MRC News No. 19�@1997�N8�����s
������ �u�H�i���Z�p���k��̊����q�����āv�@�����r�v�@�i�����H�Ƒ�w�j
���������������@�ւ�����u�H�i�����������E���������H�w�������̌����T�v�v�������q�A��J�_�u
�����@�u���S�x���H�i�p�����W���[���̎��p�ƊJ�������v�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j�u���Z�p��p�����V�R�����̉��H�v�������q�E�ۓc���O�E��J�_�u �i�_�ѐ��Y�ȐH�i�����������E�}�g��w��w�@�j���ۉ�c��
�u��X��k�Ė��w��ɎQ�����āv�쏟�F���i���k��w�j
|
��X��H�G�������@1997�N11���@��㍑�ی𗬃Z���^�[ �Q����123�� �@�ؑ����j�i����w�j�t�Z���@�ɂ�鐅���̔��ʐ����̏����A�������Y�i�_�ˑ�w�j���x�����ɂ����閌�ƃN���}�g�O���t�B�[�B���R���i���s���H�ƌ������j�H�i�H�Ƃɂ����閌���p�C�䑺���l�i���̑f�[�l�����t�[�d���j�R�[�q�[�Z�k�ւ̖��̗��p
�D���썂�j�i�������H�Ƈ��j���O�h�߂ɂ����{���̐��� �E�͓c�ƗY�i���s��w�j�����ł̋z���@�\�Ɣ얞�̃R���g���[�� �F�����ېm�i���쌧���y�H�i������j�t�Z���E�i�m�h�ߖ��ɂ��哤�I���S���̉���ƐZ�������f���ɂ�铧�ߗ����̗\��
�G���c��M�i�_�|�p���e�b�N���j�U���^���������u�̓����ƓK�p�� �G�Ɋ֗S�i�i�_�C�Z�������u�����V�X�e���Y���j�H�i�H�Ƃł̖��������̗��p�H���X�ؕ��i�����d�H���j�V������t�@�E�����O���q�n���I�n��N�v�i�����G���W�j�A�����O���j�������Z�p�ƐH�i��b�u���F��U��u�H�i���Z�p�̊�b�Ɖ��p�v |
MRC News No. 20 1998�N1�����s
������ �u�����p�H�i�̒a�������҂���v
���F�i���l������w�j
�������Љ� �u���l������w�H�w�����{�������v���{�����i���l������w�j
�����u�����A�N�^�[��p���������̍y�f�I�����v��� �������q�E�ۓc���O�E��J�_�u �i�_���ȐH�i�����������E�}�g��w�j
���E���W���[�����W��1. �������H�Ƈ� 2. ���Ɏq��3. �����H�@��4. ���C�Y�~�t�[�h�}�V�i��5.
�F�����Y��6. �I���K�m��7. ���{�S�H��8. ���N����9. �U���g���E�X��10. �_�|�p���e�b�N��11. �_�C�Z���E�����u�����E�V�X�e���Y��12. ���m�a�ч�13.
���m�h����14. �����d�H��15. ���{�A�u�R�[��16. ���{�~���|�A��17. �O�䓌���@�H��18. �O�H���C������19. �X�i�G���W�j�A�����O��20. ���b�g�}���W���p����
���ۉ�c�� �u��S��A�W�A�����m�������w�H�w��c�v �s��n��i�}�g��w�j
3.10�@1998�N�x
�@���̔N�ŁA�l�q�b�͐ݗ��P�O���N���}���l�q�b�j���[�X�ɂP�O���N�L�O���W��g��ł��܂��B�܂��A�P�O���N�L�O���ƂƂ��ĐH�i���Z�p�̖{���o�ł��邱�Ƃɂ��A�M�҂��ҏW�ψ����̖��������܂����B����́A�M�҂������@��ɈڐЂ���O�ɖ{�̏o�ł��l�����Ȃ�̒i�K�܂Ŋ���i�߂Ă����̂ŁA������x�[�X�Ɋ�揑���܂Ƃ߂邱�Ƃ��l�������߂ł��B�ҏW�ψ��̕��X�ɂ́A�x���𗘗p���ĕҏW�ψ���ɎQ�����Ă��������A���N��1999�N9��30���ɖ����o�ł��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@��P�O��H�G�������͐V���s�ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ�A�V�����H�i�Y�Ƌ���ƐV�����H�i�������ɋ��͂����肢�����Ƃ���A��я������V�����H�i�����p�Z�p�������ݗ����ĉ�����A��10��̌������ɋ��͂��Ă�����������̓��ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B��������͂��̌�V�����H�i�Z�p������iFood
Research Circle in Niigata,����FC�V���j�Ɩ��̕ύX�����݂������Ȋ����𑱂��Ă��܂��B
�@�l�q�b�ݗ����ɂ����閌�����g����_���ȂƂ̐ՂɊւ��ẮA�l�q�b�j���[�X21���ɏڂ����L�ڂ��Ă������̂ł���������K�ł��B
|
�l�q�b�ݗ��P�O���N�L�O���T����ё�P�O��t�G�������@ 1998�N5���@�����A���ۉ�ف@�Q����89�� �@���t�@�v�i�A�T�q�r�[�����j�|�A�T�q�X�[�p�[�h���C����| �A�˒J�@���i�_���ȐH�i���ʋǁj�|�H�i�Y�ƋZ�p�Ƃ̊T�v�|
�B�Ί֒���i���l������w�j�|�H�i�E���i�̔������Ǘ��| �C�y�c�@��i�X�i���Ƈ��j�|���Z�p�ƐH�i�J���| �D�����ˍW�i�_�C�Z�����w�H�Ƈ��j�|�����W���[���̊J�������| |
MRC News No. 21 1998�N11�����s�@
�l�q�b�ݗ��P�O���N�L�O���W���|�P�O���N�ɂ悹�ā|
�u�H�i���Z�p���k��̂P�O���N�ɍۂ��āv�i�H�i���Z�p���k�����l������w���F�j�u����̖������̕����v�i���H�i���Z�p���k���H�w�@��w�H�w�������w�H�w�Ȗؑ����j�j�u�H�i���Z�p���k��ݗ��̂P�N�v�i���_���ȐH��������l�q�b��\�����V����w��w�@���R�Ȋw�����ȓn�ӓ֕v�j�u�P�O�N���ӂ肩�����āv�i�H�i���Z�p���k���X�i���Ƈ��h�{�Ȋw������
�c���g���j�uMRC�͓��{�̖��Z�p�̔��W�̂��߂ɔ@���Ɋ������ׂ����v�i�H�i���Z�p���k���\�������l������w�H�w���@���{�����j�uMRC�ւ̊��ҁv�i�H�Z�p���k���\����������w��w�@�_�w�����Ȋw������
�{�e���l�j�uFrom �v���Z�X�H�w to ���������H�w for MRC�v�i�H�i���Z�p���k���\�����_���ȐH�������������H�w������ �������q�j�u�V���������p�@�J���̖��v�i�H�i���Z�p���k��ږ⊔����АH�i�@�B�J���ēc���l�j�u���ɂ͖����̉\��������v�|MRC�P�O���N�ɑz���|�i�H�i���Z�p���k����R��������w�����Ȋw��
�_�����M�j�u�P�O�N���ӂ肩�����āv�|����ɂ��ĐH�i�̐V���i�ݑ�����l�E�Ó썁���� ��� �i���В��Ƃ̘b�|�i�H�i���Z�p���k���敔�ψ������d�H�����r�j�j�u�H�i���Z�p���k��Ǝ��ɂƂ��Ă̂P�O�N�v�i�H�i���Z�p���k����L�b�R�[�}�����Ð�r�v�j
|
��P�O��H�G�������@�i�V���s�j1998�N10���@�V���A���f�z�e���@�Q����131�� �@�u�r�o�f���Z�p�̊J���ƒn��Y�Ƃ̊������v�������v�i�{�茧�H�ƋZ�p�Z���^�[�j�A�u�����q���Z�p�̍ŋ߂̐i���Ɩ������Z�p�̓����v�c���^�l�i�V����w�j�B�u���ɂ�鐴���̐����v���ѓN�j�i�_�|�p���e�b�N���j�C�u���ɂ��H�i���H�p���̐����ƍė��p�v���F��i�I���K�m���j�D�u�����u�T�j�e�[�V�����̎��ہvRalf
Krack�i�c�Ӓ��T�j�i�w���P���E�G�R���{���j�E�u�\�ʉ���ƈՐ�̗��_�Ǝ��ہv�@����q�i�i���R���H�ƋZ�p�Z���^�[�j�F�u�i�m�h�ߖ��̕��������Ƃ��̉��p�v���v�ی���i�V����w�j�G�u�i�m�h�ߖ��ɂ�键�y�u���X�̒E�F�v���ؑד��i�I���G���^���y��H�Ƈ��j |
3.11�@1999�N�x
�@�O�q�����w�H�i���Z�p�\���Z�p���p�̎�����[�x���A�ҏW�ψ��Ǝ��M�҂̋��͂ɂ����Ԃ��疳���o�ł��邱�Ƃ��ł��܂����B600�y�[�W�ɔ���c��Ȗ{���A���Z�p�҂��l�ł��w���ł���悤�ɍl���A���Ԃ���7000�~�ŏo�ł��Ė�����̂́A300�����l�q�b���Ŕ���������������ł��B200���͂l�q�b���w��������ɂP���������Ŕz�z���܂����B100���́A�V�����H�i�����p�Z�p������̊����̕��X�Ƒ��k�������V�����ōw�����A�V�����H�i���Z�p������֘A�̕��X�Ƃ��̑����Z�p�֘A�̕��X�ɔz�z���܂����B
���傤�ǁA�o�ł��ꂽ9��30���͒�������A����������ł���A30���̒�����������i�b�n���E�����ɂ��픚�������N�������L�����ڂ��Ă��܂����B���q�͗��p�̊댯���̌���ł����A�m�荇���̕����i�b�n�̎В������Ă������ƂɃr�b�N�����܂����B�V���ł̑�10��H�G�������̌��w��ɂ����āA���芠�H�������d���̌��q�F�̏�ɂ܂ōs�����i�K�ŁA���q�͂͏�肭�g���Έ��S�Ȃ̂����m��Ȃ��ƌ��q�͗��p�ɑ�����҂��ꎞ�I�ɕ����܂����B�������A���N�̂��̏o�����ŁA�l�Ԃ̔\�͂ł͌��q�͎͂g�����Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�ƍl������Ȃ����ƂɂȂ�܂����B
�@��P�P��H�G�������́A�����w����w�̑��c�����������s�ŊJ�Â��Ă͂ǂ����ƒ�Ă��ĉ������܂����B�������ɂ́A�H��������̌��C���ł��������_�Y�����H�w���Z���^�[�����̔n�ꎁ�≺�����������A����ɓ��{�b���ɂ͂l�q�b�̊����ɋ��͂��������Ă����{�V����������̂ł��肢���悤�Ɖ]�����ƂŁA���c���ɓ��s���������Ɏf���J�Â����Ă��������邱�ƂɂȂ�܂����B���̌�A�n�ꎁ���d�a�ɂȂ��Ă��܂��A��i�ł��鏊���̎s�������������̒i���𐮂��ĉ������܂����B�m���̂��Ē��̍H��ɂ܂ʼn����ɘA��čs���Ă������������ƂȂǁA�s�����ɂ͑�ς����b�ɂȂ�܂������A���ɂƂ��Ă͊y�����v���o�ɂȂ��Ă��܂��B
|
���P�P��t�G�������@1999�N5���@�����A�S�і��ف@�Q����67�� �@�u�@�\�����̍ŋ߂̓W�J�v�R���҉��i������w�j�A�u���ɂ������̍ŋ߂̓����v���J�G�F�i(��)�����Z�p�����Z���^�[�j�B�u�g�}�g�̐������������A���R�s���̖��Z�k�v���c���v�i���{�f�������e�j�C�u�H�p�������H�ւ̖����p�v�������q�i�_���ȐH�i�����������j�D�u���������f���ɂ��H�i�@�\�̉�́v�ؑ��K�h�i���s��w�j |
MRC News No. 22 1999�N8�����s
�������@�u�f���v�������ƊE����v�����Ɓv�@
���x���O�Y�i�����H�@���j
�������Љ��u������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȁ@���p�������w��U�H�i�H�w�������v�{�e���l�i������w��w�@�j
�����@�u���E������p��������ƐH�i�ւ̉��p�v��؊���i�L����w�������Y�w���j�u�V�����ݖ������H���ւ̑����I�����p�̎��ԁv��c�`���i�������ݖ����������g���j
���ۉ�c���u��Q�T�ۉ��|�w��v��J�q�Y�i�_���ȐH�i�����������j
�u��X�O��č������w��N��ɎQ�����āv ��J�_�u�i�_���ȐH�i�����������j
�u���ۖ��w��iICOM'99�j�ɎQ�����āv�W�@�p�g�i�_���ȐH�i�����������j
|
��P�P��H�G�������@�i�������s�j1999�N11���@�������A��R��ف@�Q����103�� �@�u�ߔN�̖������Z�p�̓W�]�\���p���̌���Ə����\�v���r�j�i�����d�H���j�A�u�e�[�}�p�[�N�n�E�X�e���{�X�ɂ����鎩�R�Ƃ̋����z�Ɩ����p�Z�p�v���䕶�v�i�n�E�X�e���{�X�E�Z�p�Z���^�[���j�B�u�����u�����o�C�I���A�N�^�[�ɂ��H�i�H��̔r�������v
�R�c�C��i�X�i�G���W�j�A�����O���j�C�u�d�C���͂ɂ��Ђ����A�~�����̉��H�p�������v �R���M���i�������H�Ƈ��j�C�u�g�`�b�b�o�ɂ����郁���u�����t�B���^�[�i������ߖ��j��p���������������v
���i�L�u�v�i�U���g���E�X���j�D�u�������ɂ��~�l�����������Ƃg�`�b�b�o�̎��{��v ���c�O�Y�i�m�f�j�t�B���e�b�N���j�E�u�g�}�g���H�i�̖��Z�k�ɂ����鑕�u�̃����e�i���X�v
�����Y�i�J�S�����j�F�u���_���y�𒆐S�Ƃ���L�@�p�����[���G�~�b�V�����\�z�v����`�l�i��B�H�Ƒ�w�j�G�u�t�e����p�����������h�߁v �{����i�_�C�Z���E�����u�����E�V�X�e���Y���j |
MRC News No. 23 2000�N2�����s
�������ɑウ�āu�H�i���Z�p�E���ꂩ��̌����J�������v�@ �n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j
������������@�u������w��w�@�H�w�n�����ȁv �����^��E���H�m�[�i������w��w�@�j
�����@�u�E�ʑO�i�����Z�k�@�|�V���������Z�k�Z�p�v�{�e���l�i������w��w�@�j
�|�������Z�p���W�|�H�i�@�u��������ւ̋@�\���i���f���j�̓W�J�v�g�V���Y�i�I���K�m���j�u���H�i�ւ̉��p�\�Ȗ����u�̊J���v�ɓ��V���i���������I���{�܁j�uDead-end�h�߂�Cross-flow�h�߂̎g���������l����v
�Ð�r�v�i�L�b�R�[�}�����j�u�H�p�V�R�F�f�ւ̖������@�̗��p�v�s���l�i�O�h���G�t�E�G�t�E�A�C���j�u�l�d�l�a�q�`�k�n�w�Z���~�b�N�t�B���^�[�ɂ��āv�����G�a�i���ŃZ���~�b�N�X���j�u�U�������������u�̋@�\�Ƃ��̓K�p����v
�O�Y�m�Y�i���{�|�[�����j�u�������Z�p�𗘗p�����z�G�C�R���f�ނɂ��āv�@�c���g���E�a�c�P�F�i�X�i���Ƈ��j�u�����̐����h�ߏ��ۂ̌���v�������Y�i�X�i���Ƈ��j�H�i���H�p���@�u�t�e�E�l�e���ɂ�鐅�̏v���썂�j�E��������i�������H�Ƈ��j�u�H�i�H�Ƃ̗p�������ɂ����閌�̓K�p�v
�V�r�p�Y�i�m�f�j�t�B���e�b�N���j�u�����u�����t�B���^�[�@�ɂ�鐶�ې������菇�̊�b�����v �잊���m�i���{�~���|�A���j�H�i���H�p���u�U���^���������u�ɂ��p���y��|�{�p�t�̐������v�J�c���`�i�_�|�p���e�b�N���j
��P�P��H�G�������ȉ��1�D���Z�p�̊�b�Ɖ��p2�D�H�i���H�r�������̖��_�Ƒ�3�DHACCP�Ɩ�4�D�����u�̐��Ɖq���Ǘ�
3.12�@2000�N�x
��12��H�G�������́A�H�����v���Z�X�H�w�������̌��C���ŗ����Ă�����ʌ��H�ƋZ�p�Z���^�[�̉��Ɠ����_�H��̍��ᎁ�Ɉ˗����A��{�s�̃\�j�b�N�V�e�B�ŊJ�Â����Ă��������܂����B�M�҂͑S���e�n�ōu�������Ă��������Ă��܂������A���̎��̍u������ʌ��ł̏��߂ču���ł����B��ʌ��ł́A�H�i�H�w�Ɋւ���u����͂��܂�J����Ă��炸�A���������b�͓����ɏo�����ĕ����悢�ƍl�����Ă����̂ł��傤���B��ʓs���ƌ����铌���ɍł��߂���ʌ��̒u����Ă��闧�ꂪ������悤�Ɋ������܂����B�������A���̌�A�l�q�b�̍Â������������A�ŊJ�Â��A���E�����E�������̍u������s���Ă���A�H�i�H�w�֘A�̕�������ʌ��Ɏ�������ł��܂��B��ꂪ�����w����d�ԂłQ�T���A����w����k���P���ƕ֗��ł��邱�Ƃ���D�]�����������Ă��܂��B
|
���P�Q��t�G��������2000�N6���@�����A�S�і��ف@�Q����58�� �@�u�Y�ƊE���猩���u21���I�ɂ����閌�Z�p�����v�̂�����ɂ��āv���K�Y�i�J�S�����j�A�u���J���̐헪�v �I���@�D�i�������j�B�u�t�B�����ɂ�鍁�C�����̋z���v
���䗘�Y�i��B��w�j�C�u21���I�̖��Z�p�W�]�v�����^��i������w��w�@�j |
MRC News No. 24 2000�N9�����s
�������@�u�l�q�b�̂���Ȃ锭�W�����҂���v�����@�M�i�����w�������j
�������Љ��@�u�����_�H��w�@���ጤ�����v ����F�Y�i�����_�H��w�H�w�����w�V�X�e���H�w�ȁj
�����@�u�H�i���Z�p���p���̌���ƍ���̌����J���ۑ�v�\�H�i���Z�p�i�����ԁj�̏o�ł��I���ā\�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j
|
��P�Q��H�G�������u���W�i��{�s�j2000�N10���@��{�\�j�b�N�V�e�B�@�Q����113�� �@�u�@�\���H�i�̔��W�ƍ���̓W�]�v �����G���i��֑�w�E�Z����w���j�A�u�����\���ɂ��דd�𗘗p�����^���p�N���݂̕����v
�M�@�O�i���{�~���|�A���j�B�u�H�p�V�R�F�f�̖������@�v �؍G���i�O�h���G�t��G�t��A�C���j�C�u�d�C���͂ɂ�鉖����ؒЉt����̗L�p�����̉���v �k���p�O�i��ʌ��H�ƋZ�p�Z���^�[�j�D�u�����Z�k�Ɩ��Z�k�v
�{�e���l�i������w��w�@�j�E�u��]���̎��p����`��]�������W���[���̐H�i����ւ̓K�p�`�v �吼�^�l�i�����v�����g���݇��j�F�u�דd���U�C�N���̊J���Ƃ��̉��p�v
���ˑP���i��������H�Ƈ��j�G�u�U�������������u"�|�[���Z�b�v"�̓����Ǝ��p����v �R�c�N�V�i���{�|�[�����j�H�u�[���ړ��w���N���}�g�������u�̐H�i�����ւ̉��p�W�J�v
�����N���i�I���K�m���j�I�u�������ɂ��p���H�p�����̍Đ��v �{��@�~�i��t���H�Ǝ�����j�J�u�l�d�l�a�q�`�k�n�w�Z���~�b�N�t�B���^�[�ɂ�鏜�ۂƐ����ɂ��āv
�����G�a�i���ŃZ���~�b�N�X���j�K�u�V�����H�i�����p�Z�p�����̌���ƌ�����̊����v �n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j |
MRC News No. 25 �@�@�@2001�N2�����s
�������@�u�V�������E�����̖��Z�p�v
�R���҉��i������w��w�@�H�w�����ȁj
�������Љ��@�u�X�i���Ƈ��h�{�Ȋw�������H�i�J�����v�c���g���i�X�i���Ƈ��h�{�Ȋw�������j
�|���Z�p�̎��Ӌ@��ƃ��{�p�����u���W�|�z�Ǎ��^�C�Y�~�t�[�h�}�V�i�����A���X�_�t�@�C���e��
�o���u�^���t�W�L���@�������^���R���Y�ƃV�X�e���@���͌v�^���͓d�@���A���R���Y�ƃV�X�e���@���ʌv�^���͓d�@���A�������H���A���R���Y�ƃV�X�e���@�t�ʌv�^���m�[�P���A���͓d�@���A���R���Y�ƃV�X�e���@�Z�x�v�^�����f�B�[�P�[�P�[���@���x�v�^�Z���g�����Ȋw���@���x�v�E���x�v�^���H�@�������@���x�v�^�A�^�S���@���d���v�EpH�v�E���x�v�^���͓d�@���@���x�����^���͓d�@���A�����H�Ƈ��A����v�����@���x�v�^���͓d�@���A�����v�퇊�A���R���Y�ƃV�X�e���A�`�m�[���@�Z�����v�^���}�g�Ȋw���A�x�m�H�Ƈ��A���@�����@�M�������^�C�Y�~�t�[�h�}�V�i�����@���S�������@�^���{�~���|�A���@�e�X�g�p�����u�^���{�~���|�A�����A�{�K�C�V���E�m�f�j�t�B���e�b�N���A�U���g���E�X���A���Ɏq���A�_�|�p���e�b�N���A���i���e�b�N�A�C�Y�~�t�[�h�}�V�i�����A�T���R�[���@�����u�����^�G�R���{��
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�n�Ӊ(2001�N5���`����)�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
3.13�@2001�N�x
�@���l������̑��搶����N�ފ��̌���āA�M�҂���ɏA�C�v���܂����B��13��t�G�������͑��搶�̋L�O�u���u���Z�p�����R�O�N��U��Ԃ��āv�ŃX�^�[�g���܂����B�@�H�i�̈��S����肪�N���[�Y�A�b�v����Ă��鐢����āA�H�i�̈��S�����m�ۂ��邽�߂̋Z�p�𒆐S�ɍu�����s���܂����B
�@�H�G�������́A�H�����v���Z�X�������ɖ��Z�p�̌��C�ɗ����Ă������R���H�ƋZ�p�Z���^�[�����̏��ю��Ɖ��R��w�̒������ɂ��肢���ĉ��R�s�ŊJ�Â��Ă��������܂����B���̎��A�V����w��w�@�ɗ��w���Ă��Ă����E�C�O���_�Ƒ�w�������̃��t�}���������s���A������I��������A���R���g���H���̌��w�������đՂ��܂����B���̓����A�C�m�[�w�����u�[���ɂȂ��Ă���A�t�Z���Ɠd�C���͂���K�͂ɗ��p����A���m���ł͂��Ȃ�₩�Ɋ�����i�߂Ă��܂��������݂͂ǂ��̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł��傤���A�����̂���Ƃ���ł��B
|
���P�R��t�G�������@2001�N5��25�������@�S�і��ف@�@ �@�@�L�O�u���u���Z�p�����R�O�N��U��Ԃ��āv ���F�i���l������w�j�A�@��u���u�H�i�̈��S�����l����\�H�i�ڰтƌ���\HACCP�͖��\���H�v�r�����q�i�H�i���;����j�B�u���ۉ��h�ߋZ�p�̌���ƍ���̉ۑ�v
�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j�C�u�����u�̈��S���\�Z�k�p�t�Z�����u�̉q���Ǘ��𒆐S�Ƃ��ā\�v �����Y�i�J�S�����j |
MRC News No. 26 �@�@�@2001�N9�����s
�������u���w�H�w�ƐH�i�H�w�v�ɓ��@�́i�V����w�H�w���@���w�V�X�e���H�w�ȁj�@
�������Љ��u�J�S��������Б����������Љ�v�����Y�i�J�S�����@�����������j�@
����@�u�ŋ߂̖������H�w�|�~�j���r���[�|�v �ɓ��@�́i�V����w�H�w���@���w�V�X�e���H�w�ȁj
�|���vmini���W�@�|���v����u�H�i�ɂ����閌�Z�p�ƃ|���v�̖����v �R�c�C��i�X�i�G���W�j�A�����O���j�u�T�j�^���[�|���v�V�X�e���v
���C���L�u�T�j�^���[��ʃ|���v�v ���^�N�~�i�u�_�u���_�C�A�t�����|���v�v �l�i�G���W�j�A�����O(�L) �@
|
��P�R��H�G�������i���R�s�j2001�N11�����R���ی𗬃Z���^�[�@�Q����110�� |
MRC News No. 27 2002�N3�����s
�������u�H�i������݂��������Z�p�����̔��z�v���c�p���i�����w����w�H���h�{�w�ȁj
�������Љ��u�������ه��w���X�E�o�C�I�������Љ�v����k���i�������ه��w���X�E�o�C�I�������j
3.14�@2002�N�x
�@�l�q�b�j���[�X28���ɂ́A1982�N�ɖ������g�����ݗ�����Ă��疞20���N���}���܂����W���A�u�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g���̐ݗ�����20�N�v�̋L�O�L�����f�ڂ��Ă��܂��B
�@�C�m�[�w�������ڂ��W�߂�Ƃ���Ɋ֘A���鐅�̎s�ꂪ�h�����܂��B���Ẳ��ԊO���u�[���̎������ԊO���Z���~�b�N�X����˂���V�[�g�̏�ɐ���u���Ɛ��̃N���X�^�[���������Ȃ��Ė����ǂ��Ȃ�Ƃ�����Ȋw�I�ȏ�A���̉Ȋw�����L�`���ƌ����Ȃ��ŕ���}�X�R�~����킵�����Ƃ�����܂��B���������Ӗ�����A���̍\�������߂ĕ�����Ӗ��ŏt�G����������悵�܂����B�C�m�[�w���Ƃ́A�C�ʂ���200���[�g���Ȑ[�̊C���̂��ƂŁA�C�m�ŏ��ꂽ���ł�����s���������Ȃ��K�x�ȒE�������邱�Ƃɂ��~�l�������⋋�ł��A������D�ސl�����ނ��Ƃɂ͖�肪�Ȃ����̂ƍl�����܂��B
�@��14��H�G�������́A�V�����H�i�����p�Z�p������̋��͂ĐV���ŊJ�Â����Ă��������܂����B���n�ɂ����Ă��C�m�[�w���̒E���ɋt�Z���Ɠd�C���͑��u�����������̐������s���Ă���̂Ō�����̌��w��I��������A���n�D�D�ō��n�ɓn�肢�����̏h�ɔ��܂藂���C�m�[�w���̎搅��Ɩ����u�𒆐S�Ɍ��w�����Ă��������܂����B��B����u���ɂ����Œ�����⫓��搶���Q�����ĉ�����A�y�������w���s�ƂȂ�܂����B���쒬�̒����͂��ߑ����̕��X�ɑ�ς����b�ɂȂ�܂����B�w�C�͍r�C�A�������͍��n��x�Ǝ��ɉr���Ă���悤�ɁA���{�C��11���ɂ͂���ƊC���r��₷���A�A��̑D�������P�{�x���Ȃ��Ă���Ό��q�ƂȂ�A�\��ʂ�ɂ͖{�y�ɂ��ǂ蒅���Ȃ��ł����B
�������A�Q��������20���̕��X�͊F���n�c�A�[�i���ꂽ�悤�ŁA���������Â����������֎Q������y���݂̂ЂƂƍl�����܂��B���ԂƋ��ɁA���������̗F�B�����蓌���𗣂ꂽ���������J�Â���Ȃ茻�݂͐���łP�������̌������ɐ�ւ��Ă��܂����A�`�����X����蓌���𗣂ꂽ��������J�Â������ƍl���Ă��܂��B
|
��14��t�G�������u���W�@�S�і��ف@2002�N6���@�Q����51�� �@�u�V���ȏ���ҁE�H�i�Y�Ǝ{���(��)�_�ѐ��Y����Z�p�Z���^�[�̖����v�r�ˏd�M�i(��)�_�ѐ��Y����Z�p�����j�A�u���̃N���X�^�[�\���@�\��{�I�ȍl�����Ɖ��p�̉\���\�v���эF�a�i�k�C����w�j�B�u���ɂ�鐅�ƃA���R�[���̕����v�ɓ��́i�V����w�j�C�u�A�~�m�_�����ɂ����閌���p�v���c�N�Ɓi���E���̑f���j |
MRC News No. 28 2002�N10�����s�@
�������u�x�͘p�[�w���̂��ꂩ��v�{���@��v�i�É���w�H�w���j
�������Љ�u���̑f������Ё@���y�Z�p�������Љ�v�����@���i���̑f���@���y�Z�p�������j
��e�u�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g���̐ݗ�����20�N�v�n�ӓ֕v�i�H�i���Z�p���k��@��j
���W�E�s�̖��ꗗ�@�f�ږ����[�J�[�ꗗ�@�����h�߁i�l�e�j���C���O�h�߁i�t�e�j���C�i�m�h�߂���ыt�Z���i�m�e�E�q�n�j���C�C�I�������i�h�d�j��
|
��14��H�G�������i�V���s�Eexcursion ���n�j2002�N11�����f�z�e���Q����108�� �@�u�H�i�Y�ƋZ�p�Ƃ̕����v������i�_�ѐ��Y�ȁj�A�u���Z�p�ɂ��V�H�i�̑n���v���c�O�Y�iNGK�t�B���e�b�N�j�B�u���Z�p�ɂ��V�K���i�̑n�������Ɓ��v�c���g���C�V���m�u�i�X�i���Ɓj�C�u�i�m�h�߂ɂ��V�����H�i�f�ނ̊J���|��؉��H�ɂ����閌�Z�p�̎��p���|�v�����Y�C�Z�������i�J�S���j�D�u���a���^�������W���[���̏ݖ������H���ւ̓������ʁv�����K�V���i�����@��j�E�u�x�R���ɂ�����C�m�[�w�����p�̌���v��������i�x�R���E�H�i�������j�F�u�P���C�I���I�ߖ��ɂ��C�m�[�w���E���v���i�M�`�i���Ɏq�ݼ�Ʊ�ݸށj�G�u�H�i�@�B�Ƃ��Ă̖����u�̐��ƎE�ہv
�c�Ӓ��T�i�G�R���{�E�W���p���j�H�u���������̑���|����𒆐S�Ƃ��ā|�v⫓� �L�i��B���q��w�j�I�u���Ĕr���̍Đ�����T�C�N���Z�p�̊J���v�Љ������i�����܂H�i�j�J�u���ɍב@���h�z�ɂ��ݖ����떡�̈����h�߁v�����G��i�R������j�K�u�H��p������������ɂ����閌�Z�p���p�v���㗘���i�����j��14��H�G��������b�u���u�H�i���Z�p�̊�b�Ɖ��p�v�������i���̑f�j�u�H�i�@�B������u�̃T�j�^���[���v�吼���r�i�X�i���Ɓj |
MRC News No. 29 2003�N3�����s
�������u���[�U�[������̌��������Z�p�v�_�����M�i�R��������w�����Ȋw���h�{�w�ȁj
�������Љ��u�G�R���{������� �W���p���e�N�j�J���Z���^�[�Љ�v�c�Ӓ��T�i�G�R���{���j
��e�@�u�玙�p�~���N�J���Ɩ������Z�p�Ɍg����āv�c���g���i�X�i���Ƈ��j
3.15�@2003�N�x
�@�l�q�b���_����ł���R��������w�̐_�����i���E�����Ɓj����w��ސE���邱�̂��ƂŁA���������Z�p�ɍ��߂�v���̔M�����w���Z�p27�N�|���ɂ͖����̉\��������|�x�Ƒ肵�ču�����Ă��������܂����B
�l�q�b�j���[�X30���ł͂l�q�b�ݗ�15���N���L�O���ē��W������悵�܂����B���̒��ŁA���O��̏����Ă�����uSourirajan�Ɣ�Ώ̖��̔����܂Łv�͖��Z�p�̃p�C�I�j�A��������������e�ł��̂Ő���ēǂ������������ƍl���܂��B�����̕��X�ɂ����M���������܂������A�������������̎v���Ɏx�����H�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p���������Ă������Ƃ�������A���x���������������X�ɉ��߂Č������\���グ�܂��B
�@��15��H�G�������́A�É����H�ƋZ�p�Z���^�[�̏��{���A�y�쎁�A�É���w�̐{�������̌䋦�͂ɂ��É��s�ŊJ�Â����Ă��������܂����B�É����͍u���e�[�}�Ɍ���悤�ɁA�u�m�e���ɂ�钃���o�t���̃A�~�m�_�ƃJ�e�L���̕����v�u���Z�p�ɂ�鐅�Y�G�L�X����̋@�\���y�v�`�h�̊J���v�u�ĒÎs�ɂ�����x�͘p�[�w���̗����p�Ɍ�������g�݂ɂ��āv���̌������s���Ă��薌�Z�p�Ɋւ���A�N�e�B�r�e�B�[�̍������ł���l�q�b������������ł��B
���̔N�́A�M�҂����{�H�i�Ȋw�H�w��܂���܂��A����ɂl�q�b����ł���X�i���Ƃ̓c�����A�l�q�b�ɑ���ȍv�������������Ă���J�S���̐������w�����Ȋw��b�܉Ȋw�Z�p���J�ҕ\���x����܂���A�l�q�b�j���[�X30����31���Ɏ�܌����̏Љ�L�����f�ڂ����Ă��������܂����B
|
��15��t�G�������u���W�@2003�N6���S�і��ّ�z�[���@�@�Q����59�� �@�u�����S�ł���������������ڎw���āv�J���@���i(��)�����Z�p���������j�A�u����ߐݔ��𗘗p���������̓����Ǝ��p����v���c���a�i�I���K�m���j�B�u�H�i�H��p���̐����ƃ��T�C�N���Z�p�v���c���i�X�i�G���W�j�A�����O���j�C�u���Z�p27�N�|���ɂ͖����̉\��������|�v�_�����M�i�R��������w�j |
MRC News No. 30 2003�N10�����s
�|�l�q�b�ݗ�15���N�L�O���W���|���Ƃ̂������\�u�H�i���Z�p���k��ݗ�15���N���L�O���āv�n�Ӂ@�֕v (�V����w��w�@�j�uSourirajan�Ɣ�Ώ̖��̔����܂Łv���@���F
(���l������w���_����)�u���ۗ��_�A��100�N�L�O���[���h�f�C���[�T�~�b�g�ł̍u���v�c���g�� (�X�i���Ƈ�)�u���Ƃ̂������v���R���Y (������)�u�j�[�Y����̖������A�V�[�Y����̖������v����F�Y
(�����_�H��w)�u�������̉�z���ꂱ��v���c�ĎO (���m�H�Ƒ�w)�u���^�y�f�����킩��}�C�N���G�}���V�����^�t�~�Z���܂Łv�Í�@�V���Y (�����w�H�w��)�u�������Z�p�U������̂��Ɓv�����ˍW(���C�E�G�k���Z�p�R���T���e�B���O)�u�܂����̎d��������Ă��܂��I�I�v���@�r�j
((��)�������i�Z���^�[�j
�u���Ƃ̊ւ�� �`�R���Z�v�g��Ă���v�ց`�v�R���҉� (������w��w�@)�u���Z�k�Ɠ����Z�k�v�{�e���l (������w��w�@)�u���G���v�O�c�D�� (���T���R�[)�u�H�i�����֖������������g�傷�邱�Ƃ����҂��āv���c�O�Y
(NGK�t�B���e�b�N��)�u�`�[�Y�z�G�C�̖����� �|�����_�J���V�E���̔������͂ƃt�@�E�����O�|�v�ѐA�G�� (�c���`�m��w)�u���Ƃ̂������v�c�Ӓ��T (�G�R���{��)�u�C�I���������ƐH�i�Y�Ɓv���i�M�`
(���Ɏq�G���W�j�A�����O��)�u���Ƃ̂������v�����@�@�� (���̑f��)�u�����u�����t�B���^�[�ɂ��āv����@���O (�A�h�o���e�b�N���m��)�u�I�]���ɂ��X�e�����X�|�̕\�ʏ����Z�p�@�`�X�e�����X�|�t�B���^�[�ւ̓K�p�`�v�Y�씎��
(���R���H�ƋZ�p�Z���^�[)�u���Ƃ̂������|�K�X�E���C�̖������|�v�ɓ��� (�V����w�H�w��)�u�킪�Ђ̖��|���U�C�N�דd���|�v�E��N�K�C���ˑP��(��������H�Ƈ�)
�������Љ��u����������Вn�����������Љ�v �A�����A (������)�u����������А������Z�p�J���Z���^�[�Љ�v
���c�i (������)
��e ����15�N�x���{�H�i�Ȋw�H�w���܋L�O�u�������n�t��H�i��ΏۂƂ����������H�w�Ɋւ��錤���v�n��
�֕v (�V����w��w�@)
|
��15��H�G�������@(���s) 2003�N11���@�u�P���C���@�@
�Q����128�� �@�u�P�[�N�h�߂Ƃ��Ă̔����q�E�����q�̖������v���J�p�i�i���É���w��w�@�j�A�u���������Z�p���E�̓����v���R���Y�i�������j�B�u�i�m�h�ߖ��̓����ƕ]���v�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j�C�u�m�e���ɂ�钃���o�t���̃A�~�m�_�ƃJ�e�L���̕����v���c�N���i�É������Ǝ�����j�D�u���Z�p�ɂ�鐅�Y�G�L�X����̋@�\���y�v�`�h�̊J���v�e�n���W�i�ĒÐ��Y���w�H�Ƈ��j�E�u�ĒÎs�ɂ�����x�͘p�[�w���̗����p�Ɍ�������g�݂ɂ��āv�O��q���i�ĒÎs�o�ϕ��j�u�ߔM�����C�𗘗p�����p�����̊����v�ēc���l�i���H�i�@�B�J���j�F�u�q�n�V�X�e���v�x���\�t�g�̗��p�Ɖ��p�v�y�������i�A�����I����C���N�j�G�u�n�C�t�����W�h���^���A�N�^�[�ɂ��r�������v���������i��������Č��ݻ�����j�u�����n�т��痬�o����n�����̌���ƔZ�k�E�ė��p�̉\���v������`�i(��)��ؒ��ƌ������j�j�H�u�H�i�H��r���̂l�a�q�����v���{�m�F�i�������P�~�J���Y���j�I�u�Z���~�b�N���̓W�J�v����T��i�m�f�j�t�B���e�b�N���j�@��P�T��H�G��������b�u���u�t�Z���@�A���O��ߖ@�̐��\�]���v��J�_�u�i(��)�H�i�����������j�u���v���Z�X�̓����Ɍ����������̐i�ߕ��v�d�����T�i�����Ƈ��j |
MRC News No. 31 2004�N3�����s�@
�������u���܂̖��Ɩ��v���c�O�Y�i�m�f�j�t�B���e�b�N���j
��ЏЉ��u�q�n���̍ŋ߂̓����y�ь��G�}�����p���������u�i��C����@�j�v�ȉ��h�i���T���R�[�j
�w�����Ȋw��b�܉Ȋw�Z�p���J�ҕ\���x��܋L�O���ʊ�e�u���N�g�t�F�����̍H�ƓI�Ȑ����@�̊J���v��ҁE���M�ҁ@�c��
�g���i�X�i���Ƈ��j�u�g�}�g�W���[�X�q�n�Z�k�Z�p�̌����J���Ǝ��p���|�����Ȋw�ȉȊw�Z�p���J��܂ɓ����ā|�v��Ґ� �K�Y(�J�S����)�i���M�ґ���
��Y(�J�S����)�j
3.16�@2004�N�x
�@���̔N��10��23��17��56���ɐV�������z�n���ɂ�����M6.8�̒n�k�����������̂͂܂��L���ɐV�����Ǝv���܂��B23���͓y�j���ł���A���́A�M�҂́A�����̌I�����A�c������A���R���_����ƍ�ʌ��̉z�����ŃS���t�������A��A�߂��̓���݂̂����Ή�����ŐH�������Ă������ł����B���̓��̒��A�X���ɉz���w�ɏW�����ăS���t��ɍs���^�N�V�[�̒��ʼn��R�����V�����ʂ����Ēn�k�_���o�Ă���Ǝw�E����܂����B���̌�A9��40�����̃X�^�[�g���ɂ��܂��n�k�_���o�Ă���ƌ����Ă����܂����B�n�k�_�̐��͕̂�����Ȃ��̂ł��܂�C�ɂ��������Ƀv���[���I����ċA��̓��Œn�k���N�������킯�ł��B
�@���ڂ̒n�k���傫���h�ꂽ�̂ł����A���R����̗\�������������� �ƌ������x�ł��܂�C�ɂ������ɂ��܂����B�������A�����㓯���悤�ɑ傫�Ȓn�k���N����A�c�������g�ѓd�b�̃C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ���A�n�k�͐V���ŋN�����z�V�������E�����s�ʂɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂����B���͗����̓��j���ɐV���ɖ߂茎�j����̎d���ɔ�����K�v�����������A�V�������E��������̒n�k�ł͎��������j��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�܂������A��펞�ɂ͌g�ѓd�b�ɘA��������悤�ɑ�w�ɂ��w���ɂ��`���Ă������̂ŁA�A�����Ȃ����Ƃ��瑽���傫�Ȏ��̂ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����낤�Ɛ����͂ł��܂����B
��z�V�������g���Ȃ��̂œ��k�V�����ŌS�R�����։z���̍����o�X�ŋA�郋�[�g�ŗ\������A�����V���ɋA�邱�Ƃ��ł��܂����B�K���A�V���s���ɂ͂قƂ�ǔ�Q�������A��w����Q������܂���ł����B���̌�̐������͓����ɏo��̂ɔ�s�@�𗘗p������A�o�X�𗘗p������Ƒ�ϕs�ւ����܂����B
��16��H�G�������́A�����_�H��̍��ᎁ�ƍ������̋��͂��{���ŊJ�Â����Ă��������܂������A�{���ɍs���̂��։z�����ԓ������p�ł��Ȃ��̂ŁA�k�������ԓ������M�z�����ԓ���ʂ��ĕ{���ɍs�������g�������Ԃ����Ă悤�₭���ǂ蒅����Ԃł����B�V����̈ɓ����ɉ^�]���Ă��������A��E�c�����ƂS���ł̗��s�ł�������ψ�ې[�������ł����B
������Ō䋦�͂��������Ă����R������Ⓑ�����ӂ̐H�i��Ђ̉�œI�j��A�n�k�_�̗\���A��z�V�����̒E���ȂǂȂǑ�ψ�ۂɎc��N�ŁA�n�k�卑���{�̂��낳���ɐɊ�����ꂽ�N�ł����B
�܂��A���̔N�͐H�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p�҂�{������ړI�Łw�H�i���Z�p�u�K��x���J�ݒv���܂����B�����_�H��̍��ᎁ�𒆐S�ɂ��ĉ^�c���Ă������܂������A�����g���Ă������֘A�̋@�B�ނ��_�H��Ɉړ������K�����s���Ă��������܂����B
���̔N�̘N��́A���c�l�q�b������u���Z�p�ɂ�閳�ۉ������S�ʏ`�̐����v���Z�X�̊J��
�v�Ɋւ��錤���ŁA�V����w��w�@���w�ʂ��擾���ꂽ���Ƃł���A���e���l�q�b����̎Q�l�ɂȂ�ƍl�����܂����̂łl�q�b�j���[�X�Ɍf�ڂ����Ă��������Ă��܂��B���̊w�ʘ_���̂P��ڂ̊w�p�_���́A���̌���{�ʋl����̋Z�p�܂���܂��Ă��܂��B
|
��P�U��t�G�������u���W�@2004�N6���@�S�і��ّ�z�[���@�Q����52�� |
MRC News No. 32 2004�N10�����s�@
�������u�G�l���M�[���`�Ɂv�@���� �F�Y�i�����_�H��w��w�@�j
�������Љ��u�����Ɗ�������@�Z�p�������Љ�v�d�� ���T�i�����Ƈ��j
���W�| �����̖��E�����u�E�V�Z�p �|�u�H�i�H�w�����S�O�N �|���E���ԊO���E�}�C�N���g�E���̑��|�v�n�� �֕v
(�V����w��w�@)�u��Ђ̎����̑��u�v���c �O�Y (NGK�t�B���e�b�N��)�u��Ђ̖���p�����������Z�p�v�c�� �^�I�v (�I���K�m��)�u�l�ɁA���ɂ₳�����C�I�������Z�p����銔����ЃA�X�g���v�d�y
��j (���A�X�g��) �u�g�U���͗p���U�C�N�דd�� �w�Z�C�J�����u�����x�v�E�� �N�K�C���� �P�� (��������H�Ƈ�)�u�o�d�r�����u�����J�[�g���b�W�t�B���^�[ �s�b�r-�f�^�C�v�v����
���O (�A�h�o���e�b�N���m��) �u�Z���~�b�N���V�X�e���̌���v�{�� �_���i���g���C�e�b�N�j�u�t�̖��������@�v�ɓ� �� (�V����w�H�w��) �u�C���t���[�W�����E�ۋZ�p�v�݊y �p�v (�X�i���Ƈ�) �u���ՊE���̂̓������ő���Ɉ����o���v���Z�X�̎�����ڎw���āv��ؖ�
(�Y�ƋZ�p����������)
��e�w�ʘ_���i�V����w��w�@���R�Ȋw�����ȁj�u���Z�p�ɂ�閳�ۉ������S�ʏ`�̐����v���Z�X�̊J�� �|���̂P�|�v���c �O�Y�iNGK�t�B���e�b�N���j
|
��P�U��H�G�������u���W�i�{���s�j2004�N11���@�嚠���_�Ќ�������@�Q����72�� �@�u��w�̓Ɨ��@�l���Ɗ�ƂƂ̋��͊W�v�T�R�G�Y�i�����_�H��w��w�@�j�A�u��E�ʎ����H�ɂ����閌�Z�p�̐V���ȓW�J�v�����Y�i�J�S�����j�B�u�y�N�`�����薳�ۃW���[�X�̐����ƃZ���~�b�N�����p�Z�p�̓����v���c�O�Y�i�m�f�j�t�B���e�b�N���j�C�u�����������t�̃N���X�t���[�h�߂ɂ�����t�@�E�����O�v�c���F���i�V����w�H�w���j�D�uPall
Exekia�Z���~�b�N���t�B���^�[�ɂ��N���X�t���[��߁v�p�����l�i���{�|�[�����j�E�u���ՊE�E���ՊE�����p�Z�p�̌���ƓW�]�|�H�i�����̒��o����s�H�����̉H�������܂Ł|�v�V��M�v�i���k��w��w�@�j�F�u�t�Z�����̃t�@�E�����O�Ƒ�v�쏟�F���i�I�c�H�Ƈ��j�G�u���Ɩ��ݔ��̉^�]�Ǘ��v�吼���r�i�X�i���Ƈ��j�H�u�ŐV�ƒ�p�d�q�����W���p�ɂ��V�H�i�̊J���|�����ړ���H�i����т�ŗ����̐����|�v�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j�I�u�H�i�H��̓�R���p���������Ɨ����p�v���C�F�Y�i���O���[���G�i�W�[�j�J�u�����c�A�N�`���G�[�^��p�����H�i�v���p���I�S�e�����葕�u�v�֍����T�i��ʌ��Y�ƋZ�p���������j�@��P�U��H�G��������b�u���u���v���Z�X���\��͂̊�b�v�ɓ��́i�V����w�H�w���j�u�H�i����ւ̖��Z�p�̉��p�v�������i���̑f���j |
MRC News No. 33 2005�N3�����s�@
������ �u�����Ɩ��Z�p�v�@�����@���i���̑f���j
�������Љ��u�H�i�����������E���������H�w�������̏Љ�v�@��J�_�u�i�Ɨ��s���@�l�E�H�i�����������j
��e�@�w�ʘ_���i�V����w��w�@�@���R�Ȋw�����ȁj�u���Z�p�ɂ�閳�ۉ������S�ʏ`�̐����v���Z�X�̊J��
�|���̂Q�|�v���c �O�Y�iNGK�t�B���e�b�N���j
3.17�@2005�N�x
�@�\���H�i�̕��y��H�i�i���̍��x�����̓��������H�Z�p�̕��������K�v�ł��邱�Ƃɂ��Ė�����ŋc�_��i�߂Ă��܂����B���Z�p�ɂ��Ă��������̗����łȂ��L�������Z�p�Ƃ��đ����A���̕����Z�p�Ƃ̕���������i�߂�ׂ��Ƃ̌��_�ɒB���A16�N�ԑ����Ă����w�H�i���Z�p���k��x�̖��̂��w�H�i���E�����Z�p������x�ɕύX���A�p�����́wMembrane & separation Research Circle of food�x�Ƃ����̂͏]���ʂ�w�l�q�b�x�Ƃ��邱�Ƃɂ��܂����B����ɔ����A���É���w���h�ߋZ�p�̌�����i�߂Ă�������J���ɕ���Ƃ��ĎQ�����Ă������������̏[�����͂���܂����B
�@������A�l�q�b�j���[�X34���ł��A�e��H�i�̐����ɂ����镪���Z�p�̌���ƓW�]�Ɋւ�����W��g�ݖ��E�����Z�p�ւ̍L������l�q�b����̕��X�ɏ����܂����B
��17��H�G�������́A���k��w�̐V�䎁�ƕĖ{���A�{�錧�H�ƋZ�p�Z���^�[�̗�؎��ɂ��肢���ċ{�錧�C����s�ŊJ�Â��Ă��������܂����B
�ǂ�������������̂ł��傤���H�C����͕M�҂Ɠ���݂��[���x�X�K�˂����Ă��������Ă��܂��B�C����Ɖ]���A�M�҂ɂ͔��{�Ԉ�̋ԃh���V���E�ɏo�Ă����A�V�R�ڂ����̋C����������v���o���܂��B���a60�N�̉��w�H�w��֓��x��������ŊJ�Â��鎞�A���k��̐V�䎁���H�����Ɍ�����m�ւŐH�i���w�H�w��������J�Â��ĖႦ�Ȃ����Ƃ̘b���������܂�܂����B������̖��搶�ɑ��k�����Ƃ��낢�낢��ƒ������ĉ�����n�j�Ɖ]�����Ƃɂ��ĉ�����A�����ǂ͖�쌤�����̍�R���i���݁A�����C�m��w�j���Ή����Ă���邱�ƂɂȂ�܂����B�H�i���w�H�w��������J�Â�����A���w����s���̂ł����A�V�䎁����ǂ��ɂ��邩�Ƃ̑��k�������ɓ������̂��C����ł����B
���̌�A�{�錧���Ƃ��ė�؎����Ή����ĉ�����A�C����Ɍ��w��̉����ɍs������A�������ԊO���u�[���ł��������Ƃ����ԊO���Ɋւ���u���ɏ��ْ�������ƁA����C����ɂ͑����^��ł��܂��B������ł́A�C������H��D��p�ӂ��ăA���r�̗{�B��Ɉē����ĉ������܂����B����ɁA�C����v���U�z�e���ŎQ���ґS���ɒ��H�܂ł��y�����ĉ�����A��ςȊ��҂����Ă��������܂����B���̌�A�C������H��̕��X�����k��̐V�䎁��c���Ƃ��Ă��̐H�����̌��w�ɗ��ĉ������܂����B���܂�́A��P��H�G���������J�Â������ΎR�[�̐؉��ŁA�H�����̃����o�[�Ɣ��܂肪���ŏ��H��̕��X�ƌ𗬂�[�߂܂����B
2004�N�ɂ́A�{�錧�̗�؎�����v�������������C����Ŗ��̍u���������đՂ��܂����B���̎��ꏏ�ɍu�����ꂽ�T���g���[�̍������́A�ɉq�咃���J��������������ŋC����̂��o�g�ƌ������ƂŁA�����̉p�Y�I���݂̕��̂悤�ő����̒��u�҂������Ă��܂����B
�����āA2005�N�ɂ͂l�q�b���C����ŊJ�Â����Ă����������ƂɂȂ�A�܂��܂��V�����獂���o�X�Ő��ɏo�āA�i�q�ŋC����ɓx�X�ʂ����ƂɂȂ�܂����B�������ł̍u���͖ܘ_�f���炵�����̂ł����B�����āA�C����ł��������Ȃ��ƍl������A���̋��s��ɕ��T����}�O���A�T���̉��H�H��ƃt�J�q���H��A����瑍�Ă������Ă���������ϖ��������������ł����B
|
��P�V��t�G�������u���W�@2005�N6���@�S�і��ّ�z�[���@�Q����48�� |
MRC News No. 34 2005�N10�����s�@
�������u�H�i���E�����Z�p������(MRC)�ւ̔��W�v�n�ӓ֕v (�H�i���E�����Z�p������)
�������Љ�u�V����w��w�@���R�Ȋw�����ȁ@�H�i�E�������H�w�������v�n�ӓ֕v�E�ɓ��� (�V����w��w�@)
���ʊ�e�`�H�i��������Z�p�`�u�ʼnt�����̎�@�ƍl�����v���J�p�i�i���É���w��w�@�j�u�@�\���f�ނƕ����E�����Z�p�v�{�� ���c�iCMP�W���p�����j�u���Ƃɂ�����e�핪���Z�p�̗��p�|���N�g�t�F�����̐����ƃA�v���P�[�V�����𒆐S�Ƃ��ā|�v�c��
�g���E�V�� �m�u (�X�i���Ƈ�)
���W�`�e��H�i�̐����ɂ����镪���Z�p�̌���ƓW�]�`�u�C���X�^���g�R�[�q�[�̐����Z�p�v���c�m�� (���̑f�[�l�����t�[�d��)�u�g�}�g�W���[�X�̐����Z�p�v�����Y
(�J�S����)�u�E�����������ɂ�����镪���Z�p�v�������Y (�X�i���Ƈ�) �u�ݖ������ɂ����镪���E�h�ߋZ�p�v��c�`�� (�������ݖ����������g��)�u�b���E�b�����̐����Z�p�v���v��P�v
(���{�H�i���H��)
�H�i���Z�p�u�K��u��Q��(2005�N)�H�i���Z�p�u�K��v���O�����v
|
��P�V��H�G�������@�C����s�@2005�N11���T���}�����C����z�e���ϗm�@�Q����109�� �@�u���Ăɂ�����H�i���H�p�����W���[���̊J���vMark
Steven Braun�iGEA
Filtration�]USA�j�A�u�`�[�Y�z�G�C�̂t�e�����p����v�{��@�G�v�i(��)�������_�Z���^�[�j�B�u�{�Y�r�������ւ̖������̉��p�v�����@�x�j�i���q���Y�j�C�u�V�R�������J���ɂ����镪���Z�p�̗��p�v�c���@�G�i���̑f���������J���E�H�Ɖ������j�D�u�u�����h���헪�@���Y�H�i�̕i�����P��i�ƐH�i�q���@�Ƃ̊W�v�˃���
�b��i���{�ی������j�E�u���ՊE���̒��o�Z�p��p�����r�[�������v��������i�T���g���[��
�Z�p�J���Z���^�[�j�F�u���Y���H�E�{�B�Ɗ��v�`�a�F�i���{���Y��
�����������j�G�u�H�i�@�B������u�̍ŐV�̐��@�v�c�Ӓ��T�i�G�R���{���ެ���øƶپ����j�H�u�d���E�ې��̌��ʂƎ��p��@�|�d�𐅐������u�u�s���A�X�^�[�v�̓����|�v���R����i�X�i���Ƈ�
���u�J���������j�I�u�V�����ɂ����閌�Z�p�̕��y�Ǝ��p���v�n�ӓ֕v�i�V����w��w�@�j�J�u�����u�����o�C�I���A�N�^�[�ɂ����_���y�v����F�Y�i�����_�H��w��w�@�j�@��b�u���u���Z�p�Ƃ͂ǂ�ȋZ�p�A�ǂ�ȐH�i������́H�v�吼
���r�i�X�i���Ƈ� ���u�J���������j�u���@���̉��w�v���Z�X�ւ̉��p�v���� �x�m�v�i(��)�Y�ƋZ�p�������������߸ĉ��w��۾������Z���^�[�j |
MRC News No. 35 2006�N3�����s�@
�������u�����������玖�ƕ����ɂȂ��āv�c���g���i�X�i���Ƈ��@�\�f�ގ��ƕ��E�l�q�b����j
��ЏЉ�u�m�f�j�t�B���e�b�N������Ёv���c�O�Y�i�m�f�j�t�B���e�b�N���j
3.18�@2006�N�x�@
�@�l�q�b�j���[�X36���́w�H�i���E�����Z�p�̌���ƓW�]�|�䂪�Ђ̌ւ�Z�p�Ɛ��i�|�x�Ƒ肵�āA���E�h�߁E���S�����E�t�̃N���}�g�E�Z�k�E�����E���o�ƍ���l�q�b�Ƃ��Ĉ����Ă����ׂ������Z�p�̑��Ă�ԗ��������W���s���邱�Ƃ��ł��܂����B�ǂ݉����̂�����W���ł���A���w�H�w��̕ҏW�ψ�������Ă���V����̈ɓ������������҂ɉ��w�H�w��ւ̎��M���˗����Ă������Ē����Ȃ������Ƃ̂��ƂŁA�l�q�b�̑g�D�͂Ə��\�͂̍����ɋ��Q���Ă��܂����B
�l�q�b�Ƃ��Ă͍�������̏�ł͒ł��Ȃ����M�������Ă��������ƍl���Ă��܂��̂ŁA����e�ʂƊW�҂̂����͂����肢������̂ł��B
�@��18��H�G�������́A�V�����H�i�Z�p������ƐV����̈ɓ��E�闼���̂����͂ɂ��V���s�ŊJ�Â����Ă��������܂����B����ŁA�V���ł̊J�Â͂R�x�ڂɂȂ�܂����B
|
��18��t�G�������u���W�@2006�N6���@�S�і��ّ�z�[���@�Q����56�� |
MRC News No. 36 2006�N11�����s�@
������ �u���W�w�H�i���E�����Z�p�̌���ƓW�]
�|�䂪�Ђ̌ւ�Z�p�Ɛ��i�|�x���s�ɓ������āvMRC��@�n�� �֕v�i�V����w��w�@�j
��ЏЉ��u���H���Y������Ёv����m��(���H���Y�������)
����W��H�i���E�����Z�p�̌���ƓW�]�|�䂪�Ђ̌ւ�Z�p�Ɛ��i�|
�`�������Z�p�E���u�`���������u�������Z�p�̊�b�v�吼 ���r (�X�i���Ƈ�) �u���Z�p���p�̌���v���c �O�Y (NGK�t�B���e�b�N��)�u�ŐV�̃J�[�g���b�W�t�B���^�[�̓����Ƃ��̉��p�v����
��Y(���{�~���|�A��)�u�������������D�@(MBR)�p���W���[��MUNC�|�U�Q�OA�v���{ �m�F�C�X �g�F (�������P�~�J���Y��) �u�C�m�[�w���~�l���������t�����v�����g���d�C���͑��u���v��
���V (���Ɏq�G���W�j�A�����O��)�u�d�C���͂̐H�i����ւ̓W�J�v�g�] ���h (���A�X�g��)�u�Z���~�b�N�����ۉ���ߑ��u�v���c �O�Y (NGK�t�B���e�b�N��)�u�N�����O�����������W���[���wGS�x�v���c
�� (���N����)�u�䂪�Ђ̌ւ�Z�p�Ɛ��i�v���� �� (���T���R�[)�u�w�Z�C�J�����u�����x�ɂ��g�U���́v�E�� �N�K�C���� �P�� (��������H�Ƈ�)�u�������p�������G�������g�E���W���[���v�[��
�ǐ� (������) �u�j���[�N���|�A�����u�����ɂ��āv�z�� �� (�쑺�}�C�N���E�T�C�G���X��)�u�V�^�Z�Е����������u�v�吼 �^�l (�������v�����g�e�N�m���W�[)�u�C�O�ł̐H�i�E���_�E����H�Ɠ���RO�ENF���Z�k�����ւ̓K�p�Љ�v��x
�� (�����d�H��)�`��ߋZ�p�E���u�`���������u�h�߁E����Z�p�̊�b�ƓW�J�v���J �p�i (���É���w��w�@)�u�h�ߏ��܂̌���ƓW�]�v�_�} �@ (���a���w�H�Ƈ�)�u�H�i�����ɉ����閌�h�߂̗��p�v�R�����F
(�R���Z���H�Ƈ�) �u�䂪�Ђ̌ւ�t�B���^�[�v���X�v���J ���O (���Ί_)
�`���S�����Z�p�E���u�`���������u�ŐV�̉��S�����Z�p�v���� �� (���̑f��)�u�ʏ`�����H���ɂ����鉓�S�����A�������A���S�����Z�k�ɂ��g�[�^���\�����[�V�����v��
�T (�A���t�@����o����)�u��Ђ̎����̉��S�������u�v�ؑ� ��C��� ���� (�O�H���H�@��)�`�t�̃N���}�g�Z�p�E���u�`���������u�ŐV�̉t�̃N���}�g�Z�p�̓����Ɖ��p�v�R�c
���� (�I���K�m��)�`�Z�k�Z�p�E���u�`���������u�ŐV�̔Z�k�Z�p�Ƃ��̉��p�v���� ��Y (�J�S����)�u�����Z�k(Freeze
Concentration)�v���c�p�� (�����w����w��w�@)�u�E�ʑO�i�����Z�k�@�̌����Ɖ��p�v�{�e ���l (�ΐ쌧����w)�u�g�}�g����т��̑��W���[�X�ނ̂q�n�Z�k�v����
��Y (�J�S����)�u�����i�ւ�RO�ENF�Z�k�̗��p�v�d�� ���T (�����Ƈ�)�u�ȃG�l���M�[�^�q�[�g�|���v���^��������u�v�R�� �O�u (����쌴���쏊)�`�����Z�p�E���u�`���������u�����Z�p�̌���ƓW�]�v�y�c
�� (�y�c�Z�p�m������)�u�����i�̊����Z�p�̌���ƓW�]�v���� �q�K (�����Ƈ�)�u�t��ޗ��̘A�������������u�w�X�v�����[�h�x�v�c�� �_�� (����쌴���쏊)�u�䂪�Ђ̎����̑��u�v�@�g��
�ɒm�Y (���ޗNj@�B���쏊)�uPJ-MiniMax(PJMSD)�̓����ƍl�ăf�o�C�X�v�@���� ���k (���p�E�_�����O�W���p��)�`���o�Z�p�E���u�`���������u���ՊE���̒��o�Z�p�̌���ƓW�]�v�V��M�v
(�Ɨ��@�l�Y�ƋZ�p����������)
|
��18��H�G�������@�i�V���s�j���f�z�e��2006�N10���@�Q����103�� �@�u�Q�P���I�͐��Ɠ�_���Y�f�̎���|�����\�ȎЉ�ւ̃\�t�g�����f�B���O�|�v�V��M�v�i���k��w��w�@�j�A�u�T���g���[�̊��헪�|�u���Ɛ�����v�̎��H�Ɍ����ā|�v��������i�T���g���[���B�u���S�����@�A�����u�A���S�����Z�k�@�ɂ������v���Z�X�̍œK���v�@�T�i�A���t�@�E���o�����j�C�u���ɗD�������ƃt�@�C���P�~�J���̐����E�ė��p�Z�p
�|���E�C�I�����������̃n�C�u���b�h�V�X�e���|�v�c�� �^�I�v�i�I���K�m���j�D�u�n�����̖��V�X�e�����p�ɂ��㐅�̐����v�㌴�@���i���E�F���V�B�j�E�u�ܖ��������D�̗����w�R�āv���������i�V����w�H�w���j�F�u�|�W�e�B�u���X�g���Ƃ��̑�v���������i���A�W�A�H�i���S�����Z���^�[�j�G�u���y�@�A�~�m�_���@�ɂ����閌�E�����Z�p�v�y�ƈ�Y�i���̑f���j�H�u�����̐��������J���헪�Ɛ��E�̐����������v�I���@�D�C���������i�������j�I�u�����q�@�\���̖��Ɖ\���v�؏r���i�V����w�H�w���j�@��b�u���u�����Z�p�Ƃ͂ǂ�ȋZ�p�A�ǂ�ȐH�i������́H�v�ɓ�
�����Y�i�����Ƈ� �Z�p�������j�u���Z�p�Ƃ͂ǂ�ȋZ�p�A�ǂ�ȐH�i������́H�v�吼 ���r�i�X�i���Ƈ� ���u�J���������j |
MRC News No. 37 2007�N3�����s�@
�������u���̎��オ����Ă����v��J�_�u�i�H�i�����������j
��ЏЉ�u���a���w�H��������Ёv�@�_�}�@�@�i���a���w�H�Ɗ�����Ё@�������j
3.19 2007�N�x
�@�l�q�b��ݗ�����19�N�B2007�N3���������ĐV����w���N�ސE�Ɖ]�����ƂɂȂ�܂����B���܂ł͐V����w�̓n�ӌ������Ŕ鏑�߂Ă���Ă����ɐ��T���̋��͂̉��ɂl�q�b���^�c���Ă���ꂽ�̂ł����A��N�ސE�ɂȂ��Ă��܂��Ǝ������������̎������Ȃ����������ق����̎������Ȃ����A������Ƃ����ĉ���̎x��������̂ɂl�q�b��ׂ��Ă��܂��͕̂s�{�ӂł��邱�Ƃ���A���_�Ƃ��Ď��̉ƂŎ����������S�����l�q�b�𑶑������邱�ƂɂȂ�܂����B
��19��t�G�������́A�n�ӌ������̓�����Ƃ̋��ÂƂ��Ă��������M�҂̑ފ��L�O�u�������˂����Ă��������܂����B�H�G�������́A���܂ōs���Ă��������𗣂�ĂP��2���̊J�Â͖����ł��邱�Ƃ���A��10������17���܂ł̍u����ɐ�ւ��܂����B�������A10������̍u����J��͉��̓s���ł��Ȃ薳�������邽�߁A2012�N���ߌォ��̍u����ɕύX�������܂����B���������Ăl�q�b��ׂ��Ă��܂����g�̏�ɂ������^�c�����Ē������������������悢�Ƃ̖�����ł̔��f������������ł��B
���u�K��͏]���ʂ�Q���ԊJ�Â��Ă��܂����A�u�`���n�߂�O�ɍu�t�Ǝ�u���̎��ȏЉ���s���a�C�\�X�Ƃ����u�K��ɂȂ�悤�ɁA����ɁA���Z�p�̎�u�ғ��m���A����������悤�ɔz�������^�c�����Ă���܂��B
�@�l�q�b�j���[�X38���́A�V����w�̈ɓ����̋��͂����������T�N�Ԃ�Ɏs�̖��ꗗ�̓��W��g�݂܂����B
|
��P�X��t�G����������n�ӓ֕v���� �V����w�ފ��L�O�u���� �@2007�N�U���@�z�e���͂��Ƃ���T�؍�@�Q����83���@ ���ÁG�V����w��w�@�@�n�ӌ����������� �@�u�s�҃j���j�N���@�\���H�i�����ƃx���`���[��Ƃ̌o�c�v�����O�s�i�k�C�����C��w�w���E�_�w���m�j�A�u���E�̐H�������Ɠ��{�H�i�Y�Ƃ̉ۑ萸���h�߁v�������(���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[�����E���w���m)�B�u�������Ƃ̏��i�J���헪�ƕ����Z�p���O�h�߁v�K�c�L�i�������Ƈ��햱������E�_�w���m�j�C�u�V����w�ފ��L�O�u���|�������H�w�𒆐S�Ƃ����H�i�H�w�����S�O�N�|�v�n�ӓ֕v�i���E�V�����w�@�����E�_�w���m�j |
MRC News No. 38 2007�N11�����s�@
������ �H�i���E�����Z�p������i�l�q�b�j�̖����ƓW�]�H�i���E�����Z�p������
� �n�ӓ֕v
��ЏЉ� �����Ƃ�CSR�����ɂ��ā`�u���O���[�vCSR�v�錾�`�����Ɓi���j�Z�p������(MRC����)�@�ɓ������Y
�Z�p����@���Z�p PVDF���E���W���[���\������т��̎��p��i���j�������i�Z���^�[(MRC�ږ�)���r�v�@�Z�p����@���Z�p�@�����h�ߖ��ɂ��H�i�̖��ۉ���߁i���j�g���C�e�b�N(MRC���)���c�O�Y
���W�@ �s�̖��ꗗ�@�����h���E�N�����E���A�T�����u�����V�X�e���E�O�H���[�����E���m�h���E�����EABCOR�ENGK�t�B���e�b�N�E�T���R�[�E�x�m�ʐ^�t�C�����E�������P�~�J���Y�E�I���K�m�E���{�~���|�A�E�x�m�t�B���^�[�E���{�����E���{�|�[���E�U���g���E�X�E�Q���}���T�C�G���X�W���p���E�t�r�t�B���^�[�E�쑺�}�C�N���T�C�G���X�E�@���O�h���E�Q���}���T�C�G���X�W���p���E���{�~���|�A�E�x�m�t�B���^�[�EABCOR�E�������P�~�J���Y�EPCI�E�T���R�[�EDDSS�E�����d�H�ENGK�t�B���e�b�N�E�_�C�Z�������u�����V�X�e���E�O�䉻�w�E���A�T�����u�����V�X�e���E�U���g���E�X�E���{�|�[���E�@�i�m�h�߁^�t�Z�����E�����EDDSS�E�����d�H�E�T���R�[�E�X�i�G���W�j�A�����O�E���m�a�сEPCI�E�_�C�Z�������u�����V�X�e���E�@�C�I���������E�A�X�g���E��������H�ƁE�g�N���}�E���Ɏq�E�@
|
��P�X��H�G�������i����s�j�������������ف@2007�N10���@�Q����36���@ �@�u�䂪���̍ŋ߂̐H�i���̂Ƃ��̌����v��ԗT�i(�Ёj���{�A�O���r�W�l�X�Z���^�[�햱�����j�A�u�����̋U���H�i����ƈ��S��v�ΒJ�F�C�i���{�H�i����������E�_�w���m�j�B�u�H�i�V�f�ފJ���A���S�E����̍ŐV�����ƕ����E��ߋZ�p�v�{�쑁�c�i�b�l�o�W���p���i���j�H�i�ƊJ���ҏW���j�C�u�Z���~�b�N���̔��W�Ƃ��̗��p�Z�p�\�����q�����̕����E���ۉ��𒆐S�Ƃ��ā|�v���c�O�Y�i�g���C�e�b�N�i���j�Z�p�����E�w�p���m�j�D�u���E�̐�����Ɠ����d�H�̖��Z�p�J���̓����v�g��_�u�i�����d�H�i���j�����u�������ƕ��J�����A�v���P�[�V�����O���[�v�j�E�u��E�ʎ����H�ɂ�����Z�k�Z�p�̔��W�Ƃ��̗��p�v�����Y�i�J�S���i���j�����������Z�p�J�����������E�H�w���m�j |
MRC News No. 39 2008�N4�����s
�������@�Ȋw�Z�p�p��̐��m���̕K�v���|���ۉ��h�߁|�@�n�ӓ֕v�i�H�i���E�����Z�p������
�
�E�V�Z�p�J���@�@�@���E�_�w���m�j
��ЏЉ� ���{�s���A�E�H�[�^�[�i���j���R���Y�i���{�s���A�E�H�[�^�[�i���j�C�O�c�ƕ����j
3.20�@2008�N�x
�@2008�N�łl�q�b�ݗ�20���N���}���܂����̂ŁA�t�G�������̂܂���20���N�L�O���T���J�Â��܂����B20���N�L�O���ƂƂ��āA�c�ӑ�\�������l�q�b�j���[�X�S39�����o�c�e�t�@�C���Ƃ��Ăb�c�Ɏ�荞��ʼn�����A��������ł��Ȃ��悤�Ƀv���e�N�g�����������̂��l�q�b�ɑ���v���ɉ����đ��悠�邢�͔̔����邱�Ƃɂ��܂����B�l�q�b�j���[�X40���͐ݗ�20���N�L�O���Ƃ��Č��ݍ쐬���ł��B���ݎ��M���̂��̌��e�����x���s�����l�q�b�j���[�X40���̈ꕔ�ɂȂ�܂��B
|
�l�q�b�ݗ��Q�O���N�L�O���T����ё�Q�O��t�G�������2008�N�U����������A�Q����53���@ �@MRC20���N�L�O���ʍu���@�ēc���v�@�i�ۍg�o�ό������@�����j���E�̐H�������̓����@ �AMRC20���N�L�O�u���@�n�ӓ֕v�@(�H�i���E�����Z�p������@��E�_�w���m) �H�i���E�����Z�p������20�N�̕��݂ƍ���@�B�с@�O�i�H�i�����������@�����E�_�w���m�j�@�H�i�s���ɉ�����Z�p�J���\�H�i�����������̖ڎw�������\�C���@�r�v�i�������i�Z���^�[�E�H�w���m�j�ŋ�20�N�̖��Z�p�̔��W�\���J���Ǝ��p���̐i�W�\ |
3.20�@2008�N�x
�@2008�N�łl�q�b�ݗ�20�N���}�����̂ŁA�t�G�������̂܂���20���N�L�O���T���J�Â��܂����B20���N�L�O���ƂƂ��āA�c�ӑ�\�������l�q�b�j���[�X�S39�����o�c�e�t�@�C���Ƃ��Ăb�c�Ɏ�荞��ʼn�����A��������ł��Ȃ��悤�Ƀv���e�N�g�����������̂��l�q�b�ɑ���v���ɉ����đ��悠�邢�͔̔����邱�Ƃɂ��܂����B�l�q�b�j���[�X40���͐ݗ�20�N�L�O���Ƃ��č쐬���܂����B
�@�n�ӂ̑ފ��ɔ����V����w�̋��͂������Ȃ��Ȃ�܂������A���̔N���瓌���_�H��w�̍��������Ɩ쑺�y�����̋��͂�������悤�ɂȂ�A�܂��_�H��_�w���t���d�`�������p�����{�݂����͋@�ւƂ��ċ��͂��Ē����邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���̔N��9���ɑ�1���Z�p�u�K����J�Â��܂����B13���̎Q��������D�]�ł����B
10���ɂ�CMP�W���p��(���݁AUBM���f�B�A(��))�̂����ӂœ����r�b�O�T�C�g�̐H�i�J���W��3���ԏo�W�����Ē����A2���Ԃɓn��e�N�j�J���v���[���e�[�V������100���̎�u���ɖ��Z�p�̊�b�ɂ��ďЉ�܂����B
�@���Z�p�u�K���2004�N����J�Â��Ă��܂������A�A���P�[�g�����Ɩ��Z�p�ɂ��Ă��Ȃ荂�x�Ȓm��������u������A�S���̏��S�҂܂ł��Ȃ�m�����x���ɍ������邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B2��/�N�̍u�K����J�Â���قǎ��ԓI�]�T���Ȃ������̂Ŏ��s�ł����ɗ��܂������A�ފ������Ԃ�����悤�ɂȂ����̂ŁA2009�N1���Ɉ���������S�҂̂��߂̖��Z�p�u�K����J�Â��Ă݂��Ƃ���A��u��16�����Q�����Ă���܂����B���̎��̃A���P�[�g����A��������ł͎��Ԃ��Z������̂�2���Ԃɂ��ė~�����Ƃ̈ӌ��������������߁A���N2010�N1������2���Ԃ̍u�K����J�Â��邱�Ƃɂ��܂����B
|
�l�q�b�ݗ��Q�O�N�L�O���T����ё�Q�O��t�G�������@ 2008�N�U�����������������Q����53���@ �@�@MRC20���N�L�O���ʍu���@���E�̐H�������̓����@�ēc���v�@�i�ۍg�o�ό������@�����j�A�@MRC20���N�L�O�u���@�H�i���E�����Z�p������20�N�̕��݂ƍ���@�n�ӓ֕v�@(�H�i���E�����Z�p������@��E�_�w���m)�@�B�@�H�i�s���ɉ�����Z�p�J���\�H�i�����������̖ڎw�������\�@�с@�O�@�i�H�i�����������@�����E�_�w���m�j�C�@�ŋ�20�N�̖��Z�p�̔��W�\���J���Ǝ��p���̐i�W�\�@���@�r�v�i�������i�Z���^�[�E�H�w���m�j |
MRC News �@No. 40 �@2008�N11�����s
�l�q�b�ݗ�20���N�L�O���W�@
�H�i���E�����Z�p������i�l�q�b�j20�N�̕��݁@�@�n�ӓ֕v�@�i�V�Z�p�J���@�@�@��
�H�i���E�����Z�p������@��E�_�w���m�j
�������Z�p�Ƃ̊ւ�� �@�@�@�c���g���@�i�X�i���Ɓi���j�����J���Z���^�[
�H�i���E�����Z�p������@����E�H�w���m�j
�H�i�ւ̖��Z�p���p�G���@�@�@�@���c�O�Y�@�i�i���j�g���C�e�b�N�@
�H�i���E�����Z�p������@����E�w�p���m�j
�H�i���������u�̐��Ɋւ���G���@�@�c�Ӓ��T�@�i�G�R���{�i���j�ږ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�i���E�����Z�p������@��\�����j
������Ɩ��Z�p�̔��W�@�c���^�I�v�i���Ԗ@�l�������Z�p�U���������W���[�i���ҏW���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�i���E�����Z�p������@����\�����j
�^���j���_��p����RO/NF���̉����Z�p�@ �����S��i�I���K�m�i���j�J���Z���^�[�j
�ϗL�@�������ɗD�ꂽ�A�j�I��������ASM-F�@�@�c���L�K�i�i���j�A�X�g���A�Z�p���j
�䂪�Ђ̌ւ�V�Z�p�E�V���i�|���E�����Z�p�Ƃ̊ւ��@�N����O�E���q���T�i�A�h�o���e�b�N���m�i���j�j
|
��20��H�G�������@�@�@(2008�N11���@�������������ف@�Q����42��) �u�������Z�p�U������̌���Ɩ��Z�p���p���̍L����v �c���^�I�v�@(MRC����\�����E�������Z�p�U������E�����W���[�i���ҏW��)�@�u�i�m���(NF) �Z�p�̓����Ƌ@�\���H�i�����ւ̗��p�v�n�ӓ֕v�@(MRC��E�V�Z�p�J���@�@���E�_�w���m)�@�u���ƊE�ɂ�����ŐV�̖��E�����Z�p����v�c���g���@(MRC����A�X�i����(��)�H�w���m)�@�u�R���[�Q���̉Ȋw:���̂ɂ���������Ƃ��̗L�����p�v���R�q�v�@(�����_�H��_�w���t���d�`�������p�����{��(MRC���͋@��)�E�{�ݒ��E���w���m)�@�u�J�[�g���b�W�t�B���^�[����і��ɂ��āv�ɓ������@(�A�h�p���e�b�N(��)�����̔����i��)�@�u�ڋl�܂肵�Ȃ��������Z�p-�E�g�U�̗��p�v �^�琪��((��)�i�Z�p�V�O�}�E��\������E�H�w���m) �u�H�i����ɂ�����C�I���������̗��p�v ���J�@�T(��) (�A�X�g��(��)) |
MRC News �@No. 41 �@�@2009�N4�����s
��ЏЉ�@�@�@�@�������Ɗ�����Ќ����{��
�L�c��(MRC�����A��������(��) �Z�p�J��������)
��������щ��
�E�����̃i�m����(NF) �ɂ����鉖�ނ̓���
�������Y(MRC�����A�X�i����(��)���u�J���������E�H�w���m)�@�@�@
�H�i����ɂ����镪���E��ߋZ�p�̍ŋ߂̓���
�����T�v�Y(�H�i�ƊJ���x�ҏW��)
���ۉ��h�ߋZ�p�̓����Ɖ��p
�n�ӓ֕v(MRC��A�V�Z�p�J���@�@���E�_�w���m)
3.21�@2009�N�x
2009�N�͒��N�����Ă��������}���������A8���̏O�@���I���Ŗ���}���������H�w���o�g�̔��R����������b�ɏA�C�����N�ł���A�L�����ׂ��N�ł����B���n�̑�����b�́A���̌�̊ǒ��l����2�㑱���܂����B����}�����ɂ��Ă͂��낢��Ȉӌ���������������̂ŕ]���͂��܂��A���n������b�ɂ��Ă͂��Ȃ���ҊO��ŗ��n�̒p�Ɗ������l�͎���l�ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B
����������������Љ�̓��������������̂́A�l�q�b�͏��X�ɓ����ł̉^�c�̊�Ղ��ł߂Ă��܂����B�@(��)���{���Y������������ł������{�c����(��)���{�H�i���̓Z���^�[�̋v�ď햱�����Ƃ̘b�̒�������{�H�i���̓Z���^�[�̋��͂��邱�ƂɂȂ�A���Z�p�u�K����Z���^�[�̉�c���ŊJ�Â��A�u�K��̉^�c����`���Ă��������邱�ƂɂȂ�܂����B�܂��A�����Ƃ��ĉJ�{�ے����Q�����Ă���邱�ƂɂȂ�A�u�K��̉^�c���ɂ߂ăX���[�Y�ɍs���邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�H�i�Y�ƂŎg�p����閌�Z�p�p��Ƒ�������Ŏg�p����閌�Z�p�p��ł͈قȂ�ꍇ������̂ŁA�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g���̊����̒��ŁA������ŋ��ʂ̗p�ꂪ�g����悤�ɂƍl���A1985�N11���ɐH�i�Y�Ɩ��Z�p�p��W(�������Z�p�p��W�쐬�ψ���E�����n�ӓ֕v)���쐬����܂����B
�ȗ�20�]�N�o���A���Z�p�u�K����J�u���Ă���A2���Ԃɓn���ĐH�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p�S�ʂ��u�`���钆�ŐH�i���Z�p�p��W��⑫�E��������K�v�������Ă����̂ł����Ȃ��Ȃ�����ł����ɂ��܂����B�����ŁA�n�ӂ��ފ����Ăl�q�b�̉^�c���O���ɏ���ė]�T���o���̂ŁA�H�i���Z�p�p��W��⑫�E�������ā@�l�q�b�@News�@No.42�@�ƃz�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��܂����B
|
��Q�P��t�G�������@�@�@�@�@�@�@(2009�N6����������A�@�Q����45��) �u�ŋ߂��h�ߋZ�p�̓����|�h�ߋ@�̏Љ���h�ߎ����@�E�h�ߋ@�̑I��@�|�v�@���J�@�p�i�@�i���É���w��w�@�E�H�w���m�j�u�H�i�̈��S���ƕ��͎����̖����v�g�c����(�i���j���{�H�i���̓Z���^�[)�u���Z�p���猩���������Z�p�v�@�c�Ӂ@���T�@�i�V���T�M�E�T�j�e�[�V�������{�E�i���j�i���j�G�R���{�j�u���Z�p���W�̉ߒ��ƍ���̓W�]�|30�N�]��̖�������U��Ԃ��ā[�v�����@�^��@�i������w��w�@�E�H�w���m�j |
MRC �@News �@No. 42 �@�@2009�N11�����s
�������@�@�@���Z�p���k�\�����A�N�^�[�ɂ�鐅�Y�����p�����̒��������\�@���c�q�v�@�@�@�@�@�@
�i�L�j���c������ �Z�p�m�E�i���Y�E�����Z�p�ė��j������Ɛf�f�m
���W�@�s�H�i���Z�p�p��W�t
�H�i�Y�Ɓ@�������Z�p�p��W�@2009(�l�q�b)
�@�@�@ �n�ӓ֕v�@�i�V�Z�p�J���@�@���@�H�i���E�����Z�p�������E�_�w���m
�H�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p�p��̓���ɂ��Ă̒�ā@�@�@
�n�ӓ֕v�@�i�V�Z�p�J���@�@���@�H�i���E�����Z�p�������E�_�w���m�j
�s��ʌ��e�t
�]���y�Ƃ��̈��S���@�@�@�@�@�_�}�@�i���a���w�H�Ɓi���j
�������K�X�h���C���[�g�T���Z�b�v�h�̏Љ�@
�V���F���@�i�`�f�b�G���W�j�A�����O(��)�j
�]���y�t���[�H�i�����p�������ߋZ�p�\�S�����Z���~�b�N����߃V�X�e���\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�ہ@�m�i���{�|�[��(��)�j
�n��1000m�A�����g�����]�����\�J�~�I�J���f���x���閌�Z�p�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���^�I�v�i���Z�p�U������j
|
��Q�P��H�G�������@�@�i2009�N11���@�������������ف@�Q����42���j �u�E�����̃i�m��߁v�@�������Y�i�X�i���Ɗ�����Б��u�J���������E�H�w���m�j�u���������̎s�ꓮ���ƍŐ�[�Z�p�v���ݐi��i����������Вn�����������E�H�w���m�j�u�H�i�����H��̐H�i�q���@�Ɋ�Â������Ǘ��`���������̍ŋ߂̘b��`�v������V�i�������������������ہj�u�����̒��̉��w�H�w�w�ϕ��͗�߂�Ƃ��ɖ������݂�Ƃ����̂͂Ȃ��|�`�M�Ɗg�U�̂͂Ȃ��Ȃǁ|�x�v�@�ɓ��́i�����H�Ƒ�w��w�@���H�w�����ȁE�H�w���m�j�u�G�}���V�����̑������𗘗p�����V���x�����Z���T�[�v��t��T�@�i�����_�H��w��w�@�A���_�w�����ȁE�_�w���m�j�u���̎x���p���̖����E����v����_��@�i���g�������@�����J�����j�u�����z���܂�p�����@�\���H�i�̕��������Z�p�v��q
�K�m�@�i���{�B���� �������j�@�@�@�@�@�@�@�@ |
MRC News No. 43 2010�N4�����s
�H�i���H�̊�{�Z�p�͕����Z�p�ł���@�@�@�n�ӓ֕v�@
�i�H�i���E�����Z�p�������E�V�Z�p�J���@�@���E�_�w���m�j
3.22�@2010�N�x
2009�N�����Ȋw�Z�p��c�iCSTP�j�ɂ����āA�Ȋw�Z�p�S����b���A�u�����҂��ŗD��ɂ����]���ɂȂ��S���V�������x�̑n�݁v������A30���̒��S�����҂���ь����ۑ肪���肳��܂����B
2010�N�Ɍ����v�擙�����肵�A�������J�n����܂����B�Ő�[�����J���x���v���O�����iFIRST�v���O�����j�́A�V���Ȓm��n�������b��������A���p�����������������J���܂ŁA���܂��܂ȕ����i�K��ΏۂƂ��A���悻�T�N�Ő��E�̃g�b�v��ڎw����[�I�Ȍ����J���x���v���O�����ł��B���{�S�����牞��̂����������҂̒�����g�b�v��30�l�i���S�����ҁj��I�яo���A1�l�̒��S�����҂ɖ�15���~����60���~�̃v���W�F�N�g��C����Ƃ������Ƀ��j�[�N�Ȑ��x�ł��B
�{�v���W�F�N�g�ł́A����(��)�t�F���[�̌I���D�������S�����҂ƂȂ�AMega-ton Water System�i���K�g�����V�X�e���j�̌����ۑ��29���~�]��̗\�Z���l�����܂����B
�{�����ł́A���E�ō����x���̒ሳ�C���W�����t�Z�����G�������g�Ƃ��̑�^���A�ϕ��H���z�Ǎޗ��A�Z�������d�A�G�l���M�[������̗v�f�Z�p�Ƌ��ɁA�P�~�J�����X�C���W�����V�X�e���A1mega-ton�i100��m3�j/���K�́i��400���l�̐����p�������j�C���e���W�F���g��^�C���W�����v�����g�̃V�X�e���Z�p�J���A����Ɋv�V�I�ȉ��������V�X�e���ł͏]���̎�������^���玑�����Y�^�ւ̃p���_�C���V�t�g��}��A���A�G�l���M�[�A�R�X�g�ɔz���������p���Z�p�̊J����ڎw���Č������s�����ƂɂȂ�܂����B
�@�������������̒��ŁA��22��̏t�G�������ł́A�����Z�̌I�����Ɂu���̒m�V�ɂ��Z�p�J���̕K�v���\�ߋ��̌����������m�F���č���̋Z�p�J���ɐ������|�v�Ƒ肵�ču�������܂����B
�{�u���̘b�́A�c���g��MRC����≡�R���YMRC���_����������ČI���D�t�F���[�Ɖz���ŃS���t�����A��A�n�ӂ̎ԂŐ���܂Ŗ߂�A�w�̋߂��ŗ[�H��H�ׂȂ���̉�b�̒�����A������ł����u���e�[�}�ł��B�I�����Ƃ͐̂���̃S���t�̃��C�o���Œ��ǂ����Ē����Ă����W������A�l�̗ւ��d���̏�ő傫�ȃE�G�[�g���߂��̗ǂ���ł���ƍl���܂��B�l�Ƃ̌q���肪�����Ȃ肪���Ƃ����錻�݂ɂ����āA�Ⴂ���X�ɏЉ�鎟��ł��B
�@2011�N2���ɁA�n�ӂ��w��4�N�̑��_�������牶�t�Ƃ��Ă܂��_�ѐ��Y�ȐH�i�����������Ζ����͏�i�Ƃ��Ĉ�ĂĂ����������ؑ��i�搶(MRC�ږ�E���H�i��������������)�����S���Ȃ�ɂȂ�܂����B���ҕK�ʼn�Ғ藣�Ƃ͂����A�߂����o�����ł����B�ؑ��搶�̒Ǔ�����MRC News No.45�Ɍf�ڂ���Ă��܂��̂ł���ǂ��������B
|
��Q�Q��t�G�������@�@�i2010�N6���@��������A�@37���j �u���̒m�V�ɂ��Z�p�J���̕K�v���\�ߋ��̌����������m�F���č���̋Z�p�J���ɐ������|�v�@�I���@�D�@�@�����@�t�F���[�@( �����E�H�w���m�j�@�u���̑f���ł�LCA�𗘗p�������v���ւ̎��g�݁v���{�@�T��@���Y�Z�p�J���Z���^�[�i���̑f�j�@�u�哤�����i�����ɂ����閌������Z�p�̌���v�@���ہ@�����@�Z�p�J�����i�s���j�u�������������D�@�iMBR�j�̐H�i�H��r���ւ̓K�p�v�@�����@�q�@�@�����ƕ��i�X�i�G���W�j�A�����O�j�@ |
MRC News No. 44 2010�N11�����s
���ʊ�e�@
�X�i���Ƃ̖��Z�p�J����U��Ԃ��ā@�@�@�@�@�c���g���@
�i�X�i����(��)�����J���S�������t�E�H�i���E�����Z�p������
����E�H�w���m�j
���W�@�@�킪�Х�킪�������̎����̐V�Z�p��V���i
���ȏ��]�@�g�R�g���₳�����������̖{(�����H�ƐV���Њ�)�@�@
�ɓ��@�́@�i�����H�Ƒ�w���w�H�w��U�E�H�w���m�j
�i�m��ߖ����������p�������t�����l�N���[���u�����t���b�V���N���[�������킢�v
�����@�b��
�@(�������Ɓi���j������敔)�@
���b�O�i�[���j���[�O���g�̊J��
�@�@�@�@���c�@�T�@�i�X�i���Ɓi���j�H�i�����������j
�����N���X�t���[�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������Ё@�g���C�e�b�N�j�@
���S�Ȑ��𐢊E�ɁF��t�@�E�����O�o�u�c�e���t�e�����W���[���@
���݁@�i��@�@�i�����i���@�����u�������Ƒ�2���E�H�w���m�j
���c�@�l�@���{�H�i���̓Z���^�[�̕i���ۏؑ̐��ɂ���
��@�G�q�@�i�i���j���{�H�i���̓Z���^�[�@�����������j
�H�i�̋@�\���]����ڎw������������n�̃Z�b�g�A�b�v
�R���@���O�@�i�i���j���{�H�i���̓Z���^�[�@��Ό������j
�ٕ������̊T�v�Ǝ��g�� �@���ؑ]�@����i�i���j���{�H�i���̓Z���^�[�@�����������j
�y�b�g�{�g�������̏o�ה�����ԒZ�k�V�X�e���̊J���v���@���_�@�i��a��㣁i���j�����������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��e
�H�i�́u�n���v�ɂ��ĐΒJ�F�S�i��ʎВc�@�l���{�H�i�����@�������E�_�w���m�j
�Ȋw�I���̂̍l�����|�ԊO�����M���Ƃ��ā\
�@�@�@�n�ӓ֕v�@�i�H�i���E�����Z�p�������A�����_�H��w�Q�^��������_�w���m�j
|
��Q�Q��H�G�������@�@�i2010�N11���@�������������ف@28���j �u�H�i�Y�Ƃɂ����閌�Z�p���p�̕ϑJ�ƌ���v�@�n�ӓ֕v�@�i�V�Z�p�J���@�@�@���@�_�w���m�j�u�z�d�q���Ŗ@�ɂ��t�Z�����E�̑���|�z�d�q���Ŗ@�̌����Ƒ��萸�x�|�v�哇�i�N�@(�Y�ƋZ�p�����������@���m�i���w�j)�u�H�i�Ɋւ��d�C���̓v���Z�X�v�˓c�@�m�iAGC�G���W�j�A�����O�i���jϰ�èݸޒS�����@�j�u�哤�H�i(�����E���g)�H�Ƃɂ����閌���p�Z�p�v�@ �@�@ �쓈���j�i�H��d�����i���j�쓈���ʌ��������j�u�H�i�H��ɂ�����h���h�l��v�J��@�́i�C�J�����Łi���j���s�����Z�p���������@�b��w���m�j�u�������f�_�i�g���E���̓����Ɛ��E�E�ۂւ̌��ʓI�ȗ��p�v����q�i�i���R���H�ƋZ�p�Z���^�[���w�E�V�f�ރO���[�v���E�H�w���m�j |
MRC News No. 45 2011�N4�����s
�Ǔ����@
�ؑ��i�搶�i���E�_�ѐ��Y�ȐH�i�������������E�l�q�b�ږ�j�̂������𓉂ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�n�ӓ֕v�i�H�i���E�����Z�p������@��E�_�w���m�j
��e�@�@�@
�g�X�̌ċz�h�𑪂�@�@�@�@�@�@�@�@�c���^�I�v�iT.Tech.Office�j
3.23�@�@2011�N�x
�@2011�N3��11���́A�䂪���ł�1000�N��1�x�Ƃ�����n�k�ɓ��k�n�悪�������A����ɔ����Ôg�ƌ��q�͔��d���̎��̂ɂ���ЊQ�������N�����A���{�l�̈��S�ɑ���F���E�G�l���M�[�ɑ���F������ϊv���N�������N�ɂȂ�܂����B
�@�n�k�̃}�O�j�`���[�hM��9.0�ŁA�֓��n�k�i1923�N�j��7.9�⏺�a�O���n�k�i1933�N�j��8.4���͂邩�ɏ���䂪���ł̊ϑ��j��ő�̂��̂ł����B1900�N�ȍ~�ł͐��E��4�Ԗڂɑ傫�Ȓn�k�Ƃ̂��ƂŁA�S���E�I�ɂ͔�r�I���т��ыN����傫���̒n�k�ł������悤�ŁA����̒n�k��z��O�Ƃ��錴�q�͊W�҂̔����͂��܂�ɂ����ӔC�ł���Ɗ����܂��B
|
�}�O�j�`���[�h�i�l�j�F�n�k��������G�l���M�[�̑傫����E�i�P�ʁF�W���[���j�A�}�O�j�`���[�h��M�Ƃ���Ɓ@�@�@�@�@ log10 E = 4.8 + 1.5 M �@�@�@�@�@�@ Mw(���[�����g�}�O�j�`���[�h)��M(�}�O�j�`���[�h)�ƈقȂ�A���L�͂��ڍׂȕ��͌��ʂɂ�蓱���o����A����n�k�̕\�L�ɗp������ |
|
������n�k�̗�F �A�����J�k�����J�X�P�[�h���ݍ��ݑт̒n�k�i�J�X�P�[�h�n�k�j�iM8.7 - 9.2�A1700�N�j |
���̒n�k�ɂ������N�����ꂽ�Ôg�͍ő��㍂40.1m���L�^���܂����B�֓��n���̖����n�̉Y���Ȃǂł͉t���ۂ��������Ă��܂��B���̒n�k�ɂ�鎀�ҁE�s���s���Ҍv��1��9��l�ƂȂ��ЊQ�������炵�܂����B
������ꌴ�q�͔��d���ł́A���f�����E�����g�_�E�����N����A����ԈႦ��Ί֓��ȓ��ɐl���Z�߂Ȃ��Ȃ�قǂ̑厖�̂������N�����Ƃ���ł����B�����d�͂⌴�q�͊W�҂���ɂ͓��{�l�̊�@�Ǘ��̊Â��A���a�{�P�E���S�{�P�����E�ɒm��n�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B
���邢�b�ł́A�����\�����ł����J���͓��������������̖����ŐH�i�����������ɋΖ�����Ă��܂����A�w�������Z�p�̍œK���Ɋւ��錤���x�œ��{�H�i�Ȋw�H�w��܂���܂���܂����B
|
��23��t�G�������@�i2011�N6���@�������������ف@28���j �u�o�u�c�e�������W���[���̓����Ƃ��̉��p�v�@���ݐi��@( �����E�H�w���m�j �u�H�i����ɂ�����t�e����тl�e������߂̗��p�v�Ö{�@�ܘY�@�i�������P�~�J���� ���E���������ƕ��j�u�X�p�C���������W���[����z�肵�������]�������̊T�v�Ƃ��̓K����v�쑺�@�K���@�i�g�X�N(��)�u�r�[���E���A����уr�[���p�����̏��i�R���Z�v�g�Ə���̓����v�@���g�@( �A�T�q�r�[��(����ތ����J���{��) |
MRC News No. 46 2011�N10�����s
��e�@
�\�t�g�R���C�h�̌ʼnt�����@�@�@�@�@���J�@�p�i�i���É���w��w�@�H�w�����ȁj
�K�X����C�������f�ނƂ��ẴC�I���t�́@�@�ɓ��@�́@�i�����H�Ƒ�w���w�H�w��U�j
�{�Ó������g�ރG�l���M�[�n�Y�n���ւ̒���@�@�c���^�I�v�iT.Tech.Office�j
|
��23��@�H�G�������@�@�i2011�N11���@�������������ف@22���j �u���̊�b�m���ƐH�i�Y�Ƃւ̉��p�v���@(���l������w��w�@������@)�@�����i�w�p���m�j�u�H�̈��S�����d�g�݁\���X�N���͂̍l�����\�v�@��J�q�Y�@�i�i�Ɓj�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�@
�H�����@���Ǘ������j�i�_�w���m�j�u�Y���w�̘A�g�ɂ��H�i�Y�ƂɈ琬�\�V�����H�i�Y�Ƃ��Ƃ��ā\�v �@�]��a���@�i�]��Z�p�m�������i���j�V�����H�i�����Z���^�[����) �u�ȃG�l�v���Z�X�̒�ā|���Z�p�ւ̎��g�݁|�v�R��@�m���@�i�ؑ����H�@���J�����j�@�i�_�w���m�j ) �u�Z���~�b�N���̔��W�ƐV�������p��v����T��@�@�i�m�f�j�t�B���e�b�N���Z�p���Z�p��ہ@�ے��㗝�j�u���y�v�`�h�����p�����X�|�[�c���������v�z�q�@�_�i�X�i���Ɗ�����АH�i��Ռ������@�H�i�Z�p�����������j |
MRC News No. 47 2012�N4�����s
��e�@���{�H�i�Ȋw�H�w��@��܋L�O�@
�������Z�p�̍œK���Ɋւ��錤���@��J�_�u�i�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�H�i�����������j�i�H�w���m�j
��e
���̋Z�p�J���A�����ĕ��������̎��̕Ɋw�ԁ@�@�c���@�^�I�v �iT.Tech.Office�j
3.24�@�@2012�N�x
�@1998�N�AMRC��10��H�G��������V���ŊJ�Â����Ē������̂ɍ��킹�āA�����̐V�����H�i�Z�p�������̎�я������V�����ɂ����Z�p�y���������Ƃ��āw�V�����H�i�����p�Z�p������(������:�V�����H�i�Z�p������A���́FFC�V��)�x��ݗ�����܂����B�ݗ��ȗ��A�����V����w��w�@�ɍݐЂ��Ă����n�ӂ͌ږ�Ƃ��ĉ^�c�Ɍg���A2002�N(MRC��14��H�G�������)�A2006�N(MRC��18��H�G�������)�ɁAFC�V���Ƌ��ÂŏH�G���������J�Â����Ē����Ă��܂����B
�@2012�N��FC�V���ݗ�15�N�L�O�̔N�ɂ����邱�ƂƁA���N��2013�N��MRC�ݗ�25�N�L�O�ɂ����邱�Ƃ�����A�v���Ԃ��1��2���̃X�P�W���[���ŁAFC�V���Ƌ��Â�MRC��24��H�G��������V�����f�z�e���ŊJ�Â����Ē����܂����B
�@2007�N����5�N�ԁAUBM���f�B�A(��)�̂����ӂŁw�H�i�J���W�x�ɏo�W�����Ē����Ă��܂������A���ʂ̏��ω����Ă������ߖ{�N�x����o�W�����ނ����Ē������Ƃɂ��܂����B
|
��24��t�G�������@(2012�N6���@�������������ف@22��) �u���q�͔��d���̈��S�Ɠd�C�G�l���M�[�̉~���ȋ����\���{�H�w�A�J�f�~�[����̒\�v�Í�@�V���Y�@�i������w���_�����@�i�Ёj���{�H�w�A�J�f�~�[�Ď��@�H���j�u�t��H�i��Z�p�̐i���ƕi���ێ��v�@�ΒJ�@�F�C(�i�Ёj���{�H�i��Z�p����@�������@�_��)�@�u�Z���~�b�N���̔��W�ƃ[�I���C�g���@����p�����o�C�I�G�^�m�[���Z�k�E�E���Z�p�̊J���v���c�@�D�i�������D�i���j���ƁE���i�J���{���j�u�������v�����g�����������v���Z�X�̃t�@�E�����O�}���ƒ�R�X�g���Ɍ��������g�݁\���x���������̗��p�\�v����@���m�@�i�����Ł@�d�̓V�X�e���Ё@�d�́E�Љ�V�X�e���Z�p�J���Z���^�[�j |
MRC News No. 48 2012�N10�����s
���ʊ�e�@
�T���̊��p����C����̕�����ڎw���@�쑺�@�`�G�i�����_�H��w�E�d�`�������p�����{�݁j
|
��24��H�G�������@�@(2012�N9���@�V���s�E���f�z�e���@91��) ���ʍu���@�u�䂪����ׂ��l���v�@�ێR�@�q�@�i�V�����ĉٍH�Ƌ����g���@�������j�@ �L�O�u���@�u�e�b�V��15�N�E�l�q�b24�N�̕��݂ƐH�i�Z�p�J���v�@�n�ӓ֕v(�H�i���E�����Z�p������@��@�V�����H�i�Z�p������ږ�@�_��)�@�@�u�X�i���Ƃɂ�������E�G�l���M�[���ւ̎��g�݁v�@����
��l�@(�X�i���Ɓi���j���Y�{���̊��@����)�u�V�����H�i�����Z���^�[�@�H�i�H�w�Ȃ�15�N-�v�@���@���@�@(�V�����H�i�����Z���^�[�@�H�i�H�w�Ȓ��@�_��)�@�u�H�i�ɌW���ŋ߂̘b��ƕ��͎����̏v�@���v�ԋ`���@(�i���j���{�H�i���̓Z���^�[�@���q�l�T�[�r�X���@����)�u���Z�p�J���Ƃ��̗��p�v�@��J�_�u�@(�_���@�\�E�H�������� �H��)) �u�ЊQ���̐H�ɋ��߂�����́E�V�ЂƔ��H�v�@�����@�E�@(�V����w�_�w���y�����@�_��) �u���ۉ���Ĕт̐����Z�p�v�Ԓˏ���@(�����H�i�H�Ɓi���j���s�����@���Y�{�����{����)�u�V�����̐��Y���萻�i�̓����v�C�V���G�@(�V�������Y�C�m���@���H�ہ@�ے�)�u�V�������̕ĕ����i�Ɠ����@�v����`���@(�V�������i���j�햱�����) |
�@
MRC News No. 49 2013�N4�����s
�@�H�i���E�����Z�p������iMRC�j�ݗ�25�N�L�O�ɂ�������
�@�@�@�@�@�n�ӓ֕v�@�@�i�_�w���m�j�@�V�Z�p�J���@�@���@�l�q�b��@�@
�AMRC�n��25���N�ɂ悹��
�c���g��@�@�i�H�w���m�j�@�X�i���Ɗ�����Ё@�l�q�b����@
�B�킪�Ђ̎����̐V���i�V�v���~�A���A�C�X�N���[���umeiji THE
PREMIUM Gran�i�O�����j�v�@�L�c�@���i�H�w���m�j�@������� �����@�i���Ȋw�������@�l�q�b����
�C���Ђ̖��Z�p���p���i�̂��Љ�
�z�q�@�_�@���m�i�H�w�j�j�X�i���Ɗ�����АH�i��Ռ������@�l�q�b����
�D���Ђɂ����閌���p�ɂ���
�g���F��Y��O�~���N���~���N�T�C�G���X�������H�i���H�������l�q�b��
�E�r�[�����h�߂ɂ����閌�̗��p
�剺�@�����@�@�@�@�T���g���[��ފ�����Ё@���s�r�[���H��Z�t��
�F��t�@�E�����OPVDF�������W���[���ƐV�K����߉^�]�Z�p
�H��a��A�X�씎���A���ݐi��(�H�w���m)�����i���j�����u�������Ƒ�2���@�l�q�b����\����
�G���^���O��ߖ����W���[��
���ˏC�u�@�@�_�C�Z���E�����u�����E�V�X�e���Y������ЋZ�p�J���Z���^�[�@�����@
�H�킪�Ђ̐����p����ߐݔ��@�@���c���a�@�@�I���K�m���@�\�ޗ����@
�I��ɂ�鐅�������̕��ː����E�f�����Ɋւ��錤��
�����T�@�@�@�@(��)���{�H�i���̓Z���^�[�@����������
�J�H�i�Y�Ƃɂ����閌�E�����Z�p���p�̓���
��ȖF�s�@�@�@UBM���f�B�A���@�����u�H�i�ƊJ���v�ҏW��
�K�V�������Z�p�@�h�t�B�����͔|�h
�c���^�I�v�@�@�Ȋw�Z�p�W���[�i���X�g�@�@�l�q�b����\����
�L�H�i���Z�p�Ƃ̏o��@�|�V���y�f�^�����A�N�^�[�̊J���|
���c�q�v�@�@�Z�p�m(���Y������Z�p�ė�)�@�l�q�b�ږ�
�M�H�i�Y�Ƃɂ����閌�������u�̐��Ɍg�����
�c�Ӓ��T�V���T�M�E�T�j�e�[�V�������{�@(��)�G�R���{������Ё@�l�q�b�ږ�
�N���C���p�{�g���ʂ̊J���@�@�@���� ���@��a��㣊�����Ё@�����������@������@
�O����̓d�͎���ɂ��Ă̈�l�@
�Í�V���Y�@(�H�w���m)�@������w���_�����@�l�q�b�ږ�
�P��������p�����V�K���\�G�l���M�[���d
��Á@�[(�H�w���m)�E����@����(�H�w���m)�@�R����w��w�@���H�w�����ȁ@�����@�@�@�@
�Q�b���̉t����������Z�p�@
�����@�K���@(�_�w���m)�@�����_�H��w�_�w�����@�@�@�����@�l�q�b���
�R���̓X�e�b�v����O�h�ߖ@�Ɋ�Â��P�[�N���k���̕]��
���J
�p�i�@(�H�w���m)�@���É���w��w�@�H�w�����ȁ@�����@�l�q�b���
�S�V���O���������@�̍ĕ]��
�ɓ��@�́@�i�H�w���m�j�@�����H�Ƒ�w���w�H�w��U�@�@�����@�l�q�b���
21�H�i���E�����Z�p������(�l�q�b)25�N�̂����
�@�@�@�@�n�ӓ֕v�@�i�_�w���m�j�@�����_�H��w�Q�^�������@�@�@�l�q�b��@
�@
3.25�@�@2013�N�x
1989�N(�������N)�ɐݗ����ꂽ�l�q�b��2013�N�Őݗ�25�N���}���܂����B��25��t�G�������̑O�ɋL�O���T���s���A�l�q�b2���̑��F�搶�A���E�h�߉�c���{���̓��J�搶����j�����܂����B�c���������́A�l�q�b�������\���č���̎��g�ݕ��j�Ɋւ��鈥�A������܂����B�����̖ؑ����j�搶�ɂ��j�������肢���܂������A���s���������Ƃ̂��Ƃł����B
25�N�Ԃɂ킽��H�i���E�����Z�p�Ɋ֘A����ŐV���M�������Ă����l�q�b�j���[�X�S��50���܂ł��b�c�Ɏ��^���āA25�N�L�O���ƂƂ��ĉ���F����ɔz�z���邱�Ƃɂ��܂����B�l�q�b�j���[�X50����������A�����������Ăb�c���쐬���܂��̂ł����������҂����������B
�Љ��́A�C�m�i�o���͂��钆���ƃA�W�A�����Ƃ̖��C�������A�䂪���͐�t�������߂����i�Ƌْ������܂����܂��B�܂��A���j�F�����߂��蒷�N��������𑱂��Ă����؍����V�哝�̂ɑ��]���ȏ�ɉ䂪���ɑ��锽���p�������߂ė��Ă��܂��B�������A���̃A�W�A�����͓��{�̗F�D���Ō����ĉ䂪�����Ǘ����Ă���킯�ł͂���܂���B
���ׁi�����܂�j��2�������{�ᔻ���J��L���Ă���A�h�ʌ����߂����Ă͍��ɂ����͏Փ˂��N�����Ă����������Ȃ��ɂȂ��ė��Ă��銴���܂��B����́A�䂪���͈��͂�������A�n�b�L���Λ����Ȃ��ň������ł���ƒ�����؍����l���Ă���A���j�F�������ɉ��������������Ƃ��������̐헪�ɂ̂����s���ł��B
���{�l���n�b�L�����̂�����Ȃ��͓̂��{�l���m�ł͈�ʔ����ł͂���̂ł����A�Ȋw�Z�p�ɂ����Ă��A�������ȋU���i�H�j�Ȋw�Z�p�ɂ��Ă��̂�����Ȃ��ƁA�Ȋw�Ҏ��̂̔\�͂��^���邱�ƂɂȂ�܂��B���q�͂��߂����č��܂Ō��q�͊֘A�̉Ȋw�҂������Ă������S�_�b�����S�ɕ���Ă��܂��܂����B���������_����A50���ł͓n�ӂ��g�������đ̌��������e���܂߂ĐH�i�ƊE��Y�܂��U���H�i�ƋU���i�H�j�Ȋw�Z�p�����グ�Ă݂܂����B
�@2013�N�̈Â��j���[�X�Ƃ��Ă͋�B��w��⫓��L�搶���S���Ȃ�ꂽ���Ƃł��B�l�q�b�j���[�X50���̒Ǔ����ɏq�ׂ��悤�ɁA�n�ӂ̊w�ʐR���̕��卸�߂ĉ�����A�ȗ��A�l�q�b�ݗ�����ɂ���B���삯���ĉ������܂����B�l�q�b��14��H�G��������V���ŊJ�Â����������u���ɂ����ʼn�����A�I����A�l�q�b�Ƃe�b�V���̕��X��1���ō��n���w�ɍs���Ȃǂl�q�b�̉^�c�ɑ傫�ȍv�������ĉ��������搶�ł��B�搶�̂����������F�肢�����܂��B�����т�l�q�b�Ƃ̊W�ɂ��Ă͒Ǔ������������������B
|
MRC�ݗ��Q�T�N�L�O���T�@�@(2013�N6���@�������������ف@) �@ �J��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�l�q�b �@��@ �n�ӓ֕v �A �@�@�@
�@�@�@�@�@�j���@�@�@�l�q�b�Q��@��@
���F �B �@ �@�@�@�@�@�j���@�@ ���E�h�߉�c���{�� ���J�p�i �C �l�q�b�����\�@
���A�@�@ �l�q�b��� �c���g�� �@��25��t�G�������@�@(2013�N6���@�������������ف@32��) �@�L�O�u���@MRC25�N�̂���݂Ɩ��E�����Z�p�J���@�n�Ӂ@�֕v�@�E�@�_�w���m �i�H�i�������Z�p������E��j�i�����_�H��w�E�Q�^�������j �A���ʍu���@�H�i�]���ƐV���i�J���@�╍�d��
�@�E�@�_�w���m ((��)�X�i���ƁE�햱���s�����@) �B�ŋ߂̖��Z�p�̔��W�ƓW�]�@�\���o�X�gRO/NF���̊J���\ �s���@�����E�H�w���m�i�L����w��w�@�E�����j �C�s�s�����̋@�\���ɂ�鍂�x��������я������̐A���H��ւ̓W�J ���R�@���Y�@(�l�q�b���_���)�i(��)�@���{�s���A�E�H�[�^�[�E�ږ�) �D�����u�̉q���Ǘ��ƍŋ߂̃T�j�e�[�V�����Z�p �{�V�@�j�F�@�i�G�R���{�i���j �Z�p���}�l�[�W���[�j |
�l�q�b�j���[�X�ւ̎s�̖��ꗗ�̓��W�́A5���i1990�j�A13���i1994�j�A21���i1998�j�A28���i2002�j�A38���i2007�j�Ɖߋ��T��A�قڂT�N�����Ƀf�[�^�[���X�V���Ă��܂����B�s�̂���Ă��閌�ꗗ�̃f�[�^�[�x�[�X�͂l�q�b�j���[�X�ȊO�ɂȂ����ߑ�������̕��X����̈�������������A�N�Ԑ����̂l�q�b�j���[�X������ȊO�̉�Ђɍw������Ă��܂��B�f�[�^�[�̐����́A���H��̈ɓ��͐搶�ɂ��肢���A���̓x�����W���Ƃ��ďo�ł��邱�Ƃɂ��܂����B
MRC News No. 50 2013�N12�����s
�@�@�@�H�i���E�����Z�p������(�l�q�b)25�N�̂���݁\���W�ҁ\�l�q�b��n�ӓ֕v
�A�@⫓��@�L�搶�̂������𓉂ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�q�b��@�@�n�ӓ֕v
�����w�@��w�����@���c�p��
�B���ʊ�e�@�U���H�i�ƋU���i�H�j�Ȋw�Z�p�@�@�@�@�@�l�q�b��@�@�n�ӓ֕v
�@�C�@Mega-ton Water System�@���ۃV���|�W�E�����@ �l�q�b��@
�n�Ӂ@�֕v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�q�b�����@ �c�Ӂ@���T
�@�D�@���W�\�s�̖��ꗗ�\
|
�@��25��H�G�������@�@(2013�N11���@�������������ف@30��) �@�ʼnt�����ɂ����閌���p�̓W�J�@ ���J�@�p�i�i�����E�H�w���m�j ���É���w��w�@�@�@�H�i���E�����Z�p������@��� �A���Z�p�J���ւ̒���E�S�O�L�]�N�@�\�������x����Ⴋ�����ҁE�Z�p�҂ɑ��錾�t�\ ���R�@���Y�@�}�g��w�k�A�t���J�����Z���^�[�q������������ �i���j�����i���j�E�H�i���E�����Z�p������@���_��� �B�T���̊ۂ��Ɗ��p�ɂ�铌���{��k�Ђ���̕����x���@�`�C����ł̎��g�݁` �쑺�@�`�G�i�����E�_�w���m�j�����_�H��w�@�d�`���������{�� �H�i���E�����Z�p������@��\���� �C���Z�x�t��H�i��ΏۂƂ������ߗ����̗\���@�\�`�[�Y�z�G�C�E�������Ƃ��ā\ �c���g���@�@(�H�w���m)�@ �X�i���Ɗ�����Ё@ �H�i���E�����Z�p������@��� |
4�D���E�����Z�p�J���̕���
4.1�@MRC�ݗ����ɒ�Ă������Z�p�J���̕���
�l�q�b�̐ݗ����A1989�N6���̑�1��t�G�������ɂ����āu�H�i�J���ɂ����閌�Z�p�̖��́\����ɖ��Z�p�W�����邽�߂ɂ́\�v�Ƒ肵�ču�������Ē����܂����B�����ł́A���ꂩ��̌��������Ƃ��Ĉȉ��̓_���Ă��Ă��܂��B
�@�H�i�E�o�C�I����ł̕����E�����E�Z�k�ɂ����Ė��Z�p�͕K�{�̋Z�p�ɂȂ��Ă��遖�H�i�������A���������邱�Ƃɂ��V�����H�i�̑n�o���o�C�I�e�N�m���W�[���p�ɂ����镨�����Y�ɂ����Ẵ_�E���X�g���[���Z�p���H�i�̍��i���������i�폭�ʐ��Y�ւ̑Ή��������M�W���[�X����ш����̐����������u�����o�C�I���A�N�^�[�̊J���\�V�����̐G�}�^�Ƌ������ߌ^�\
�A���E���W���[�����̂��̂̋@�\�����コ������]�n�����遖�ϔM���E�ϖ�i���E�ϋv���E�ψ��͐��̌��ざ�n���z�����̉��ǁi�\�ʉ����j�����o�E�����H���ւ̗��p���A�t�B�j�e�B�[�����̊J������ї��p�@�̊J�����A������\���A���ց����̖��̎����@�\�ւ̐ڋ�
�����W���[���Ƒ��u�̉��ǂɂ�薌�̕������\��ς����遖�����W���[���\���̉��ǁ����u�v�@�̉��ǁ��^�]�����̑I��
�B�w��I���������̕����@�\�̉𖾁i���̖��E�l�H�����Ɂj��Fouling�ɂ�閌�@�\�̒ቺ�@�\�̉𖾁����q�H�w�I�v�Ɋ�Â����̍쐬�@�@
��Ă���25�N�Ԍo�������A�����̒�Ă̈ꕔ�͎������A�ꕔ�̓n�[�h���̍������猤���r��ɂ���A����Ɉꕔ�͎������s�\�ł͂Ȃ����ƒ��߂����Ȃ�悤�Ȃ��̂�����܂��B�������A�����̕����Ƃ��Ă͐������ƍl�����A������`�������W��������K�v���������܂��B
4.2�@���݂̎Љ��Ɩ��E�����Z�p�J���̕���
�@20�N�Ԃ̖��E�����Z�p�̔��W�܂��A���݂̎Љ��Ɩ��E�����Z�p�Ƃ̊ւ��ɂ��ĕM�҂Ȃ�ɐ������\�S�Ɏ����܂����B����̖��E�����Z�p���W�̕����́A�����̏z�E�ė��p�V�X�e���̍\�z�C�H���������̌���C���N�ێ��ɖ𗧂H�i�A���S�ȐH�i�E���������H�i�̐������ɖ𗧂Z�p�J���ƍl�����܂��B
�@�ߔN��BRICs�����̌o�ϓI���W�ɂ�鍒�ޏ���̑�����o�C�I�R�������̂��߂̍��ޗ��p���ɂ�萢�E�̐H������N�����A�䂪���̐H���̒l�i���������ĉƌv���������Ă���Ƃ̔ߖ��������Ă��܂��B�������A�䂪���̐H����������40%��������Ă���ɂ��S��炸�A�e���r�ł̓`�����l�����O�����ԑg�S���Ő��E����H�����������ґ�̌����s���������������Ă���悤�Ɍ����܂��B���̓�̌��ۂ͂ǂ��炪���{�̎����\���Ă���̂ł��傤���B���́A���̓�̌��ۂ͂ǂ�������{�̎���Ȃ̂ł��B
���n�̌����ҁE�Z�p�҂͈�ʂɎЉ��ɑa���̂ŁA�Q�l�̂��ߌ��݁i2008�N�����j�̎Љ�I���������܂��ƁA�䂪���̋��^�����w�͂Q�lj����Ă��܂��Ă���A�K�ٗp����ʉ����Ă��܂��B�ʔN�ŋΖ��������^�����Ґ���4485���l���܂����A���̂����A�N����200���~�ȉ��̐l��1022��7000�l�ŁA������759��7000�l�A�j����263���l�ƂȂ��Ă��܂��B����A�N��1000���~�ȏ�̐l��224��2000�l�őO�N��4.4�����ɂȂ��Ă��܂��B���^�̕��ς�435���~�őO�N��2���~�Ⴍ�Ȃ��Ă���A9�N�A���Ō������Ă��܂��B����ɔ���2006�N�ɖ��Ԋ�Ƃ��x���������^�̑��z��200��346���~�ƑO�N���0.8���������Ă���ɂ��S��炸�A�������ꂽ�����Ŋz�͑O�N��9.9������9��9321���~�ŁA���^���z�ɐ�߂�Ŋz�̊�����4.97����3�N�A���ő������Ă��܂��B���^�����w���Q�lj����Ă��邱�ƁA��������܂ł͌i�C���ǂ������Ƃ���Ă��܂����A��X�����ɂ͍D�i�C�������ł��Ȃ��������Ƃ͏�L�̏��番����܂�
�Ꮚ���ґw�̏�������Ƃ����������X�ɐH�����������邱�Ƃ͉䂪���̐�������ɂ������ł�����̂ƍl�����܂����A���̂��߂̍���������łɒZ���I�ɋ��߂�̂łȂ��A�ŋ��̖��ʎg�����Ȃ��A�����̗ǂ��s��������w���i������K�v������܂��B�ŋ��̖��ʌ����́A�Љ�̐��n���ɔ����e��̎Y�ƁE�K�w���l�����Ă����������v���A�Љ�\�����ω������̂Ɏ��ʂ����Ƃ���Ƃ��납�琶���Ă�����̂ł��B�Â��̎��̉�Ђł��������Ƃ��N��̂ł����A��Ђ̏ꍇ�͋Ɛѕs�U���邢�͓|�Y�Ƃ����u���[�L��������̂ɑ��A�O�҂̏ꍇ�͓|�Y�̊댯���������ĂȂ��Ƃ���ɖ�肪����܂��B
�H�����i�̍����͐��E�I�ȌX���ŁA�䂪�������̓w�͂őS�ʓI�ɉ����ł�����ł͂Ȃ��̂ł����A�p�������H�������̗L�����p�Ɣr������̗L�������̉�����ɂ��A���H���E����H�����������邱�Ƃ͂ł��܂��B�����������ɒǂ��ł��������Ă���̂��A�A���H���̈��S���ɑ����ŁA����_�ŕ��̕��͂ɂ������p�͔���Ȃ��̂ɂȂ�ƍl�����܂����A���Ɍ̈ӂɓŕ�������������ꂽ�ꍇ�͔�����茟���ł͔���������Ȃ��ł��낤�Ƃ����s��������܂��B
�\�S�D�@���݂̎Љ��ƐH�i���E�����Z�p�J���̕���
|
���݂̎Љ� |
���� | �����̂��߂̕��� | �H�i���E�����Z�p�J���̕��� |
|
�o�ϊ����̑��� |
�E��ʐ��Y���ʏ��陋�ʔp�� �E�n������� |
�E�Ȏ����E�z�^�Љ�\�z �E���C�t�T�C�N���A�Z�X�����g�i�k�r�`�j |
�E�H�i���H�r������̗L�������̉����ė��p |
|
���E�l���̑����EBRICS�̔��W |
�E���E�I�ȐH���s�� ����E�I�G�l���M�[�s�� |
�E�H���������̌��� �E
�ȃG�l���M�[���H�Z�p �E�H�������̗L�����p |
�E�哤���A���������̗L�����p �E�����p���k�͔| �E�H�i���H�r������̗L�������̉����ė��p �E���̍ė��p�V�X�e�� |
|
���������̌��� |
�E���S���u�� �E���N�u�� |
�E���ۉ��h�ߋZ�p�̗��p |
�E���y�E�����H�i�̈��S���m�� �E�������E�H��p���̖��ۉ� �E�@�\�������̕��� �E�H�i��������ɂ��V�H�i�̑n�� |
|
����Љ� |
�E���������H�i�u�� �E���N�u�� |
�E���ۉ��h�ߋZ�p�̗��p |
�E���𥐶�W���[�X�����̕��������������̐��� |
1973�N��1979�N�̃I�C���V���b�N�̍ۂ́A�r���E�p��������L��������������������ɗ��p���܂����B�������A���̌�̉~���̐�����A���ނ͊O������w��������������������Ă��܂����B���ꂩ���茵�����𑝂��Ă���ƍl�����鐢�E�̐H������̕N���͍P�v�I�Ȃ��̂ƂȂ�ƍl�����I�C���V���b�N���̑�ȏ�̓w�͂��K�v�ɂȂ�A���E�����Z�p�̖����͂���w�d���Ȃ���̂ƍl�����܂��B
�T�D������
�@�l�q�b���ݗ�����25�N�̍Ό�������܂����B�ݗ�������130�З]��̊�Ɖ�����Q�����Ă��܂������A���݂�3����1�̋K�͂Ɍ������Ă��܂��܂����B�������A25�N�̒����ɂ킽���Ė��E�����Z�p��^�ɕK�v�Ƃ��ė��������̊�Ɖ�����c���Ă��ꂽ���̂Ɗ����Ă��܂��B�܂��A�H�i���Z�p�u�K���ъ�b���Z�p�u�K��ɂ����ẮA����O�̊�Ƃ̕��X�������߂���u����܂��B����O�̊�Ƃ�����ɂȂ��Ă����l�q�b�̉^�c�͊y�ɂȂ�̂ł����A�N���͕��������Ȃ������Z�p�͗��p�������A���邢�͖��Z�p�Ɋ֘A����Z�p�҂��琬�������ƍl�����Ƃ��������邱�Ƃ��Ӗ����Ă�����̂ƍl�����܂��B
�@�A�x�m�~�N�X���v���X�ɏo�邩�}�C�i�X�ɏo�邩�c�_�̕������i�K�ł͂���܂����A�䂪���͋Z�p�J���E�Z�p�����𑣐i���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͋i�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B����A�H�i���H�Z�p�̒�����S���܂łɐ����������Z�p�W�����A����Ɍ�i�̌����ҁE�Z�p�҂��琬����������l�q�b�Ƃ��ĉʂ����čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@�䂪���̗��n�̑�w����E��w�@����ł́A�d���̋���k�}�ł��悤�Ȃ��܂�Ӗ��̂Ȃ������ł��A�������s���A�f�[�^�[�����܂Ƃ߂Ċw�p�_������邱�Ƃ��w�ʂ��擾���邽�߂ɕK�v�Ƃ���ė��܂����B���̂��߁A��ʓI�ɁA�䂪���̗��n�o�g�҂̎���͋��������̃^�R�c�{���Ă菟���ŁA�S�̂����Ȃ������ҁE�Z�p�҂���X���ɂ��邱�Ƃ��뜜����Ă��܂����B���̓T�^�I�Ȍ��ꂪ���q�͑��ł���A�����������̂ɂȂ������ƍl�����܂��B�O�L2���̗��n�o�g�̑�����b�����̌��ꂩ������܂���B
�@���ꂩ��̎Љ�͑��l�Ȑl�ނ��K�v�ł���A���n����ɂ����Ă����l�ȋZ�p���R�[�f�B�l�C�g����̋Z�p�V�X�e���Ƃ��đg�ݗ��ĂĂ�����l�ނ̈琬���K�v�ƍl�����܂��B���Ȃ킿�A�X�̗v�f�Z�p���V�X�e���Ƃ��đg�ݗ��āA���S�ɃV�X�e�������Ă�����l�ށA���C�h�A���O���̎�������l�ނ̈琬���K�v�ƂȂ�܂��B�������A�X�̗v�f�Z�p�̌����J�����s���l�ނ��琬����K�v�����邱�Ƃ͐\���܂ł�����܂���B
�@���������Ӗ�����A�I�����̎w������Mega-ton Water
System�i���K�g�����V�X�e���j�̌������傫�Ȑ��ʂ��グ�邱�Ƃ����҂���Ɠ����ɁA�l�q�b�ł͔N2��J�Â��閌�Z�p�Ɋ֘A����u�K��ŏ�L�̋Z�p�҂̈琬���߂������܂ňȏ�̔M�ӂ������Ăl�q�b���^�c���Ă����\��ł��܂��B
�@����Ƃ���낵�������͂��������܂��悤���肢�\���グ�܂��B
�Q�l����
�P�j�H�i�Y�ƃZ���^�[�Z�p�����@���W�@�����Z�p�F12���i1988�j
�Q�j�x�c��;�@�玙�p�����̊J���Ɩ������Z�p�F�@���@21�i2�j85�i1996�j
�R�j�n�ӓ֕v;�@�������Z�p�ɂ�������F�h�ۖhꀊw��@8�i10�j436�i1980�j
�S�jA. Watanabe, S. Kimura and S. Kimura; Flux Restoration of Reverse Osmosis
Membranes by Intermittent Lateral Surface Flushing for Orange Juice Processing:
J. Food Science Vol.43. 985(1978)
�T�jA. Watanabe, S. Kimura, Y. Ohta and S. Kimura; Nature of the Deposit on Reverse Osmosis Membranes during Concentration of Mandarin Orange Juice: J. Food Science
Vol.44. 1505(1979)
�U�j�ؑ����j�A�n�ӓ֕v�@��\�ҏW�F�H�i�����ɂ����閌���p�Z�p�G�H�i�Y�Ɩ����p�Z�p�����g���i1987�j
�V�j�����p�Z�p������G�H�i�Y�Ƃɂ����閌�����V�X�e���F�Ő�[�������Z�p�ւ̉��p����ԏ��X�i1989�j
�W�j�H�i�Y�ƃn�C�Z�p���[�V�����E�V�X�e���Z�p�����g���ҁA�@�\���H�i�f�ނ̍��x�����E�����ƊJ��(1992)