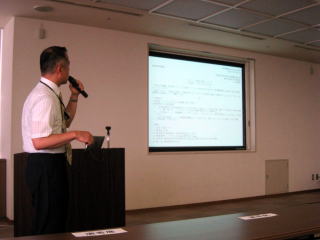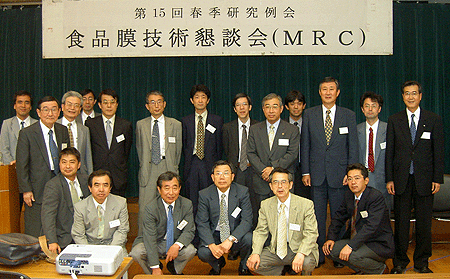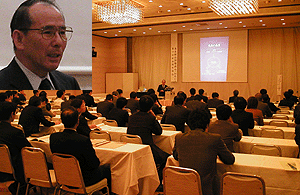研究例会の記録 |
|---|
第36回 秋季研究例会プログラム・講演概要(対面・オンライン併用)
日時:2024年11月7日(木) 12:35~19:00
場所:(一財)日本食品分析センター別館 日本水産油脂協会ビル
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町32−7 TEL 03-3469-7131
主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
2024年度総会・第36回春季研究例会プログラム・講演概要
2024年6月13日
|
35年記念式典・2023年度 総会 |
① 開会挨拶 |
MRC会長 |
渡辺敦夫 |
12:15~12:35 |
|
|
③ 2023 年度 総会 議事 |
12:35~12:55 |
||||
|
休憩 ( 5 分) |
|||||
|
研 究 例 会 |
|||||
|
題 目 |
講 演 者 |
|
|||
|
① 記念講演 或る農林官僚の回顧録 |
中川 坦 |
13:00~13:55 |
|||
|
講演概要 |
初めに農水省の機構と各局の連携等組織運営の概要を紹介する。その後、我が国でのBSE発生を受けて食品安全行政を抜本的に見直すこととなり、新設された消費・安全局長として、3年間の在任中に体験した様々な事件・事故への対応の内、特に米国でのBSE発生と牛肉輸入問題への対応の顛末を振り返る。さらに、タンザニアでの大使の日常についても紹介したい。 |
||||
|
休憩 ( 5 分) |
|||||
|
② 特別講演 |
栗原 優 ( 工学博士 ) |
14:00~14:25 |
|||
|
講演概要 |
逆浸透膜による海水淡水化 (RO 法 ) は、膜の発明以来
60 年が経過した。中東中心に長年蒸発法と競合してきたが、 RO 法が主流となり日本は RO 膜で70%以上の市場シェアとなっている。プラント規模は 100 万トン / 日( 400万人の生活用水相当
) と大型化し、太陽光発電を使用し、造水コストは $ 0.3 - 0.5/ m3と手頃な価格となっている。 |
||||
|
休憩 ( 10 分 ) |
|||||
|
③ SDGs を支え る
膜技術 |
渡辺敦夫 (農学博士) |
14:35~15:00 |
|||
|
講演概要 |
澱粉製造・大豆加工・小豆加工・水産練り製品・ミルク加工・畜肉加工等の排水から有価成分の回収利用の実用・研究が、円高が進む前にはきめ細かく行われていた。円高が進み食料・飼料が安く輸入できるようになりこれらの装置が停止させられた。 SDGs・食料安全保障そして円安の進む中で食料資源の有効利用を再考する必要がある。また、おいしい食品・安全な食品製造に膜技術は不可欠である。膜技術の果たしてきた役割と今後の可能性について紹介する。 |
||||
|
休憩 ( 5 分 ) |
|||||
|
④ ㈱明治における膜分離技術の現状、課題、将来展望 |
豊田 活(工学博士) |
15:05~16:00 |
|||
|
講演概要 |
㈱明治ではチーズホエイ濃縮用の RO/NF 膜装置やチーズホエイ中のたん白質を分離、濃縮する UF 膜装置、生乳
/脱脂乳濃縮用 RO/NF 膜装置、更には高付加価値な乳飲料やクリームの製造用 NF 膜装置など多くの膜分離装置 を稼働させている。本講演ではこれらの事例を紹介し、㈱明治での膜利用の現状、課題などを紹介する。 |
||||
|
休憩 ( 5 分 ) |
|||||
|
⑤ プラントベースドフードの発展―大豆タンパクの
分離・大豆ミートと大豆利用の現状と展望― |
佐本 将彦 ・博士(農学) |
16:05~16:55 |
|||
|
講演概要 |
弊社の創業者は、大豆タンパク質が将来のプロテインクライシスのリスクヘッジとして期待される理念を示し、その商品開発を強く導いた。伝統食品とは異なるユニークな物性を示す大豆タンパク質素材の SPI 、TVP 、さら に、プラントベースフード( PBF )のコンセプトに沿った分画豆乳やプライムミートなどの商品を紹介する。 |
||||
|
交 流 会 1.開会の挨拶
2.乾杯 3. 会員からの MRCへの応援・助言 等 4.締め |
17:10
~19:00 |
||||
|
食品膜・分離技術研究会(MRC) |
||||
|
第34回秋季研究例会プログラム・講演概要(対面・オンライン併用) |
||||
|
日時:2022年11月18日(木) 12:35~17:00 |
||||
|
開会挨拶 |
MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) |
12:35~12:45 |
||
|
休 憩 (講演準備) |
12:45~12:50 |
|||
|
研 究 例 会 |
||||
|
題 目 |
講演者 |
|||
|
① 循環型社会の実現を目指す当社の膜技術―チューブラー膜モジュールの新展開― |
中塚 修志 (工学博士) |
12:50~13:45 |
||
|
講演概要 |
地球環境の変化が激しい中、水・食料・エネルギーを三位一体で考慮し、循環型社会の実現を目指していくことが極めて重要である。本講演では、将来の水循環社会を俯瞰し、その中での貢献を期待して、当社が最近開発したチューブラーRO/NF膜モジュールの特徴と適用事例を中心に当社の膜技術を紹介する。 |
|||
|
休 憩 (講演準備) |
13:45~13:50 |
|||
|
② 植物性タンパク質の特性と食品への応用 |
廣瀬 太洋 |
13:50~14:45 |
||
|
講演概要 |
環境への負荷が小さいタンパク質源として注目を浴びている植物性タンパク質のうち、小麦グルテンの基礎的な物性から、それらの物性を活かした食品への応用、および昨今の社会的課題の解決に向けた活用方法まで幅広く紹介する。 |
|||
|
休 憩 (講演準備) |
14:45~15:00 |
|||
|
③ 軟質食品の3D フードプリンティング研究 |
堀内 真美 (博士(工学)) |
15:00~15:55 |
||
|
講演概要 |
3D フードプリンターは、3D CADのデジタル設計データを食品で直接出力することができ、従来の食品加工技術では実現できない未来の食を創り出す技術として期待されている。本講演では、介護食などに適した軟質食品を中心とする3Dフードプリンティング技術とその可能性について紹介する。 |
|||
|
休 憩 (講演準備) |
15:55~16:00 |
|||
|
④ マイクロ科学工学に基づく脂質食品の構造制御と高度化 |
中嶋光敏(工学博士) |
16:00~16:55 |
||
|
講演概要 |
食品特性はその構造に依存し、目的とする機能を発現するためにマイクロ科学工学に基づく構造制御が重要である。非多孔質疎水性膜を用いた脂質成分分離、単分散液滴の製造を可能とするマイクロチャネル乳化、脂肪酸で修飾した高活性リパーゼを用いた油脂のエステル交換技術について易しく紹介する。 |
|||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
|||
|
交流会(於;ラウンジリリア・川口リリア1階) |
17:00~19:00 |
|||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
| 日時:2022年6月21日(火) 12:20~19:00(総会・研究例会・交流会) 開催方法: 対面 オンライン(Microsoft Teams)併用にて開催 開催場所:川口総合文化会館(川口リリア)11階 大会議室(JR川口駅西口至近) |
|
| 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近) 主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)(TEL: 090-4534-1489) 協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設 |
|
|
2022年度総会 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) |
12:20~12:45 |
||
|
休 憩 |
12:45~12:50 |
|||
|
研 究 例 会 |
||||
|
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
||
| 日本生物工学会 2021年度生物工学技術賞受賞記念講演 ① 「ペプチドアレイ」を基盤とする低抗原性生理活性ペプチドの製造に関する研究
|
越智 浩 ・ 博士(工学)
(森永乳業株式会社研究本部素材応用研究所 副所長、バイオプロセス研究室 室長、デイリーマテリアル研究室 室長)
|
12:50~13:45 |
||
|
講演概要 |
乳たんぱく質の酵素加水分解物(乳ペプチド)は、育児用ミルクにおけるアレルゲン性低減や消化吸収性の向上などの用途で世界中で使用され、また近年では、血圧関係など健康に関わる機能性が注目を浴びている。演者らは、「ペプチドアレイ」をコアテクノロジーとして、配列レベルで精緻に分析・設計・製造するための2つの基幹技術を開発し、日本生物工学会より2021年度の生物工学技術賞を授与されたので、その内容をご紹介する。 | |||
|
休 憩 |
13:45~13:50 |
|||
| ② 膜技術とともに歩んだ39年
-膜技術開発が事業に及ぼした影響-
|
新谷 卓司・博士(工学) (京都大学 高等研究院・物質-細胞統合拠点 特任教授、(元)日東電工(株)開発部長、神戸大学 特命教授) |
13:50~14:45 |
||
|
講演概要 |
演者は日東電工(株)で33年、神戸大学で6年とRO膜を中心に膜技術開発に携わってきた。その中で、あれがセレンディピティだったのかと思わせる出来事は3回しかありませんでした。それらの発見がどのような状況の中から生まれたのか、その発見が膜事業にどのように影響を及ぼしたのかについて、半導体用超純水市場と海水淡水化市場を中心に紹介する。 | |||
|
休 憩 |
14:45~15:00 |
|||
| ③ 食品飲料・バイオ用途向け耐熱性中空糸膜モジュールの開発 | 小林 憲太郎 (東レ株式会社 地球環境研究所研究員) |
15:00~15:55 |
||
|
講演概要 |
食品飲料製造やバイオ分野において、精製・濃縮工程への適用を目指した耐熱中空糸UF膜モジュールを開発した。東レの高強度PVDF製中空糸膜を用いて実現した外圧式クロスフローろ過方式の膜モジュールで、低圧損、高耐熱性が特徴。実証例として微生物発酵液の長期ろ過事例などを紹介する。 |
|||
|
休 憩 |
15:55~16:00 |
|||
|
④ 食料・飼料原料としての虫の魅力:未利用資源からの生産に向けた研究開発 |
鈴木 丈詞 ・ 博士(農学) 東京農工大学 准教授 |
16:00~16:55 |
||
|
講演概要 |
虫を食べる─これを想像するだけで嫌悪感を抱く方も多いと思われる。しかし世界では、少なくとも約20億人の伝統食の一部を1,900種以上の昆虫が担っている。安全で、栄養価に優れ、さらに従来の家畜動物と比較してエネルギーや水の利用効率が高い等の特性を持った昆虫を対象とし、持続可能な生産に向けた研究開発について紹介する。
|
|||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
|||
| 交流会(川口リリア・1階ラウンジリリア) | 17:05~19:00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
食品膜・分離技術研究会(MRC) |
||||
|
第33回秋季研究例会プログラム・講演概要(対面・オンライン併用) |
||||
|
|
日時:2021年11月18日(木) 12:35~17:00 |
|||
|
開会挨拶 |
MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) |
12:35~12:45 |
||
|
休 憩 (講演準備) |
12:45~12:50 |
|||
|
研 究 例 会 |
||||
|
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
||
|
① カーボンナノチューブ等のナノカーボンを用いた先進水処理膜 |
遠藤守信 (工学博士) |
12:50~14:05 |
||
|
講演概要 |
カーボンナノチューブ(CNT)は、世界で量産が進み、その応用の一つとして海水淡水化をはじめ各種水処理膜への展開が期待されている。我々はこのカーボンナノチューブとナノカーボンの一つであるグラフェンを用いて耐ファウリング性を有した海淡用逆浸透膜を開発した。これらの逆浸透膜は、浄水器や牛乳処理等でも優れた機能を発現することを示した。ここでは、CNT等のナノカーボンを用いた特色ある水処理膜について、その膜科学と応用について報告する。 |
|||
|
休 憩 (講演準備) |
14:05~14:10 |
|||
|
② 食品産業における膜利用技術の進展 |
渡辺敦夫 (農学博士) |
14:10~15:00 |
||
|
講演概要 |
MRC基礎膜技術講習会の講師を10数年にわたり行ってきた。この中で、関心が高いのは膜機能の維持回復と衛生管理に関連する項目であった。そこで、食品産業で膜技術を利用する場合の基本的問題点とその解決法について改めて考えてみたい。より効率的な利用技術の開発に役立てて頂ければ幸いである。 |
|||
|
休 憩 (講演準備) |
15:00~15:10 |
|||
|
③ 食品の乾燥技術 -噴霧乾燥装置の進歩― |
金澤 宏希 |
15:10~16:00 |
||
|
講演概要 |
噴霧乾燥を行うことにより長期保存が可能になることから、噴霧乾燥技術は食品・乳製品工場において幅広く活用されている。噴霧乾燥装置(スプレードライヤ)のパイオニアであるデンマークのGEA Niroにおける噴霧乾燥装置の歴史と最新の技術動向について紹介する。 |
|||
|
休 憩 (講演準備) |
16:00~16:05 |
|||
|
④ 食品産業における省エネルギー濃縮装置 |
井上智裕 (株)ササクラ 水処理事業部 部長代行 |
16:05~16:55 |
||
|
講演概要 |
当社は船舶用機器・海水淡水化プラント等を扱ってきました。技術開発の中で蒸気圧縮機を使い、省エネルギー型蒸発濃縮装置を開発し、2019年に化学産業向け排水濃縮で省エネ大賞を受賞しました。さらに食品産業向けに展開したVVCC型濃縮装置はお茶エキス濃縮に実用されています。ここでは、食品濃縮装置を中心に紹介します。 |
|||
|
閉会挨拶 MRC名誉副会長(田村吉隆) |
16:55~17:00 |
|||
MRC 2021年度総会・MRC 第33回春季研究例会プログラム・講演概要
| 日時:2021年6月3日(木) 12:20~17:00
開催方法: オンライン(Microsoft Teams 使用)にて開催 主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)(TEL: 090-4534-1489) 協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設 |
| 2021年度総会 | ① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) ② 総会 議事 |
12:20~12:45 | ||
| 研 究 例 会 | ||||
| 題 目 | 講演者 |
時間 |
||
| ① 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けての食品研究-膜分離技術の利用に関する研究の成果等を踏まえて- | 鍋谷 浩志 (博士(工学)) 東京家政大学 教授 (元)農研機構食品研究部門長 |
12:50~13:45 | ||
| 講演概要 | 持続可能な開発目標(SDGs)の達成が、人類にとっての最大の課題の一つとして注目されている。講演者が、農研機構食品研究部門(旧食品総合研究所)において36年間にわたって取り組んできた膜分離技術の利用に関する研究の成果等を踏まえて、SDGsを達成するために食品研究が取り組むべき課題をいくつか提案したい。 | |||
| 休 憩 | 13:45~13:50 | |||
| ② 飲料用途に使用される3M™ LLiqui-Cell™ 分離膜モジュールの特長と機能について | 野々木麻里| Specialist スリーエム ジャパン イノベーション(株) フィルター製品技術部 |
13:50~14:45 | ||
| 講演概要 | 食品や飲料、医薬品の製造に欠かせないものに水処理がある。この処理で問題になる不純物は単なる微粒子や微生物の類だけでなく、水に溶解している例えば酸素などの“溶存ガス”が問題になってくる。また製品によっては溶存ガスを増加させるなどのコントロールが必要になる。この溶存ガスの調整ができる膜技術を利用した3M™ Liqui-Cel™ 分離膜モジュールについて、実例と共に紹介する。 | |||
| 休 憩 | 14:45~15:00 | |||
| ③ 2050年温暖化ガス排出ゼロと地球環境問題 | 石谷 孝佑(農学博士) (一社)日本食品協会 理事長 (元)国際農林水産業研究センター 国際研究総括官 |
15:00~15:55 | ||
| 講演概要 | 菅政権は「2050年温暖化ガス排出ゼロ」に舵を切った。地球温暖化の原因は二酸化炭素やメタン等の温暖化ガスによって起こされるもので、このまま気温が上がると大変なことになるという。しかし、過去の歴史を見ると、温暖化の時代に食料・人口が増え、寒冷化の時代には飢餓、伝染病、戦乱が増え人口が停滞した。地球温暖化、エネルギーと物作りの問題を振り返る。 | |||
| 休 憩 | 15:55~16:00 | |||
| ④ 食品産業におけるForward Osmosis(FO)膜による食品濃縮について | 伊東 護 美浜(株) AMP IONEX BU. ビシネスユニット長 |
16:00~16:55 | ||
| 講演概要 | 飲料を中心とする食品の濃縮には真空濃縮が用いられることが多い。しかし風味の劣化や熱変質は発生してしまう。これに対してROなどの膜による濃縮も試みられているが、閉塞が起きやすく運転圧力が高いなどの問題点もある。ここにFO膜を適用する場合のメリットを、FO膜技術と共に紹介する。 | |||
| 事務局連絡 | 16:55~17:00 | |||
| 交流会(変異ウイルス感染等を避けオンラインでの開催のため中止) | ||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
MRC 2020年度総会・MRC 第32回秋季研究例会プログラム・講演概要
|
2020年度総会 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) ② 総会 議事 |
12:20~12:45
|
||
| 研 究 例 会 |
||||
|
題 目 |
講 演 者 |
時間 |
||
|
① ビール製造における濾過技術の進歩 ―珪藻土濾過と膜濾過― |
西川 政吾 (農学修士)
サントリービール㈱武蔵野ビール工場
|
12:50~13:45 |
||
|
講演概要 |
ビール濾過という固液分離工程により酵母および混濁成分を取り除くことで飲用時の生ビールの香味が造り込まれている。このビール濾過技術について、従来から用いられてきた珪藻土濾過と、近年誕生し普及が進むクロスフロー式精密濾過(膜濾過)システムを比較しながら、技術的な背景やビール品質、生産性等の評価事例を中心に紹介と解説を行う。 |
|||
| 休 憩 | 13:45~13:50 | |||
|
② 栗田工業における膜技術の取り組み ―逆浸透薬品群を中心として― |
川勝孝博 (工学博士) 栗田工業株式会社 開発本部 研究主幹 |
13:50~14:45 |
||
|
講演概要 |
栗田工業は、純水製造、廃水処理、廃水回収といった水処理における装置、薬品、メンテナンスを提供している。本講演では、水処理における主要技術である膜技術に焦点を当てて、栗田工業の取り組みについて逆浸透薬品群を中心として紹介する。 |
|||
| 休 憩 | 14:45~15:00 | |||
|
③ オープンクリーンシステムKOACHの 無菌・防塵化原理と実用例 ―食品市場における有効性― |
すずきたけと |
15:00~15:55 | ||
|
講演概要 |
一般のクリーンベンチはチャンバー内を無菌・防塵化するものであったが、ここで紹介するものはチャンバーのない開放系での無菌・防塵化システムである。これを、オープンクリーンシステムKOACHと呼ぶ。開放系で無菌エアーを互いに向き合う2面から層流に供給し、層流エアー内を無菌・防塵状態に保つことが出来る。KOACHの空気清浄化原理とこのシステムの実用化例および食品市場での可能性・有効性について言及する。
|
|||
| 休 憩 | 15:55~16:00 | |||
|
④ -食品の安全性高度化のための食中毒細菌対策- |
川本 伸一 (農学博士) (日本食品科学工学会専務理事・事務局長) (法政大学 客員教授) (農研機構食品研究部門アドバイザー) |
16:00~16:55 | ||
|
講演概要 |
食中毒細菌は、フードチェーンの各段階で様々なストレスに暴露され、従来の検査培地では増殖できない(検出できない)損傷菌となる。しかし、損傷菌は、その後のストレス応答修復で、増殖が回復し、病原性が保持あるいは増強される可能性がある。従って、損傷菌は食中毒発生の重大な潜在的リスクである。損傷菌研究の現状と今後の対策の必要性について概説する。 |
|||
| 事務局連絡 終了挨拶 | 16:55~17:00 | |||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
|
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) |
12:40~12:55 |
||
|
休憩 (5分) |
12:55~13:00 |
||
|
題 目 |
講演者 |
時間 |
|
|
①『海水淡水化エンジニアとして歩んだ40年 |
三菱商事(株)水事業部シニア・アドバイザー |
13:00~13:55 |
|
|
講演概要 |
海水淡水化のエンジニアとして、筆者が三菱重工で歩んだ路を振返り、主にサウジアラビアにて従事した「蒸発法およびRO膜法の海水淡水化プラントの実像」や、その過程で遭遇したことや伝えたいことを、紹介する。併せて三菱重工および三菱商事水事業の簡単な紹介を行う。 |
||
|
休憩 (5分) |
|||
|
②『逆浸透膜の開発と性能向上 |
神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 |
14:00~14:55 |
|
|
講演概要 |
近年、逆浸透(RO)膜は非常に身近な分離・濃縮・精製法の一つとして超純水や海水淡水化はもとより、浄水器や食品・医製薬へと様々な分野で用いられるようになってきた。今回RO膜の歴史を各膜メーカーの開発戦略と共に紐解くとともに、各種膜の製膜方法および開発動向について説明する。更には今後の展望についても言及する。 |
||
|
休憩(15分) |
|||
|
③食品製造工場向け用水/排水処理における膜分離技術 |
オルガノ(株) 開発センター |
15:10~15:55 |
|
|
講演概要 |
食品製造に適した用水の製造、工場排水の処理、水回収再利用において、膜分離技術が果たす役割は大きい。本講演では、用水製造におけるUF膜の運用方法、および、排水処理におけるMBRの適応事例について報告をする。 |
||
|
休憩(5分) |
|||
|
④ 『AIによる食の安全・安心の確保―キューピー(株)における実用例―』 |
キューピー(株)生産本部 |
16:00~16:55 |
|
|
講演概要 |
キユーピーにおいてはAI活用をイノベーションと位置付け、志をコアとした、現場力×AIによるイノベーションを推進している。食品業界で最も重要な安全・安心を担保するために開発したAI原料検査装置を中心にAI活用について紹介する。 |
||
|
交流会 |
1.開会の挨拶 2.乾杯 3.締め |
17:05~19:00 |
|
MRC 2019年度総会 および MRC 第31回春季研究例会プログラム
|
2019年度総会 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫(農学博士)
|
12:30~12:45 |
||
| ② 2019年度総会 議事 |
12:45~13:05 |
|||
|
休憩 (5分) |
13:05~13:10 |
|||
|
第31回春季研究例会 |
||||
|
題 目 |
講 演 者 |
時間 |
||
|
①エネルギー・水技術の将来展望 〜水素・燃料電池および正浸透海水淡水化技術の未来〜 |
東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 教授 山口猛央(工学博士) |
13:10~14:05 |
||
|
講演概要 |
近未来の技術展望として、エネルギーおよび水の問題は避けて通れない。大規模に再生可能エネルギーを利用するためには、水電解および燃料電池技術が必要になるが、革新的な膜および触媒材料とシステムの観点から未来の技術として紹介する。また、世界規模の水ストレスを解決するためには省エネルギー海水淡水化が必要であるが、逆浸透法よりも優れた正浸透技術を実現するために必要な膜とは何かを、食品産業への利用を踏まえてやさしく紹介する。 |
|||
|
休憩 (5分) |
||||
|
②雪印メグミルクにおける膜・分離技術の利用 |
雪印メグミルク株式会社 ミルクサイエンス研究所 |
14:10~15:05 |
||
|
講演概要 |
乳業では、さまざまな膜・分離技術が利用されている。雪印メグミルクは1982年の農水省指導の膜研究組合でのfoulingに関する基礎研究を踏まえて、多くの技術的積み重ねを行ってきた。本講演では、当社における膜・分離技術と、それを利用した商品について紹介する。 |
|||
|
休憩(15分) |
||||
|
③スプレードライ技術と粉末酒の発明について |
佐藤食品工業株式会社 技術本部 森
一浩 |
15:20~16:00 |
||
|
講演概要 |
当社ではスプレードライ技術を用いて天然調味料(鰹、昆布、椎茸のエキスや酢、醤油等)や茶エキス、果実・野菜等を粉末化し、加工食品メーカー向けに原料を供給してきた。その過程において当社は粉末中にエタノールを30%程度保持する「粉末酒」の開発に成功し、酒税法への収載を経て今なお独自の製品として販売している。粉末酒の紹介と合わせて、当社粉末加工技術の概要を紹介する。 |
|||
|
休憩(5分) |
||||
|
④運動の効果を支援するスポーツ栄養食品の研究開発 |
株式会社 明治 研究本部 三本木 千秋 |
16:05~16:55 |
||
|
講演概要 |
2020年オリンピック・パラリンピックを契機に、また健康増進の観点からも運動・スポーツ実施の関心が高まってきている。アスリートのみならず多くの運動実施者にとって有益な栄養情報や栄養食品が身近なものになり、例えばプロテイン(たんぱく質)摂取を日常の食シーンに見ることも珍しくない。本講演では、運動と栄養の相乗効果について、最新の研究成果・当社商品の変遷など紹介する。 |
|||
|
交流会 |
1.開会の挨拶 2.乾杯 3.締め |
17:05~19:00 |
||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2018年11月8日(木) 川口総合文化会館(川口リリア)11階 大会議室
|
2018年度 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫(農学博士) |
12:40~12:55 |
|
|
研究例会 |
|||
|
題 目 |
|
|
|
|
① 記念講演 |
名古屋大学大学院 教授 |
12:55~ 13:55 |
|
|
概要:多種多様なコロイドに対応できる固液分離技術は、古くから存在する技術であるが、現在もなおその展開が注目されている基盤技術でもある。本講演では、固液分離の設計・操作指針を得るために必須となる、ケーク層や膜目詰まりの新しい簡便な評価手法を解説するとともに、固液分離の高効率化のための新しい技術も紹介する。 |
|||
|
休 憩 (10分) |
|||
| ② 特別講演 新生(株)明治の経営戦略 そのメリットと研究開発分野の広がり |
(株)明治 研究戦略総括部長 |
14:05~15:05 |
|
|
概要:明治製菓と明治乳業は2009年に経営統合後、2011年の再編を経て現在に至る。2011年以降の業績好調は、一概に統合効果とは言えず、「選択と集中」による高付加価値戦略と固定費の削減効果が高かった。しかし、高付加価値戦略の中で価値創造の軸を一元化できたことが最大の統合効果であったかもしれない。 |
|||
|
休 憩 (15分) |
15:05~15:20 |
||
|
③ 『食品工場における防虫管理―実験結果や各種データで示す防虫管理のポイント』
|
イカリ消毒株式会社 黒川 哲哉 LC環境検査センター科学分析グループ 主任 |
15:20~16:05 |
|
|
概要:防虫対策を検討する上で、これまで常識とされてきた事項を、調査・実験データにて徹底的に検証した内容を紹介する。1.陰圧・陽圧での虫の侵入実験 2.昆虫の誘引と物体の色の関係 3.封水トラップの防虫効果 4.モニタリングデータから見る地域・季節変動等の考察 5.歩行性昆虫の侵入要因の検証 |
|||
|
休 憩 (5分) |
16:05~16:10 |
||
|
④『岩井機械工業(株)における食品向け膜装置と各種殺菌装置の特徴』 |
岩井機械工業株式会社 小久保雅司 技術センター グループリーダー |
16:10~16:55 |
|
|
概要:膜設備導入に当っては事前に濃縮液や透過液をサンプリングし、目的の濃縮・分離製品を製造できるか見極める必要がある。本講演では食品向け膜装置の実験設備の紹介と共に、濃縮・分離後の製品を殺菌するための各種装置と特長についてご紹介する。 |
|||
|
事務局連絡 |
16:55~ 17:00 |
||
|
交 流 会 (1階 ラウンジリリア) |
17:05~19:00 |
||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2018年度総会および設立30年記念研究例会プログラム
日時:2018年6月14日(木) 12:25~19:00
場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA)
〒332-0015
埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近)
TEL: 048-258-2000 FAX:
048-258-2100
主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
|
|
① 開会挨拶 |
MRC会長 |
渡辺敦夫(農学博士) |
12:25~13:20 |
|
|
式典および2018年度総会 |
② 祝辞 |
(前)MRC 会長 |
大矢晴彦(工学博士) |
||
|
|
③ 祝辞 |
東レ(株)フェロー |
栗原 優(工学博士) |
||
|
|
④ 謝辞 |
MRC名誉副会長 |
田村吉隆(工学博士) |
||
|
|
MRCの歩んだ30年―MRCが果たしてきた役割と今後の展望― |
||||
|
|
⑤ 2018年度総会 議事 |
13:20~13:35 |
|||
|
休憩 (5分) |
13:35~13:40 |
||||
|
設立30年記念 研究例会 |
|||||
|
題 目 |
講 演 者 |
|
|||
|
① 記念講演 森永乳業(株)における膜技術戦略 |
大川 禎一郎 博士(工学) |
13:40~14:40 |
|||
|
―育児用粉乳の改質を中心にして― |
森永乳業(株) 専務取締役 研究本部長 |
||||
|
講演概要 |
森永乳業における膜技術は基幹製造技術の1つとして、産業利用と科学的解析研究を重ね、現在、高い価値を有する素材や製品を創出するためになくてはならない存在となっている。今回の記念講演では、育児用粉乳をヒト母乳にいかに近づけるかという命題に挑戦し、これを成し遂げていくなかで、膜・分離技術が果たした役割に焦点を当て、その歴史を振り返ってみたい。 |
||||
|
休憩 (15分) |
|||||
|
② トマトジュース濃縮における逆浸透膜の利用 |
深谷 哲也 博士(農学) |
14:55~15:30 |
|||
|
カゴメ(株)イノベーション本部 部長 |
|||||
|
講演概要 |
世界のトマト加工品製造で用いられる濃縮プロセスの主流は、真空加熱濃縮法である。より高濃縮することで、保管、輸送コストを最小限に抑えることができる一方で、新鮮なフレーバーの揮散、加熱による香味や色調の劣化といったデメリットも多い。本講演では、トマト本来の新鮮な香りや色調を維持したまま濃縮する方法として、長年カゴメが取り組み、実用化した逆浸透(RO)膜濃縮法について述べる。 |
||||
|
③洗浄剤市場から見た |
宮澤 史彦 |
15:30~16:05 |
|||
|
食品膜技術の発展とMRC |
エコラボ(合同)マーケティングマネジャー |
||||
|
講演概要 |
弊社は、1980年代初頭(当時はヘンケル白水社)より国内において膜・膜設備用洗浄剤のウルトラジールの販売を開始し、MRCメンバーに助言をいただきながら、国内の膜設備の発展と共に歩んできた。食品企業においては、乳業以外の膜利用も増え、特に近年の膜面積の増加は目覚ましいものがある。本講演では、洗浄剤市場から見た食品用膜技術の発展について、MRCにおける活動を含め発表する。 |
||||
|
④湘南香料(株)における事業の発展と新分離技術 |
大崎 洋 |
16:05~16:25 |
|||
|
湘南香料(株) 専務取締役 |
|||||
|
講演概要 |
当社は1923年から天然の香りと味を求めて「ナチュラル」をキーワードに、高品質な天然原料から果汁・野菜汁やエキス・食品香料等を製造し、大手食品/飲料メーカーを中心に販売してきた。1978年に限外ろ過膜を実用化し、1984年に液化炭酸ガス抽出および逆浸透膜による果汁の濃縮を実用化した。本講演では当社の発展の歴史と製造工程で使用している膜分離・抽出技術について紹介する。 |
||||
|
⑤ハチミツと膜分離技術 |
小暮 直樹 |
16:25~16:55 |
|||
|
(株) 加藤美蜂園本舗 品質保証室長 |
|||||
|
講演概要 |
昨年4月、国内では初めて、ハチミツの摂取が原因とされる乳児ボツリヌス症による死亡事例があった。
ハチミツを食品加工原料として広く利用するには、限外ろ過処理によりボツリヌス胞子を除去し清澄化する必要がある。高粘稠性のハチミツの限外ろ過には多くの問題があったが、それらを解決することにより加工原料として利用できるようになった。ハチミツの限外ろ過に関する開発内容等について紹介する。 |
||||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
||||
|
1.開会の挨拶 |
|||||
|
2.乾杯 |
|||||
|
3.MRCへの提言・MRCの想い出 |
|||||
|
4.締め |
|||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第29回秋季研究例会プログラム・講演概要
| 2017年11月9日(木) 川口総合文化会館(川口リリア)11階 大会議室 |
| 2017年度 | ① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 | 12:40~12:55 |
| 研究例会 | ||
| 題 目 | 講 演 者 | |
| ① 膜工学に関連する10大モデル |
東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻 教授 伊東章 (工学博士) |
13:00~13:50 |
|
概要:演者は、液体膜を中心に膜分離技術の研究を行ってきたが、新潟大学工学部においては渡辺敦夫教授と共同して食品産業における膜技術の研究も行った。化学工学誌に化学技術者が知っておくべき「化学工学10大モデル」を連載したが,これを膜工学の理論解析に役立てるべく演繹を試みた。膜技術の知識の再整理の参考になることを期待する。 |
||
| 休 憩 (5分) | 13:45~13:55 | |
|
② 食品工場における膜を利用した水の再利用 |
一般財団法人 造水促進センター専務理事 大熊那夫紀 |
13:55~14:50 |
| 概要:世界の水危機を背景にした水の再利用をめぐる国際標準化の動向、水再利用の現状や最新動向を紹介し、食品工場における膜を利用した水再利用の事例を通じ、我が国の食品工場における水の再利用について考える。 |
||
| 休 憩 (10分) | 14:50~15:00 | |
|
③ 水素エネルギー利用技術の現状と将来展望 |
岩谷産業株式会社 産業ガス・機械事業本部 |
15:00~15:55 |
| 概要: 講演概要:クリーンなエネルギーとして期待されている水素。水素利用の現状から、燃料電池自動車向けの水素ステーション整備や運用の状況、また、今後普及が見込まれる燃料電池フォークリフトや再生可能エネルギーの活用など、水素利用の事例をご紹介します。 | ||
| 休 憩 (5分) | 15:55~16:00 | |
| ④ 中空糸膜の食品工業分野への製造プロセス以外への展開について | 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株) 技術統括室 アクアグループ グループマネージャー 小林 真澄 |
16:00~16:55 |
| 概要: 膜分離技術は食品工業分野において多岐に使用されている。今回は、製造プロセス以外で活用される膜分離技術について、概要を紹介する。製品脱気および脱気水の活用、含油排水処理における前処理技術と膜分離技術の組み合わせ等につき、実例を交え紹介する。 | ||
| 事務局連絡 | 16:55~17:00 | |
| 交 流 会 (1階 ラウンジリリア) | 17:05~19:00 | |
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2017年総会・第29回春季研究例会プログラム・講演概要
2017年6月8日(木) 川口総合文化会館(川口リリア)11階大会議室
|
2017年度総会 |
①
開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 ② 総会 議事 |
12:25~12:55 |
|||
|
研 究 例 会 |
|||||
| 題 目 |
|
|
|||
|
① 農研機構における食品研究の動向
|
国立研究開発法人 |
13:00~13:55 |
|||
|
講演概要 |
平成28年4月の農研機構の組織改編に伴い、「食品総合研究所」は「食品研究部門」と名称を改めた。ここでは、新たにスタートした「食品研究部門」における研究の推進体制及び推進方向について解説するとともに、食品の機能性の評価・解明・利用、安全性・信頼性の確保、及び次世代加工・流通技術の開発の分野における最近の研究トピックスを紹介する。 |
||||
| ② 東レの地球環境事業への取組 ―新エネルギー利用の現状と展望― |
東レ株式会社 |
13:55~14:50 |
|||
|
講演概要 |
東レは、環境関連製品・技術を「グリーンイノベーション事業」として拡大することを基本戦略の柱の一つとしています。東レの省エネ、再エネ、新エネ、バイオマス、水処理などへの取組を紹介するとともに、それらを生み出した研究開発・事業開拓の考え方をご紹介します。 |
||||
| 休憩 |
14:50~15:05 |
||||
|
③ 旭化成におけるMF・UF膜モジュールの用途開発の現状 |
旭化成株式会社 膜・水処理事業部 膜・水処理システム技術部 主幹研究員プロセスGrリーダー 古本 五郎 |
15:05~16:00 | |||
|
講演概要 |
旭化成は、1977年、PAN(ポリアクリロニトリル)製中空糸UF膜を商品化以降、電着塗装用塗料の回収を皮切りに、膜ろ過の用途を開拓し、事業を拡大してきた。今回は、食品用酵素、日本酒、ゼラチン、醤油などの食品分野の適用例を紹介するとともに、弊社のろ過技術開発の進め方について紹介させていただく。 |
||||
| ④ 食品業界におけるクロスフロー式精密ろ過技術の導入の傾向と実際 |
|
16:00~16:55 |
|||
|
講演概要 |
ワインやビールを初めとして、品質、コスト、生産性の改善の視点から、日本でも急速に精密ろ過技術のクロスフロー化が普及しつつある。 |
||||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
||||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第28回秋季研究例会プログラム・講演概要
| 2016年11月9日(水) 川口総合文化会館(川口リリア)11階 大会議室 |
| 2016年度 | ① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 | 12:40~12:55 |
| 研究例会 | ||
| 題 目 | 講 演 者 | |
| ① 食品加熱技術の特性と利用 ―伝導・対流・放射(遠赤外)・マイクロ波・誘電加熱・ヒートポンプ・コージェネレーション・燃料電池等― |
渡辺 敦夫 (食品膜・分離技術研究会 会長 農学博士) |
13:00~13:50 |
|
概要:食品加工において加熱技術は最も基本となる単位操作でありあらゆる工程で利用されているため、技術開発が進み多くの省エネルギー技術が開発されている。しかし、その特性を理解し有効に利用しているとは考えられないことが多い。そこで、各種の加熱技術の特性とその利用について紹介する。 |
||
| 休 憩 (5分) | 13:45~13:55 | |
|
② 遠心分離+膜分離によるハイブリッド食品分離技術とその適用事例 |
青木 裕 アルファ・ラバル株式会社 |
13:55~14:50 |
| 概要:講演概要:130年前に乳脂肪濃縮のために発明されたディスク型遠心分離機、65年前に鯨油製造における収率改善のために開発されたデカンタ型遠心分離機を前段に組み込むことで油分の混入のない液体食品を膜分離に受け渡すことが可能になり、その弱点を克服できた。その3つの分離技術の複合である「ハイブリッドセパレーション」を詳細に説明したあと、水産物、柑橘類における二つの適用事例を紹介する。 |
||
| 休 憩 (10分) | 14:50~15:00 | |
|
③ CIP最適化に関連する、装置、製品品質向上洗浄プログラム、膜洗浄プログラムの紹介 |
宮澤史彦 |
15:00~15:55 |
| 概要: 液体を扱う食品工場においては、製品製造後、CIPによる洗浄が行われる。CIPは、食品の品質を維持するためには不可欠であるが、CIPで消費される水、エネルギー、電気代等のコストは、食品工場全体の中でも少なくない。CIPを最適化することは、工場全体の経費節減に大きく貢献することになる。本講演では、最近のCIP最適化手法トピックについて紹介する。 | ||
| 休 憩 (5分) | 15:55~16:00 | |
| ④ コンビニエンスストアーの仕組みと今後の展開について―商品開発・品質管理・食品配送と流通システム― | 伊賀 維津雄 |
16:00~16:55 |
| (株)キースタッフ 食品コンサルタント (元)味の素㈱加工食品開発研究所長、食品製造部長 (元)(株)ローソン 執行役員 品質管理本部長 |
||
| 概要: 日本におけるコンビニエンス(以下CVS)市場は、売り上げ規模で10兆円を超え、店舗数では60,000店にせまる勢いで発展し、流通業界の主体となってきている。この日本型CVSの仕組みを組織、商品開発、品質管理の面よりより解説し、今後進むべき展開の方向性についても紹介する。 | ||
| 事務局連絡 | 16:55~17:00 | |
| 交 流 会 (1階 ラウンジリリア) | 17:05~19:00 | |
2016年度総会・第28回春季研究例会プログラム・講演概要
日時:2016年6月9日(木) 12:25~19:00
|
2016年度総会 |
①
開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 ② 総会 議事 |
12:25~12:55 |
|||
|
研 究 例 会 |
|||||
| 題 目 |
|
|
|||
|
① ナノろ過濃縮によるホエイの高度脱塩及び透過流束の経時変化予測
|
栄養学博士 関信夫 |
13:00~14::00 |
|||
|
講演概要 |
チーズ製造の際に副生成物として得られるホエイに関して、塩素型陰イオン交換樹脂とナノろ過を組合わせた新規な高度脱塩方法を開発したので報告する。また、多様な成分を含むホエイを2つの成分からのみからなると仮定した透過流束の経時変化を予測するモデルについても報告する。 |
||||
| 休憩 |
14:00~14:05 |
||||
| ② ダイセン・メンブレン・システムズの膜技術戦略 |
中塚修志 |
14:05~14:50 |
|||
|
講演概要 |
弊社の膜技術は、多様な膜製品を提供することにとどまらず、装置・システムとしてユーザーの要望に応えるソリューション提供を目指している。本講演では弊社膜製品全般を紹介するとともに、 特に、特徴のある最近の膜技術について詳細に述べる。 |
||||
| 休憩 |
14:50~15:05 |
||||
|
③ カルビーのヒット商品『ベジップス』の開発物語 |
柚木英明 カルビー株式会社 研究開発本部新規ブランド課課長 |
15:05~16:05 | |||
|
講演概要 |
本講演では、2013年 日本食料新聞社優秀ヒット賞、2014年日本経済新聞社 日経MJ賞受賞商品『ベジップス』について紹介します。 1)カルビー株式会社 2)開発フェーズ 3)マーケテイングフェーズに分けて、開発段階から全国展開に至る新規事業の取組みについてお話させていただきます。 |
||||
| 休 憩 |
16:05~16:10 |
||||
| ④ イオン交換樹脂による食品の分離精製 |
|
16:10~16:55 |
|||
|
講演概要 |
吸着剤による分離精製は食品産業において広く利用されており、中でもイオン交換樹脂は脱塩、脱色、軟化、抽出、クロマトグラフィー、風味改善など様々な用途で用いられている。ここでは、イオン交換樹脂の特徴および食品精製事例をその原理とともにいくつか紹介する。 |
||||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
||||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第27回秋季研究例会プログラム・講演概要
| 2015年11月6日(金) 川口総合文化会館(川口リリア)11階 大会議室 |
| 2015年度 | ① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 | 12:40~12:55 |
| 研究例会 | ||
| 題 目 | 講 演 者 | |
| ① 食品膜・分離技術の特性と利用 ―ろ過・遠心分離・クロマトグラフィー・抽出・濃縮・乾燥― |
渡辺 敦夫 (食品膜・分離技術研究会 会長 農学博士) |
13:00~13:50 |
|
概要:分離技術は、膜技術にとどまらずろ過・遠心分離・クロマトグラフィー・抽出(超臨界流体抽出を含む)さらに、水を分離する観点から濃縮・乾燥まで含めることができる。これら分離技術は単独の単位操作として利用されることは少なく組み合わせ技術として利用されるため、膜技術利用をはかる場合もこれら種々の分離技術の特性を理解して工程を組み立てることが必要である。各分離技術の特性と利用について紹介する。 |
||
| 休 憩 (5分) | 13:45~13:55 | |
|
② 水道分野における膜適用の進展 |
鮫島 正一 ((一社) 膜分離技術振興協会) |
13:55~14:50 |
| 概要:膜ろ過浄水場に関する最新動向として、(1)当協会及び水道技術研究センターの膜モジュール規格、(2)浄水分野における産官学共同研究の成果、(3)高回収率実現のための多段ろ過や運用コスト削減のための水位差利用ろ過等の適用事例等について説明する。 | ||
| 休 憩 (10分) | 14:50~15:00 | |
|
③ 水処理膜の市場動向と東レの膜技術戦略 |
峯岸 進一 |
15:00~15:55 |
|
概要:21世紀になって、世界的な水不足、水環境の悪化が進行しており、持続可能な水資源の確保、水環境の保全・浄化は人類にとって大きな課題となっている。水処理膜技術はこれらの課題を解決するために期待されており、特にUF、MBRの市場伸び率は10~20%/年と高く、順調に拡大している。水処理膜の市場動向および東レの最近の事業状況、新しい膜の開発・技術動向について紹介する。
|
||
| 休 憩 (5分) | 15:55~16:00 | |
| ④ 食品製造における数値シミュレーションの活用事例~各種単位操作から生体の嚥下現象まで~ | 神谷 哲 ((株)明治 博士(工学))) |
16:00~16:55 |
| 概要: ICT分野の技術革新により、ここ数年で製造現場における数値シミュレーションに対するハードルが低くなってきた。各種製造装置に対して数値シミュレーションを用いることで、装置性能の新しい評価方法やスケールアップ方法を見いだせる可能性がある。さらに近年では医食工連携による、人の飲み込みを模擬する生体シミュレーションも可能になってきた。本講演では当社における数値シミュレーションの活用事例を紹介する。 | ||
| 事務局連絡 | 16:55~17:00 | |
| 交 流 会 (1階 ラウンジリリア) | 17:05~19:00 | |
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第27回春季研究例会プログラム・講演概要
| 日時:2015年6月11日(金) 12:35~19:00 場所:川口総合文化会館(川口リリア) 11階 大会議室 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100 |
|
2015年度総会 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 |
12:35~12:55 |
|||
|
② 総会 議事 |
|
||||
|
研 究 例 会 |
|||||
|
題 目 |
|
|
|
||
|
① 特別講演:Mega-ton Water System研究の成果 |
栗原 優・工学博士 |
13:00~14::00 |
|||
|
(東レ(株) フェロー) |
|
||||
|
講演概要 |
水は我々の生活に不可欠で極めて身近な存在だが、その水が世界的に大きな注目を集めるようになっている。世界レベルでの人口増加と経済発展に起因し、水需要の増大と水環境汚染が進行しているためである。ここでは、膜という新しい技術で、世界の水問題にどう対応しているかについて述べる。そして内閣府の「最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の中心研究者として、参加し、その成果として21世紀型水処理基幹技術を日本のイニシアチブで構築し、世界の水問題解決に貢献する実状について述べる。 |
||||
|
休憩 |
14:00~14:05 |
||||
|
② 実用化の進むナノろ過(NF)技術 |
渡辺敦夫 ・ 農学博士 |
14:05~15:05 |
|||
|
―その進展と利用― |
(食品膜・分離技術研究会 会長 ) |
||||
|
|
|
|
(東京農工大学 参与研究員) |
||
|
講演概要 |
MRCは1990年の第2回春季研究例会で『逆浸透と限外濾過の中間領域における高度分離技術』としてナノろ過を取り上げて以来、MRCニュースに掲載された報告は23報にのぼる。演者は、食総研在籍中に行ったオリゴ糖の分離に関する研究以来、新潟大学においてもNFを中心に研究を行ってきた。これらの研究成果を中心に、MRCニュースに掲載された報告の現時点でのまとめを行い、今後の利用の参考に供したい。 |
||||
|
休憩 |
15:05~15:20 |
||||
|
③ マルハニチロのリスク管理とフードディフェンスへの取組み |
荻原 正明 |
15:20~16:20 |
|||
|
環境・品質保証部 副部長兼課長 |
|||||
|
(マルハニチロ(株)) |
|||||
|
講演概要 |
2014年12月にグループ会社であるアクリフーズで起きた農薬混入事件以後、第三者検証委員会からの提言を踏まえて、マルハニチログループのリスク管理体制の見直し・強化が図られてきているが、その中でフードディフェンス体制の再構築にどのように取り組んできているか、これまでの活動を紹介する。 |
||||
|
|
1.はじめに ≪農薬混入事件について≫2.リスク管理システムとその運用3.フードディフェンスの考え方と管理基準4.フードディフェンスの取組み |
||||
|
休 憩 |
16:20~16:25 |
||||
|
④ 薬品処理プログラムによる膜設備の運転管理 |
池嶋 規人・博士(地球環境学) |
16:25~16:55 |
|||
|
(片山ナルコ (株)) |
|||||
|
講演概要 |
当社では、シミュレーションソフトにより算出した薬剤の最適添加量をTRASARTM技術によるモニタリング・管理を実施するとともに、ファウリング原因に対応した洗浄プログラムで、安定化と効率化を多くの工場やプラントに提供してきた。本講演では、これら薬品処理実施の利点について紹介する。 |
||||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
||||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第26回秋季研究例会プログラム・講演概要
| 日時:2014年11月7日(金) 12:35~19:00 場所:川口総合文化会館(川口リリア) 11階 大会議室 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100 |
| 2014年度 | ① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 | 12:35~12:45 |
| 研究例会 | ||
| 題 目 | 講 師 | |
| ① 横行する虚偽科学技術を見抜け ―田村膜・磁場凍結・遠赤外線肌着等― |
渡辺 敦夫 (食品膜・分離技術研究会 会長 農学博士) |
12:45~13:45 |
| 概要:STAP細胞発見との報道から数か月後にはその真偽をめぐって論争が起こり、現状では、可能性は限りなく小さいと見られている。近年、競争的研究資金獲得競争が過激になり、『本当みたいなウソの話』が多くなっている。ネーミングにおいても奇を衒い、機能水という言葉があるが、水が水以外の機能を持つのか?電解水なら電解水、溶液なら溶液と云えばよい。こうした、怪しげな科学技術に飛びつけば、研究費人件費の無駄になるし、技術者の成長の阻害にもなる。演者は、50年近い研究生活の中でこうした虚偽科学技術の本質解明にも向き合ってきたので、これらの状況を紹介する。 | ||
| 休 憩 (10分) | 13:45~13:55 | |
| ② 固形化粉ミルクの製造技術の開発 | 柴田 満穂 ((株)明治・薬学博士) |
13:55~14:55 |
| 概要:近年、出生数の低下や母乳化指向の高まりによって国内の粉ミルク市場は縮小傾向にあり、新たな育児スタイルを創出する商品の開発が強く求められていた。そこで、粉ミルクを固形化して使用者の利便性を高めるという、これまでにない全く新しい形態の粉ミルクを開発した。本講演では、固形化粉ミルクの製造技術の開発、並びにその物理化学的な特性について紹介する。 | ||
| ③しょうゆ製造工程における膜の利用 ―いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆのご紹介― |
熊倉 啓三 (キッコーマン食品株式会社) |
14:55~15:25 |
| 概要:しょうゆ製造工程には、さまざまな膜が利用されている。当社の利用状況とその歴史を主題として報告する。また、ここ数年、市場で好評を得ている「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」について、特徴のある容器とともに紹介する。 | ||
| 休 憩 (10分) | 15:25~15:35 | |
| ④ 乳業膜一筋 ―人乳化を目指して膜技術研究47年― |
田村 吉隆 (森永乳業株式会社 工学博士) (食品膜・分離技術研究会 副会長) |
15:35~16:55 |
| 概要:1967年入社、乳児用ミルクの人乳化を目指し、原料となる牛乳並びにチーズホエイ中の過剰な塩類を除去する連続式電気透析(ED)脱塩の開発・導入に取組んだ。弊社へのED導入と共にニュージー、西ドイツに輸出。その後牛乳・ホエイの成分分画、ホエイの濃縮を目的に限外ろ過(UF)設備、逆浸透(RO)設備導入に携わり、研究面では農水省の食品産業膜利用技術研究組合の活動で貴重な刺激を頂戴した。近年ホエイのナノろ過(NF)脱塩プロセスを導入すると共にホエイNFの理論的解析に関して化学工学論文集に2論文が掲載された。膜技術研究の契機と経過を紹介する。 | ||
| 事務局連絡 | 16:55~17:00 | |
| 交 流 会 (1階 ラウンジリリア) | 17:05~19:00 | |
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2014年度総会・第26回春季研究例会プログラム・講演概要
| 日時:2014年6月5日(木) 12:30~19:00 場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA) 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近) TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100 主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC) |
|
2014年度総会 |
①
開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 ② 総会 議事 |
12:30~12:50 |
|||
|
研 究 例 会 |
|||||
| 題 目 |
|
|
|||
|
① 特別講演:日本の科学捜査 |
三宅 文太郎・医学博士 |
12:50~13:50 |
|||
|
講演概要 |
日本の科学捜査について、科学捜査に関わる組織とその陣容を説明し、法と科学との関係、鑑識と鑑定の実際を、以下のような項目を中心に紹介していきます。1 法と科学 2 警察の組織と科学捜査 3 鑑識と鑑定 犯罪の捜査と立証におけるその位置づけ 4 鑑識の実際(鑑識課の仕事) 5 鑑定の実際(科捜研の仕事)5-1 DNA鑑定 5-2 薬物、文書などの、DNA以外の科学鑑定 |
||||
| ② 液状食品処理における膜機能の低下(透過流束の低下と分画分子量の変化)とファウリング |
渡辺敦夫 ・ 農学博士 |
13:50~14:35 |
|||
|
講演概要 |
液状食品は多成分系であり、蛋白質・多糖類・脂質・オリゴ糖・ペプタイド・塩類・有機酸・色素などが存在するため、食品の膜処理においてファウリングを起こし易く、膜機能は低下し易い。このため、食品産業においては膜機能の低下要因の解明と膜機能の維持のための研究が多く行われてきた。今後の膜技術開発の参考として頂くことを目的に、これら研究の内容を紹介する。 |
||||
| 休憩 |
14:35~14:50 |
||||
|
③水道水膜処理技術の動向と問題点 |
山村 寛・工学博士 |
14:50~15:35 |
|||
|
講演概要 |
膜ファウリングの発生を抑制するためには、膜ファウリングの原因物質を知り、原因物質に応じた分離膜・前処理・運転方法を選択する必要がある。本講演では、膜ファウリング原因物質の特性解析方法、及び膜前処理方法について、これまでの研究結果を基に紹介する |
||||
| 休 憩 |
15:35~15:40 |
||||
| ④ 親水化PVDF中空糸膜モジュールについて |
佐藤 芳雄 |
15:40~16:25 |
|||
|
講演概要 |
当社の親水化PVDF中空糸膜は、高い化学的耐久性及び耐ファウリング性を有し、かつ、独自のモジュール構造及び物理洗浄方法により、洗浄時の濁質の排出性に優れ、高濁度原水の安定したろ過が可能である。親水化PVDF中空糸膜のこれらの特長及び実用例について紹介する。 |
||||
|
⑤ 食品工場における洗浄と殺菌 |
田辺 忠裕 |
16:25~16:55 |
|||
|
講演概要 |
食の安全の確保は食品企業で最重要の課題であり、食品機械装置の洗浄と殺菌はHACCPの前提条件プログラム(PP)の一つに挙げられている。ここでは定置洗浄(CIP)の最適化について一般の機械装置と膜装置との比較において紹介する。 |
||||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
||||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第25回秋季研究例会プログラム・講演概要
| 日時:2013年11月8日(水) 12:45~19:00 場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA) 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近) TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100 主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC) 協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設 |
|
2013年度 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 |
12:45~12:55 |
||
|
研 究 例 会 |
||||
|
題 目 |
|
|||
|
①固液分離における膜利用の展開 |
入谷 英司(教授・工学博士) |
12:55~13:55 |
||
|
講演概要 |
逆浸透法から始まった膜分離技術は、現在では、広範な分野で利用されている。濾過、遠心分離、圧搾などに代表される機械的な固液分離においても、分離対象粒子の多様化、微細化への対応の必要性から、近年、膜利用が進んでいる。ここでは、固液分離における膜利用の考え方と今後の展開について概説する。 |
|||
|
②膜技術開発への挑戦・40有余年 ―明日を支える若き研究者・技術者に送る言葉― |
横山 文郎 |
13:55~14:45 |
||
|
講演概要 |
機能膜、特に逆浸透膜を中心とした膜技術に関する開発・普及に携わった膜メーカーの技術者の立場より、半導体向け超純水製造、海水淡水化、都市下水処理による飲料水の製造などの例について、日本の膜技術の黎明期より、世界に向けての今日までの発展の歴史を振り返ってみる。また、膜システム設計プログラムの開発、膜へのスケール析出機構の解明など、膜メーカー技術者としての研究結果について述べる。 |
|||
|
休 憩 |
14:45~15:00 |
|||
|
③サメの丸ごと活用による東日本大震災からの復興支援 ~気仙沼での取り組み~ |
野村 義宏(教授・農学博士) |
15:00~15:50 |
||
|
講演概要 |
サメは宮城県気仙沼港に集約的に水揚げされ、中華食材であるヒレ、練り製品の原料である肉、コンドロイチン硫酸の原料である軟骨と、全てが利用されてきた。しかし、先の東日本大震災により気仙沼のサメ加工業が甚大な被害を受けて、復旧に向けた取り組みが進んでいる。当研究室で行ってきたサメの丸ごと活用に関する研究を進めることで、サメ加工業の再生の一助としたい。本研究では、サメの肉、軟骨、皮を原料とした以下の研究を纏め報告する。①サメ肉の骨密度改善効果 ②コンドロイチン硫酸による変形性膝関節症(OA)の改善効果 ③サメ皮由来コラーゲンによる皮膚改善効果 |
|||
|
休 憩 |
15:50~15:55 |
|||
|
④ 高濃度液状食品を対象とした透過流束の予測 ―チーズホエイ・牛乳を例として― |
田村吉隆 |
15:55~16:55 |
||
|
講演概要 |
高濃度食品液の解析例として、ホエイの逆浸透における透過流束の解析法を示す。実験データを輸送方程式に入れて得られる浸透圧差から濃縮側膜界面の溶質濃度を求め、これらを濃度分極式に入れることで物質移動係数を求める。この結果、逆浸透時の透過流束変化を予測することが可能になる。 |
|||
|
事務局連絡 |
16:55~17:00 |
|||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
|||
食品膜・分離技術研究会(MRC) 設立25年記念
2013年度総会・第25回春季研究例会プログラム・講演概要
| 日時:2013年6月5日(水) 12:20~19:00 場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA) 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近) TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100 主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC) 協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設 |
|
2013年度総会 |
① 開会挨拶 MRC会長 渡辺敦夫 |
12:20~12:50 |
||
|
研 究 例 会 |
||||
|
題 目 |
|
|||
|
① 記念講演 MRC25年のあゆみと膜・分離技術開発 |
渡辺 敦夫 ・ 農学博士 |
12:55~13:25 |
||
|
講演概要 |
1989年(平成元年)に設立されたMRCは今年で25年目を迎えた。この間、49巻のMRCニュースと48回にわたる春・秋の研究例会、9年間の膜技術講習会、5年間にわたる基礎膜技術講習会、2回の乾燥・包装技術講習会を開催し、食品産業における膜・分離技術の研究開発と人材の育成に取り組んできた。MRC25年のあゆみを振り返り、今後の食品膜技術発展の方向を探りたい。 |
|||
|
② 特別講演 食品評価と新製品開発 |
岩附慧二 ・ 農学博士 |
13:25~14:25 |
||
|
講演概要 |
2010年2月以来、毎年、新潟大学で「食品評価論」の講義を行っており、「おいしさ」に関する科学的な評価法や商品設計技術について体系的に考察を進めてきた。そこで、本講演では、食品評価と新製品開発の概要について紹介する。食品産業における製品開発の難しさや面白さの理解に役立てば幸いである。 |
|||
|
休 憩 |
14:25~14:40 |
|||
|
③ 最近の膜技術の発展と展望 ―ロバストRO/NF膜の開発状況― |
都留 稔了 ・ 工学博士 |
14:40~15:40 |
||
|
講演概要 |
無機膜は耐熱性,耐溶媒性,機械的強度などに優れおり,高分子膜では適応不可能な高温分離や有機溶媒系分離に関して多くの研究が報告されてきた。本講演では最近の高分子膜技術の発展状況にも触れたのち、無機材料を分離膜材料として用いた水処理技術(精密濾過膜,限外濾過,ナノ濾過,逆浸透法)について紹介する。さらに,JST戦略的創造研究推進事業(CRSET)では,“多様な水源に対応できるロバストRO/NF膜の開発”を提案している。高温・塩素存在下でも使用可能なRobust膜の最新の開発状況について紹介したい。注)Robust:ロバスト((耐久性の高い) |
|||
|
休 憩 |
15:40~15:45 |
|||
|
④ 都市下水の機能膜による高度処理および処理水の植物工場への展開 |
横山 文郎 (MRC名誉会員) |
15:45~16:25 |
||
|
講演概要 |
中東、北アフリカ、中央アジア地域では農業用水が潤沢ではなく、既存の水源(河川、湖沼、井戸水等)では増大する需要に対応できなくなっており、対策が強く望まれている。対策の一つとして海水淡水化による造水があるが、造水コストが高いと言う問題がある。ここでは、新しい水源として都市下水の機能膜法高度処理による造水と、処理水の植物工場への展開について述べる。 |
|||
|
⑤ 膜装置の衛生管理と最近のサニテーション技術 |
宮澤 史彦 |
16:25~16:55 |
||
|
講演概要 |
食品加工に使用する機能膜のサニテーションは非常に重要であるが、そのサニテーションのためには通常の食品用の洗剤ではなく、機能膜専用の洗剤が必要である。弊社は膜が食品加工に使用されるようになった創成期から膜用の洗剤を開発し貢献してきた。その中で膜洗剤自身、洗浄の方法およびそのアプリケーションも新たに開発されてきた。本講演では、最近の膜のサニテーション方法について紹介する。 |
|||
|
交流会 |
17:05~19:00 |
|||
食品膜・分離技術研究会(MRC) 第24回秋季研究例会・
FC新潟2012年度第2回研究例会プログラム
実行委員長:城 斗志夫・・・副実行委員長:片岡龍磨:橋本真一
|
日時:2012年9月13日(木)~9月14日(金) |
|
9/13 (木) |
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
|||||
|
①実行委員長挨拶 城 斗志夫 (新潟大学農学部) ②MRC会長挨拶 渡辺 敦夫 (新技術開発院・院長)③FC新潟会長挨拶 江川 和徳 (江川技術士事務所) |
13:00~13:10 |
10分 |
||||||
|
特別講演 我がせんべい人生 |
丸山 智 |
新潟県米菓工業協同組合理事長 |
13:10~14:00 |
50分 |
||||
| 休 憩 |
14:00~ |
15分 |
||||||
| 功績者 表彰式 |
14:10~ |
|||||||
|
②記念講演 |
渡辺敦夫 |
食品膜・分離技術研究会 会長 |
14:15~ |
45分 |
||||
|
(概要) 産官学連携の研究組合として農水省に初めて設立された食品産業膜利用技術研究組合は設立30周年、その後、設立されたMRCは24年、この流れの中で設立されたFC新潟は15年目を迎えた。演者は、農水省当時から産官学連携研究の真っただ中で研究・活動を行ってきた。産官学連携研究を成功に導くための研究会活動等の役割とその成果について紹介する。 |
||||||||
|
③森永乳業における環境・エネルギー問題への取り組み |
遠藤 雅人 |
森永乳業(株) |
15:00~15:45 |
45分 |
||||
|
(概要) 森永乳業では以前よりコージェネレーションによる自家発電の導入を進めている。環境面での取組の一つとして進めていたが、昨年以降の電力供給が不安定な状況においては食品の供給責任を果たすという意味で大きな役割を果たしている。あわせて、バイオマスボイラとメタン発酵を組み合わせた熱利用システムなど、その他の取組を紹介する。 |
||||||||
|
休 憩 |
15:45~ |
15分 |
||||||
|
④新潟県食品研究センター -食品工学科の15年- |
浅野 聡 |
新潟県食品研究センター |
16:00~16:40 |
40分 |
||||
|
(概要) 食品工学科はH9年に新潟県食品研究所から新潟県農業総合研究所食品研究センターに改編した時に新設された科である。当初4人体制でスタートし、翌年~5名、翌々年~現在迄6名である。生物機能工学研究、生産工学研究の分野において対象業界、組合を特定せず広範な研究を行っている。 |
||||||||
|
⑤食品に係わる最近の話題と分析試験の状況 |
佐久間義則 |
(財)日本食品分析センター |
16:40~17:15 |
35分 |
||||
|
(概要) 大震災による原発からの放射能漏洩は,飲料水,お茶,米など多くの食品を汚染した。また,生食肉による食中毒事件や輸入品の残留農薬・抗生物質など,食品の安全に係わる問題は多い。これらの問題について事例,その分析試験結果や状況を紹介する。 |
||||||||
| 実 行 委 員 会 連 絡 |
17:15~ |
5分 |
||||||
| 夕 食 (交流会) 祝辞 新潟県食品産業協会 会長 佐藤 功 |
17:20~ |
100分 |
||||||
|
9/14 (金) |
⑥膜技術開発とその利用 |
鍋谷浩志 |
農研機構・食総研室長 博士(工学) |
9:00~9:45 |
45分 |
|||
|
(概要) 食品産業における膜技術利用の現状と今後の開発方向について解説する。また、液状食品の膜処理における膜透過現象を理論的に表現することを可能とし、食品用膜分離システムの設計・最適化を試みた結果の概要を紹介する。 |
||||||||
|
⑦災害時の食に求められるもの・天災と非常食 |
藤村 忍 |
新潟大学農学部准教授 農博 |
9:45~10:30 |
45分 |
||||
|
(概要) 災害時の食について、従来の非常食の概念で対応できない部分が多いことが判明した。健康面の二次災害を防止し、被災直後から被災地での復旧・救援活動を支える食事は新たに災害食としての位置づけが必要とされている。我が国有数の食づくりの地、新潟が中越・中越沖地震などを被災し、新たに始まった展開を概説する。 |
||||||||
|
休 憩 |
10:30~ |
15分 |
||||||
|
⑧無菌化包装米飯の製造技術 |
赤塚昌一 |
佐藤食品工業(株)開発部長 |
10:45~11:15 |
30分 |
||||
|
(概要) 無菌化包装米飯は、市場流通開始からの約20年間で着実に生産量を伸ばし、年間約100トンまでに達している。生産量伸展の原動力となった日本人のニーズに答えるおいしさと安全性を考慮したメーカー独自の製造方法について各社の特徴とともに紹介する。 |
||||||||
|
⑨新潟県の水産練り製品の特徴 |
海老名秀 |
新潟県水産海洋研 加工課 課長 |
11:15~11:45 |
30分 |
||||
|
(概要) 新潟県は、水産練り製品生産量が全国の上位3位内である。今でこそ一般的な原料魚であるスケトウダラだが、現在の貯蔵性のある原料(冷凍すり身)化、弾力のある良質な練り製品化が出来たのは、新潟県の業界の技術協力、技術開発、実用化等の貢献が無くては語れない。新潟県の水産練り製品の歴史、技術、これからについて講演する。 |
||||||||
|
⑩新潟製粉の米粉商品と特徴 |
藤井義文 |
新潟製粉(株)常務取締役 |
11:45~12:05 |
20分 |
||||
|
(概要) 新潟県が開発したコメの微細製粉技術。これを利用した新規米粉の特徴と弊社で製造している製品について紹介する。 |
||||||||
| 見学会案内・実行委員会連絡 出発=12:20 バス車内で昼食 解散予定=17:45(新潟駅) | ||||||||
|
見学会 |
① 佐藤食品工業(株) ②(株)堀川 | |||||||
| 食品膜・分離技術研究会(MRC)第24回秋季研究例会・FC新潟2012年度第2回研究例会の会場風景 | ||
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2012年度総会・第24回春季研究例会プログラム・講演概要
日時: 2012年 6月19日(火) 12:40~19:00
場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA).
〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近)
TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100
主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
| 2012年度総会 | ① MRC会長挨拶 渡辺敦夫 | 12:20~12:50 | ||||
| 研究例会 | ||||||
| 題 目 | ||||||
| ① 原子力発電所の安全と電気エネルギーの円滑な供給―日本工学アカデミーからの提言― | 古崎 新太郎 (東京大学名誉教授 (社)日本工学アカデミー監事) |
12:55~13:55 | ||||
| 講演概要 | 昨年3月11日の東日本大震災による津波災害で東京電力第一発電所は爆発事故を起こし、その被害は今なお続いている。日本工学アカデミーでは原子力発電所の安全と事故後の電力供給について、検討会を設け提言を発表した。ここではその概要を、 (1)原発の安全性の確保、(2)再生エネルギーの可能性、(3)省エネルギーの効果、(4)低炭素社会に向けた再生可能エネルギー利用のシナリオ、の順に説明する。 | |||||
| ② 液状食品包装技術の進歩と品質保持 | 石谷 孝佑 ((社)日本食品包装技術協会 理事長) |
13:55~14:50 | ||||
| 講演概要 | 液体食品には、酸性食品の果汁、栄養豊富な牛乳、低酸性飲料のお茶、栄養価のない水、塩分のある調味料の醤油・つゆ等、酸性の食酢・ポン酢等のほか、コーンスープなどの固液食品や、ゼリー・プリンなどのように温度により変化する弾性食品、粘稠度の高いケチャップ・マヨネーズ、更なる混合物のサラダドレッシング、水分を含まない食用油などがあり、非常に多様です。包装容器としても、古くからある金属缶、ガラス瓶をはじめ、近年多用されているペットボトルなどのプラスチックボトルやプラスチック製の高ガス遮断性多層チューブ、多種多様な紙容器、アルミ箔・酸化アルミ蒸着・ガラス蒸着などの高ガス遮断性包装容器、酸素吸収能のある包装容器など、選択肢が拡大している。これらの包装容器をどのように使いこなすか、中身の品質をどのように保持するかなどについて、判りやすく解説する。 | |||||
| 休憩 | 14:50~15:05 | |||||
| ③ セラミック膜の発展とゼオライト無機膜を用いたバイオエタノール濃縮・脱水技術の開発 | 藤田 優 (日立造船(株)事業・製品開発本部) |
15:05~16:00 | ||||
| 講演概要 | 従来の膜とは異なり、脱水性能・耐久性が高い新型のゼオライト膜エレメント、及びそれを用いた省エネルギー性の高い脱水システム(商標登録:HDS?)の開発について紹介する。このシステムは我が国最大のバイオエタノールプラント(北海道十勝地区、15,000kL/年)の脱水システムに採用され、3年を経過した現在もノーメンテナンスで順調に稼動している。 | |||||
| ④ 水処理プラント向け膜処理プロセスのファウリング抑制と低コスト化に向けた取り組み―温度応答性膜の利用― | 松代 武士 (㈱東芝 電力システム社 電力・社会システム 技術開発センター) |
16:00~16:55 | ||||
| 講演概要 | 当社は発電、浄水、海水淡水化プラント向けの膜処理プロセスの開発を進めている。膜処理プロセスの課題であるファウリング抑制を低コストで実現するため、温度応答性膜を浄水処理へ適用した事例と海水淡水化プラントの前処理膜プロセスに温水洗浄を適用した事例について紹介する。 | |||||
| 交流会 | 17:10~19:00 | |||||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第23回 秋季研究例会プログラム・講演概要
日時: 2011年11月9日(水曜日)
場所: (財)川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA) 11階大会議室.
〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近)
主催: 食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
| 時間 | 講演者 | 講演演題 | 所属 |
| 10:00~10:10 | 会長挨拶 | ||
| ①10:10~11:10 | 大矢勝 | 洗浄の基礎知識と食品産業への応用 | 横浜国立大学(教育人間科学)教授 (学術博士) |
| 講演概要: 洗浄は汚れの特性を理解した上で、洗浄剤の種類、機械力の種類等をうまく組み合わせて取り組むことが求められる。今回は食品工業の汚れとして油脂、澱粉、蛋白質等の性質、洗浄剤として界面活性剤、酸・アルカリ剤、酸化・還元剤、金属イオン封鎖剤、有機溶剤等、そして機械力として高圧水、超音波、泡沫利用等について整理し、洗浄の全体像を系統的にまとめることを目指す。 | |||
| ②11:10~12:10 | 大谷敏郎 | 食の安全を守る仕組み―リスク分析の考え方― | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 食総研 企画管理部長 (農学博士) |
| 講演概要 :食品の安全を守る仕組み」としてのリスク分析の考え方とわが国の体制について概観した後、主に農薬や食品添加物などの化学物質のリスク評価とリスク管理の具体的な方法を、農薬を例に詳しく解説する。さらに、この化学物質の例を基に放射性物質のリスク評価と食品への影響について現状を紹介する。 | |||
| 12:10~13:10 | 昼食 | ||
| ③13:10~14:10 | 江川和徳 | 産官学の連携による食品産業に育成―新潟県食品産業を例として― | 江川技術士事務所(元)新潟県食品研究センター所長 |
| 講演概要:新潟県の食品産業は平成21年度の県工業統計で出荷額75000億円と製造業第1位の基幹産業に成長した。業界発展の経緯から、学官の研究支援や技術知見の普及活動の充実、および企業規模によらない易導入性の技術開発など発展につながる特質について紹介する。 | |||
| ④14:10~14:55 | 山川 洋亮 | 省エネプロセスの提案-膜技術への取り組み- | 木村化工機㈱開発部 (農学博士) |
| 講演概要: 近年のエネルギー及び環境問題に対して、個別機器のみではなく、プロセス全体からシステムを考える必要があり、省エネや環境負荷低減を考慮したシステムを提案する。当社では、蒸発濃縮・蒸留装置を製造販売しており、膜分離は、前濃縮やスケールの原因となる成分の除去及び精製を目的として利用を図っている。本講演では、当社の膜技術への取り組みと、蒸発濃縮・蒸留装置との組み合わせを中心に紹介する。 | |||
| 14:55~15:15 | 休憩 | ||
| ⑤15:15~16:00 | 小坂慎一 | セラミック膜の発展と新しい応用例 | NGKフィルテック㈱技術部技術一課 課長代理 |
| 講演予定:日本ガイシではアルミナ系セラミック膜はじめゼオライト膜等の研究も行ってきた。セラミック膜はMF膜やUF膜としての利用から1~5nmの細孔を持つNF膜まで開発されてきた。最近では、新しい製法によるセラミックス膜製造技術も開発されてきた。近年のセラミック膜の発展と新しい応用例について紹介する。 | |||
| ⑥16:00~16:50 | 越智 浩 | 乳ペプチドを応用したスポーツ飲料粉末 | 森永乳業株式会社食品基盤研究所 食品技術研究部部長 |
| 講演概要: “乳ペプチド”はラクトフェリン・ビフィズス菌・ラクチュロースと並び、弊社の代表的な機能性素材である。乳たんぱく質を酵素で分解して得られる乳ペプチドは、たんぱく質・アミノ酸では得られない機能を持ち、育児用ミルク・流動食をはじめとして様々な製品へ応用されている。今回、特に演者が取組んできたペプチド配合スポーツ飲料粉末の開発と効能を中心に、当社乳ペプチドの特徴と応用例を紹介したい。 | |||
| 16:50~16:55 | 事務局連絡 | ||
| 17:05~19:00 | 交流会(1階:ラウンジリリア) | ||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2011年度総会・第23回春季研究例会プログラム・講演概要
日時: 2011年 6月14日(火) 12:40~19:00
場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA).
〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近)
TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100
主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
| 2011年度 総 会 | ①MRC会長挨拶 ②議事 |
12:40~13:05 | |
| 研 究 例 会 | |||
| 題 目 | 講 演 者 | 時間 | |
| ① | PVDF中空糸膜モジュールの特徴とその応用 | 峯岸 進一 (東レ ㈱ ) |
13:10~13:50 |
| 講演概要 | 水処理設備に用いられる精密ろ過・限外ろ過膜ではインテグリティ(完全性)とファウリング(汚れ)の制御が重要な性能である。高強度・低ファウリング性の東レPVDF(ポリフッ化ビニリデン)中空糸膜の特長とその応用例、PVDF中空糸膜による膜ろ過プロセス基本設計手法について紹介する。 | ||
| 休 憩 | 13:50~14:00 | ||
| ② | 食品分野におけるUFおよびMF中空糸膜ろ過の利用 | 古本 五郎 (旭化成ケミカル(㈱) 膜・水処理事業部) |
14:00~15:00 |
| 講演概要 | 微生物発酵液への膜分離技術の利用は、医薬及び食品分野にて主に検討され、弊社では1980年代から用途を開拓し実績を積み重ねてきた。今回は食品分野を中心に利用例を紹介するとともに、ラボ実験段階から生産機稼動にいたる技術検討のプロセスについても紹介したい。 | ||
| 休 憩 | 15:00~15:10 | ||
| ③ | スパイラル膜モジュールを想定した平膜評価試験の概要とその適応例 |
川村 幸太 (トスク(㈱) | 15:10~15:50 |
| 講演概要 | 膜を利用した製造プロセスの構築には、実地試験から得られたデータを設計へ正確に展開する事が重要となります。 水処理用途や製造プロセス用途向けのスパイラル膜製品の構造や特徴を紹介するとともに、その特徴を利用でき、かつ様々な用途や膜種を利用できる平膜評価試験の概要や応用例を紹介します。 | ||
| 休 憩 | 15:50~15:55 | ||
| ④ | ビール・発泡酒等およびビール用飲料の商品コンセプトと消費の動向 | 青木 賢吉 ( アサヒビール(㈱酒類研究開発本部) |
15:55~16:55 |
| 講演概要 | ビールの歴史、製造方法を振り返り、日本の酒税法から生まれた、発泡酒、新ジャンル、そして昨年から伸張著しいビアテイスト飲料について、単に節税目的だけでなく、それぞれの制約の中で顧客価値を向上させる技術背景を解説する | ||
| 交 流 会 | 17:05~19:00 | ||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第22回 秋季研究例会プログラム・講演概要
日時: 2010年11月12日(金)
場所: (財)川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA) 11階大会議室.
〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近)
主催: 食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
| 時間 | 講演者 | 講演演題 | 所属 |
| 10:00~10:10 | 会長 挨拶 | ||
| ①10:10~11:10 | 農学博士 渡辺敦夫 |
食品産業における膜技術利用の変遷と現状 | 新技術開発院 院長 |
| 講演概要:食品産業における膜技術利用は着実に進展してきたが、時代の経済状況により浮き沈みがあり、実用化されていたものが利用されなくなっているものもある。地球環境問題が大きくクローズアップされてきている状況の中で、また、若い膜技術研究者に今までの知見を伝承する意味からも、過去から現在までの利用例を総点検して、今後の発展の参考にすることは有効であると考える。 | |||
| ②11:10~12:10 | 博士(理学) 大島永康 |
陽電子消滅法による逆浸透膜細孔の測定-陽電子消滅法の原理と測定精度- | 産業技術総合研究所 研究員 |
| 講演概要 :陽電子とは、電子と同じ質量をもつが、電子とは逆符号の電荷(プラス電荷)をもつ素粒子の一種である。自然界にはほとんど存在しないが、加速器やRIを用いて人工的につくりだすことができる。この陽電子を用いた高分子中の自由体積の大きさを計測する方法(陽電子寿命法)について紹介する。 | |||
| 12:10~13:150 | 昼食 | ||
| ③13:10~13:50 | 工学修士 戸田 洋 |
食品に関わるイオン交換膜プロセス | AGCエンジニアリング(株)マーケティング担当部長 |
| 講演概要: AGCエンジニアリング㈱におけるイオン交換膜プロセスの紹介と食品分野における応用技術を紹介する。あわせてイオン交換膜プロセス、特に電気透析法に対する食品分野特有の課題とその対応について事例を挙げ、更に新しい膜技術の紹介を行う。 | |||
| ④13:50~14:35 | 川嶋正男 | 大豆食品(豆腐・油揚)工業における膜利用技術 | 羽二重豆腐(株)顧問 川嶋特別研究室長 |
| 講演概要:大豆食品の豆腐、油揚製造過程で生成する未利用資源の豆乳凝固分離、圧密後に生成する大豆ホエーは水質汚濁負荷濃度が高い排液である。この処理に膨大な経費とエネルギーが消費され、負担が大きい。この有効成分を新規(1)の食材化とするため膜利用技術による濃縮技術を確立して、乳酸発酵の活用培養への有効なる機能化食材を実証したことを述べる。 | |||
| 14:35~14:50 | 休憩 | ||
| ⑤14:50~15:50 | 邑井 良守 | 食品工場の防虫防鼠対策とその科学 | イカリ消毒(株) 技術研究所課長 |
| 講演概要:近年、食品への農薬汚染、鳥インフルエンザや口蹄疫といった伝染病が立て続けに発生したことから、消費者の衛生意識が格段に向上している。異物混入等といった事故がひとたび起これば、直ちに企業の存続が危うくなるほどの意識を各メーカーは持たなくてはならない。食品工場の防虫防そ対策における最新のトレンドは、事故が起こらないような状態を維持する技術の研究と開発であり、ここではその一端を紹介する。 | |||
| ⑥15:50~16:50 | 工学博士 福崎智司 |
次亜塩素酸ナトリウムの特性と洗浄・殺菌への効果的な利用 | 岡山県工業技術センター 化学・新素材グループ長 |
| 講演概要:次亜塩素酸ナトリウムの有効利用の鍵は、溶液のpH調整にある。弱酸性水溶液中の非解離型次亜塩素酸(HOCl)は、有効塩素濃度あたりの殺菌効果は大きい。一方、アルカリ性水溶液中の次亜塩素酸イオン(OCl-)は、有機物汚れに対して洗浄力を発揮する。処理対象をモノから空間へ向けた活用法についても紹介する。 | |||
| 16:50~16:55 | 事務局連絡 | ||
| 17:05~19:00 | 交流会(1階:ラウンジリリア) | ||
食品膜・分離技術研究会(MRC)
2010年度総会・第22回春季研究例会プログラム・講演概要
日時:2010年6月18日(金) 12:40~19:00
場所:川口総合文化センター リリア(KAWAGUCHI LILIA).
〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1 (川口駅西口下車至近)
TEL: 048-258-2000 FAX: 048-258-2100
主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
| 2010年度 総 会 | ①MRC会長挨拶 ②議事 |
12:40~13:05 | |
| 研 究 例 会 | |||
| 題 目 | 講 演 者 | 時間 | |
| ① | 温故知新による技術開発の必要性 ―過去の研究動向を確認して今後の技術開発に生かす- | 栗原 優 東レ、工学博士 |
13:10~14:25 |
| 講演概要 | 膜を用いた水処理は、水問題解決のため21世紀の基幹技術として期待されている。新規膜の研究開発も世界各国で国家支援のもと活発に行われるようになり、1960~70年代の再現である。多くの基礎研究が開発・企業化段階でいわゆる「死の谷」に落ちてかえりみられない例は、数知れない。この膜の研究開発について、温故知新による技術開発の必要性と「老・壮・青」のコンビによる産・官・学の効率的な研究開発の事例から学ぶべきである。 | ||
| 休 憩 | 14:25~14:35 | ||
| ② | 味の素㈱でのLCAを利用した環境貢献への取り組み | 松本 慎一 味の素、生産技術開発センター |
14:35~15:35 |
| 講演概要 | 当社では早くからLCA視点での環境貢献への取り組みを開始した。2000年ごろから包材のLC-CO2の算定方法の開発に着手し、2003年に完成させた。一方、食品とアミノ酸のLC-CO2については、2007年に産業連関表を利用したデータベースを完成させ、CO2発生量を算定出来るようになった。2009年から飼料用リジンについて「カーボンフットプリント制度試行事業」へ参画している。これを添加した飼料は、温室効果ガスである亜酸化窒素の発生量を削減できるので、飼料用リジンの環境貢献を明らかにする予定である。今後ともLC-CO2の算定手法を環境貢献の「見える化」ツールのひとつとして活用し、低炭素化社会の構築につなげていきたい。 | ||
| 休 憩 | 15:35~15:50 | ||
| ③ | 大豆たん白製品製造における膜・分離技術の現状 | 内丸正治 不二製油、技術開発部 |
15:50~16:25 |
| 講演概要 | 不二製油グループは大豆の計り知れない可能性に着目し大豆たん白製品の研究開発を進めてきました。その中で膜・分離技術は大豆たん白製品の製造には無くてはならない技術です。今回は水処理から製造プロセス、排水処理に至るまで、製造過程で利用される膜・分離技術の一部を紹介します。 | ||
| ④ | 膜分離活性汚泥法(MBR)の食品工場排水への適用 | 高瀬 敏 森永エンジニアリング、環境事業部 |
16:25~16:55 |
| 講演概要 | 活性汚泥法において最終沈殿槽での固液分離に膜を用いた膜分離活性汚泥法(MBR)は、管理の容易さ、コンパクトな設備、高度な処理水水質等の特徴と種々材質と形式の膜製品化などから実績を重ね、公共下水道への導入、数万m3/日以上の大規模設備などと普及が進んできている。また水需要の逼迫から排水再利用を目的とする高度処理法としてMBRは海外で広く採用されてきており、国内でも活用が広がる状況にある。こうした動向も踏まえMBRの食品工場排水への適用等について紹介する。 | ||
| 交 流 会 | 17:05~19:00 | ||
MRC 第21回秋季研究例会 プログラム
日時:2009年11月13日(金曜日)
場所:(財)川口総合文化センター(11階:大会議室)
〒332-0015 川口市川口3-1-1
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部付属硬蛋白質利用研究施設
| 時間 | 講演者 | 講演演題 | 所属 |
| 9:45~9:55 | 会長挨拶 | ||
| ①10:00~11:00 | 佐藤 幾郎 | 脱脂乳のナノろ過 | 森永乳業株式会社装置開発研究所 |
| 講演概要:乳業においては、ナノろ過(NF)は牛乳やホエイを脱塩濃縮する技術として広く利用されている。透過する塩類は主に一価で、かつ塩素の阻止率が著しく低いことが観測されている。そこで、脱脂乳のNFを例に、二価塩類が透過しない理由、一価塩類の流束について荷電膜における電解質透過理論のひとつであるTMSモデルにより解析した例を紹介する。 | |||
| ②11:00~12:00 | 峯岸 進一 | 水処理膜の市場動向と最先端技術 | 東レ株式会社 地球環境研究所 |
| 講演概要:21世紀になって、世界的な水不足、水環境の悪化が進行しており、持続可能な水資源の確保、水環境の保全・浄化は人類にとって大きな課題となっている。さらに、最近は、水環境悪化による健康リスクの顕在化に対する高度処理、地球温暖化を抑制する低消費エネルギーが求められるようになり、これらを解決するために膜分離技術が注目されている。高分子を素材とした水処理用分離膜の市場および技術動向について講演する。 | |||
| 12:00~12:50 | 昼食 | ||
| ③12:50~13:50 | 川口 寿之 | 食品製造工場の食品衛生法に基づく水質管理~水質検査の最近の話題~ | (財)日本食品分析センター 多摩研究所水質試験課 |
| 講演概要:食品工場で使用する水は,食品衛生法に規定されている「飲用適の水」の規格を遵守する必要がある。そのための水質管理の参考となるよう,検査項目,検査頻度等について解説する。さらに最近問題となっている地下水汚染物質等についても紹介する。 | |||
| ④13:50~14:35 | 伊東 章 | 生活の中の化学工学『煮物は冷めるときに味がしみるというのはなぜ-伝熱と拡散のはなしなど-』 | 東京工業大学大学院理工学研究科 |
| 講演概要:「煮物は冷めるときに味がしみるというのはなぜ-伝熱と拡散のはなし-」「水蒸気と除湿のはなし」「においと吸着」 「「ハー」は暖かく「フー」は冷たいのはなぜ」「風船はなぜしぼむ」などの日常生活の疑問に対しては,よく理科的観点からの説明がなされる。これに対して,工学的・化学工学的観点からの説明も大胆なモデル化の点で興味深いものである。そのような化学工学的観点からの日常の疑問への回答を紹介し,化学工学の有用性を一般にアピールする機会としたい。 | |||
| 14:35~14:50 | 休憩 | ||
| ⑤14:50~15:35 | 千葉 一裕 | エマルションの相分離を利用した新温度履歴センサー | 東京農工大学大学院連合農学研究科 |
| 講演概要:温度感受性エマルションの相分離現象およびアミド水溶液の相分離現象を利用することにより、食品等の低温輸送の個別温度管理状態を認証できるセンサー(タグ)を開発した。エマルションはヤシ油、大豆レシチン等で構成し、冷却により温度監視状態に自動的に入り、その後の加温で不可逆的に相分離が起こる。僅かな温度変化に伴う相分離現象は、温度履歴を可視化する他、多様な化学プロセス等への応用が期待される。 | |||
| 15:35~15:40 | 休憩 | ||
| ⑥15:40~16:10 | 中川 浩一 | 膜の支持用紙の役割・性状 | 阿波製紙㈱ 研究開発部 |
| 講演概要:最近のRO膜をはじめとする分離膜はめざましい進歩をとげているが、平膜の場合には支持体紙も一定の役割を果たしている。初期の分離膜には乾式不織布が支持体として用いられていたが、現在では湿式抄紙法を用いた湿式不織布が多用されている。そこで、一般にはあまり知られていない分離膜支持体紙の役割・性状について、製造する者の立場から紹介する。 | |||
| ⑦16:10~16:50 | 大倉 幸洋 | 合成吸着剤を用いた機能性食品の分離精製技術 | 日本錬水㈱ 研究所 |
| 講演概要:工業規模のクロマト分離技術としての擬似移動床分離は、澱粉糖精製分野における陽イオン交換樹脂を用いた水系のクロマト分離を中心に発展してきた。今や身近な分析機器である高速液体クロマトグラフィー (HPLC)と同じ分離モードに基づいて、合成吸着剤を利用した分配クロマトグラフィーでも、工業規模の分離プロセスとして適用できる可能性は十分にある。実際に弊社が装置納入した順相溶媒系クロマト分離の類似例として、ビタミンE群の擬似移動床分離の検討事例を紹介する。 | |||
| 16:50~16:55 | 事務局連絡 | ||
| 17:05~19:00 | 交流会(1階:ラウンジリリア) | ||