研究例会の記録 (1989~2008)
第20回秋季研究例会
日時:2008年11月7日(金曜日)
会場:(財)川口総合文化センター
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関:東京農工大学農学部付属硬蛋白質利用研究施設
| 時間 | 講演者 | 講演演題 | 所属 |
| 9:45~9:55 | 会長 挨拶 | ||
| ①10:00~11:00 | 田村真紀夫 | 膜分離技術振興協会の現状と膜技術実用化の広がり | 膜分離技術振興協会 膜協ジャーナル編集長 MRC副代表幹事 |
| 膜協会は設立25年を迎えた。その間、対象とする主たる分野は、注射用水の製造から、上水の浄化等へ変化してきたが、膜分離技術を広めると言う目的に基づいて、関連の民間会社を中心に活動を継続してきた。今回はその活動の歴史と現状、膜分離技術の実用分野に関して紹介する。 | |||
| ②11:00~12:00 | 渡辺 敦夫 | ナノ濾過(NF)技術の特性と機能性食品製造への利用 | 新技術開発院 院長 MRC会長 農学博士 |
| 多くの機能性成分は、分子量数100~数1000程度でありNFで分離できる範囲に入る。NFは,ROやUFと異なり膜内での溶質の拡散速度が分離性能に影響を与えるためNFの特性を理解して利用することが必要である。演者は長年に渡りNFの研究を行ってきたので、NF利用のコツと応用例について、分かり易く紹介する。 | |||
| 12:00~12:50 | 昼食 | ||
| ③12:50~13:50 | 田村 吉隆 | 乳業界における最新の膜・分離技術事情 | 森永乳業(株) MRC副会長 工学博士 |
| 育児用粉乳の開発を目的に膜分離研究に携わって41年、1975年には連続式イオン交換膜電気透析脱塩設備が稼動、その後1980年脱脂乳の濃縮に限外濾過濃縮設備、1981年にはホエイ濃縮に逆浸透濃縮設備を導入した。当時800㎡程度であったが、今では5000㎡以上の膜分離設備が稼動し、目的も多岐に亘るようになった。乳業界の最新の膜分離・技術事情について紹介する。 | |||
| ④13:50~14:40 | 西山敏夫 | コラーゲンの科学:生体における役割とその有効利用 | 東京農工大農学部付属硬蛋白質利用研究施設 施設長 理学博士 |
| 硬蛋白質利用研究施設は、「硬タンパク質」の生物学的な機能や構造形成、さらには生体素材としての特性や活用の研究を行っている。硬タンパク質の主成分である「コラーゲン」は、ヒトの体に含まれるタンパク質の30%近くを占め、皮膚、骨、軟骨、腱をはじめ、各臓器の結合組織を構成している。本講演では、皮膚を中心に各種コラーゲンの構造や機能など生体における役割を解説し、それらの有効利用についての現状を紹介する。 | |||
| 14:40~14:55 | 休憩 | ||
| ⑤14:55~15:25 | 伊東 未央 | カートリッジフィルターおよび膜について | アドバンテック東洋㈱濾紙販売促進部 |
| 加熱を行うことなく微生物を除去できる無菌化濾過技術は、食品の安全性の確保や高品質化等の目的で利用が広がっており、最終の仕上げ濾過にはカートリッジフィルターが広く使用されている。濾過機構や濾過方法、各種カートリッジフィルターの構造や特長、各種メンブレンフィルターの特長や用途等、濾過やフィルターに関して紹介する。 | |||
| 15:25~15:30 | 休憩 | ||
| ⑥15:30~16:10 | 真鍋 征一 | 目詰まりしない膜分離技術―孔拡散の利用 | (株)セパシグマ代表取締役 工学博士 |
| 膜間差圧を駆動力とする膜ろ過では孔の目詰まりが不可避である。新規な孔拡散型平膜分離装置では濃度勾配を駆動力として物質は孔内を移動する。そのため①孔の目詰まりなし、②篩効果とブラウン運動の活発度の差を共に利用(分子量分画も可能)、③孔径分布の広がりの影響を受け難い、④膜の再生が容易(膜のリユース化)。これらの特徴を利用した分離例を示す。 | |||
| ⑦16:10~16:50 | 桶田 裕 | 食品分野におけるイオン交換膜の利用 | (株)アストム |
| イオン交換膜の利用法としては電気透析と拡散透析があり、各種産業分野で広く用いられている。食品分野においても製塩・乳業・醤油・梅調味液・漬物などで幅広く利用されている。主な利用目的は有機物と無機塩の分離であるが、原料の種類が多岐にわたる為、イオン交換膜の種類や運転方法などは各々異なっている。食品分野での実例や応用例について講演する。 | |||
| 16:50~16:55 | 事務局連絡 | ||
| 17:05~19:00 | 交流会(1階:ラウンジリリア) | ||
MRC第20回 秋季研究例会アンケート 集計
回答総数 30
1.研究例会の全体的構成(研究例会の長さ・各講演の長さ)をどのように感じましたか
①ちょうど良い時間構成であった*24名 ②朝9時45分からでは早すぎる*1名 ③もっと膜・分離に関する情報を学びたいので2日間にして欲しい*3名 ④2日間にして半日の見学会を入れて欲しい1名 ⑤その他 意見**地方から参加すると2泊になってしまうのでもう少し開始時間を遅くして貰えると良い。
2.本研究例会に出席し興味を持たれた講演はどの講演ですか(複数あげて頂いてOKです)?どの様な点に興味を持たれましたか?
全体的評価*** 総ての講演が参考になった。どのように企業で活用しているかが分かった。投資額の大きい膜装置をどのように償却するか熟考する機会になった。
講演1 (膜分離技術振興協会の現状と膜技術実用化の広がり) 最近の膜技術の動向が分かりよかった4名 日本での膜技術発展過程の話に興味を持った。25年間の膜の歴史。
講演2 (ナノ濾過(NF)技術の特性と機能性食品製造への利用)NFは食品分野の利用が多く参考になった5名 輸送機構の話が参考になった2名。今回の講演を聴いてNFの特性・原理がよく分かった。3名 分かり易く原理と応用例を学べた6名。 RO膜の孔径0.6nm、NF膜の孔径0.7nm。食品産業における利用例に興味を感じた。
講演3 (乳業界における最新の膜・分離技術事情)MFで脂肪を除くと日持ちが良くなるとのこと参考になった。 乳業界の現状が分かり大変参考になった11名 乳を多種多様な原料に分画し、そこから新しいものを作り出す技術。
講演4 (コラーゲンの科学:生体における役割とその有効利用)コラーゲンそのものに材料としての興味を持った2名。今後の応用方向等興味深かった1名。コラーゲンの重要性を始めて認識した。
講演5 (カートリッジフィルターおよび膜について)カートリッジフィルターについて詳しく知ることができよかった5名
講演6 (目詰まりしない膜分離技術―孔拡散の利用)早く実用化して欲しい。目詰まりをしない孔拡散に興味大6名。蛋白質の分離もできそう。これまでの膜分離の原理と異なるものであり興味がある。イオン交換膜によるHCl,NaCl の回収に興味を持った。2名 目詰まりしない膜分離技術に興味を持ち、拡散分離に興味を持った。新しい技術として興味深かった。実演を見てみたい。新しい考え方に興味を持った。
講演7 (食品分野におけるイオン交換膜の利用)イオン交換膜の応用例。3名 バイポーラー膜に興味を持った。2名
4.食品産業における膜・分離技術に関して聞いてみたい講演テーマ・講師がいれば記入下さい。
結晶化技術 サプリメントや機能性食品の動向を食品会社の方から聞きたい。異性化等や醤油などにおける膜技術 野菜ジュースの濃縮。スポンジ洗浄。凍結濃縮技術。濾過技術について。機能性食品製造における膜技術の実用例。
5.食品産業に関連する加工技術で聞いてみたい講演テーマ・講師がいれば記入下さい。
発酵技術と分離精製 野菜ジュースやハードヨ-グルトの加工。 ヒアルロン酸、コンドロイチンなど大学で真面目に取り組んでいるところがあれば聞いてみたい。機能性食品の製造での膜利用の成功例。安全性に関する法的規制。
6.MRCのこれからの活動予定は以下の通りです。
①MRCニュースの発行(10月or 11月)発行予定
②2009年1月23日『初級者のための食品膜技術講習会』**講師**渡辺*田辺
③2009年4月MRCニュース41号発行予定
④2009年6月12日 第21回総会・第21回春季研究例会(13時から17時)
⑤2009年8月6/7日『中級・上級者のための食品膜技術講習会』
⑥2009年9月15/16日『食品乾燥・包装技術講習会』**講師**土田*渡辺*石谷
⑦2009年10月14/15/16日 食品開発展出展予定(プレゼンテーション2日)
⑧2009年10月or 11月にMRCニュース42号発行予定
⑨2009年11月20日MRC第21回秋季研究例会
以上の活動の中でMRCは会員の方々の意見をできるだけ反映させた運営を行うように心掛けていますが、運営上で改善すべき点(例えば、講習会を行って欲しい技術内容)等がありましたら記入下さい。
①現状で問題ない8名 ②濾過技術に関する講習会4名 ③分離技術全般についての講習会3名 ④その他 商品開発の成功例などについても聞いてみたい。
7.その他 MRCに対するご意見がありましたら記入下さい。
①できる限り資料を統一して欲しい(パワーポイントの印刷物など 事務局回答 原稿が出てくるのが遅く事務的に追いつかない。MRCの講演要旨はしっかり書かれているのでこの程度でOKでしょう)
②時間を知らせるタイマーの音が耳障りであった(事務局回答;時間通りに研究会を推進するため他の方法で講演者に時間を知らせることを考えてみます)。
③分離膜の材料設計や孔径コントロール等について。
④次回の研究会や勉強会に出席したい。
⑤講演内容は難しいので事前に講演要旨を貰えると予習できる(事務局回答 先ずはしっかり基礎力を付け内容を理解できるようになること。原稿が出てくるのが遅く事務的に追いつかない。MRCの講演要旨はしっかり書かれているのでこの程度でOKでしょう)。
⑥研究例会でいろいろな分野の話、別の見方、考え方が聞けて有り難い。
⑦実プラントの見学ができると良い。
食品膜・分離技術研究会(MRC)設立20周年記念式典および
2008年度総会・第20回春季研究例会
日時:2008年6月20日(金)12:20~19:00
会場:川口総合文化センター リリア
主催 :食品膜・分離技術研究会(MRC)
協力機関 :東京農工大学農学部附属硬蛋白質利用研究施設
| 時間 | 講演者 | 講演演題 |
| ①13:00~14:25 | 柴田 明夫 (丸紅経済研究所 所長) |
MRC20周年記念特別講演 世界の食料需給の動向 |
| ②14:25~14:55 | 渡辺 敦夫 (食品膜・分離技術研究会会長) |
MRC20周年記念講演 食品膜・分離技術研究会20年の歩みと今後 |
| 14:55~15:10 | 休息 | |
| ③15:10~15:55 | 林 徹 (食品総合研究所 所長) |
食品行政に於ける技術開発 ―食品総合研究所の目指す方向― |
| ④15:55~16:55 | 川崎 睦夫 (造水促進センター) |
最近20年の膜技術の発展 ―膜開発と実用化の進展― |
第19回秋季研究例会
日時:2007年10月23日(火曜日)
会場:(財)川口総合文化センター
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
共催:CPMジャパン(株)『食品と開発』
| 時間 | 講演者 | 講演演題 | 所属 |
| ①10:00~11:00 | 門間 裕 | 我が国の最近の食品事故とその原因 | (社)日本アグリビジネスセンター 常務理事 |
| ②11:00~120:0 | 石谷 孝佑 | 中国の偽物食品事情と安全対策 | 日本食品包装研究協会会長 農学博士 |
| 12:00~13:00 | 昼食 | ||
| ③13:00~14:00 | 宮川 早苗 | 食品新素材開発、安全・環境対策の最新動向と分離・ろ過技術 | CMPジャパン(株)『食品と開発』 編集長 |
| ④14:00~14:40 | 原田 三郎 | セラミック膜の発展とその利用技術―高分子成分の分離・無菌化を中心として- | (株)トライテック 技術部長 学術博士 |
| 14:40~15:00 | 休憩 | ||
| ⑤15:00~16:00 | 吉川 浩志 | 世界の水事情と日東電工の膜技術開発の動向 | 日東電工(株)メンブレン事業部 開発部アプリケーショングループ |
| ⑥1600~17:00 | 早川 喜郎 | 野菜・果実加工における濃縮技術の発展とその利用状況 | カゴメ(株)総合研究所 技術開発研究部長 工学博士 |
| 17:10~19:00 | 交流会 |
渡辺敦夫教授 新潟大学退官記念講演会および
MRC第19回総会および春季研究例会 2007年6月8日(金)
場所:ホテルはあといん乃木坂 東京都港区南青山1-24-4
渡辺敦夫教授 新潟大学退官記念講演会および
MRC第19回総会および春季研究例会プログラム
日時:2007年6月8日(金) 12:30~19:10
場所:ホテルはあといん乃木坂 -健保会館-
東京都港区南青山1-24-4 TEL:03-3403-0531 FAX:03-3403-3176
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
共催:渡辺研究室同窓会,新潟県食品技術研究会(FC新潟)
|
2007年度 総 会 |
①MRC会長挨拶 |
12:30~12:55 |
|
|
研究例会 |
|
||
|
題 目 |
|
|
|
|
①行者ニンニク等機能性食品研究と |
西村 弘行 |
13:00~13:45 |
|
|
②世界の食料需給と日本食品産業の課題 |
野口 明徳 |
13:45~14:30 |
|
|
休憩 |
14:30~14:55 |
||
| ③明治乳業の商品開発戦略と分離技術 |
桑田 有 |
14:55~15:40 |
|
|
④新潟大学退官記念講演 |
渡辺 敦夫 |
15:40~17:00 |
|
|
交流会 |
17:10~19:10 |
||
【講演概要】
①「行者ニンニク等機能性食品研究とベンチャー企業の経営」西村 弘行(北海道東海大学 学長)
北海道内に自生あるいは寒冷地の栽培に適した食用植物の中には健康機能の高いものが知られ、その高度活用が望まれている。その代表的な北方系食用植物には抗疲労、抗動脈硬化、男性ホルモン増強などの機能性を持つ行者ニンニクをはじめチコリーやヤーコン等が知られている。道産食材の健康機能を in vitro および in vivo 系で解明し、成果を大学発ベンチャーで事業化に成功した事例を紹介する。ベンチャー企業経営戦略についても論ずる予定である。
②「世界の食料需給と日本食品産業の課題」野口 明徳(国際農林水産業研究センター理事)
カロリーベースで約60%の食料を海外に依存する日本は、未だ続く世界人口増加、限りある水・土地資源、食料利用と工業利用の拮抗、世界の食料需給の現状を注視すべきである。その上で、増大しつある高齢層と縮小可能性のある国内市場を視野に入れて、日本の食品産業が今後どうあるべきかを考えたい。
③「明治乳業の商品開発戦略と分離技術」桑田 有(明治乳業㈱ 常務取締役)
明治乳業の商品開発では、発酵・チルド、栄養、乳化・食品の3つの事業領域を設け研究を行っており、各領域での分離技術を紹介する。発酵・チルド領域では、ヨーグルトスターターおよびプロバイオティクス技術、ブランド牛乳の製造、栄養領域ではカルニチンの濃縮、たんぱく質の各画分の分離等がある。また、乳化・食品領域では、脱脂乳およびチーズホエイの脱塩、バクトフュージでの品質向上等があげられる。
④「新潟大学退官記念講演 -膜分離工学を中心とした食品工学研究40年-」渡辺 敦夫(新潟大大学院 教授)
演者は大学卒業以来、大略民間会社10年、農林水産省19年、新潟大学11年と立場の異なる職場を経歴してきたが、これらの職場で行ってきた仕事は膜分離工学を中心とした食品工学研究であった。トマトケチャップやグリンピース等の農産物加工、凍結粉砕の特性解明、マイクロ波利用・遠赤外線の加熱特性の解明、膜利用型排水処理・高粘度食品の高濃度濃縮用セラミック膜モジュールの開発、ナノ濾過特性の解明等の膜分離工学に関する研究、また、農林水産省で初めて設立した食品産業膜利用技術研究組合の運営等にも携わってきた。さらに、本食品膜・分離技術研究会の設立と運営等、幅広い研究および研究活動の中で学んだ事柄等について紹介する。
第18回秋季研究例会 参加者103名
2006年10月26日(木)~27日(金)
場所:新潟市 新潟東映ホテル 新潟市弁天2-1-6 TEL:025(244)7101
実行委員長:伊東 章,副実行委員長:城 斗志夫・江川 和徳,会計:城 斗志夫・田村 肇
庶務・会計監査:赤塚 昌一・渡辺 憲一
日時:2006年10月26日(木)~10月27日(金)
場所:新潟東映ホテル 新潟市弁天2丁目1-6 Tel:025-244-7101 Fax:025-241-8485
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
共催:新潟県食品技術研究会(FC新潟)
協賛:新潟県食品産業協会
<基礎講座>(10月26日(木)9:30~11:30)
|
10/26 (木) |
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
|
|
①分離技術とはどんな技術、どんな食品が作れるの? |
伊藤光太郎 |
(雪印乳業㈱技術研究所) |
9:30‐10:30 |
|
|
②膜技術とはどんな技術、どんな食品が作れるの? |
大西 正俊 |
(森永乳業㈱装置開発研究所) |
10:30‐11:30 |
|
<研究例会>(10月26日(木)12:30~21:00,10月27日(金)9:00~17:00)
|
10/26 (木) |
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
||
|
MRC会長挨拶 渡辺 敦夫(新潟大学大学院) |
12:30‐12:50 |
||||
|
休 憩 |
12:50‐13:00 |
||||
|
①21世紀は水と二酸化炭素の時代-持続可能な社会へのソフトランディング- |
新井 邦夫 |
(東北大学大学院) |
13:00‐14:00 |
||
|
②サントリーの環境戦略 |
高屋 雅光 |
(サントリー㈱) |
14:00‐15:00 |
||
|
休 憩(展示物紹介) |
15:00‐15:25 |
||||
|
③遠心分離機、膜装置、遠心薄膜濃縮機による飲料プロセスの最適化 |
青木 裕 |
(アルファ・ラバル㈱) |
15:25‐16:00 |
||
|
④環境に優しい水とファインケミカルズの精製・再利用技術 |
田村 真紀夫 |
(オルガノ㈱) |
16:00‐16:25 |
||
|
⑤地下水の膜システム利用による上水の製造 |
上原 勝 |
(㈱ウェルシィ) |
16:25‐16:45 |
||
|
⑥含油乾燥汚泥の流動層燃焼 |
清水 忠明 |
(新潟大学工学部) |
16:45‐17:05 |
||
| 実 行 委 員 会 連 絡 |
17:05‐17:10 |
||||
|
夕 食 (交流会) |
17:20‐19:00 |
||||
|
分科会 ①食品の安全性とポジティブリスト |
19:00‐21:00 |
||||
|
10/27 (金) |
⑦ポジティブリスト制とその対策 |
佐藤 元昭 |
(元和歌山大学客員教授) |
9:00‐10:00 |
|
|
⑧発酵法アミノ酸製法における膜・分離技術 |
冨家 一郎 |
(味の素㈱) |
10:00‐10:30 |
||
|
休 憩 |
10:30‐10:45 |
||||
|
⑨東レの水処理膜開発戦略と世界の水処理動向 |
栗原 優 |
(東レ㈱) |
10:45‐11:45 |
||
|
⑩高分子機能膜の夢と可能性 |
青木 俊樹 |
(新潟大学工学部) |
11:45‐12:05 |
||
|
見学会案内・実行委員会連絡 |
12:05‐12:15 |
||||
|
新潟東映ホテル出発 = 12:20 バス車内で弁当昼食 |
12:20‐ |
||||
|
見学会 バスで高速道(小千谷より)⇒ 越後製菓(14:00~14:40) ⇒ 朝日酒造(15:00~16:30) |
|||||
第18回春季研究例会 参加者56名
2006年6月9日(金)
場所:全林野会館大ホール 東京都文京区大塚3-28-7
|
2006年度 総 会 |
①MRC会長挨拶 |
12:30~12:55 |
|
|
研究例会 |
|
||
|
題 目 |
|
|
|
|
①食品産業における珪藻土・パーライト濾過助剤の利用 |
神笠 諭 |
13:00~13:55 |
|
|
②食品産業における国外・国内の |
今須 欣之輔(日本アブコー㈱) |
13:55~14:50 |
|
|
展示物紹介 |
14:50~15:00 |
||
|
休憩 |
15:00~15:20 |
||
|
③最近の食品濃縮技術とインベンシスシステムス㈱の分離技術 |
松山 良平 |
15:20~16:15 |
|
|
④食品の乾燥とその関連技術 |
山本 仁巳 |
16:15~17:10 |
|
|
交流会 |
17:20~19:15 |
||
第17回秋季研究例会 参加者109名
2005年11月10日(木)~11月11日(金)
場所:宮城県気仙沼市 サンマリン気仙沼ホテル観洋 気仙沼市港町4-19(TEL.0226-24-1200)
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
協賛:宮城県食品工業協議会,山形県食品産業協議会,岩手県食品産業協議会,福島県食品産業協議会,
気仙沼市水産加工業振興協議会,(財)日本食品分析センター,日本細菌検査株式会社,㈱フロンティ
アエンジニアリング,(独)産業技術総合研究所東北センター,㈱インテリジェント・コスモス研究機構,
㈱白松がモナカ本舗,東北インテリジェント・コスモス構想推進宮城県委員会, (社)みやぎ工業会
後援:宮城県,岩手県,気仙沼市
<基礎講座>(11月10日(木)9:30~11:30)
|
11/10 (木) |
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
|
|
①分離技術とはどんな技術、どんな食品が作れるの? |
佐藤 武 |
(味の素㈱) |
9:30‐10:15 |
|
|
②膜技術とはどんな技術、どんな食品が作れるの? |
大西正俊 |
(森永乳業㈱) |
10:15‐11:00 |
|
|
③無機膜の化学プロセスへの応用 |
水上富士夫 |
((独)産業技術総合研究所コンパクト化学プロセス研究センター) |
11:00‐11:30 |
|
<研究例会>(11月10日(木)12:30~21:00,11月11日(金)9:00~16:00)
|
11/10 (木) |
題 目 |
講 演 者 |
時 間 |
||
|
MRC会長挨拶 渡辺 敦夫(新潟大学大学院) |
12:30‐12:50 |
||||
|
休 憩 |
12:50‐13:00 |
||||
|
①欧米における食品加工用モジュールの開発 |
Mark S.Braun |
(GEA Filtration-USA) |
13:00‐14:00 |
||
| ②チーズホエイのUF膜利用事例 |
宮沢 秀夫 |
((財)蔵王酪農センター) |
14:00‐14:20 |
||
|
③畜産排水処理への膜分離の応用 |
佐藤 富男 |
(㈱ヒルズ) |
14:20‐14:40 |
||
|
休 憩(展示物紹介) |
14:40‐15:05 |
||||
|
④天然調味料開発における分離技術の利用 |
田村 宏 |
(味の素㈱ 調味料開発・工業化センター) |
15:05‐15:45 |
||
|
⑤ブランド化戦略 水産食品の品質改善手段と食品衛生法との関係 |
戸ヶ崎惠一 |
(日本細菌検査㈱) |
15:45‐16:25 |
||
|
中原 光一 |
(サントリー㈱商品技術部) |
16:25‐17:05 |
|||
|
実 行 委 員 会 連 絡 |
17:05‐17:15 |
||||
|
夕 食 (交流会) |
17:30‐19:00 |
||||
|
分科会 ①食品・水産加工に期待される分離技術 |
19:00‐21:00 |
||||
|
11/11 (金) |
気仙沼魚市場見学(希望者) (サンマ漁の最盛期) |
6:45‐7:45 |
|||
|
⑦水産加工・養殖と環境 |
奏 和彦 |
(日本水産㈱中央研究所) |
9:00‐9:50 |
||
| ⑧食品機械・膜装置の最新の洗浄法 |
田辺 忠裕 |
(エコラボ㈱ジャパンテクニカルセンター) |
9:50‐10:30 |
||
|
休 憩 |
10:30‐10:50 |
||||
|
⑨電解殺菌水の効果と実用例 -電解水製造装置「ピュアスター」の特性- |
松山 公喜 |
(森永乳業㈱ 装置開発研究所) |
10:50‐11:10 |
||
|
⑩新潟県における膜技術の普及と実用化 |
渡辺 敦夫 |
(新潟大学大学院) |
11:10‐11:30 |
||
|
⑪メンブレンバイオリアクターによる乳酸醗酵 |
國眼 孝雄 |
(東京農工大学大学院) |
11:30‐12:00 |
||
|
見学会案内・実行委員会連絡 |
12:00‐12:10 |
||||
|
気仙沼ホテル観洋出発 = 12:20 バス車内で弁当昼食 |
12:20‐ |
||||
|
見学会 |
Aコース 12:45~14:00 村田水産 視察 ⇒ 15:40 JR一ノ関駅到着,解散 | ||||
| Bコース 13:10~15:10 ㈱中華高橋水産 視察 ⇒ 17:00 JR一ノ関駅到着,解散 | |||||
第17回春季研究例会 参加者48名
2005年6月10日(金)
会場:全林野会館大ホール(東京都文京区大塚3-28-7)
2005年度 総 会 ①MRC会長挨拶
②議事12:30~12:55
研究例会
題 目
講 演 者 ①食品産業の現状と技術開発施策の展開方向 北村 義明(農林水産省 食品産業企画課 技術室長)
13:05~14:05
②中国の経済発展と食糧問題・技術動向
石谷 孝佑(前日中農業技術研究開発センタープロジェクト首席顧問)
14:05~15:05
展示物紹介
15:05~15:15
休憩
15:15~15:35
③精密濾過膜による無菌化濾過食品の開発動向 原田 三郎(NGKフィルテック㈱ 取締役開発部長)
15:35~16:25
④世界の水事情と膜技術利用の現状と展望 横山 文郎(前東レ㈱ メンブレン事業部 海外営業担当部長)
16:25~17:15
交流会
17:25~19:15
第16回秋季研究例会 参加者72名
2004年11月18日(木)~11月19日(金)
会場:府中市 大國魂神社結婚式場
協賛:東京都食品産業協議会,埼玉県食品工業協会,山梨県食品技術研究会,新潟県食品技術研究会
<基礎講座>(11月18日(木)9:30~11:30)
①膜プロセス性能解析の基礎 伊東 章(新潟大学工学部)
②食品分野への膜技術の応用 佐藤 武(味の素㈱)
<研究例会>(11月18日(木)12:40~21:00,11月19日(金)9:00~17:00)
11/18(木)
MRC会長挨拶 渡辺敦夫(新潟大学大学院)
実行委員長挨拶 国眼孝雄(東京農工大学大学院)
①大学の独立法人化と企業との協力関係
亀山 秀雄(東京農工大学大学院)
②野菜・果実加工における膜技術の新たな展開
早川 喜郎(カゴメ㈱)
③ペクチン入り無菌ジュースの製造とセラミック膜利用技術の動向
原田 三郎(NGKフィルテック㈱
④微生物懸濁液のクロスフロー濾過におけるファウリング
田中 孝明(新潟大学工学部)
⑤Pall Exekiaセラミック膜フィルターによるクロスフローろ過
角屋 正人(日本ポール㈱)
⑥超臨界・亜臨界水利用技術の現状と展望 -食品成分の抽出から
不可食成分の可食化処理まで-
新井 邦夫(東北大学大学院)
<分科会> ①膜技術の基礎と応用
②膜のファウリングとメンテナンス
③新食品の創造と新技術
④循環型社会形成のための新技術
11/19(金)
⑦逆浸透膜のファウリングと対策 川勝 孝博(栗田工業㈱)
⑧乳業膜設備の運転管理 大西 正俊(森永乳業㈱)
⑨最新家庭用電子レンジ利用による新食品の開発-こげ目入り食品およびゆで卵等の製造-
渡辺 敦夫(新潟大学大学院)
⑩食品工場の難燃性廃棄物処理と利活用 小海 孝雄(㈱グリーンエナジー)
⑪超磁歪素子を用いた食品計測用動的粘弾性測定装置 関根 正裕(埼玉県産業技術総合センター)
【見学会】
① 東京農工大学工学部
② 鉄道総合技術研究所
第16回春季研究例会 参加者52名
2004年6月11日(金)12:30~19:00
会場:全林野会館大ホール(東京都文京区大塚3-28-7)
|
総会 |
12:30~12:50 |
|
|
研究例会 |
||
|
題 目 |
||
|
①燃料電池用膜の開発 |
山口 猛央 |
13:00~13:40 |
|
②製造現場から立ち上げたトレーサビリティ |
高山 勇(キユーピー㈱) |
13:40~15:00 |
|
休憩(展示物紹介) |
15:00~15:25 |
|
| ③食品工業に於けるフィルター利用の現状 |
桜井 光三 |
15:25~16:05 |
| ④分離精製技術のターゲットとなる機能性素材の 市場動向 |
宮川 早苗 |
16:05~17:05 |
|
交 流 会 |
17:15~19:00 |
|

第15回秋季研究例会 参加者128名
2003年11月20日(木)~11月21日(金)、
会場:ブケ東海静岡 (静岡市紺屋 9-9)
協賛:静岡県食品技術研究会、静岡県資源環境技術研究会、静岡化学工学懇話会、静岡県食品産業協議会、静岡県環境資源協会、しずおか産業創造機構、静岡県水処理協会、 Applied
Biological Chemistry 研究会
 <基礎講座>(11月20日(木)9:30~11:30)
<基礎講座>(11月20日(木)9:30~11:30)
①逆浸透法、限外ろ過法の性能評価 鍋谷 浩志 ((独)食品総合研究所)
②膜プロセスの導入に向けた検討のすすめ方 重松 明典 (雪印乳業㈱・技術研究所)
<研究例会>(11月20日(木)12:40~21:00,11月21日(金)9:00~17:00)
11/20(木)
MRC会長挨拶 渡辺敦夫(新潟大学大学院)
実行委員長挨拶 須藤雅夫(静岡大学) 12:40‐13:00
①ケーク濾過としての微粒子・高分子の膜分離 入谷 英司 (名古屋大学大学院)
13:00‐13:50
②膜技術・世界の動き 横山 文郎 (東レ㈱) 13:50‐14:40
③ナノ濾過膜の特性と評価 渡辺 敦夫 (新潟大学大学院) 14:40‐15:10
休 憩 15:10‐15:30
④NF膜による茶抽出液中のアミノ酸とカテキンの分離 佐田 康稔 (静岡県茶業試験場)
15:30‐15:50
⑤膜技術による水産エキスからの機能性ペプチドの開発 菊地 数晃 (焼津水産化学工業㈱)
15:50‐16:20
⑥駿河湾深層水の利活用に向けた取組みについて 三野 敏克 (焼津市経済部)
16:20‐16:40
⑦過熱水蒸気を利用した廃棄物の乾燥 柴田 正人 (㈱食品機械開発) 16:40‐17:00
実行委員会連絡 17:00‐17:10
夕 食 (交流会) 17:10‐19:00
分科会 19:10‐21:00
①膜技術の基礎と応用-膜分離と濾過・支援ソフト-
②新食品の創造と膜利用
③循環型社会と膜利用(排水処理と工場用水再利用を含む)
④新しい膜の開発と利用分野の拡大
11/21(金)
⑧ROシステム設計支援ソフトの利用と応用 土居 昌博 (アメリオン・インク)
9:00 ‐9:40
⑨ハイフリンジ揺動型リアクターによる排水処理 佐分利 治 (日立プラント建設サービス㈱)
9:40 ‐10:10
休 憩 10:10‐10:30
⑩茶園地帯から流出する地下水の現状と濃縮・再利用の可能性 松尾 喜義 ((独)野菜茶業研究所)
10:30‐10:50
⑪食品工場排水のMBR処理 橋本 知孝 (旭化成ケミカルズ㈱) 10:50‐11:10
⑫セラミック膜の展開 小坂 慎一 (NGKフィルテック㈱) 11:10‐11:40
見学会
ブケ東海静岡出発 = 11:55 バス内で昼食
[A班]㈱大川原製作所;12:45~14:15 ⇒ はごろもフーズ㈱ 焼津工場;14:45~16:15
[B班]はごろもフーズ㈱ 焼津工場;13:15~14:45 ⇒ ㈱大川原製作所;15:15~16:45
第15回総会・15周年記念式典 および春季研究例会 参加者59名
日時:2003年6月6日(金) 12:30~19:00
場所:全林野会館大ホール
|
総会 (記念式典) |
12:30~13:00 |
|
|
研究例会 |
|
|
|
題 目 |
|
|
|
①より安全でおいしい水道水を目指して |
谷口 元 |
13:10~14:10 |
|
②膜技術を利用した浄水処理の特長と実用化例 |
村田 周和 |
14:10~14:55 |
|
休憩 |
14:55~15:15 |
|
|
③食品工場用水の製造とリサイクル技術 |
横田 潔 |
15:15~16:15 |
|
④膜技術27年 |
神武 正信 |
16:15~17:00 |
|
交 流 会 |
17:15~19:00 |
|
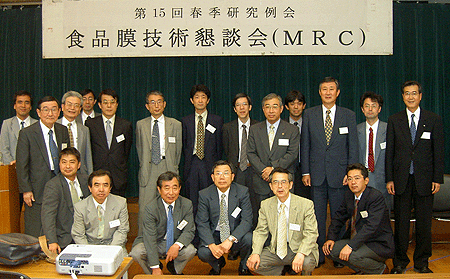
第14回秋季研究例会 参加者108名
2002年11月7日(木)~11月8日(金)、会場:新潟市 東映ホテル
協賛:新潟県食品産業協会・新潟県食品膜技術研究会、新潟県食品研究センター、(財)新潟県下水道公社、新潟大学大学院
<基礎講座>11月7日(木)
①食品膜技術の基礎と応用 佐藤 武 (味の素・発酵技術研究所)
②食品機械・膜装置のサニタリー性 大西 正俊 (森永乳業・装置開発研究)
<研究例会>11月7日(木)
①食品産業技術対策事業の方向 川口 尚 (農林水産省・技術室)
②膜技術による新食品の創造 原田 三郎 (NGKフィルテック)
③膜技術による新規製品の創造<乳業> 田村 吉隆 (森永乳業・栄養科学研究所)
④ナノ濾過による新しい食品素材の開発 早川 喜郎住村 克暢 (カゴメ・基礎研究所)(カゴメ)
⑤醤油生産量10%アップのための火入れ澱処理―攪拌翼型セラミック膜モジュールの効用―
井出 政義松下幸之助 (キノエネ醤油)(元新潟大学大学院)
⑥富山県における海洋深層水利用の現状 加藤 肇一 (富山県・食品研究所)
⑦1価イオン選択透過膜による海洋深層水脱塩 正司 信義 (旭硝子エンジニアリング)
⑧食品機械としての膜装置の洗浄と洗剤 田辺 忠裕 (エコラボ・ジャパン)
分科会
①膜技術の基礎と応用
②食品機械・膜装置の洗浄と洗剤(工場の洗浄含む)
③循環型社会と膜利用(排水処理と工場用水再利用を含む)
④新食品の創造と膜利用
11/8(金)
⑨おいしさの測定 筬島 豊 (九州女子大学・九大名誉教授)
⑩洗米排水の再生・リサイクル技術の開発 片岡 龍磨 (たいまつ食品)
⑪超極細繊維による醤油もろ味の圧搾濾過 安藤 秀喜 (山崎醸造・研究開発室)
⑫工場廃水・下水処理における膜技術利用 尾上 利次 (東レ・水処理技術開発センター)
<見学会>
① ㈱栗山米菓・中条工場
② ㈱日立産機システム・中条事業所(元日立製作所・中条工場)

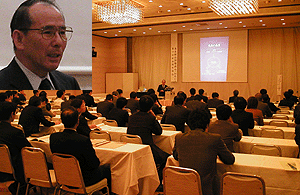


第14回 総会および 春季研究例会 参加者51名
日時:2002年6月7日(金) 12:40~19:15 場所:全林野会館
| 総会 | 12:40~13:00 | |
| 研究例会 | ||
| 題 目 | 講演者 | |
| ①新たな消費者・食品産業施策と (独)農林水産消費技術センターの役割 |
池戸 重信 (独立行政法人農林水産消費技術センター) |
13:10~14:10 |
| ②水のクラスター構造 ―基本的な考え方と応用の可能性― |
中林 孝和 (岡崎国立研究機構) |
14:10~15:10 |
| 休憩 | 15:10~15:30 | |
| ③膜による水とアルコールの分離 | 伊東 章 (新潟大学) |
15:30~16:15 |
| ④アミノ酸製造における膜利用 | 川喜田哲哉 (元 味の素㈱) |
16:15~17:00 |
| 交 流 会 | 17:15~19:15 | |
第13回秋季研究例会 2001年11月1日(木)~11月2日(金)、岡山国際交流センター2、 参加者110名
協賛:中国四国地域農林水産・食品先進技術研究協議会、岡山県食品新技術応用研究会、岡山県工業技術センター


第10回基礎講座 「膜技術の基礎と応用」
太田英明(中村学園大学)、田村真紀夫(オルガノ㈱)
研究例会
①膜を利用したカビの培養と機能解明
中西一弘(岡山大学)
②果汁分野における膜利用
首藤正彦(愛媛県農業協同組合連合会)
③PVAゲルと中空糸膜による余剰汚泥ゼロの排水処理システム
三浦 勤(㈱クラレ)
④ゴアテックス膜を用いた吟醸製麹システムの開発
狩山昌弘(㈱フジワラテクノアート)
⑤安全な食品を製造する工場の設計
山下義弘(日立プラント建設)
⑥無菌室メンテナンスの実例
佐久間欣也(日東アリマン㈱)
⑦アルミナ表面に吸着したタンパク質の脱着速度論
福崎智司(岡山県工業技術センター)
⑧膜処理用オンラインセンサーとタンクの内面洗浄
水島茂雄(化工機商事㈱)
⑨海洋深層水の食品利用の現状
久武陸夫(前高知県工業技術センター)
分科会
①膜技術の基礎と応用
②食品の安全管理と工場設計(膜装置の洗浄含む)
③水処理における膜利用(深層水、工場用水等を含む)
④メンブレンバイオリアクターの利用と問題点
⑩セラミック多孔膜の開発と応用
都留稔了(広島大学)
⑪熱再生式MF膜装置
西川克己(㈱ナムテック)
⑫わが社の膜-最新の逆浸透膜の開発状況-
玉井克彦(東レ㈱)
⑬わが社の膜-機能膜装置への電解凝集の適用-
続木 悟(㈱サンコー)
⑭わが社の膜-水処理用ハイフラックス酢酸セルロース膜-
中塚修志(ダイセル化学工業㈱)
⑮わが社の膜-電気透析による食品脱塩-
正司信義(旭硝子エンジニアリング㈱)
見学会
① ナイカイ塩業㈱
② ㈱クラレ岡山工場


第13回春季研究例会
2001年5月25日(金)13:10-19:30 :東京 全林野会館
記念講演
「膜技術研究30年を振り返って―食品産業と膜技術―」
大矢晴彦(横浜国立大学)
テーマ:食品の安全性と膜利用技術
基調講演
「食の安全性を考える―食品クレームの実状と対策―」
荒木恵美子 ((財)日本食品分析センター)
1)「無菌化濾過技術の現状と今後の課題」
渡辺敦夫(新潟大学大学院)
2)「膜装置の安全性―トマト濃縮用逆浸透装置の衛生管理を中心として―」
早川喜郎(㈱カゴメ)
第12回秋季研究例会 2000年10月 埼玉、大宮ソニックシティ 参加者113名
協賛:埼玉県工業技術センター、埼玉県食品工業協会、新潟県食品膜利用技術研究会
基礎講座:第9回「初・中級者のための基礎講座」
「膜分離技術の基礎と応用-クロスフロー膜のプロセス開発の進め方-」
原田三郎(NGKフィルテック㈱)
「膜プロセスの維持・管理について」
早川喜郎(カゴメ㈱)
①日高秀昌(常磐大学・短期大学部)
-機能性食品の発展と今後の展望- 1
②柚木 徹(日本ミリポア㈱)
-高性能膜による荷電を利用したタンパク相互の分離- 5
③青木宏光(三栄源エフエフアイ㈱)
-食用天然色素の膜精製法- 9
④北村英三(埼玉県工業技術センター)
-電気透析による塩蔵野菜漬液からの有用成分の回収- 15
⑤宮脇長人(東京大学大学院)
-凍結濃縮と膜分離- 19
⑥大西真人(日立プラント建設㈱)
-回転膜の実用化例~回転平膜モジュールの食品分野への適用~- 32
⑦杉戸善文(大日精化工業㈱)
-荷電モザイク膜の開発とその応用- 40
⑧山田康之(日本ポール㈱)
-振動式膜分離装置"ポールセップ"の特長と実用化例-
47
⑨遠藤 勲(理化学研究所)
-バイオセパレーションエンジニアリングと膜分離技術- 54
⑩佐藤康平(オルガノ㈱)
-疑似移動層式クロマト分離装置の食品製造への応用展開- 56
⑪宮城 淳(千葉県工業試験場)
-膜分離による廃棄食用油脂の再生- 64
⑫高橋秀和(東芝セラミックス㈱)
-MEMBRALOXセラミックフィルターによる除菌と清澄について 73
⑬渡辺敦夫(新潟大学大学院)
-新潟県食品膜利用技術研究会の現状と研究会の活動状況- 80
第12回春季研究例会 2000年6月 東京、全林野会館 参加者58名
①石黒幸雄(カゴメ㈱)
-産業界からみた「21世紀における膜技術研究」のあり方- 1
②栗原 優(東レ㈱)
-膜開発戦略- 5
③松井利郎(九州大学農学部)
-フィルムによる香気成分の吸着- 12
④中尾真一(東京大学大学院)
-21世紀の膜技術展望- 17
第11回秋季研究例会 1999年11月 鹿児島、城山会館 参加者103名
共催:鹿児島県農産物加工推進懇話会
協賛:(財)鹿児島県工業倶楽部、鹿児島県食品産業協議会、鹿児島県食品安全性問題研究会、宮崎県工業技術センター、熊本県技術振興協会、長崎県調味食品技術研究会
基礎講座:第8回「初・中級者のための基礎講座」
柚木 徹(日本ミリポア㈱)
-膜技術の基礎-
①川崎睦男(日東電工㈱)
-近年の膜分離技術の展望・実用化の現状と将来- 1
②藤井文夫(ハウステンボス技術センター㈱)
-テーマパーク「ハウステンボスにおける自然共生と膜利用技術」 10
③山田佑一(森永エンジニアリング㈱)
-メンブレンバイオリアクターによる食品工場の排水処理- 20
④山根信正(旭化成工業㈱)
-電気透析による漬け物、梅干しの加工廃水処理- 28
⑤西山昌慶(ザルトリウス㈱)
-HACCPにおける膜を利用した微生物試験- 34
⑥水迫邦男(㈱鹿農) 代理 原田三郎(NGKフィルテック㈱
-膜処理によるミネラル水製造とHACCPの実施例- 38
⑦坂本宏司(広島県立食品工業技術センター)
-果汁工業への膜利用/無機質膜によるカンキツ果汁の清澄化とフレーバーの回収-
42
⑧早川喜郎(カゴメ㈱)
-トマト加工品の膜濃縮における装置のメンテナンス- 50
⑨白井義人(九州工業大学)
-乳酸発酵を中心とする有機廃棄物ゼロエミッション構想- 59
⑩野田義治(福岡県醤油醸造協同組合)
-新しい醤油製造工程への総合的膜利用の実態- 69
⑪宮崎泰光(ダイセン・メンブレン・システムズ㈱)
-UF膜を用いた生酒の濾過- 81
第11回春季研究例会 1999年5月 東京、全林野会館 参加者67名
①山口猛央(東京大学大学院工学系研究科)
-機能性膜の最近の展開- 1
②蒲谷秀彦((財)水道技術研究センター)
-膜による浄水処理の最近の動向- 10
③高田式久(日本デルモンテ㈱)
-トマトの生理活性物質、リコピンの膜濃縮- 18
④中嶋光敏(農林水産省食品総合研究所)
-食用油脂加工への膜利用- 26
⑤木村幸敬(京都大学大学院農学研究科)
-小腸膜モデルによる食品機能の解析- 39
第10回秋季研究例会 1998年10月 新潟、東映ホテル 参加者131名
共催:新潟大学・新潟県食品研究センター・新潟県食品産業協会・新潟県食品膜技術研究会
基礎講座:第7回「初・中級者のための基礎講座」
初級編「膜技術とは何なの・何ができるの・何が実用化されているの」田村吉隆(森永乳業㈱)
中級編「醤油製造における膜技術利用の実際」田上秀男(ヒゲタ醤油㈱)
①中島忠夫(宮崎県工業試験場)-SPG膜技術の開発と地域産業の活性化-
1
②田中真人(新潟大学)-微粒子化技術の最近の進歩と膜乳化技術の特徴-
9
③小林哲男(神鋼パンテック㈱)-膜による清酒の製造- 15
④浅川友二(オルガノ㈱)-膜による食品加工用水の精製と再利用-
22
⑤ Ulrich Hoelzgen(ヘンケル・エコラボ㈱)-膜装置サニテーションの実際-
27
⑥福崎智司(岡山県工業技術センター)-表面汚れと易洗浄化の理論と実際-
48
⑦小久保謙一・渡辺敦夫(新潟大学大学院)-ナノ濾過膜の分離特性とその応用-
55
⑧道木泰徳(オリエンタル酵母工業㈱)-ナノ濾過膜による発酵ブロスの脱色-
62
⑨渡辺敦夫 総合質問 Hour(Q&A)
第10回春季研究例会 1998年5月 東京、健保会館 参加者89名
①薄葉 久(アサヒビール㈱)-アサヒスーパードライ物語- 1
②戸谷 亨(農水省食品流通局)-食品産業技術対策事業の概要- 3
③石関忠一(横浜国立大学)-食品・医薬品の微生物管理- 10
④冨田 守(森永乳業㈱)-膜技術と食品開発- 14
⑤中西祥晃(ダイセル化学工業㈱)-膜モジュールの開発動向- 21
第9回秋季研究例会 1998年11月 大阪国際交流センター 参加者123名
協賛:大阪工研協会・香川県食品試験場・(財)和歌山テクノ振興財団
基礎講座:第6回「食品膜技術の基礎と応用」
①木村尚史(大阪大学)-逆浸透法による水中の微量成分の除去- 1
②加藤滋雄(神戸大学)-高度分離における膜とクロマトグラフィ- 7
③小山 清(大阪市立工業研究所)-食品工業における膜利用- 15
④井村直人(味の素ゼネラルフーヅ㈱)-コーヒー濃縮への膜の利用- 26
⑤小川高史(旭化成工業㈱)-限外濾過による日本酒の精製- 32
⑥河田照雄(京都大学)-小腸での吸収機構と肥満のコントロール- 36
⑦松原保仁(香川県発酵食品試験場)
-逆浸透・ナノ濾過膜による大豆オリゴ糖の回収と浸透圧モデルによる透過流束の予測-
41
⑧高田一貴(神鋼パンテック㈱)-振動型膜分離装置の特長と適用例- 46
⑨伊関祐司(ダイセンメンブレンシステムズ㈱)-食品工業での膜処理水の利用-
56
⑩佐々木 武(日東電工㈱)-新しい低ファウリング性RO膜- 64
⑪馬場康夫(東レエンジニアリング㈱)-膜分離技術と食品- 71
第9回春季研究例会 1997年5月 つくば、工技院筑波研究センター共用講堂 参加者名175名
日本膜学会との共同開催
①渡辺敦夫(新潟大学大学院)-膜技術開発における産・官・学の特徴と役割-
1
②古川俊夫(キッコーマン㈱)-醸造業への膜分離技術の展開- 15
③鍋谷浩志(農水省食総研)-膜性能へのファウリング成分と浸透圧の影響-
25
④川崎睦男(日東電工㈱)-最適食品膜システム「最先端の超低圧RO膜とモジュールの現状-
29
⑤神武正信(山口県立大学)-膜装置の運転管理システム- 43
第8回秋季研究例会 1996年11月 横浜、ホリディ・イン横浜 参加者127名
基礎講座:第5回「食品膜技術の基礎と応用」
①大矢晴彦(横浜国立大学)-膜は何をしてきたか、これから何をするのか-
1
②冨田 守(森永乳業㈱)-乳業への膜利用- 12
③今野次雄(旭化成工業㈱)-食品用膜分離装置の設計と管理- 15
④角 博明(昭和化学工業㈱)-ケイソウ土濾過と今後の展開- 20
⑤柚木 徹(日本ミリポア㈱)-膜によるタンパク質相互の高度分離- 23
⑥松本幹治(横浜国立大学)-膜分離プロセスの運転管理- 26
⑦種谷新一(岩手大学)-食品加工の未来と膜の役割- 34
⑧伊藤新次(㈱加藤美蜂園本舗)-膜利用システムの実用化の秘訣- 42
⑨竹内正彦((社)長野県農村工業研究所)-逆浸透法によるリンゴ果汁の濃縮-
49
⑩奥沢洋平(埼玉県食品工業試験場)-発酵食品製造における膜利用について-
53
⑪赤松 卓(ライオン㈱)-パームカロチンマイクロカプセルの開発と特性-
58
第8回春季研究例会 1996年5月 東京、健保会館 参加者77名
①中尾真一(東京大学)-世界の最新膜事情と今後の膜研究開発の展開- 1
②柘植秀樹(慶応義塾大学)-晶析と膜分離- 5
③鈴木寛一(広島大学)-膜乳化技術と食品エマルションへの応用- 9
④河村和彦(三晃商会㈱)-膜販売商社から見た膜の発展- 15
第7回秋季研究例会 1995年11月 野田市、チサンホテル大利根 参加者139名
協賛:フードフォーラムつくば・(財)日本醤油研究所・東京都食品産業協議会
基礎講座:第4回「食品膜技術の基礎と応用」
①相島鐵郎(キッコーマン㈱)-食品分野におけるケモメトリックス手法の応用-
1
②斎藤恭一(千葉大学)-膜によるタンパク質の高度分離- 5
③太田英明(農水省中国農業試験場)-果汁産業における電気透析の応用- 10
④鍋谷浩志(農水省食総研)-膜による農産物の高付加価値化- 14
⑤吉川ユミ(横浜国立大学)-トレハロース分離・精製における膜利用- 20
⑥松尾育朗(旭化成工業㈱)-UF膜による食品工業原料水の精製- 23
⑦田辺忠裕(ヘンケル白水㈱)-食品産業で用いられる膜装置の洗浄と殺菌-
26
⑧溝口健作(工技院物質工学工業技術研究所)-膜技術開発の最先端- 35
⑨田上秀男(ヒゲタ醤油㈱)-セラミック膜による醤油火入れオリ処理- 39
⑩鈴木隆幸(千葉県工業試験場)-ルーズRO膜による醤油の淡色化- 44
⑪三枝弘育(東京都立食品技術センター)-膜による淡色ウスターソースの製造-
49
⑫野口勝弘(キリンビール㈱)-ポリスルホン膜周期逆洗システムのビール濾過への応用-
52
第7回春季研究例会 1995年5月 東京、健保会館 参加者76名
①木村尚史(大阪大学)-膜技術の歴史的推移と今後の研究開発のあり方- 1
②国眼孝雄(東京農工大学)-サイクロデキストリンと膜分離- 5
③都甲 潔(九州大学)-脂質膜を利用した味覚センサーの食品産業への利用-
13
④神武正信(雪印乳業㈱)-ナノフィルトレーションの食品製造への応用- 18
第6回秋季研究例会 1994年12月 名古屋、愛知厚生年金会館 参加者178名
共催:包装食品技術協会 協賛:(財)和歌山テクノ振興財団
基礎講座:第3回「食品膜技術の基礎と応用」
①戸田 清(東京大学)-ホローファイバー利用による酢酸発酵の効率化- 1
②菊池祐二(農水省食総研)-ミクロン細孔の微細加工と血液細胞等の通過の可視化-
5
③入谷英司(名古屋大学)-膜濾過における濾過ケークの役割- 10
④脇田昌宏(NGKフィルテック㈱)-食品分野におけるセラミック膜の応用-
13
⑤昆布 隆(カルピス食品工業㈱)-大豆オリゴ糖製造における膜利用の実際-
16
⑥久米仁司(協同乳業㈱)-ナノフィルトレーション膜の乳業への応用- 19
⑦小林 猛(名古屋大学)-微生物の培養と膜分離- 24
⑧松本 豊(静岡県工業技術センター)-膜型バイオリアクターによる酵素の生産-
27
⑨森嶋 朗(佐藤醸造㈱)-醤油の膜濾過の実際- 31
⑩中内道世(和歌山県工業技術センター)-電気透析によるしらす煮汁・梅干調味廃液からの有価成分の回収-
40
第6回春季研究例会 1994年5月 東京、健保会館 参加者94名
①都留稔了(東京大学)-膜機能の現状と展望- 1
②松本幹治(横浜国立大学)-ハイブリッド膜プロセスの現状と展望- 9
③古川俊夫(キッコーマン㈱)-食品工業における膜利用の現状と展望- 15
④浅野祐三(森永乳業㈱)-食品加工における膜乳化技術の現状と展望- 29
第5回秋季研究例会 1993年11月 仙台、第1、第2ワシントンホテル 参加者109名
共催:(財)東北産業技術開発協会・東北地区化学工学懇話会
協賛:宮城県食品工業協議会・あきた食品振興プラザ・岩手県食品加工研究会・福島県食品協議会
後援:宮城県高度技術振興財団
基礎講座:第2回「食品膜技術の基礎と応用」
①山内文男(東北大学)-蛋白分解バイオリアクタにおける膜利用- 40
②野村悟郎(昭和産業㈱)-大豆ホエーからのβ-アミラーゼの回収- 46
③大谷敏郎(農水省食総研)-ICOM’93報告
④柴田正人(愛知県食品工業技術センター)-醤油の濾過速度と珪藻土使用量との関係-
50
⑤山田康則(カゴメ㈱)-果汁工業における膜利用- 55
⑥Todd Nelson(Filtration Engineering Co., Inc. 米国)-Membrane Filtration
in the Dairy Industry-60
⑦大見忠弘(東北大学)-超LSI製造におけるウルトラクリーン技術と膜分離技術の役割-
73
⑧中嶋光敏(農水省食総研)-食品品質向上と膜利用技術- ビデオ鑑賞
⑨佐藤和久(東北大学)-バイオプロダクトからの脱塩- 78
⑩斉藤孔男(福島県会津若松工業試験場)-アルコール飲料と膜利用- 83
⑪半田敏久(㈱ハチテイ)-水産加工における膜利用- 91
⑫新井邦夫(東北大学)-分離技術と超臨界流体技術- 97
第5回春季研究例会 1993年5月 東京、日本工業倶楽部会館 参加者82名
①木村尚史(東京大学)-Progress of Membranes and Membrane Processes-
1
②渡辺敦夫(東陶機器㈱)-Membrane applications in Japanese food industry
21st Century:Role of Membrane Technology-- 6
③Prof. M.Cheryan(Univ. of Illinois 米国)-Corn Refining in USA in the
29
④Prof. P.Dejmek(Lund Univ. スウェーデン)-Food application of membrane technology
in Europe- 36
第4回秋季研究例会 1992年12月 九州厚生年金会館 参加者134名
共催:北九州市バイオインダストリー研究会・岡山県食品新技術応用研究会・熊本県工業技術振興会・鹿児島県食品技術研究会・宮崎県食品工業技術協会
後援:北九州市
基礎講座:第1回「膜利用技術の基礎と応用」
①藤尾雄策(九州大学)-膜利用技術と食品製造- ①1- 7
②鍋谷浩志(農水省食総研)-低阻止率逆浸透膜利用による高濃度濃縮とオリゴ糖類の分離-
②1-14
③中島忠夫(宮崎県工業試験場)-SPG膜の食品膜技術への応用- ③1- 3
④佐橋裕子(日東電工㈱)-膜技術を利用した高度不飽和脂肪酸の分離・精製-
④1- 4
⑤柚木 徹(日本ミリポアリミテッド㈱)-セラミック膜による大量濾過- ⑤1-
3
⑥山村弘之(東レ㈱)-食品分離用膜エレメントの紹介- ⑥1- 5
⑦中西志郎(オルガノ商事㈱)-アルコール飲料製造への膜利用- ⑦1- 4
⑧中西一弘(岡山大学)-微生物菌体培養液のクロスフロー濾過- ⑧1- 3
⑨湯之上雅子(熊本県工業技術センター)-甘夏果汁の膜による清澄化および脱酸-
⑨1- 4
⑩下薗かおり(鹿児島県農業試験場)-サツマイモアントシアニン色素の濃縮精製-
⑩1- 5
⑪農 新介(オーム乳業㈱)-限外濾過濃縮乳によるフレッシュチーズの製造と製品の性状
⑪1- 4
⑫伊関祐司(ダイセル化学工業㈱)-果汁工業への膜利用(和歌山県南海果工㈱における実施例を中心として)-
⑫1- 3
第4回春季研究例会 1992年6月 東京、日本工業倶楽部会館 参加者108名
①柳本正勝(農水省食総研)-食品産業の将来と研究組合活動- 1
②宮脇長人(東京大学)-膜分離技術の高度分離への応用- 12
③田村吉隆(森永乳業㈱)-牛乳成分の膜分画- 19
④神武正信(雪印乳業㈱)-牛乳類の限外濾過における透過流束低下について-
27
第3回秋季研究例会 1991年10月 札幌プリンスホテル 参加者148名
共催:(財)北海道銀行中小企業人材基金
①梅林寺良一(東レ㈱)-RO膜の技術発展の概要- ①1- 9
②久保田昇(旭化成工業㈱)-UF膜の現状と今後の展開- ②1- 4
③松尾 繁(富士写真フイルム㈱)-MF膜の現像と今後の動向- ③1-35
④清水康利(東陶機器㈱)-セラミック膜の現状と展望- ④1- 6
⑤T.アボット(米国農務省北部研究所)-New Crops and Membrane application-
⑤1- 8
⑥三上拓志(よつ葉乳業㈱)-乳加工における膜利用- ⑥1- 5
⑦宍戸賢一(サッポロビール㈱)-ビール製造における濾過技術- ⑦1- 4
⑧榎本雄三(ノボノルディスクバイオケミカルズ㈱)-工業用酵素の生産と膜利用- ⑧1- 3
第3回春季研究例会 1991年5月 東京、食糧会館 参加者146名
①伏島正健(日本ミリポアリミテッド㈱)-米国における膜利用技術の現状-
①1- 7
②大谷敏郎(農水省食総研)-ヨーロッパにおける膜利用技術- ②1- 5
③伊藤新次(㈱加藤美蜂園本舗)-ハチミツレモン製造における膜技術- ③1-14
第2回秋季研究例会 1990年11月 大阪リバーサイドホテル 参加者123名
①松本隆一(京都大学)-バイオプロダクトの膜分離- ①1- 6
②渡辺敦夫(農水省食総研)-逆浸透法による高濃度濃縮- ②1- 6
③長谷川宏(日本碍子㈱)-セラミックMF・UF膜の食品分野への応用- ③1-
5
④長谷川展裕(神鋼パンテック㈱)-生酒製造用限外濾過装置について- ④1-
4
⑤馬場 透(鹿児島県加工研センター)-鹿児島県における膜技術利用研究の現状-
⑤1- 2
⑥岩崎賢一(香川県食品試験場)-香川県における膜利用技術の現状- ⑥1- 4
⑦野口 誠(鳥取県食品加工研究所)-鳥取県における水産物を中心とした膜利用技術の現状について-
⑦1- 4
⑧太田義雄(広島県食品工業センター) ⑧1- 3
第2回春季研究例会 1990年5月 東京、機械振興会館 参加者144名
①中尾真一(東京大学)-逆浸透、限外濾過中間領域における技術開発の展望
①1- 9
②片岡二郎(味の素㈱)-低阻止率逆浸透膜による調味料の製造- ②1- 3
③大塚隆一(明治製菓㈱)・渡辺敦夫(農水省食総研)-フラクトオリゴ糖の高度分離-
③1- 4
④村上勝志(オリエンタル酵母㈱)-糖蜜を利用した発酵廃液の脱色- ④1- 3
第1回秋季研究例会 1989年11月 つくば、青木屋 参加者120名
①中嶋光敏(農水省食総研)-ヨーロッパにおけるメンブレンバイオリアクター開発の動向-
1
②山野 繁(東陶機器㈱)-セラミック膜の食品への応用- 16
③加藤保彦(ダイセル化学工業㈱)-UF中空糸膜による清澄果汁の製造- 19
④大矢晴彦(横浜国立大学)-限外濾過膜の評価法について- 23
⑤田村吉隆(森永乳業㈱)-乳業における膜利用の動向- 41
⑥田辺忠裕(ヘンケル白水㈱)-膜の洗浄- 52
⑦横山文郎(東レ㈱)-アミノ酸等のROによる分離濃縮- 59
⑧川崎睦男(日東電工㈱)-ルーズRO膜による調味液処理- 67
第1回春季研究例会 1989年6月 東京、竹橋会館 参加者130名
①木村尚史(東京大学)-膜技術の展望- 1
②佐田栄三(京都大学)-生物機能と膜分離操作- 3
③渡辺敦夫(農水省食総研)-食品開発における膜技術の魅力-「更に膜技術を発展させるためには」
12