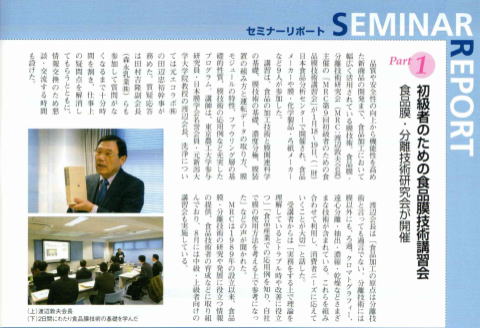|
第17回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
|
|
2024年8月7-8日
|
|
日 時
|
内 容
|
講 師
|
|
7日
水曜
|
10:00~11:15
75分
|
① イントロダクション
受講者自己紹介・講師自己紹介および総合学習(技術者・研究者のリーダーとしての心構え等)
② 食品加工技術と膜関連科学の基礎 ―逆浸透・真空・凍結濃縮、クロマ
ト、浸透圧、正浸透、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:15~11:20
|
休憩
|
|
11:20~12:10
50分
|
③ 食品産業における膜技術 - 膜利用と発展の歴史・ろ過-
|
|
12:10~13:10
|
昼食 ⑫ビデオ(対面受講者のみ)・(財)日本食品分析センター紹介と膜技術・分離技術
|
13:10~14:40
90分 |
④ 膜技術の基礎―膜の特性、モジュール構造とその特性―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、膜モジュールの構造と特性―
⑤ 濃度分極と膜ろ過法
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データーの取り方―線速・圧力・温度の影響、加圧ポンプ・配管材・圧力計・温度制御 ― |
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~17:00
40分
|
Q&Aアワー(MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います) |
| 17:00~18:50 |
情報交換・交流会(対面受講者のみ)
|
|
8日
木曜
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質――透過流束の低下と分離性能の変化、fouling(付着層の形成と目詰まり)とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束(critical
flux)、限界流束(limiting flux)
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食 ⑫ ビデオ
膜技術関連 等
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄と殺菌
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1)飲料工業への膜利用
(2)醸造工業への膜利用
(3)水産工業への膜利用
(4)食品分野以外への膜利用 |
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1)無菌化濾過による食品の製造
(2)ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
⑩ メンブレンバイオリアクター――遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備、
|
|
16:00~16:30
|
質問事項記入 & 質疑(質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
時間割&プログラム内容が多少変更になることがあります
|
|
渡辺敦夫:農学博士、MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕:MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
|
|
第16回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
|
|
2023年8月8日、9日
|
|
日 時
|
内 容
|
講 師
|
|
8月
8日
火曜
|
10:00~11:15
75分
|
① イントロダクション
受講者自己紹介・講師自己紹介および総合学習(技術者・研究者のリーダーとしての心構え等)
② 食品加工技術と膜関連科学の基礎 ―逆浸透・真空・凍結濃縮、クロマ
ト、浸透圧、正浸透、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:15~11:20
|
休憩
|
|
11:20~12:10
50分
|
③ 食品産業における膜技術 - 膜利用と発展の歴史・ろ過-
|
|
12:10~13:10
|
昼食 ⑫ビデオ(対面受講者のみ)・(財)日本食品分析センター紹介と膜技術・分離技術
|
13:10~14:40
90分 |
④ 膜技術の基礎―膜の特性、モジュール構造とその特性―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、膜モジュールの構造と特性―
⑤ 濃度分極と膜ろ過法
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データーの取り方―線速・圧力・温度の影響、加圧ポンプ・配管材・圧力計・温度制御 ― |
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~17:00
40分
|
Q&Aアワー(MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います) |
| 17:00~18:50 |
情報交換・交流会(対面受講者のみ)
|
|
8月
9日
水曜
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質――透過流束の低下と分離性能の変化、fouling(付着層の形成と目詰まり)とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束(critical
flux)、限界流束(limiting flux)
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食 ⑫ ビデオ
膜技術関連 等
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄と殺菌
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1)飲料工業への膜利用
(2)醸造工業への膜利用
(3)水産工業への膜利用
(4)食品分野以外への膜利用 |
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1)無菌化濾過による食品の製造
(2)ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
⑩ メンブレンバイオリアクター――遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備、
|
|
16:00~16:30
|
質問事項記入 & 質疑(質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
時間割&プログラム内容が多少変更になることがあります
|
|
渡辺敦夫:農学博士、MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕:MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
|
| 第15回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
2022年8月3日、4日
|
|
日 時
|
内 容
|
講 師
|
|
3日
水曜
|
10:00~11:15
75分
|
① イントロダクション
受講者自己紹介・講師自己紹介および総合学習(技術者・研究者のリーダーとしての心構え等)
② 食品加工技術と膜関連科学の基礎 ―逆浸透・真空・凍結濃縮、クロマト、浸透圧、正浸透、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:15~11:20
|
休憩
|
|
11:20~12:10
50分
|
③ 食品産業における膜技術 - 膜利用と発展の歴史・ろ過-
|
|
12:10~13:10
|
昼食 ⑫ビデオ・(財)日本食品分析センター紹介と膜技術・分離技術
|
|
13:10~14:40
90分
|
④ 膜技術の基礎 ― 膜の特性、モジュール構造とその特性―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、膜モジュールの構造と特性
―
⑤ 濃度分極と膜ろ過法
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データーの取り方 ― 線速・圧力・温度の影響、加圧ポンプ・配管材・圧力計・温度制御
―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~17:00
40分
|
Q&Aアワー(MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
|
情報交換・交流会(対面受講者)
|
|
4日
木曜
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―― 透過流束の低下と分離性能の変化、fouling(付着層の形成と目詰まり)とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束(critical flux)、限界流束(limiting flux)
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食 ⑫ ビデオ
膜技術関連 等
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄と殺菌
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例 ―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
⑨ 膜技術の応用例 ―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―― 遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備、
|
|
16:00~16:30
|
質問事項記入 &
質疑(質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
時間割&プログラム内容が多少変更になることがあります
|
|
渡辺敦夫:農学博士、MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕:MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
|
|
| |
第14回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
2021年8月4日、5日
|
日時
|
内容 |
講師
|
|
4日水曜
|
10:00~11:15
75分
|
① イントロダクション
受講者自己紹介・講師自己紹介および総合学習(技術者・研究者のリーダーとしての心構え等)
② 食品加工技術と膜関連科学の基礎 ―逆浸透・真空・凍結濃縮、クロマト、浸透圧、正浸透、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫 |
|
11:15~11:20
|
休憩
|
|
11:20~12:10
50分
|
③ 食品産業における膜技術-膜利用と発展の歴史・ろ過-
|
| 12:10~13:10 |
昼食 |
|
13:10~14:40
90分
|
④ 膜技術の基礎―膜の特性、モジュール構造とその特性―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、膜モジュールの構造と特性―
⑤ 濃度分極と膜ろ過法
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データーの取り方―線速・圧力・温度の影響、加圧ポンプ・配管材・圧力計・温度制御 ―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~17:00
40分
|
Q&Aアワー(MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
情報交換・交流会(肺炎ウイルス感染防止のため中止)
|
5日
木曜 |
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質――透過流束の低下と分離性能の変化、fouling(付着層の形成と目詰まり)とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束(critical
flux)、限界流束(limiting flux)
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食 ⑫ ビデオ 膜技術関連 等
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄と殺菌
(1)膜装置の洗浄の実際
(2)膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1)無菌化濾過による食品の製造
(2)ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1)飲料工業への膜利用
(2)醸造工業への膜利用
(3)水産工業への膜利用
(4)食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター――遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備、
|
|
16:00~16:30
|
質問事項記入 & 質疑(質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
プログラム内容が多少変更になることがあります |
| 渡辺敦夫: 農学博士、MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
講義時間は目安です。状況により長短が出ます
|
MRC第14回 初級者のための食品膜技術講習会(2021年)
アンケート集計 抜粋
|
|
参加者(8名・内回答者6名))美浜(株)佐藤食品工業(株)キッコーマン食品(株)(2名)森永乳業(株)(2名)スリーエムジャパンイノベーション(株) 三菱ケミカル(株)
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(5名)③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい
・初級者用の講習会でしたので、ちょうどよいレベル感で受講することが出来た・もう少し質問の時間が欲しかった・時間が伸びてもいいので、もう少し休憩を挟んで欲しかった
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う(4名) ②ある程度役に立つ(2名)
・膜ろ過装置の改造や洗浄性確認などで役に立つと考えている・濃度分極やcritical
fluxに関する話が、膜の基礎知識として勉強となった・洗浄に関する話は実製造の現場において役立つと考える・膜分離技術の基礎を習得できた・膜技術に関する知識の会得、フィルター等を売る側として食品系企業についての状況や製造方法、使用膜について知れた点・膜技術は食品で広く使われているのに対し研究者が少ないことから、より専門的知識を付けて企業の中でも優位に立つためにとても必要であると感じた
3.イントロ&受講者自己紹介は役に立ちましたか?
①役に立った(5名)
・自己紹介で受講者の人となりが知れて良かった(2名)・本講習会の目的の一つとして企業同士の意見交換があると思う
4.下記の講義内容は ①役に立った、②さらに詳しく知りたい、③わかり難かったに印をつけてください。④その他の意見の方は意見を記入ください。
① 講師紹介および国際情勢・その他 総合学習(我が国の置かれている国際情勢を踏まえ、技術者・研究者のリーダーとしての心構えを講義) (①役に立った(5名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見記入欄 ・渡辺先生の経歴が分かったので、その後講義を受ける上で理解がしやすかった・社会人や技術者としての心構えを教えていただけたのでその心構えをもって仕事をしていきたいと考える・他国の情勢や研究者としての心得について学べてよかった・技術者研究者のリーダーとしての心構えに関して納得するところ共感するところが多かった
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎(①に立った(5名)、②詳しく知りたい(1名))
意見記入欄 ・膜技術の基礎を知ることができたので初心者の私には非常に役に立った・どのような用途で膜が用いられてきたのかが分かり、大変興味深かった・膜関連技術及び浸透圧について深く学べてよかった・知識、原理→実例という流れが非常に分かりやすく、膜技術に疎い私自身でもよく理解できた・膜に関する基礎的な内容を学ぶことができた・浸透圧とモル濃度の関係から粉末化基材として使用するデキストリンもDEが低い方が効果的であると感じた
③膜技術と発展の歴史 (①役に立った(5名))
意見記入欄・一つ前の資料「②食品の加工技術と膜関連科学の基礎」と近い内容もあったため、「③膜技術と発展の歴史」と併せても良いかと思った・膜技術の歴史を通じて当初と現在における訴求性の違いについて学べてよかった・食品の製造方法などが多く載っており非常に参考になった・醤油や粉乳の製造工程など多くの場面で膜が使用されていることを学ぶことができた。
④製膜・膜材質・モジュール構造 (①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(1名))
意見記入欄 ・膜選定の基準ともなる話でしたので、機会がありましたら更に話を伺いたい・普段カートリッジフィルターを扱うことが多いためその他のフィルターや膜の構造特性を知ることができ参考になった・モジュールの構造について詳しく知らなかったためトラブルシューティングや効果的な利用の観点などからも非常に重要な講義であると感じた・カートリッジフィルターに関して興味が湧き詳しく知りたくなった・製造トラブルの中でも「菌数異常」のトラブルが多く発生しており、カートリッジフィルターの応用の中に耐熱性菌の除去と記載があり工程中(殺菌前など)に導入することができるのであれば、菌数トラブルを防ぐことができるのではないかと感じた
⑤濃度分極と膜濾過法 (①役に立った(4名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった(1名))
意見記入欄 ・濃度分極に関する基本的な考え方が分かり今後の業務で役立つと感じた・知識不足のため計算式については難しい点も多々あったので勉強致します・初心者の自分には少し難しく理解が不十分なところがあったので後でしっかり復習します・技術サービス業務が主であるため理論原理といった開発や研究者よりの知識を学ぶことができ非常に勉強になった・膜処理について感覚的に行っていたため定量的な視点が必要という点で非常に役に立った・今後は膜の内部の状態についても定量的に考えることで膜技術についてより深い知識を付けたい・計算式が多く講義の中で理解することが厳しかった・モジュール内の流れに関してはイメージすることができた。
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(1名))
意見記入欄 ・膜選定をする際はMRCニュースを参考にしようと思った・フラックスに影響を与えるファクターについても理解することができ、勉強になった・非常にわかりやすくためになったがもう少し詳しく知りたかった・膜と膜モジュールデータベースについてデーターが見やすく整理されておりとても参考になる・透過流束をCritical Flux以下で運用することの大切さを数値やグラフなどから可視化して学ぶことができたので良かった・膜の寿命が短く洗浄剤の検討を実施しいるので、RO膜の洗浄に効果的な温度、洗浄剤、洗浄方法を詳しく知りたいと考えた
⑦ファウリング層の基礎的性質 (①役に立った(6名)、)
意見記入欄 ・ファウリングの基本的性質から膜機能の低下の要因までわかりやすく説明していただいてとても参考になった・理論部分の理解としてかなり役立った・内容が多く深いためより詳細に伺いたいと思った・先生のお話自体は非常に分かり易かった・ファウリングの問題が実際に膜ろ過装置で起こっているので、現象を理解する上で非常に参考になった・特に溶質と膜のファウリングに関係する相互作用が参考になった・膜やフィルター選定の際に役立ちそうだと感じた・RO膜の寿命を改善するのにやみくもに洗浄剤や運転方法を変えるのではなく、何が理由でファウリングが形成されているのかを把握してから検討することが大事だと感じた・現場を見て改善策を考え実行していきたいと思う
⑧応用例―その1-(①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(1名))
意見記入欄 ・乳製品だけでなく醤油、清酒、ジュースなど様々な分野に膜が利用されていることがわかってよかった・個人的には生ビールや日本酒の生酒における膜利用が興味深く大変面白かった・それぞれの食品や飲料への応用例がまとまっていて分かりやすかった・フィルター事業部ですので、それぞれ深堀りして勉強していきたいと思う・RO膜の洗浄でスポンジボールは使用していないと思うので一度試してみたいと感じた
⑨応用例―その2―(①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(1名))
意見記入欄 ・えぐみに関する硝酸イオンや塩化物イオンを取り除く際に等モル透過で陽イオンも抜けてしまうが、陽イオンを維持したまま硝酸イオンや塩化物イオンを取り除く方法があるのか詳しく知りたいと思った・牛乳に関する膜処理技術について詳細に教えていただけたので有難かった・無菌化ろ過について非常に興味があったのでとても参考になった・膜には多くの使用用途があり応用例があることを知ることができた・水と微生物のみ除去できる膜があればいいなと思った・RO膜は水のみ透過するため処理液中にいた微生物は濃縮される方向にいくためRO膜での菌増殖も問題になっている
⑩膜リアクター (①役に立った(6名)、)
意見記入欄 ・メンブレンバイオリアクターは物質の生成から排水処理の分解まで様々な用途で用いられていることがわかってよかった・浄化設備で膜リアクターを使用しているという話を伺ったことがあり、実際の原理部分を学ぶことができ良かった・膜リアクターに関してはほとんど初見でしたので知見が広がった・製造で使用できなくなった膜を再利用したり汚泥層に膜を使用することはすごく効率が良いことと感じた・当社は昔ながらの会社で昔ながらの製法で製造しているため改善できる点が多くあると改めて感じた
⑪膜の洗浄 (①役に立った(4名)、②詳しく知りたい(2名))
意見記入欄 ・実際に工場での洗浄方法に関する基礎が理解出来たため大変有意義でした・ファウリングが目詰まり由来か付着層由来かによって洗浄方法が異なるのかが気になった・膜やろ過装置の洗浄に苦労しているので非常に役に立った・学んだ内容を活かしていきたいと考える・膜の洗浄に関してはよく弊社のお客様からも聞かれる点ですので、知識が得られかつ整理できて非常にためになった・膜の寿命を延ばすために非常にためになった・洗浄における重要な要素や洗剤の用途、各膜および溶液に対する適切な洗浄の手順など今後の役に立つ情報が得られてとてもよかった
5.その他希望する講義内容 ・製品の製造中にファウリングが起きFluxが低下した際に行える改善策(製造中なのでNaOHやHCl等は不可として)はどのようなものがあるか具体的に聞きたい・洗浄や洗剤に関して詳しくまた運転データーの取り方などについて詳しく聞きたい・食品や飲料のラインについて仕込み水からチェック段階までの全体の膜やフィルター選択や各役割について聞きたい・RO膜のみに特化した講義もあるとそれに特化して把握することができるかなと思った・今回のように総合的な膜の講義はあらたな視点を増やすことができるのでこれも重要だと感じた・膜の内部の輸送現象についても詳しくお聞きしたい
6.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか ・膜技術の基礎、濃度分極、膜の洗浄・膜に関する基礎知識、基礎原理、及び実際に扱う上での注意すべき点について理解が深まった・洗浄、装置の組み方と運転データーの取り方・応用例と洗浄について非常に参考になった・特に洗浄は実液の中身に依存するところが多く学ぶのに苦労していたが今回の講義でキーポイントを学べたのでとても参考になった・応用例に関しても通常コンフィデンシャルな部分が多いので各社さんがどのような技術や膜を使用しているのか知ることができ勉強になった・講義内容すべてが新鮮でとても役に立ったが特に講師紹介および国際情勢、製膜・膜材質・モジュール構造、濃度分極と膜濾過法、装置の組み方と運転データーの取り方、ファウリング層の基礎的性質、膜の洗浄などが非常に役に立ちました(2名)。
7.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか ・膜技術の基礎・膜の洗浄・今後弊社で導入する際の膜の選定や導入後のより効率的な洗浄方法のために役立てたいと考える・気体の分離や溶解技術など・膜分離(RO)、濾過、遠心分離、濃縮、乾燥技術、クロマトグラフィーについて学びたい
8.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
・この度は二日間貴重なお話をしていただきありがとうございました。今回はコロナウイルス感染予防対策ということもあり対面で御講義を受講することは叶いませんでしたが、今後対面で受講する機会がいただければ、膜を利用することの重要性を体感するために日本酒の飲み比べなども行ってみたいと感じました。・講義内容や時間配分ともに非常に良かったです・日本最高の膜技術・知識を持つ先生方の講義や質疑応答を受講でき、大変参考になりました。・
膜分離技術に関して幅広く知ることができて良かった・
食品業界を中心に膜分離技術の利用状況などについて知ることができて勉強になった・この度はこのような貴重な機会を頂戴し、ありがとうございました。今回学んだ内容を忘れないように今後膜・分離技術とかかわっていきたいと思います。また購入させていただいたテキストに関しましても、1冊で網羅的にまとまっているテキストを今まで見つけられておりませんでしたので、辞書のように活用していきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします・コロナでオンラインでの受講となってしまった点のみが悔やまれます。先生方や他企業様と対面で交流ができれば、更に面白い話を伺うことができたかと思います。私の知識が無いこともありますが、もう少し基礎的な部分から話を聞きたかった・二日間のご講義ありがとうございます。貴重な情報が多かっただけに、終わってみると二日間という期間はあまりに短く、今後も機会がございましたら、是非先生方の講義を受講させていただきたいと感じました。今回ご講義頂いた情報をベースに、食品膜技術の教科書を読み、膜に関する理解を深めていきます。今後とも引き続きよろしくお願い致します・講義資料が詳細まで書かれておりわかりやすかったです。ただ少し文字数が多いところがあり、少ない方が見やすいかなと感じました。今回の講義に参加させて頂き、膜技術を利用しているのは食品分野だけでないこと、食品でも多くの分野や製品に利用されていることを知ることができました。まだまだ、理解が及ばない部分はありますが、見て、考えて、聞いてを繰り返すことで理解を深めていきたいと思っております。
|
| |
第13回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
2020年8月27日28日
| 日時 |
内容 |
講師 |
| 27日 |
10:00~11:15
75分 |
イントロダクションと受講者自己紹介
① 講師自己紹介および総合学習(技術者・研究者のリーダーとしての心構え等)
② 食品加工技術と膜関連科学の基礎 ―逆浸透・真空・凍結濃縮、クロマト、浸透圧、正浸透、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出― |
渡辺敦夫 |
| 11:15~11:20 |
休憩 |
11:20~12:10
50分 |
③ 食品産業における膜技術ー膜利用と発展の歴史・ろ過ー |
| 12:10~13:10 |
昼食 ⑫ビデオ・(財)日本食品分析センター紹介と膜技術・分離技術 |
13:10~14:40
90分 |
④ 膜技術の基礎―膜の特性、モジュール構造とその特性―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、膜モジュールの構造と特性―
⑤ 濃度分極と膜ろ過法 |
| 14:40~15:00 |
休憩 |
15:00~16:10
70分 |
⑥ 膜装置の組み方と運転データーの取り方―線速・圧力・温度の影響、加圧ポンプ・配管材・圧力計・温度制御 ― |
| 16:10~16:20 |
質問事項記入 |
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー(MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。質問がなくなるまで質疑を行います) |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(感染防止の観点からどうするか現在検討中です。交流会は受講者間の意見交換ができたと評判が良いので何とか開催する予定です) |
| 28日 |
10:00~12:00
120分 |
⑦ ファウリング層の基礎的性質――透過流束の低下と分離性能の変化、fouling(付着層の形成と目詰まり)とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束(critical flux)、限界流束(limiting flux) |
渡辺敦夫 |
| 12:00~13:00 |
昼食 ⑫ ビデオ 等 |
13:00~14:00
60分 |
⑪膜モジュールの洗浄と殺菌
(1)膜装置の洗浄の実際
(2)膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕 |
14:00~15:00
60分 |
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1)無菌化濾過による食品の製造
(2)ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造 |
渡辺敦夫 |
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1)飲料工業への膜利用
(2)醸造工業への膜利用
(3)水産工業への膜利用
(4)食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター――遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備、 |
| 16:00~16:30 |
質問事項記入 & 質疑(質問がなくなるまで質疑を行います) |
プログラム内容が多少変更になることがあります
渡辺敦夫:農学博士、MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕:MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
第12回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
2020年1月8日、9日
| 日時 |
内容 |
講師 |
| 8日 |
10:00~11:15
75分 |
イントロダクションと受講者自己紹介
① 講師自己紹介および総合学習(技術者・研究者のリーダーとしての心構え等)
② 食品加工技術と膜関連科学の基礎 ―逆浸透・真空・凍結濃縮、クロマト、浸透圧、正浸透、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出― |
渡辺敦夫 |
| 11:15~11:20 |
休憩 |
11:20~12:10
50分 |
③ 食品産業における膜技術ー膜利用と発展の歴史・ろ過ー |
| 12:10~13:10 |
昼食 ⑫ビデオ・(財)日本食品分析センター紹介と膜技術・分離技術 |
13:10~14:40
90分 |
④ 膜技術の基礎―膜の特性、モジュール構造とその特性―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、膜モジュールの構造と特性―
⑤ 濃度分極と膜ろ過法 |
| 14:40~15:00 |
休憩 |
15:00~16:10
70分 |
⑥ 膜装置の組み方と運転データーの取り方―線速・圧力・温度の影響、加圧ポンプ・配管材・圧力計・温度制御 ― |
| 16:10~16:20 |
質問事項記入 |
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー(MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。質問がなくなるまで質疑を行います) |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(MRC役員が出席され豊富な情報が得られます) |
| 9日 |
10:00~12:00
120分 |
⑦ ファウリング層の基礎的性質――透過流束の低下と分離性能の変化、fouling(付着層の形成と目詰まり)とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束(critical flux)、限界流束(limiting flux) |
渡辺敦夫 |
| 12:00~13:00 |
昼食 ⑫ ビデオ 等 |
13:00~14:00
60分 |
⑪膜モジュールの洗浄と殺菌
(1)膜装置の洗浄の実際
(2)膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕 |
14:00~15:00
60分 |
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1)無菌化濾過による食品の製造
(2)ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造 |
渡辺敦夫 |
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1)飲料工業への膜利用
(2)醸造工業への膜利用
(3)水産工業への膜利用
(4)食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター――遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備、 |
| 16:00~16:30 |
質問事項記入 & 質疑(質問がなくなるまで質疑を行います) |
MRC12回 初級者のための食品膜講習会( 2 0 2 0年)アンケート集計抜粋
受講者合計15名:
キッコーマン食品(2名)・カゴメ(1名)・不二製油・秋田屋本店(2名)・岩井ファルマテック・江崎グリコ(2名)・ミッカン・エ学院大学・明治(2名)・三菱ケミカルアクア・ソリューション・新田ゼラチン(アンケート回収数15)
1. 本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
①丸2日間では長すぎる(1名) ②ちょうど良い時間構成であった(14名)
一日あたりの時間もちょうど良かったです。
同じような内容もあったのでもう少し整理する必要があるのではないか。1日では短すぎるので2日でちょうど良いと思います。初級も中級も一緒にやって貰えると遠くからの旅費が助かる。
2. 本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
意見記入欄①たいへん役に立つと思う(13名) ②ある程度役に立つ(2名)
膜をこれから使おうとしている人間にとって利用例や基本的注意点が役に立った。自社で学ばない知識、曖昧な点を解決することができた。他企業の話が聞けた。実際の事例を入れてかつ基礎的な話も入れて頂きわかりやすかったです。膜技術の基礎を習得できた-ことで今後膜の選定から試験、考察までのステップに役立つと思う。食品産業における膜技術の全体像を勉強できました。業務を行う上で基礎知識として役立つ。基礎知識がなかったので参考になりました。アイデアの参考になった。原料の加工法を検討する上で、選択肢が増えた。濃縮を考える上で考慮する点の参考になった。クロマトによる分離をメインでやってきたのでその前工程の膜分離を理解できたのは役にたつ。膜のファウリングの詳細、データ,図、写真について解説していただき理解が進んだ。業界標準を知ることができ自社の今後の研究方向(新規加工法など)を考える参考になった。膜を使用する検討においてその評価の仕方などに役立つ。膜の使用法、洗浄法などの見直し役に立つ。 膜技術の基本を知ることができ実際に利用する場合の対応が容易になった。
3. イントロ&受講者自己紹介は役に立ちましたか? ①役に立った(15名)
意見記入欄 お互いを知れることでその後の交流に役立った(4名)。もう少し短い時間でやれるのではないか。
4. 交流会は役に立ちましたか? ①役に立った (15名)
意見記入欄 膜ユーザーがどんな用途に膜を使っているのか意見を聞け、膜を使用する側と開発側の意見交換は役に立った。お互いの繋がりに役立ち今後の仕事に役立つ。今後の検討のヒントを得られギブアンドテイクができると良いと思う。
5. 下記の講義内容は
①講師紹介および国勢情勢・その他 総合学習(我が国の置かれている国勢情勢を踏まえ、技術者・研究者のリーダーとしての心構えを講義) ①役に立った(12名) ②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった(1名)
意見記人欄 もう少し詳しく知りたかった。膜だけでなく日々の健康面での大切さを教えて頂き今後改善していきたいと思う。講師紹介に関するもので面白かった。研究者として考えを聞けたのは貴重であった。
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎 ①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(3名)、
意見記入欄 食品分野で利用される分離技術全体が分かり比較になるので勉強になりました。例が多くわかりやすかった。デキストランや糖類を膜で処理するので阻止率に注意しながら行いたい。
③膜技術と発展の歴史 ①役に立った(13名)、②詳しく知りたい(2名)、
意見記入欄 トマトジュースを例に話していただけたので分かりやすかった。濾過助剤と膜との関わりをもっと知りたい。
④膜の特性とモジュール構造 ①役に立った(14名)、②詳しく知りたい(1名)、
意見記入欄 メーカー商談で知識が点として理解されていたものが線に繋がった。今まではっきりしなかったモジュールの構造がよくわかった。セラック膜の構造・製造法がイメージできわかり易かった。
⑤濃度分極と濾過法 ①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった(1名)
意見記入欄 運転条件により濃度分極が変化するので運転時に気をつけたい。ろ過中の物質移動について理解が深まった。
⑥装置の組み方と運転データの取り方 ①役に立った(13名)、②詳しく知りたい(2名)
意見記入欄 限界透過流束を把握して取り組みたい。
⑦ファウリング層の基礎的性質 ①役に立った(13名)、②詳しく知りたい(1名)、
意見記入欄 排水処理のグループでMBRを扱っているのでファウリングと言う言葉について注意していきたい。自己阻止型ダイナミック膜の話が興味深かった。もっと詳しく教えてほしい。
⑧応用例―その1- ①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(2名)、
意見記人欄 実際吏用例を聞けて良かった(4名)。出羽桜は講習会の前に聞いていたので良かった。応用例は会社として関わっていることが多く参考になった。各製品の背景、使用している原理を知ることが出来興味深かった。
⑨応用例―その2- ①役に立った(11名)、②詳しく知りたい(3名)、
意見記入欄
⑩膜リアクター ①役に立った(11名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった(1名)
意見記入欄 MBRは会社として扱っており食品業界に広めていきたい。
⑪膜の洗浄・殺菌 ①役に立った(13名)、②詳しく知りたい(2名)、
意見記人欄 洗浄、殺菌については水処理で現場に行くと聞かれることがあり勉強出来よかった。洗浄剤についての知識が役に立つ。膜装置以外の洗浄にも役に立つと思う。
⑫昼食時のビテオ上映 (①役に立った(12名)、②役に立たなかった(話をしていて聞いていなかった3名、)
受講者と話をしており、聞いていなかった(3名)。講義中に教材として上映していただけると集中してみることが出来ると思います。
⑬その他希望する講義内容
意見記人欄 洗浄法とそのメリットとテメリット。食品以外での例について聞いて見たい。パイボーラー膜、ゼオライト膜等、新規の技術についても聞いてみたい。膜の選定法や材質の特徴をもっと詳しく教えてほしかった。用語でわからないものがあったので解説表があれば有り難い。
6. 今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
意見記人欄 ファウリング層の基礎的性質(5名)。洗浄に関する基礎知識(4名)。ファウリングが生じる原因、その防止法など基本を理論的に学び参考になった。食品の加工技術と膜関連科学の基礎。膜技術と発展の歴史。装置の組み方と運転データの取り方。応用例。運転データの取り方は実際にも役立と感じた(2名)。膜の構造について説明してもらい理解が深まった。洗浄に関する薬剤、酸アルカリの作用が理解できた。ファウリングについて様々な例に合わせて解説していただき大変勉強になりました。
7.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
意見記人欄 最新の濃縮技術(3名)。育児用粉乳の製造プロセス。乾燥技術(膜―クロマト―乾燥)。凍結濃縮などの新技術。晶析。超臨界流体抽出。
8.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
意見記人欄 受講者同士の交流ができ今後のビジネスに繋げられる(6名)。こまめに休憩を入れていただいたので最後まで集中して受講できた。スラ
イドにない情報(他社の取り組みや歴史など)を合間にお話いただき興味探かった。普段自分が関わっている業界以外の情報について生の情報が得られたのが大変役立った。もう少し簡単な内容が良い。化学工学的な知識が全くない人にもわかるように。実際の使用例について『なぜ膜を選んだか』についても聞いてみたかった。実際の製造ラインを見て勉強してみたい。内容ごとにデータ、資料、写真が多く具体的に理解ができた。1時間ごとに休憩がほしい。60~90分で休憩がほしい。交流会で他社の苦労がわかり良かった。用語でわからない言葉があったので解説が
あると有り難いです。食品産業における膜の利用や問題点について詳細に説明していただき勉強になりました(2名)。膜技術の基礎を知ることができ非常に有益な講習を有り難うございました。講義内容について行けない部分があり基礎学力不足を感じた。
|
|
MRC第19回食品膜技術講習会 in Tokyo 2023プログラム
|
日時
|
内容
|
講師
|
テキスト頁
|
|
1/11
水
|
10:00~12:00
120分
|
① 膜技術および関連技術の総合学習
1.講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2.分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(SDGs対応技術含む)と将来展望
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員)
|
テキスト
および
教材
|
|
12:00~12:50
|
昼 食(膜関連ビデオ放映)
|
|
12:50~14:15
85分
|
② 膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO, NF, UF, MF,の原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ――
|
工学博士 田村 吉隆
(元森永乳業研究所長)
(MRC名誉副会長)
|
P.17~83
|
|
14:15~14:25
|
休 憩
|
|
14:25~15:35
70分
|
③ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜・無機膜の特性
2. 各種膜モジュールの特性
3. 電気透析(ED)の原理と特徴
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
|
P.103~172
p.173~204
|
|
15:35~15:45
|
休 憩
|
|
15:45~16:45
60分
|
④ 膜プロセス開発の進め方
1 RO・NF膜プロセスの開発
2 UF・MF膜プロセスの開発
3 運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化
|
博士(工学) 越智 浩
(森永乳業(株)
研究本部 素材応用研究所)
|
p.205~242
P.260~282
|
|
16:45~17:00
|
☆Q&Aアワー MRC役員参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します)
|
司会 渡辺
|
|
|
17:10~18:55
|
情報交換交流会(汚染状況が改善すれば参加費3000円(別途徴収)で開催するかも知れません)
|
|
1/12
木
|
9:30~10:50
80分
|
⑤ 膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.ファウリング層の基礎的性質
2.NF利用による食品製造と利用の注意点
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
|
P.245~259
|
|
10:50~11:00
|
休 憩
|
|
11:00~12:10
70分
|
⑥ 膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例
|
田辺忠裕
(シラサギ・サニテーションラボ)
(MRC幹事)
|
P.283~293
P.294~311
P.312~325
|
|
12:00~12:50
|
昼 食(膜関連ビデオ放映)
|
|
13:10~14:10
60分
|
⑦ 乳業における膜利用
1.牛乳の特性と膜分離
2.RO:粉乳製造工程での予備濃縮、RO透過液等の再利用
3.NF:ホエイの脱塩濃縮
4.UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5.MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離
|
市場 幹彦
((㈱)明治イノベーションセンター )
|
P.349~374
|
|
14:10~14:20
|
休 憩
|
|
14:20~16:10
110分
|
⑧ 電気透析の特徴と応用例
1.電気透析膜の特徴
2.電気透析の食品加工への利用(醸造・乳業・製糖・漬物・梅干し)
⑨ 食品加工への膜利用
1.飲料工業への膜利用
2.醸造工業への膜利用
3.水産工業への膜利用 その他
⑩ メンブレンバイオリアクター
1.食品製造への利用
2.排水処理への利用
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
|
P.144~149
P.229~241
P.513~532
P.381~442
P.443~507
P.535~559
|
|
16:10~16:30
|
①Q&Aアワー and 総合討論
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します)
|
司会 渡辺
|
|
|
講師の都合および感染状況によりオンライン講義になることがあります。各項目の時間配分は状況により変化することがあります。
|
|
|
第18回M R C 食品膜・分離技術研究会技術講習会 in Tokyo 2022 プログラム
|
|
日時
|
内容
|
講師
|
テキスト頁
|
|
1/12
水
|
10:00~12:00
120分
|
① 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3. 膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員)
|
テキスト
および
教材
|
|
12:00~12:50
|
昼 食(膜関連ビデオ放映)
|
|
12:50~14:15
85分
|
② 膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO,NF,UF,MF,の原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ――
|
工学博士 田村 吉隆
(MRC名誉副会長)
|
P.17~83
|
|
14:15~14:25
|
休 憩
|
|
14:25~15:35
70分
|
③ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜・無機膜の特性
2. 各種膜モジュールの特性
3. 電気透析(ED)の原理と特徴
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
|
P.103~172
p.173~204
|
|
15:35~15:45
|
休 憩
|
|
15:45~16:45
60分
|
④ 膜プロセス開発の進め方
1. RO・NF膜プロセスの開発
2. UF・MF膜プロセスの開発
3. 運転モードとその特性
4. 運転条件の設定と最適化
|
工学博士 伊東 章
(東京工業大学名誉教授)
(MRC顧問)
|
p.205~242
P.260~282
|
|
16:45~17:00
|
☆Q&Aアワー MRC役員参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します)
|
司会 渡辺
|
|
|
17:10~18:55
|
情報交換交流会(中止の予定・汚染状況が良ければ開催するかも知れません)
|
|
1/13
木
|
9:30~10:50
80分
|
⑤ 膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3. ファウリング層の基礎的性質
4. NF利用による食品製造と利用の注意点
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
|
P.245~259
|
|
10:50~11:00
|
休 憩
|
|
11:00~12:10
70分
|
⑥ 膜の洗浄とメンテナンス
1. 膜装置の日常管理とメンテナンス
2. 膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3. 洗浄剤と膜洗浄の実施例
|
田辺忠裕
(シラサギ・サニテーションラボ)
(MRC幹事)
|
P.283~293
P.294~311
P.312~325
|
|
13:10~14:10
60分
|
⑦ 乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:粉乳製造工程での予備濃縮、RO透過液等の再利用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離
|
市場 幹彦
((㈱)明治 )
|
P.349~374
|
|
14:10~14:20
|
休 憩
|
|
14:20~16:10
110分
|
⑧ 電気透析の特徴と応用例
1. 電気透析膜の特徴
2. 電気透析の食品加工への利用(醸造・乳業・製糖・漬物・梅干し)
⑨ 食品加工への膜利用
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター
1. 排水処理への利用
2. 食品製造への利用
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
|
P.144~149
P.229~241
P.513~532
P.381~442
P.443~507
P.535~559
|
|
16:10~16:30
|
①Q&Aアワー and 総合討論
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します)
|
司会 渡辺
|
|
|
MRC第18回食品膜技術講習会 in Tokyo 2022 アンケート結果 抜粋
参加企業: 三菱ケミカルアクアソリューション(株)、オルガノ株)内外化学製品(株)、(株)秋田屋本店、東レ(株)、カゴメ(株)東洋紡(株)佐藤食品工業(株)、(参加企業8社・回答7名)
下記の質問に当てはまる項目の番号を丸○で囲んでください。
1.この講習会を何で知りましたか?
① MRCからの電子メール ②上司から指示された(5名) ③インターネットのHPで(1名) ④その他(1名)
2.オンラインでの講習会の問題点(出来れば改良方法も)・良かった点を教えて下さい。
①問題点:ネット環境が原因だと思いますが、一部、音声が聞き取り難かったり、途切れたりしました。環境が改善すれば問題無いかと思います。接続不良や声が伝えづらい場面もあったため、受講者側でも対策できることをシミュレーションしておきたい。映像や音声が途切れ、主催者側のネット環境が悪いと感じました。
会場側の質疑応答では、マイクの近くにいる人の声音しか聞こえていません。マイクの数が足りていないのか、単純にOFFのまま発言しているのかわかりませんが、会場全体の音声が拾えるように対応をお願いいたします。声が聞こえなくなったりノイズがひどくなったりしたので、回線を強化するなどで対応してはどうか。
②良かった点:オンラインだったことで、休憩時間に業務対応が出来たので非常に助かりました。特に2日間となると判定業務等、実施できることで参加しやすくなります。 遠方からでもしっかりした講習を受講できる点はとても有難く感じた。対面受講とほぼ遜色なく感じました。 通信環境について、より高速・高容量のルーターをご用意いただく。移動せずに済むため参加のハードルは大きく下がったと感じた。オンラインなので、移動に時間がとられず、参加しやすかったです。コロナ禍や遠方などの理由により、オンラインでなければ参加できなかったかもしれない方が参加できるようになった点。
3.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
① 丸2日間では長すぎる(1名) ②ちょうど良い時間構成であった(6名)
意見を記入ください 膜技術の概論中心に、膜理論のすべてが詰まった濃密な2日間だと感じました。膜メーカーからの参加者にとっては、初日はかなり基本的な内容でした。初日だけや2日目だけの参加も可能にすれば、参加者が増える可能性もあるように感じました。日程を1日にしていただくと、もっと参加しやすいです。
4.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
①たいへん役に立つと思う(5名) ②ある程度役に立つ(2名) ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
4-1 どういう点で役に立つと思いますか? 膜技術の原理や特徴などが理解できたので、使用時の注意点、トラブル発生時の原因究明等に非常に役立つと思いました。膜メーカーではあるが、食品分野への参入ができておらず、食品で必要とされること、注意すべき点などが非常によくわかりました。 当社ではRO膜を中心に使用しておりますが、他の膜を併用する技術は個人的に参考になりました。 他の分野での利用方法を知ることができたため。教科書「食品膜技術 膜技術利用の手引き」を講習参加前から持っておりましたが、今回の講義で読むポイントや内容の理解が深まったと感じます。業務上NF膜の使用が主となるため、膜の特性について知らなかったことを学べたことは非常に有効。ファウリングや食品利用など知識が足りていない部分が良く分かった。
5.下記の講義内容は①役に立った、②さらに詳しく知りたい、③わかり難かった。④その他の意見の方は意見を記入ください。
①膜技術および関連技術の総合学習 渡辺(①役に立った(6名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった(1名)
意見記入欄 概論や渡辺先生の経歴だけでなく技術者としての心構えを教えて頂き、導入としてとても良かった。技術者として社会人として国際社会で仕事をしていく上で役に立った。参加された他社の方の自己紹介があり知り合いになれて良かった。この内容で2時間以上は、時間のかけすぎではないでしょうか。
②膜技術の基礎Ⅰ 田村(①役に立った(4名)、②詳しく知りたい(2名)、わかり難かった(1名)
意見記入欄 私の勉強不足に尽きます。膜運転の応答を数式で表現できると感じ驚いた。本講義内容に膜理論の全てが詰まっていると想像した。 式の導出は、初見では、ついていくのが難しかったです。
③膜技術の基礎Ⅱ 渡辺(①役に立った(6名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
意見記入欄 膜選定にあたり、スペックは意識しても材質を意識したことが無かったので、とても参考になった。
④膜プロセス開発の進め方 伊東(①役に立った(4名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった)
意見記入欄 実践的な内容であり、とても参考になった。 開発の進め方は分かりましたが、式の導出が難しかったです。
⑤膜技術の基礎Ⅲ Fouling NF 渡辺(①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
意見記入欄 ⑤膜技術の基礎Ⅲ Fouling NF 渡辺(①役に立った(4名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった)
意見記入欄 膜装置設計とその低下要因についてはしっかりと頭に叩き込んでおき、実践していきたい。
⑥膜の洗浄とメンテナンス 田邊(①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
意見記入欄 膜モジュールの設置洗浄に対して実践的であった。今後新規にモジュール導入する機会があれば本講義をバイブルとしたい。後半で紹介していた文献データについて、もう少しお話をお聴きしたかったです。
⑦乳業における膜利用 市場(①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
意見記入欄 各品目に対してどのような膜を使用しているか、また膜を使用して何が作れるかつまびらかにされており、単純に面白かった。 詳しく紹介していただき、わかりやすかったです。
⑧電気透析の特徴と応用 渡辺 ①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
意見記入欄 梅干し調味液からの脱塩は興味深く、実際どのような風味のものが出来上がるのか興味深かった。他にも応用できるか気になった。
⑨食品加工への膜利用 渡辺(①役に立った(6名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
意見記入欄 膜技術は様々な食品分野で利用されているという文言をまさに実感できる内容であった。必要に応じて各々深堀していきたい。過去の技術を紹介されている場面が何度かありましたが、同時に、最新技術も教えていただけると幸いです。
⑩メンブレンバイオリアクター 渡辺(①役に立った(6名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
意見記入欄 食品製造以外の活用事例を知ることが出来て有益であった。これからの時代の考え方にも即していると感じた。かけあしで説明された印象です。
◎今後受講したい膜技術関連の講義内容 本当に初心者なので、何が必要かもはっきりとは見えていないため、先生方のこれは知っていた方が良いと思われることは、全てお聞きしたいと思います。今後も引き続き膜技術講習会を実施して頂けたらと思います。一般的な膜技術(水処理などで実績のある技術)を食品プロセスに適用する場合のステップ(必要な予備試験、認証など)、膜運転で生じやすいトラブルとその解決方法(トラブルシューティング実例)、膜の洗浄法に関して、詳しく聞きたいです。
6.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
膜技術の総論、高分子膜・無機膜の特性、ファウリング層の基礎的性質、膜の洗浄とメンテナンス「食品加工への膜利用」と「膜の洗浄とメンテナンス」 ファウリング理論の基礎、膜の洗浄およびモジュールの理想的な組み立て、 ファウリング全般、ナノろ過、膜の洗浄とメンテナンス
膜の洗浄とメンテナンス,乳業における膜利用 基礎データ取得後の実際の設備設計の流れについて、詳しく聞きたいです(ワンパスorフィードアンドブリードなどの構成の選定)。 膜理論式に関する解説、膜の洗浄に関する思想、食品業界での応用例
7.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
濃縮技術(3名) 今回は情報収集のため、参加させていただきました。弊社は食品業界ではないため、希望する分野はありませんが、興味のある分野の際は、また参加させていただきたいと思います。
8.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
講演者の方々の説明が、細かいところまで丁寧にお話頂き、とても理解しやすかったです。初心者のため、説明を受けても分からない部分もありましたが、そこは自分で勉強した上で、再度受講したいと感じました。残念だったのは時間が無く、省略されたスライドが有りましたが、直接、演者の方のお言葉でお聞きしたかったです。私が初心者過ぎたため、理解できなかった部分もありますが、本当に丁寧な講義で楽しかったです。今後も是非、続けて頂けたらと思います。この度は有難う御座いました。食品膜利用に精通した方々とつながりを持つことができました。講師の方々は皆フレンドリーで会話しやすい雰囲気があり、良かったです。 テキストを含め、膜技術に関してこれ以上の内容のものは無いのでは?と感じるほどの濃密な講義でした。それだけに渡辺先生のおっしゃった、講義はあくまで「教科書の読み方が分かるようになるもの」という言葉が響きました。計算式構築しかりトラブル対応しかり、基本はやはり運転データの積み上げと解釈なのだと改めて感じました。しっかり意識していきたいです。講義ごとに質問時間を設けたほうが、その講義に対しての質問が出やすいかと感じました(時間管理が難しくなるのだとは思いますが。)各講義の後にも、質疑応答の時間が欲しいと思いました。不明点を解決できないまま、次の講習に入っていくので、頭の整理が追い付かない場面がありました。 時間が限られている中での講習で、たびたび講義内容が被っているのが気になりました。同じ内容を分けて説明されるのは、聞きにくいです。
|
|
MRC 第17回食品膜技術講習会 in Tokyo 2021 プログラム
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
1
月
13日
(水) |
10:00~12:00
120分 |
①膜技術および関連技術の総合学習
1.講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2.分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員) |
テキストおよび教材 |
12:00~
12:50 |
昼 食(膜関連ビデオ放映) |
12:50~14:15
85分 |
②膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.膜技術の総論
(1)クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2)RO,NF,UF,MF,の原理と特徴2.膜技術の基礎的理論――逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過―― |
工学博士田村吉隆
(食品膜・分離技術研究会)
(MRC名誉副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:15~14:25 |
休 憩 |
14:25~15:35
70分 |
③膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.高分子膜・無機膜の特性
2.各種膜モジュールの特性 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.103~163
p.173~201 |
| 15:35~15:45 |
休 憩 |
15:45~16:45
60分 |
④膜プロセス開発の進め方
1 UF・MF膜プロセスの開発
2 RO・NF膜プロセスの開発
3 運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化 |
工学博士伊東章
(東京工業大学名誉教授)
(MRC顧問) |
p.205~241 |
| P.260~277 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&AアワーMRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
1
月
14日
(木) |
9:30~10:50
80分 |
⑤膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3.ファウリング層の基礎的性質
4.NF利用による食品製造と利用の注意点 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.245~259 |
| 10:50~11:00 |
休 憩 |
11:00~12:10
70分 |
⑥食品加工への膜利用
1.飲料工業への膜利用
2.醸造工業への膜利用
3.水産工業への膜利用
⑦メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.381~442
P.443~507 |
| P.535~559 |
| 12:10~13:00 |
昼 食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:30
90分 |
⑧電気透析の原理と応用例
1.電気透析膜の構造と特徴
2.電気透析の理論
3.運転条件の設定と最適化
4.電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
⑨乳業における膜利用
1.牛乳の特性と膜分離
2.RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3.NF:ホエイの脱塩濃縮
4.UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5.MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
伊藤光太郎
(雪印メグミルク(㈱) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:30~14:50 |
休 憩 |
14:50~16:10
80分 |
⑩膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギ・サニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
①Q&Aアワーand 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
MRC第17回食品膜技術講習会 in Tokyo 2021 アンケート(抜粋) 講習会参加者12名 回答者(9名)
|
|
1.
|
この講習会を何で知りましたか?
|
|
①
|
MRCからの電子メール(1名) ②上司から指示された(4名) ③インターネットのHPで(4名)
|
|
2.
|
オンラインでの講習会の問題点(出来れば改良方法も)・良かった点を教えて下さい。
|
|
①
|
問題点 通信容量の制限により一部音声がとぎれとぎれであった。内容上は特にございませんが、やり方が普段と異なっているので段取りがうまくいかなかった点があったかと思われます。こちら側のスピーカーの問題かもしれませんが、質疑の際に音声が聞こえにくい場合がありました。 1日目に音声が途切れ、映像が止まっているところがあり分かりにくい位箇所があった。スライドを読むだけ、用意した原稿を読むだけの講義は内容が理解しづらいと感じた。経験談等を織り交ぜて話していただくととても分かりやすいと思った。
|
|
②
|
良かった点 社内から参加できるため、気軽に参加しやすかった。食品に膜を使用する技術は、はじめてでしたが、海淡用の膜との違いなどにも触れながらの説明でしたので混同することもなく非常にわかりやすかったです。出張が不要で参加しやすくなった。オンライン講義とはいえ、十数人の参加者であると各々が話し易かったり、挨拶する時間もあるので良かったかと思います。また、質疑応答の時間も十分に設けられていたので良かったです。それぞれのテーマの講義は1~2時間程度であったのでちょうどよかった。
|
|
3.
|
本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
|
|
①
|
丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(8名) ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい(1名)
|
|
難しい部分も多くあったためこの程度の時間は必要かと思われます。これ以上長くなると、だれてしまうかと思われるためこの程度がちょうどよいかと思われます。
|
|
4.
|
本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
|
|
①
|
たいへん役に立つと思う(5名) ②ある程度役に立つ(4名)
|
|
4-1
|
どういう点で役に立つと思いますか? 食品膜の開発を進めるにあたり、どのような需要があり、解決すべき課題を知ることができた。弊社では海淡などは行っていますが、食品はこれまで取り扱ってきていませんでしたので、範囲の拡大に非常に勉強になりました。膜分離の基礎から応用まで広く学ぶことができ、基礎知識を習得することができた。
|
|
5.
|
下記の講義内容は
|
|
①
|
膜技術および関連技術の総合学習 渡辺(①役に立った(9名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 実例のなどを踏まえて説明されていたためわかりやすく勉強になりました 膜技術の歴史を知れてよかった。
|
|
②
|
膜技術の基礎Ⅰ 田村(①役に立った(2名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった(5名))
|
|
意見記入欄 非常にためにはなったのですが、難解だった部分が多くありもう少し聞きたかったと感じました 音声が途切れ途切れになっていた上、どんどん進めてしまっていたため、理解が追い付かなかった。
|
|
③
|
膜技術の基礎Ⅱ 渡辺(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 弊社ではあまり使うことがない膜などの勉強になりました 有機膜の基礎を知れてよかった。
|
|
④
|
膜プロセス開発の進め方 伊東(①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 テスト方法などの点はあまり詳しくなかったので非常に勉強になりました
|
|
⑤
|
膜技術の基礎Ⅲ Fouling NF 渡辺(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 弊社の海淡だとファウリングは炭酸カルシウムが中心のため、食品だとどういうものが発生するかがわかった。トマトジュースや卵白アルブミンなど普段扱わない液体のファウリング傾向を知れて勉強になった。
|
|
⑥
|
食品加工への膜利用ⅠⅡ 渡辺(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 実例や、どういった理由から膜が用いられる課などがわかり勉強になった。急ぎ足での説明だったので、後ほど復習します。膜技術の基礎、食品への膜利用、乳業における膜利用(類似業種の動向は気になる)
|
|
⑦
|
メンブレンバイオリアクター 渡辺(①役に立った(6名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 排水処理以外のMBRは知らなかったため非常に参考になった 実例を含んだ内容で参考になった。
|
|
⑧
|
電気透析の原理と応用 伊藤(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 電気透析膜の構造、原理などが非常にわかりやすかったと思う ホエイの各脱塩技術を知れて参考になった。
|
|
⑨
|
乳業における膜利用 伊藤(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 乳業というくくりの中でも多くの膜がそれぞれどういった役割で使われているのかがわかり勉強になった 膜種ごとに実例を含んだ内容で勉強になった。
|
|
⑩
|
膜の洗浄とメンテナンス 田邊(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
|
|
意見記入欄 食品でのファウリング除去の部分が非常に参考になった。普段使用しない洗浄剤について勉強になった。
|
|
今後受講したい膜技術関連の講義内容
|
|
膜運用の実例や失敗例、膜メンテナンスなどについてもっと聞きたい 実運転における最適な運転条件の選定方法、膜モジュール・膜装置設計方法、正浸透膜について 個人的にはユーザーでの膜の使用方法等について詳しく聞きたい。乾燥技術。
|
|
6.
|
今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
|
|
各膜の適用分野や、課題を知ることができた点。膜洗浄とメンテナンス、 食品での運用を弊社ではしたことがほぼないため、どういったファウリングが発生するか、どういった対応をとらなければならないかなどが勉強になった。 Fouling。膜の洗浄とメンテナンス(2名)。 乳業における膜利用。 UF膜・MF膜プロセス開発。
|
|
7.
|
食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
|
|
濃縮技術全般。 膜、蒸発や凍結などの注意点や実例や注意点などが学べる機会があればよいと感じました。 食品業界での膜利用プロセスの課題と膜モジュールの開発方針。膜分離と競合する他の分離技術との比較。遠心分離。乾燥技術。膜分離技術。濃縮技術。ナノバブル。
|
|
8.
|
本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
|
|
オンラインなので仕方がないのですが、他の業界の方とお話ができればよかったと思いました。 膜技術の理論から実際の現場での応用まで幅広く知ることができ有意義でした。自身の仕事にどう生かせるか考えていきたいと思います。途中小さなトラブルはあったが、全体的にはスムーズな進行だったと思いました。食品メーカーの方と実際にお話し、どのような分離技術が求められているか直接意見をお聞きしたかったです。 講義内容は大変有意義であったが、話が脱線してしまい、時間が無くなるということがあった。 Web開催で仕方がないが、どういう方が出席されているかがわからなくて残念でした。(会社名はわかるが部者や年齢等がわからなかった)。講習会の開催ありがとうございました。難しい内容でしたが大変勉強になりました。また、他社の受講者と講師の先生方の質疑応答もとても参考になりました。
|
第16回MRC 食品膜技術講習会 in Tokyo 2019 プログラム
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
| 8月7日水 |
10:00~12:00
120分 |
①膜技術および関連技術の総合学習
1.講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2.分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員) |
テキストおよび教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
12:50~14:15
85分 |
②膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.膜技術の総論
(1)クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2)RO,NF,UF,MF,の原理と特徴2.膜技術の基礎的理論――逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過―― |
工学博士田村吉隆
(食品膜・分離技術研究会)
(MRC名誉副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:15~14:25 |
休憩 |
14:25~15:35
70分 |
③膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.高分子膜・無機膜の特性
2.各種膜モジュールの特性 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.103~163
p.173~201 |
| 15:35~15:45 |
休憩 |
15:45~16:45
60分 |
④膜プロセス開発の進め方
1UF・MF膜プロセスの開発
2RO・NF膜プロセスの開発
3運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化 |
工学博士伊東章
(東京工業大学名誉教授)
(MRC顧問) |
p.205~241 |
| P.260~277 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&AアワーMRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会渡辺 |
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
| 8月8日木 |
9:30~10:50
80分 |
⑤膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3.ファウリング層の基礎的性質
4.NF利用による食品製造と利用の注意点 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.245~259 |
| 10:50~11:00 |
休憩 |
11:00~12:10
70分 |
⑥食品加工への膜利用
1.飲料工業への膜利用
2.醸造工業への膜利用
3.水産工業への膜利用
⑦メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.381~442
P.443~507 |
| P.535~559 |
| 12:10~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:30
90分 |
⑧電気透析の原理と応用例
1.電気透析膜の構造と特徴
2.電気透析の理論
3.運転条件の設定と最適化
4.電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
⑨乳業における膜利用
1.牛乳の特性と膜分離
2.RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3.NF:ホエイの脱塩濃縮
4.UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5.MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
柴真由美
(雪印メグミルク(㈱) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:30~14:50 |
休憩 |
14:50~16:10
80分 |
⑩膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギ・サニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
①Q&Aアワーand 総合討論 |
司会渡辺 |
各項目の時間配分は状況により変化することがあります。
|
MRC第16回食品膜技術講習会 in Tokyo 2019 アンケート結果(抜粋)
参加企業(18名):キッコーマン食品(株)(2名) 旭化成(株) 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)(2名) (株)日本触媒 グリコ栄養食品(株)岩井ファルマテック(株) エコラボ(合) 佐藤食品(株)(2名) AGCエンジニアリング(株)(2名) (株)ロキテクノ(株) 秋田屋本店(2名) 岩井機械工業(株) NGKフィルテック(株)
1.この講習会を何で知りましたか?
① MRCからの電子メール4名 ②上司から指示された9名 ③インターネットのHPで4名 ④その他1名
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった17名 ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
①たいへん役に立つと思う 9名 ②ある程度役に立つ 8名 ③余り役立たない 1名(電気透析の話を聞きたかった)
意見 膜技術の全体像を勉強できた。 今後の基礎研究に役立つ。新事業テーマの提案。コスト面や洗浄方法、作業工程の見直しなどいろいろと検討できた。まだ膜について勉強が足らないと感じたのでもっと勉強したい。中級向けということであったので内容を理解できるか不安であったが、初級者にもわかりやすいように概況から応用までを理論を介して説明して頂けた。膜システムの添加剤開発においては、分離テスト方法や理論式などは性能評価に役立ちます。
4.下記の講義内容は如何でしたか?
①膜技術および関連技術の総合学習 (①役に立った(16名) ②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
意見 膜だけでなく分離技術全般の話が聞けて良かった。今回参加者の人なりが分かり良かったです。自己紹介(参加者相互が知り合える)があって良かった(4名)。実験のコツ、論文のポイントなどもっと詳しく知りたかった。日本人は完ぺきを求めすぎて効率を損なうきらいがあるとの話が心に残った。膜技術の使われ方の概略が理解できた。研究の進め方など参考になった。
②膜技術の基礎Ⅰ(①に立った(11名)、②詳しく知りたい(4名)、③わかり難かった(3名)
意見 乳業における膜利用について勉強になった。濃度分極については自分の知識不足で理解できなかった。自分のレベルが低いため理解できない部分が多かった。原理まで理解するには必要な内容と思いますが、仕事の範囲では直接必要ない内容かもしれない。式を覚えて研究に役立てたいと思った。自分でも手を動かし数式を理解して見ようと思った。温度が高ければFluxが高くなると思っていたがfoulingにより低くなることがあるとのことで参考になった。Critical fluxがあることを初めて知った。膜を使う覚悟ができた。計算でfluxを推定できることを知った。 数式が多かったがテキストに書いてあったのであとでゆっくり復習したい。自分の計算能力がないので理解できなかった。
③膜技術の基礎Ⅱ (①役に立った(14名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった(1名)
意見 膜技術の特徴、膜の素材について基礎知識が身についた。膜の分類、開発過程が分かりやすかった。RO膜以外の知識が弱かったため他の膜の知識がついたことは良かった。先生の実際の体験をもとに話をして貰えたので大変役に立った。膜技術発達の歴史が良く分かった。
④膜プロセス開発の進め方 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(4名)、③わかり難かった(4名)
意見 実用的な話が多く役に立った。複数のRO膜の組み合わせ運転について考えてみたい。現在平膜テスト機を導入し、実用化しようと考えてているので参考になった。実際の取り組み方法が分かり興味深かった。透過流束など理論的内容が理解できなかった。基礎知識が足りず分かりにくかったです。試験の進め方が分かり良かったので後輩にも受講させたいと思った。
⑤膜技術の基礎Ⅲ Fouling NF (①役に立った(14名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった(1名)
意見 透過流束の低下要因の解析方法が良く分かった。Foulingの挙動の概要を理解することができた(3名)。膜装置の運転方法ではfoulingを理解することが必要であることが分かった。流れ方向(軸方向)にfoulingが変化することが理解できた。
⑥食品加工への膜利用Ⅰ.Ⅱ (①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった(2名)
意見 キャロットジュースなど実例を挙げて説明して貰えて分かりやすかった。幅広い応用分野が理解できた(4名)。
⑦メンブレンバイオリアクター (①役に立った(11名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった(1名)
意見 MBRの実際例を勉強できた(4名)。MBRの問題点も話してもらえると良い。醸造への利用例があったら教えて欲しい。
⑧電気透析の原理と応用 柴(①役に立った(15名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった)
意見 電気透析の基礎を理解することができた(3名)。丁寧な説明で分かりやすかった(2名)。具体的運転条件(膜面積・流量・温度など)についても教えてもらえると有り難い。
⑨乳業における膜利用 (①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(5名)、③わかり難かった)
意見 RO~MFまで乳業で幅広く利用されている膜技術の実際例が分かった(4名)。膜技術の幅広い応用例が考えられる。日常的に膜技術を利用してきたが、専門的に取り組んで来ておらず、内容を社内で幅広く共有したいと思った。大変興味深く聴講できた。各膜の実用例を一つ一つ説明して頂き参考になりました。
⑩膜の洗浄とメンテナンス (①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(4名)、③わかり難かった)
意見 問題のあった実機での事例があったら教えて欲しかった。洗浄について考慮しなければならない点を全体的に教えてもらい参考になった(3名)。具体的にイメージしやすく分かりやすかった。社内では違う成分を処理しても同じ洗剤を使っていたが、再検討して見たい。
⑪昼食時のビデオ上映(①役に立った(13名)、②役に立たなかった(1名)、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい(2名)
意見 何か流れていると見てしまうので良いことだと思います。
◎
今後受講したい膜技術関連の講義内容(例えば;プロセス設計を詳しく聞きたい)
実技を含めた膜テストの方法に関する講義があると良い。洗浄・メンテナンスを詳しく講義して欲しい。イオン交換膜。膜技術の基礎の講義を受けたい。膜を利用の実例とその課題。正浸透について詳しく聞きたい。ビールの濃縮などで実用化されているようなのでこれから普及するのではないでしょうか。膜テスト機を保有する実験室で運転方法などを学べたら役立つと思います。応用例をもっと知りたい。膜洗浄のエンジニアリング。NF膜の利用例と注意点を深く学びたい。プロセス設計とスケールアップ。
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか?
fouling について(6名)。膜の洗浄・メンテナンス(5名)。基礎的なプロセス設計を進めるため田村先生と伊東先生の講義をベースにデータを取り研究を進めたいと思った。洗浄についてさらに検討を進めようと考えた。ダイナミック効果関連事項が興味深かった。濃度分極式の意味が理解できたこと。
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか?
清澄技術。分離精製技術。イオン交換膜技術。濃縮技術(3名)。乾燥。MFを利用した除菌技術。アミノ酸類の分離。
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
自己紹介や交流会があり、いろいろな人と知り合いに慣れ良かった(5名)。横のつながりができ、今回も仲間ができました。目からうろこで、イオン交換の分離より膜分離の方が興味深い。濃度分極式など単位を入れてもらえるとわかりやすい。先生方が実例や苦労されたことを交えながら説明頂き理解しやすかった。2日間で膜技術を網羅的に学べるのは良かった。普段関わることの無い業界の方と意見交換ができ良かった。膜の挙動や洗浄方法を学べてよかった。食品という変動要因が大きい物質を扱うにもかかわらず、理論がしっかりしていることに驚いた。
8.PDFでのテキスト配布いかがでしたか?
①紙で配布してもらいたい ②PDFは効率的で良かった(12名) ③その他( )
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月8日
(水) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員)
|
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO, NF ,UF, MF, EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村 吉隆
(食品膜・分離技術研究会)
(MRC名誉副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休 憩 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.103~143
p.173~201 |
| 15:35~15:45 |
休 憩 |
15:45~16:45
60分 |
◎膜プロセス開発の進め方
1. UF・MF膜プロセスの開発
2 .RO・NF膜プロセスの開発
3.運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化
|
工学博士 伊東 章
(東京工業大学名誉教授)
(MRC顧問) |
P.205~241
P.260~277 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月9日
(木) |
9:30~10:50
80分 |
◎膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3.ファウリング層の基礎的性質
4.NF利用による食品製造と利用の注意点 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.245~259 |
| 10:50~11:00 |
休 憩 |
11:00~12:10
70分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員) |
P.381~442
P.443~507
P.535~559 |
| 12:10~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:30
90分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
河邉 唯明
(雪印メグミルク(㈱)) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:30~14:50 |
休 憩 |
14:50~16:10
80分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギ・サニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
講師は変更になる可能性があります
|
MRC第15回食品膜技術講習会 in Tokyo 2018 アンケート結果抜粋
1.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う8名 ②ある程度役に立つ5名 ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
①膜を使用する上で起こった問題や現象を理論として理解するのに役立つ(2名)
②膜の選定と実運用・今後膜を扱うとき理論的に扱うことができる
③膜の洗浄法や運転条件の改善につなげられる
④社内でデーターを取り改善していく
⑤情報が非常に多くすべてを理解できなかったが、さらに社内で勉強して共有したい
⑥運転条件の適正化、洗剤の選定などで役に立つ
⑦現象を理論的に理解するのに役に立つ
⑧現在し使用しているUF膜の問題点を見つけ出すことができた
⑨食品加工工場での実際の沪過工程について知ることができ沪過のコンセプト作りに役立つ
2.下記の講義内容の評価
①膜技術および関連技術の総合学習 渡辺(①役に立った(10名) ②詳しく知りたい(2名)
②膜技術の基礎Ⅰ 田村(①に立った(7名)②詳しく知りたい(4名)わかり難かった(2名)
③膜技術の基礎Ⅱ 渡辺(①役に立った(11名)②詳しく知りたい(2名)
④膜プロセス開発の進め方 伊東(①役に立った(8名)②詳しく知りたい(3名)③わかり難かった(2名)
⑤膜技術の基礎Ⅲ Fouling NF 渡辺(①役に立った(11名)②詳しく知りたい(2名)
⑥食品加工への膜利用 渡辺(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(4名))
⑦メンブレンバイオリアクター 渡辺(①役に立った(8名)②詳しく知りたい(3名)③わかり難かった(1名)
①排水処理でも多くの問題あるのでさらに勉強したい
⑧電気透析の原理と応用例 川邉(①役に立った(9名)②詳しく知りたい(3名)
⑨乳業における膜利用 川邉(①役に立った(11名)②詳しく知りたい(2名)
①膜を選べばいろいろな成分を分離できることがわかった
⑩膜の洗浄とメンテナンス 田邊(①役に立った(10名)②詳しく知りたい(1名)
①洗浄については課題が多いのでまずは問題点を整理してみたい②膜の洗浄に時間が大切であるが、長ければ良いというものではなく、洗浄液の交換も必要③
⑪昼食時のビデオ上映(①役に立った(10名)②役に立たなかった(1名)③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい(1名)見てなかった
3.今後受講したい膜技術関連の講義内容
①プロセス設計関係
②現場で作業している者にも膜の基礎を理解させられるような講習を受けさせたい
③MF関連の詳しい話を聞きたい
④理論式を用いた例題
⑤エンジニアリングに重点を置いた講義
⑥今後の膜技術の利用
⑦新しい膜の紹介
4.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
①膜の洗浄とメンテナンス(2名)
②ファウリング③膜技術基礎Ⅱ
③膜プロセス開発(2名)
④同じ溶液でも運転初期と中期・終期ではファウリング状況が変わることが分かった
⑤膜技術の基礎Ⅰ
⑥基礎膜技術Ⅲ
5.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
①沪過
②UF膜の運転条件設定と最適化について掘り下げた講習(2名)
③濃縮技術④噴霧乾燥⑤除菌技術
6.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
①受講者同士の交流ができ良かった(4名)
②他業界での膜利用状況が分かり良かった(2名)
③いろいろな業種の方と知り合えた
④膜関係以外の話、異業種の話が聞けて知識を広めることができた
⑤全体的に難しかった
⑥生産に関連する問題点や課題を例にした話があればもっと良い
⑦講師がいろいろな業種の人で良かった
⑧営業の方が講習を受けており感心した
7.PDFでのテキスト配布いかがでしたか?
①紙で配布してもらったが文字が小さく読みづらいところがあった
②PDFは効率的で良かった(7名)
③パソコンを用意しPDFで配布して貰った方が効率的と思った
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月2日
(水) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員)
|
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO, NF ,UF, MF, EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村 吉隆
(食品膜・分離技術研究会)
(MRC名誉副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休 憩 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(元・新潟大学大学院 教授) |
P.103~143
p.173~201 |
| 15:35~15:45 |
休 憩 |
15:45~16:45
60分 |
◎膜プロセス開発の進め方
1. UF・MF膜プロセスの開発
2 .RO・NF膜プロセスの開発
3.運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化
|
横山 文郎
(筑波大学客員共同研究員)
(MRC名誉会員) |
P.205~241
P.260~277 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月3日
(木) |
9:30~10:50
80分 |
◎膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3.ファウリング層の基礎的性質
4.NF利用による食品製造と利用の注意点 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(元・農水省食総研研究室長) |
P.245~259 |
| 10:50~11:00 |
休 憩 |
11:00~12:10
70分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~442
P.443~507
P.535~559 |
| 12:10~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:30
90分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
河邉 唯明
(雪印メグミルク(㈱)) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:30~14:50 |
休 憩 |
14:50~16:10
80分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
| |
|
MRC第14回食品膜技術講習会 in Tokyo 2017 アンケート結果(2017年8月2日3日)
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(7名)
意見 ①先生の楽しいお話を聞きながら緊張することなく講義を聞くことができました②顧客からの膜利用について問い合わせに答えることができるようになった ③工場での運転や膜の洗浄・メンテナンスなど実用に役立つ知識を得ることができた④食品業界の膜利用に関する具体的な利用法・条件等の生情報を得られたので満足⑤普段デッドエンド沪過ばかりを扱っているので新鮮な情報が多かった⑥
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
意見 ①たいへん役に立つと思う(7名) ②ある程度役に立つ ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
①膜に関する知識が不足していることを自覚した。膜装置を使っている時どういう現象が起きているか多少想像できるようになった。②ファウリングに関する基礎知識・考え方を学ぶことができ、膜のファウリング分析業務に役立てたい③先達の知見を勉強することが大切なことが分かった④頭の中で膜処理により起きている現象をイメージできる基礎力を付けたいと思った⑤実際の運転条件に関する講演が聞けると良い⑥
4.下記の講義内容は
①膜技術および関連技術の総合学習 (①役に立った(7名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①将来のビジョンを持ち仕事に取り組むべきと思った②
②膜技術の基礎Ⅰ(①に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見
③膜技術の基礎Ⅱ(田村)(①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①理論的な式の理解は今後復習して理解を深めたいと思います②計算式が複雑で難しかったが勉強して理解したい③数式が多かったので予習してから受けたかった④勉強不足でついて行けませんでした。本を買って勉強します⑤
④膜技術の基礎Ⅲ(①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①大変役に立った②食品別のファウラント等について知ることができた③
⑤膜プロセス開発の進め方(横山) (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①プロセスの考え方が分かり良かった②運転条件に関する実際的な知見があれば知りたいです③
⑥食品加工への膜利用 (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①具体例が多くあり分かり易かった
⑦メンブレンバイオリアクター (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見
⑧電気透析の原理と応用例(河邉)(①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見
⑨乳業における膜利用(河邉)(①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①実務に近い話が聞けて良かった②雪印の具体的例があり分かり易かった③あまりなじみのない業界だったので良かった④
⑩膜の洗浄とメンテナンス(田邊) (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見 ①ファウリングの想像力が付き良かった ②洗浄剤の使用順序で洗浄効果が異なることが分かった③洗浄方法の大きな流れを知ることができた④
⑪昼食時のビデオ上映(①役に立った(7名)、②役に立たなかった、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい)
意見
⑫ 今後受講したい膜技術関連の講義内容
意見 ①具体的なノーハウ実際に使っているメーカーや機械メーカーに聞いてきたいと思った ②ファウリングの要因解明の例について③工場運転時のトラブル事例や解決方法など紹介して欲しい③初心者向けの膜技術講習を受けたいと思いました。来年1月の受講を楽しみにしています④工場見学がしたい⑤膜の洗浄⑥ファウリング
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
意見 ①ファウリング層の性質(2名)②ファウリング層の基礎的性質を理解し現場とも共有し安定的運転に役立てていきたい③最新の用途開発例④ファウリングに関する講義④物質移動や浸透圧に関する講義⑤トマトジュースのRO濃縮
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
意見 ①濃縮技術②吸着③クロマト分離法の応用例②沪過・膜技術・吸着③各種の膜の選定方法③チーズホエ―の濃縮④排水処理に関する講義
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
意見 ①交流会があり他社がどんなことを考えているか分かった良かった②受講者や先生方との交流ができ良かった③講義が難しく感じるときがあった④膜の運転状態を定量的に確認することも重要であるが、頭の中で起こっている現象をイメージすることの重要性を学んだ⑤膜技術に関する基礎知識不足を痛感した。渡辺先生からご助言頂いたように会社の先輩の論文や膜に関する文献をきちんと読み勉強しようと思った⑥食品業界での膜利用について具体的に教えて頂き大変勉強になりました。受講者どうしの交流もありとても有意義でした⑦大変勉強になりました。ありがとうございました
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月3日
(水) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員)
|
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO, NF ,UF, MF, EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村 吉隆
(森永乳業(株))
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休 憩 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
p.173~201 |
| 15:35~15:45 |
休 憩 |
15:45~16:45
60分 |
◎膜プロセス開発の進め方
1. UF・MF膜プロセスの開発
2 .RO・NF膜プロセスの開発
3.運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化
|
横山 文郎
(筑波大学客員共同研究員)
(MRC名誉会員) |
P.205~241
P.260~277 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月4日
(木) |
9:30~10:50
80分 |
◎膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3.ファウリング層の基礎的性質
4.NF利用による食品製造と利用の注意点 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.245~259 |
| 10:50~11:00 |
休 憩 |
11:00~12:10
70分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~442
P.4430~507
P.535~559 |
| 12:10~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:30
90分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
十亀仁美
(雪印メグミルク(㈱)) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:30~14:50 |
休 憩 |
14:50~16:10
80分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
| |
|
MRC第13回食品膜技術講習会 in Tokyo 2016 アンケート結果
参加企業名(参加者数13名、アンケート回答者12名)
明治3名、雪印1名、カゴメ1名、キッコーマン1名、オルガノ1名、AGCエンジニアリング1名、高砂香料1名、 天野エンザイム3名、三和酒類(株)1名
1.この講習会を何で知りましたか
① MRCからの電子メール2名 ②上司から指示された6名 ③インターネットのHPで3名
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった12名
意見 ①2日間は適当な長さであったが、講義の内容が豊富過ぎて理解が付いていかなかった(個人の知識不足ではあるが)
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う 8名 ②ある程度役に立つ 4名
意見 ①新規事業を行う上で膜利用の留意点や概要を知ることができた②食品の応用例も参考になった2名 ③実工程にスケールアップする方法④濃縮条件を検討するうえで参考になった⑤膜メーカーとしてユーザーの意見を交流会などを通じて直接聞くことができニーズを確認できた⑥酵素製造においては膜技術は必須の技術であり透過流束、ランニングコスト、酵素透過などの検討に役立った⑦様々な考え方や手法を学び論文や技術情報の重要性を認識した⑧RO水の再利用など環境を考慮した工程設計に役立つと感じた⑨膜技術を実際に利用しておりさらに利用方法がよく理解できた⑩今後膜技術を利用する際役立つ⑪基礎知識の拡充ができた⑫テキストを復習すれば実際の業務に役立つ⑬これから膜技術の利用を進めるが、膜の選定から洗浄までとても勉強になった
4.下記の講義内容は役に立ちましたか
①膜技術および関連技術の総合学習 ①役に立った12名
意見記入欄 最初の自己紹介の時間が長かった
②膜技術の基礎Ⅰ ①に立った6名、②詳しく知りたい4名、わかり難かった2名
意見記入欄 ①浸透圧による解析については基礎知識不足で理解できなかったのでこれから勉強する②もっと時間を取って装置設計まで内容を追加して欲しい③科学的な解析から濃縮・分離条件を導き出しており参考になったが十分理解できなかった④今回の理論解析を知っていたので前回より理解が進んだ⑤内容が高度であったので今後勉強していきたい⑥化学工学的アプローチに興味を持った⑦
③膜技術の基礎Ⅱ ①役に立った12名、
④膜技術の基礎Ⅲ ①役に立った11名
意見記入欄 ①ファウリングの原因(膜表面とたんぱくの吸着など)とその検証方法について理解できた
⑤膜プロセス開発の進め方 (①役に立った12名
意見記入欄 ①膜検討のポイントや実験の進め方が具体的で分かり易かった
⑥食品加工への膜利用 (①役に立った12名、
⑦メンブレンバイオリアクター (①役に立った12名、
⑧電気透析の原理と応用例(①役に立った12名、
⑨乳業における膜利用(①役に立った12名
意見記入欄 除菌率を向上させたMF膜について
⑩膜の洗浄とメンテナンス (①役に立った11名、②詳しく知りたい1名
意見記入欄 実際に使っている洗剤・酵素が学べてよかった
⑪昼食時のビデオ上映(①役に立った12名
⑫ 今後受講したい膜技術関連の講義内容
①海外における乳業メーカーの膜利用実態②膜プロセスの開発2名②膜に関する最新情報(耐塩素成膜の開発等)③膜メーカーやエンジニアリング会社の情報が欲しい④基礎膜技術講習会
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
①ファウリング関連②洗浄③乳業関連④運転条件の設置と最適化⑤ファウリング層の基礎的性質4名⑥安定的に透過流束を設定する方法⑥膜技術基礎Ⅰ⑦プロセス設計の手順と過去の事例、トラブル、失敗成功談などを知りたい⑧膜技術の基礎が分かった2名⑨電気透析の原理と応用⑩
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
①フィルター関連②超臨界流体抽出②食品濃縮技術3名③セラミックフィルター④分離技術
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
①基礎を理解するうえで有意義だった②配布資料がカラーの方が分かり易いところがある③様々な膜利用分野が分かり良かった4名④テキストが充実していて良い⑤とても良い勉強になった⑥具体的な過去の実績の説明があり理解が深まった⑦勉強不足なのでさらに復習して理解を深めたい
⑧他分野の人と交流ができ有意義であった2名⑨膜技術に関して網羅的に勉強できた
8.MRC会員外の方 ①必要に応じて入会を考えたい
|
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月6日
(木) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(東京農工大参与研究員)
(日本膜学会名誉会員)
|
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO, NF ,UF, MF, EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村 吉隆
(森永乳業(株))
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休 憩 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
p.173~201 |
| 15:35~15:45 |
休 憩 |
15:45~16:45
60分 |
◎膜技術の基礎Ⅲ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
3.ファウリング層の基礎的性質
4.NF利用による食品製造と利用の注意点
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.245~259 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月7日
(金) |
9:20~10:20
60分 |
◎膜プロセス開発の進め方
1. UF・MF膜プロセスの開発
2 .RO・NF膜プロセスの開発
3.運転モードとその特性
4.運転条件の設定と最適化 |
横山 文郎
(筑波大学客員共同研究員)
(MRC名誉会員) |
P.205~241
P.260~277 |
| 10:20~10:30 |
休 憩 |
10:40~12:00
80分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~442
P.4430~507
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:30
90分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
十亀仁美
(雪印メグミルク(㈱)) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:30~14:50 |
休 憩 |
14:50~16:10
80分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
|
MRC第12回食品膜技術講習会 in Tokyo 2015 アンケート集計
参加企業:キッコーマン・日本アブコー(2名)・ノボザイムズジャパン(2名)・AGCエンジニアリング・日本特殊陶業・三菱レーヨンアクア・ソリューションズ・帝人・キリン・興人ライフサイエンス・理研ビタミン・イビデン(13名)
1.この講習会を何で知りましたか
① MRCからの会報(1名) ②上司から指示された(5名) ③インターネットのHP(4名)
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(13名)
意見を記入ください 講習生同士の討論会・意見交換が交流会と別にあると良い・自社商品の仕様に関連していないが、食品加工プロセスでの理解が深まった・理論の再確認・応用分野の知識拡大・ EDは普段使用しているが,ROを前段で使用している系もあるので、基礎的なことを学べて良かった・
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う(7名) ②ある程度役に立つ(5名)
①,②の方にお聞きします。どういう点で役に立つと思いますか? 研究計画の見直しに役立てたい・平膜試験機を使う程度の実験を行っているが、食品を扱う上での基礎知識になった・ セラミック膜の開発コンセプトを考え直す機会ができた・膜を利用するにあたり他企業ではどのように使用しているかが理解できたため設計の際役立つ・基礎的な考え方を学ぶことができた・ 基礎的な原理をじっくり理解できた・スケールアップのデータ収集の仕方が分かった・膜技術の使い分けやファウリングについての知識を得ることができた・今後のビジネス方針に役立つ・
4.下記の講義内容は如何でしたか?
①膜技術および関連技術の総合学習 (①役に立った(13名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった)
②膜技術の基礎Ⅰ(①に立った(12名)、②詳しく知りたい、わかり難かった(1名)
③膜技術の基礎Ⅱ(①役に立った(13名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
④膜技術の基礎Ⅲ(①役に立った(13名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
⑤膜プロセス開発の進め方 (①役に立った(11名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
⑥食品加工への膜利用 (①役に立った(11名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
⑦メンブレンバイオリアクター (①役に立った(13名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
⑧電気透析の原理と応用例(①役に立った(13名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
⑨乳業における膜利用(①役に立った(12名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
⑩膜の洗浄とメンテナンス (①役に立った(13名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見記入欄 膜の洗浄や殺菌をどうすればよいかわかった・
⑪昼食時のビデオ上映(①役に立った(11名)、②役に立たなかった(1名)、
意見記入欄 興味深かった・
⑫ 今後受講したい膜技術関連の講義内容 ・プロセスの開発・膜に求められる機能・膜装置を取り入れた際の配管の組み方等を聞きたい・UF膜の各社の特性使い方を知りたい・装置の設計に関してポンプの選定や計装機器の選定・ 膜間に実液を流す時の圧損がどの程度か、流路材における供給液の分散具合・膜の開発最新動向(全世界での)・
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか ・田村先生の理論(2名)、ファウリングの基礎知識(3名)・乳業における膜利用技術・膜の洗浄とメンテナンス・膜技術の基礎・食品加工への膜利用(3名)・乳業への利用・洗浄(3名)・ 横のつながりや膜業者と情報交換ができた・膜の洗浄やメンテナンスが役立つ・
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか ・イオン交換樹脂、濃縮・膜技術の基礎・膜と濃縮(3名)・ 乾燥技術・ ビールやワイン製造での膜利用・
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
先生をはじめ、受講生とざっくばらんに話をすることができ良かった(2名)・お弁当美味しかったです・堅苦しい雰囲気でなくて良かった・数式を使った説明では例題を出してもらうと分かり易い・他の会社の方と話ができて良かった・ 他に類を見ない情報交換会であった・異業種、競合他社、客先と話ができ、ニーズを聞くことができた・ 膜を使う受講者同士の交流ができ、自社の進んでいる点、遅れている点が理解できた・大変勉強になりました。ありがとうございました(2名)・ 先生の知識がたくさん講義にちりばめられていてよかったです・ とても参考になりました・
|
食品膜・分離技術研究会(MRC)
第11回MRC 食品膜技術講習会 in Tokyo 2014 プログラム
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月5日
(火) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO, NF ,UF, MF, EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村 吉隆
(森永乳業(株))
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休息 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
3.ファウリング層の基礎的性質 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
p.173~201
p.245~260 |
15:35~16:45
70分 |
◎膜プロセス開発の進め方 |
横山 文郎
日本ピュアウォーター
(MRC名誉会員) |
P.205~229 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月6日
(水) |
9:20~10:30
70分 |
◎無機膜の性質と無菌化ろ過
1. 無機膜の種類、構造および製法
2. 無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3. 食品用膜と一般工業用膜の相違点
4. 無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用) |
学術博士 原田 三郎
(MRC顧問)
((元)トライテック(㈱)) |
P.153~163
P.443~459 |
| 10:30~10:40 |
休息 |
10:40~12:00
80分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
4. 食品分野以外への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:20
80分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
吉岡孝一郎
(雪印メグミルク(㈱))
〔MRC監査〕 |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:20~14:40 |
休息 |
14:40~16:10
90分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
| MRC第11回食品膜技術講習会 in Tokyo 2014 アンケート 回答結果 |
受講生勤務先 サンエイ糖化(株)キューピー(株)日本特殊陶業(株)キッコーマン食品(株)エスエスケイフード(株)サントリーグローバルイノベーションセンター(株)森永乳業(株)半田技術士事務所
1.この講習会を何で知りましたか
① MRCからの会報 1名 ②上司からの指示 4名 ③インターネットのHP 3人
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった 8名
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う5名 ②ある程度役に立つ3名
2-1 ①,②の方にお聞きします。どういう点で役に立つと思いますか?
◎無機膜の知識しかなかったが有機膜の勉強をして有益であった ◎自分がかかえる課題の解決へのヒントを得た。膜処理中の膜表面の挙動や理論を学ぶことができた◎試験結果の解析やシュミレーションの方法を習得できた◎理論や考え方、今後の利用の参考になる◎膜の運転方法検討に大いに役に立つ◎膜を利用する際の考え方や注意点を広く知ることができた◎他業界における情報を得ることができた
4.下記の講義内容は①役に立った、②さらに詳しく知りたい、③わかり難かった。④その他の意見の方は意見を記入ください。
①膜技術および関連技術の総合学習 (①役に立った7名 ②詳しく知りたい1名、③わかり難かった)
意見記入欄
②膜技術の基礎Ⅰ(①に立った5名、②詳しく知りたい2名、わかり難かった1名)
意見記入欄 ◎数式が多く難しかった◎乳の膜処理において温度によって透過流束が変化することがおもしろかった
③膜技術の基礎Ⅱ(①役に立った6名、②詳しく知りたい2名、③わかり難かった)
意見記入欄
④膜プロセス開発の進め方 (①役に立った2名、②詳しく知りたい5名、③わかり難かった1名)
意見記入欄 ◎難しかった
⑤無機膜の性質と無菌化ろ過 (①役に立った6名、②詳しく知りたい2名、③わかり難かった)
意見記入欄 ◎もっとも業務に関係する内容であった。さらに実例を交えて話を聞きたい
⑥食品加工への膜利用 (①役に立った7名、②詳しく知りたい1名、③わかり難かった)
意見記入欄
⑦メンブレンバイオリアクター (①役に立った6名、②詳しく知りたい2名、③わかり難かった)
意見記入欄
⑧電気透析の原理と応用例(①役に立った8名、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見記入欄 ◎原理が良く分かった
⑨乳業における膜利用(①役に立った、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見記入欄 ◎膜の違いによりできるものが違いわかり易かった◎乳についてわかり易く説明頂き有難うございました
⑩膜の洗浄とメンテナンス (①役に立った8名、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
意見記入欄
⑪昼食時のビデオ上映(①役に立った6名、②役に立たなかった、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい2名)
意見記入欄
⑫ 今後受講したい膜技術関連の講義内容(例えば;プロセス設計を詳しく聞きたい)
◎基礎講座を受けたいと思った◎周辺機器の選定(RO用ポンプなど)◎基礎講座を受講して知識を深めたい ◎ 実際に使われている工場の見学 ◎基礎講習を受けたいと思った
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか(回答例;ファウリング層の基礎的性質)
◎膜の洗浄 ◎膜技術Ⅱ ◎無機膜の性質と無菌化ろ過 ◎膜の洗浄とメンテナンス ◎乳業における膜利用 ◎膜分離の理論 ◎ファウリングの基礎的性質
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;乾燥技術・濃縮技術)
◎濃縮技術 ◎実際の膜使用におけるデータの取り方 ◎膜の扱い ◎乾燥・濃縮についても総合的に勉強したい ◎凍結乾燥 ◎抽出
◎乾燥
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
例えば:①内容が難しく90分くらいで休憩を入れていただきたい。②受講者同士の交流ができ、他の業界の状況がわかり良かった。
◎解析に関しては演習問題があると良い◎膜技術について体系的に学ぶことができた ◎受講して今まで感じてきたなぜが明確になり課題解決に向けた考えが纏まった。また、先生方の講演だけでなく他業界との繋がりも増え非常に有意義な2日間でした ◎膜の基礎知識を持ってなかったので講義は難しかったが、質問の時間がたくさん用意されておりお蔭で少しずつ理解が深まりました ◎交流会を開いて頂けたことで先生方、受講生と話ができ2日間大変有益でした。◎内容は難しかったがわかり易く説明頂きちょうどよかった ◎他業種、他社の状況や多くの方と交流ができ有意義でした ◎質問時間をしっかり取って頂け良かったです ◎低圧・高流速で低Fluxでの運転が効率の良い運転だと教えて頂き勉強になりました ◎濃度を上げて運転しても、ものによりFluxがゼロになったりならなかったり色々な現象があることが興味深かったです |
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
7月29日
(月) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村 吉隆
(森永乳業(株))
(MRC副会長) |
P.1~12P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休息 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
3.ファウリング層の基礎的性質 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
p.173~201
p.245~260 |
15:35~16:45
70分 |
◎膜プロセス開発の進め方 |
横山 文郎
日本ピュアウォーター
(MRC名誉会員) |
P.205~229 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
(質問が無くなるまで、時間延長して対応します) |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
7月30日
(火) |
9:20~10:30
70分 |
◎無機膜の性質と無菌化ろ過
1. 無機膜の種類、構造および製法
2. 無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3. 食品用膜と一般工業用膜の相違点
4. 無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用) |
学術博士 原田 三郎
(MRC顧問)
((元)トライテック(㈱)) |
P.153~163
P.443~459 |
| 10:30~10:40 |
休息 |
10:40~12:00
80分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
4. 食品分野以外への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:20
80分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
吉岡孝一郎
(雪印メグミルク(㈱))
〔MRC監査〕 |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:20~14:40 |
休息 |
14:40~16:10
90分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月6日
(月) |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3. 膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村吉隆
(森永乳業)
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休息 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2. 各種膜モジュールの特性
3. ファウリング層の基礎的性質 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
P.173~201
P.245~260 |
15:35~16:45
70分 |
3. 膜プロセス開発の進め方 |
工学博士 伊東 章
(東京工業大学大学院教授)
(MRC副会長) |
P.205~229 |
| 16:45~17:00 |
☆ Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応 |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月7日
(火) |
9:20~10:30
70分 |
◎ 無機膜の性質と無菌化ろ過
1. 無機膜の種類、構造および製法
2. 無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3. 食品用膜と一般工業用膜の相違点
4. 無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用) |
学術博士 原田 三郎
(MRC顧問)
((元)トライテック(㈱)) |
P.153~163
P.443~459 |
| 10:30~10:40 |
休息 |
10:40~12:00
80分 |
◎ 食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
4. 食品分野以外への膜利用
◎ メンブレンバイオリアクター
1. 排水処理への利用
2. 食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:20
80分 |
◎ 電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎ 乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
伊藤光太郎
(雪印メグミルク(㈱))
(MRC会計監査) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:20~14:40 |
休息 |
14:40~16:10
90分 |
◎ 膜の洗浄とメンテナンス
1. 膜装置の日常管理とメンテナンス
2. 膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3. 洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC会計幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワーand 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月1日
月 |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1.
講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2.
分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
テキスト
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎
膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2)
RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村吉隆
(森永乳業)
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休息 |
14:25~15:35
70分 |
◎
膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2. 各種膜モジュールの特性
3.
ファウリング層の基礎的性質 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
p.173~201
p.245~260 |
15:35~16:45
70分 |
3. 膜プロセス開発の進め方 |
横山文郎
(日本ピュアウォーター)
(MRC名誉会員) |
P.205~229 |
| 16:45~17:00 |
☆
Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応 |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月2日
火 |
9:20~10:30
70分 |
◎ 無機膜の性質と無菌化ろ過
1.
無機膜の種類、構造および製法
2. 無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3. 食品用膜と一般工業用膜の相違点
4.
無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用) |
学術博士 原田 三郎
(MRC副会長)
(トライテック(㈱)) |
P.153~163
P.443~459 |
| 10:30~10:40 |
休息 |
10:40~12:00
80分 |
◎ 食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1.
飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
4. 食品分野以外への膜利用
◎
メンブレンバイオリアクター
1. 排水処理への利用
2. 食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:20
80分 |
◎ 電気透析の原理と応用例
1.
電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4.
電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎ 乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2.
RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5.
MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
伊藤光太郎
(雪印メグミルク(㈱))
(MRC会計監査) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:20~14:40 |
休息 |
14:40~16:10
90分 |
◎ 膜の洗浄とメンテナンス
1.
膜装置の日常管理とメンテナンス
2. 膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3. 洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC会計幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワーand
総合討論 |
司会 渡辺 |
|
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8月5日
木 |
10:00~12:00
120分 |
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
テキス
および
教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 膜技術の総論
(1) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2) RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士 田村吉隆
(森永乳業)
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休息 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1. 高分子膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
3.ファウリング層の基礎的性質 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院 院長) |
P.103~143
p.173~201
p.245~260 |
15:35~16:45
70分 |
3.膜プロセス開発の進め方 |
横山文郎
(日本ピュアウォーター)
(MRC名誉会員) |
P.205~229 |
| 16:45~17:00 |
☆ Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応 |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8月6日
金 |
9:20~10:30
70分 |
◎ 無機膜の性質と無菌化ろ過
1. 無機膜の種類、構造および製法
2. 無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3. 食品用膜と一般工業用膜の相違点
4. 無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用) |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.153~163
P.443~459 |
| 10:30~10:40 |
休息 |
10:40~12:00
80分 |
◎ 食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1. 飲料工業への膜利用
2. 醸造工業への膜利用
3. 水産工業への膜利用
4. 食品分野以外への膜利用
◎ メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:20
80分 |
◎ 電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特徴
2. 電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4. 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎ 乳業における膜利用
1. 牛乳の特性と膜分離
2. RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3. NF:ホエイの脱塩濃縮
4. UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5. MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
伊藤光太郎
(雪印乳業)
(MRC会計監査) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:20~14:40 |
休息 |
14:40~16:10
90分 |
◎ 膜の洗浄とメンテナンス
1.膜装置の日常管理とメンテナンス
2.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3.洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギサニテーションラボ)
(MRC会計幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワーand 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
MRC食品膜技術講習会 in Tokyo 2009
日時:2009年8月6日(木)~7日(金)
場所:(財)日本食品分析センター会議室(日本水産油脂協会ビル3F)
主催: 食品膜・分離技術研究会(MRC)
協賛: 化学工学会、日本膜学会、石油学会
| 日時 |
内容 |
講師 |
テキスト頁 |
8/6
(木) |
10:00~12:00
120分 |
◎膜技術および関連技術の総合学習
1.
講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.
膜技術、その発展の歴史(問題点解決の歴史)と将来展望 |
農学博士
渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
テキストおよび教材 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:10
80分 |
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.
膜技術の総論
① クロスフローろ過とデッドエンドろ過
② RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
2. 膜技術の基礎的理論
――
逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ―― |
工学博士
伊東
章
(東京工業大学大学院教授)
(MRC副会長) |
P.1~12
P.17~74 |
| 14:10~14:25 |
休息 |
14:25~15:35
70分 |
◎膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.
高分子膜の特性
2. 各種膜モジュールの特性
3. ファウリング層の基礎的性質 |
農学博士
渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院。院長) |
P.103~143
p.173~201
p.245~260 |
15:35~16:45
70分 |
4. 膜プロセス開発の進め方 |
横山文郎
(日本ピュアウォーター)
(MRC名誉会員) |
P.205~229 |
| 16:45~17:00 |
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応 |
司会 渡辺 |
|
| 17:10~18:55 |
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流) |
8/7
(金) |
9:20~10:30
70分 |
◎無機膜の性質と無菌化ろ過
1. 無機膜の種類、構造および製法
2.
無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3 食品用膜と一般工業用膜の相違点
4 無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用) |
学術博士
原田三郎
(トライテック)
(MRC副会長) |
P.153~163
P.443~459 |
| 10:30~10:40 |
休息 |
10:40~12:00
80分 |
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)1 飲料工業への膜利用2
醸造工業への膜利用3 水産工業への膜利用4 食品分野以外への膜利用◎メンブレンバイオリアクター1 排水処理への利用2 食品製造への利用 |
農学博士
渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長) |
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559 |
| 12:00~13:00 |
昼食(膜関連ビデオ放映) |
13:00~14:20
80分 |
◎電気透析の原理と応用例
1. 電気透析膜の構造と特性
2.
電気透析の理論
3. 運転条件の設定と最適化
4 電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1
牛乳の特性と膜分離
2 RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3 NF:ホエイの脱塩濃縮
4
UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5 MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離 |
伊藤光太郎
(雪印乳業)
(MRC会計監査) |
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532 |
| 14:20~14:40 |
休息 |
14:40~16:10
90分 |
◎膜の洗浄とメンテナンス
1 膜装置の日常管理とメンテナンス
2
膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
3 洗浄剤と膜洗浄の実施例 |
田辺忠裕
(シラサギ・サニテーションラボ)
(MRC会計幹事) |
P.283~293
P.294~311
P.312~325 |
| 16:10~16:30 |
☆ Q&Aアワー and 総合討論 |
司会 渡辺 |
|
Page Top
MRC膜技術講習会 in Tokyo 2009 アンケート 回答
1.参加者18名 回答者18名
2.参加企業(1社で複数名参加の会社があります)
四国化成工業(株)・カルピス(株)・(有)半田研究所・日本ポール(株)・雪印乳業(株)・日本錬水(株)・(株)日本生物科学研究所・サントリー食品(株)・森永乳業(株)・キリン協和フーズ(株)・理工協産(株)・ユニチカ(株)・(株)海月(くらげ)研究所・カゴメ(株)・東レ(株)
3.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
①2日間では長すぎる 0名
②ちょうど良い時間構成であった 17名
③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい 1名(何日くらいを希望しますか?3 日、どの課題の講義を期待しますか? 応用例 他業界での応用例)
4.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①役に立つと思う18名
②余り役立たない 0名
③全く役立たないだろう 0名
①と答えた方 どういう点で役に立つと思いますか
・基礎から始まり各業界での使用例、メンテナンス等一連の流れが理解できた。特に、洗浄を詳しく講義していただける機会は少ないので有意義だった。
・理論から実用例までの講義があり、条件設定や選定に役立つと思う。
・膜全般に関する基礎知識(用語も含めて)を深められ、初級者にとっても役に立つと感じました。
・理論と実際が学べ、業界の方との意見交換ができた。
・実機導入の際にトラブルが起きた場合、順序だった考え方で対応できると思う。
・各種の膜技術の利用方法、メンテナンス、注意点は将来的に膜を利用するとき役立つと思う。
・現在研究を進めている技術について全体的に勉強ができた。
・野菜加工に応用できる点が多くあると思う。
・膜に関しては素人であったのですが、非常にわかり易く教えていただき有難うございました。
・膜の透過流束とファウリングの影響など、操作条件の検討が重要であると認識できた。
・膜の洗浄法、保存法についても有益な情報でした。
・食品由来の蛋白質抽出において、エタノールによる蛋白沈殿を行っているが、膜技術を用いることでコストダウンが図れるように感じた。
・膜の実際の導入例を色々聞くことができ良かった。
・膜業界の現状を知ることができました。今まで行ってきた単位操作、解析についてより理論的に知ることができ、役に立つと感じました。
・なかなか聞けない情報を聞くことができた。開発の方向を修正して行くことができる。
・食品用の膜の要求される点が分かり、膜全般についての知識が広がった。
5.本講習会の講義内容でさらに詳しく知りたい点がありましたら指摘して下さい
・濃度分極の計算例・膜技術の理論面
・膜の応用例(コスト・メリット比較)2名
・膜を使用することにより最終製品に与える種々のメリット(物性、閾値、概観、香り・味等)。
・膜技術を利用した成功例や失敗例などを知りたいと思います。
・膜装置のサニタリー性を上げる工夫について
・今後の膜自体の開発の方向
・膜を利用したプロセス開発について詳しく聞かせてもらえると良い。
・膜プロセス開発の進め方(2名)
・有機膜と無機膜の長所と短所
6.今回の講習会で最も役に立った講義はどの点ですか
・食品加工の応用例・無機膜と無菌化濾過 2名
・ファウリングの発生やその対処法
・RO・NF・UF等の基礎理論
・電気透析膜について特に学びたかったので分かり易い基本原理の説明と実際の運転のイメージなどが解説され非常に参考になりました。
・分離・濃縮・食品の膜技術利用、乳業における膜利用、うやむやだった知識の部分をまとめて講義していただけ良かった。
・洗浄について体系的に学ぶことができ、今後役立つと思う。
・無菌化濾過(2名)と膜の洗浄・メンテナンスについて
・濃度分極モデル・ゲルモデル
・多くの応用法を勉強できた点。ファウリングの基礎知識を学び、劣化との違いが分かった。
・お世辞ではなくすべて勉強になりました。
・膜の洗浄とメンテナンス 3名
・実際に膜プロセスを行っている方の話、質疑を聞くことにより、今後膜プロセス導入時の検討事項をピックアップすることができました。
・基礎理論
・ダイアフィルトレーションの算出法
7.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
・抽出技術・分画技術・選択的分離技術(特定のものを分離濃縮する技術)
・濃縮技術(2名)・培養液の清澄化
・イオン交換樹脂
・香味変化に関係する物質の分離、そして精製が可能か知りたい。
・分離機器のサニタリー性について
・蛋白質の濃縮と精製
・膜による特定の分画成分の分離技術(他の技術と比較して長所と短所)
・噴霧乾燥技術
・分離技術(膜・遠心分離・フィルタープレス等)の使い分け、選定法
8.食品加工技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
・乳化・分散・食品の物性に関する分野
・濃縮技術(膜でなく減圧濃縮など)
・原料や加工機械の洗浄について学びたい。
・セラミック膜やRO・NFについて
・無菌化濾過
・分離精製技術全般
9.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
・膜メーカー、膜メンテナンス会社、食品製造会社、造水会社等の方と膜に関わる交流が持てた点が良かった。・講義資料も分かり易く、同じ内容が配布され良かった。・質疑時間も十分取って頂けたので多くの疑問が解決できた。もっと多くの話(膜メーカーの実使用例など)を聞いてみたい。
・講習会を開催していただき有難うございました。膜に関する事象を実際のお話を交えながらご説明戴き大変分かり易く楽しく聞くことができました。本で理解できていなかった分野を理解でき有意義な講習会でした。
・実際の現場で活躍されておられる方々が講師に来ておられ、内容が臨場感あふれ、理解し易かった。実際の事例も紹介豊富で、今後自分が直面するかもしれない技術的な問題についても情報収集でき有意義なセミナー受講でした。2日間有難うございました。
・いずれも、なるほどと気付かされる点があり、交流会で意見交換もでき大変役立ちました。有難うございました。
・アットホームな雰囲気で質問等がし易かったし、理論から実用まで学ぶことができた。多くの業種の方々と意見交換ができた。2日間と時間が短いのに内容が多すぎる感じがした。
・密度が濃く短時間で多くのことが勉強できた。
・とても勉強になりました。膜技術に関する基礎知識から応用例まで、特に、野菜ジュース等の加工に関して例を挙げて説明戴き、広く勉強でき良かったです。
・食品への膜技術の利用に関して詳しく説明していただき大いに勉強になった。
・本当はもっと長期間講義を聴きたいのですが、業務との兼ね合いの中で2日間の講義はちょうど良かったと思います。内容もポイントを絞り分かり易く教えて頂いた。
・実機の見学会は無理だとしてもビデオ映像などをまじえて説明してもらえれば更に分かり易くなると思います。
・基礎理論に関する丁寧な説明が良かったです。
・講師の先生の膜技術に対する思い入れが伝わり非常に勉強になりました。今回の講習会の内容を生かし自社のレベルアップに繋げて行きたい。
・各分野のエキスパートの方々の講義を受けることができ満足しています。質疑の時間も十分で有意義でした。計算式について具体的な数値(実例)をご説明いただければより理解し易かったと思います。
・多くの企業の方と知り合いになれ有意義でした。
・濃度分極等の式の説明をもう少し丁寧にしてくれるほうが良いと思った。
Page Top
MRC 食品膜技術講習会 in Tokyo 2008
開催日 2008年8月4~5日(月・火の2日間)
開催場所 川口総合文化センター リリア 11階中会議室
プログラム
|
日時
|
内容
|
講師
|
テキスト頁
|
| 8/4
月
|
10:00~12:00
120分
|
◎
膜技術および関連技術の総合学習
1.
講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2.
分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
3.
分離技術・膜技術ビデオ(50分)
4.膜技術、その発展の歴史と将来展望
|
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授)
|
|
|
12:00~13:00
|
昼食(膜関連ビデオ放映)
|
|
13:00~14:45
105分
|
◎膜技術の基礎Ⅰ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.
膜技術の総論
(1)
クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(2)RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
2.
膜技術の基礎的理論
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ――
|
農学博士 渡辺敦夫
(新技術開発院)
|
P.1~12
P.17~74
|
|
14:40~14:55
|
休息
|
|
14:50~16:25
90分
|
◎
膜技術の基礎Ⅱ(膜技術を使いこなす基礎知識を講義する)
1.
高分子膜の特性
2.
各種膜モジュールの特性
3.膜プロセス開発の進め方
|
農学博士 渡辺敦夫
(新技術開発院)
|
P.103~143
P.173~201
P.205~220
|
|
16:25~17:00
|
☆Q&Aアワー MRC役員会参加者全員対応
|
司会 渡辺
|
|
|
17:10~18:55
|
情報交換交流会(MRC役員と講習生の交流)
|
| 8/5
火
|
9:10~10:20
80分
|
◎無機膜の性質と無菌化ろ過
1.
無機膜の種類、構造および製法
2.
無菌化ろ過と除菌性能の評価方法
3.
食品用膜と一般工業用膜の相違点
4.無菌化濾過による食品の製造(精密濾過技術の利用)
|
学術博士 原田三郎
(トライテック)
|
P.153~163
P.443~459
|
|
10:20~10:30
|
休息
|
|
10:30~12:00
90分
|
◎食品加工への膜利用(無菌化濾過以外)
1.
飲料工業への膜利用
2.
醸造工業への膜利用
3.
水産工業への膜利用
4.
食品分野以外への膜利用
◎メンブレンバイオリアクター
1.排水処理への利用
2.食品製造への利用
|
学術博士 原田三郎
(トライテック)
(MRC副会長)
|
P.381~438
P.460~507
P.565~576
P.535~559
|
|
12:00~12:20
|
☆Q&Aアワー
|
|
12:20~13:00
|
昼食
|
|
13:00~14:20
80分
|
◎電気透析の原理と応用例
1.
電気透析膜の構造と特徴
2.
電気透析の理論
3.
運転条件の設定と最適化
4.
電気透析の食品加工への利用(ED:ホエイの脱塩その他)
◎乳業における膜利用
1.
牛乳の特性と膜分離
2.
RO:ホエイの予備濃縮、市乳への応用
3.
NF:ホエイの脱塩濃縮
4.
UF:WPC、TMP、チーズ原料乳のタンパク質濃度調整
5.MF:HTST乳、チーズ原料乳の除菌、カゼインとホエイの分離
|
伊藤光太郎
(雪印乳業)
〔MRC会計監査役〕
|
P.144~149
P.229~241
P.349~374
P.513~532
|
|
14:20~14:35
|
休息
|
|
14:30~16:15
100分
|
◎膜の洗浄とメンテナンス
1.膜機能の低下要因としてのファウリング
2.膜装置の日常管理
3.膜装置の洗浄および殺菌と衛生管理
4.洗浄剤と膜洗浄の実施例
|
田辺忠裕
(エコラボ)
(MRC代表幹事)
|
P.245~260
P.283~293
P.294~325
|
|
16:10~17;00
|
☆総合討論
|
司会 渡辺
|
|
Page Top
参加企業名(18名)
| 四つ葉牛乳(株) |
| カゴメ(株) |
| 寿高原食品(株) |
| フジ日本精糖 |
| 日本錬水(株) |
| アストム(株) |
| 日本ピュアウォーター(株) |
| 日本ピュアウォーター(株) |
| 大分醤油協業組合 |
| 大分醤油協業組合 |
| 東レ(株) |
| (株)ロキテクノ |
| (株)曽田香料 |
| 森永乳業(株) |
| 森永乳業(株) |
| 旭化成ケミカルズ(株) |
| 日東アリマン(株) |
| グリコ乳業(株) |
MRC膜技術講習会 in Tokyo 2008 アンケート
回答者17名・回答内容は一部要約しています
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
(無回答1名)
①2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(16名) ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい(何日くらいを希望しますか? 日、どの課題の講義を期待しますか? )
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
(無回答1名、①と②の両方に○を付けたもの1名) ① 役に立つと思う(16名) ②余り役立たない(1名) ③全く役立たないだろう
①と答えた方 どういう点で役に立つと思いますか
意見
1.膜を使用する上で基礎を知り膜に対する基盤ができた。
2.現在の濃縮試験で運転条件を検討できる。
3.今までと違った運転の仕方を考えてみたい。
4.今後膜を扱う際取り付き易くなった。
5.様々な分野の知識が得られ視野が広くなった。
6.濃縮や分離において選択肢が増えた。
7.膜の性質やメンテナンスを学んだことで実際の使用において正しい使用ができる。
8.膜の洗浄法とファウリング。
9.膜の基礎を学んだので膜で起こる現象が理解できた。
10.基礎を知らずに対応してきたが、イレギュラーに対応できなかったが基礎を学んで対応が可能になる。
11.今後の膜技術の活用に役立つ。
12.本では分からなかったことが理解できた。
13.実際には理論を知らなくても膜の利用はできるが、理論を知ることで問題が起こった時対応できるようになったと思う。
14.MBRの講義が役に立った。
15.もう少し基礎についての話が欲しかった。
15.膜プロセス、ファウリング、洗浄・メンテナンスの話が役に立った。
16.膜がどのような分野で利用されているかがよく分かった。
17.アプリケーションの知見を深めることができ、また濾過についてのヒントが得られた。
18.ファウリング現象がよく分かった。
19.実験において測定すべき項目がよく分かった。
3.本講習会の講義内容でさらに詳しく知りたい点がありましたら指摘して下さい(回答例;膜技術の応用例について)
意見
1.膜技術の排水処理への利用と新技術。
2.実際の使用例(能力・コスト等を含めて・2名の方)。
3.膜の基礎(1日目に出席できなかったので)。
4.MFによる除菌技術。
5.分画とダイアフィルとレーション。
6.膜装置の設計(膜・ポンプ・配管等の選定)。
7.初心者向けのテキストが欲しい。
8.膜技術を利用した新ビジネスの創出。
9.実験室レベルでの実験とスケールアップにおけるデーターの整合性。
4.今回の講習会で最も役に立った講義はどの点ですか(回答例;ファウリングについて)
意見
1.定流束濾過の方が定圧濾過より透過流束が高くなりやすいという点。
2.ファウリング防止の運転条件(2名)。
3.膜間差圧の問題点。
4.膜技術の応用例(3名)。
5.膜の洗浄とメンテナンス(6名)。
6.透過流束とファウリングの関係、濃度分極。
}7.膜技術の基礎と総論(5名)。
8.総て役だった。
5.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;濃縮技術)
意見
1.固体からの抽出・分離技術。}
2.乾燥技術(2名)。
3.膜ユーザーの発表。
4.果汁の清澄化濾過。
5.殺菌・熱処理。
6.微粒子の分級。
7.晶析技術。
8.膜の洗浄技術
6.食品加工技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
意見
1.果汁飲料に関する加工技術。
2.殺菌。
3.乳化技術。
4.凍結技術。健康食品分野。
5.機能性食品分野(高価格食品の分野でどの様な分離技術が利用されているか)。
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい。
意見
1.膜に関する基盤を作るには良い講習会である。
2.技術の利用に関する説明が少ないように感じた。
3.大変分かりやすい内容で膜初心者には実験に取り付きやすくなったと感じる。但し、もう少し膜について知識を持っていればより有意義であったろうと感じた。
3.膜の情報交換ができ知らなかったことを知ることができた。
4.もう少しゆとりがあればと感じた。
5.複数の先生から最新の膜技術を学べて良かった。
6.一コマの時間が長く疲れた。
7.大変役に立つ講義を有り難うございました。
8.2日間でしたが充実した講義を聞くことができ勉強になりました。
9.基礎の解説について初心者でも分かるように解説して頂き有り難うございました。
10.基礎と実際の現象についてもっと結びつけて講義してくれると分かりやすい。
11.それぞれ専門の方が専門分野を詳しく説明して下さったので興味深く受講できた。
12.私は膜の初心者なのでもう少し基礎の原理の話をしてくれると有り難い。
13.2日間に渡り大変貴重な講義をして頂き大変勉強になりました。今回の講義内容を社内でも共有し役立たせたいと思います。
14.基礎から勉強でき、膜の分離特性の理解が進んだので問題が起こった時、理論的に対応ができると思う。
15.短時間で総ての膜技術に関する講義が聴けて良かった。
16.一方的な講義型は疲れるので、問題を出すとか質問をするとか工夫してくれると良いです。
17.非常に親しみやすい雰囲気を出して下さった講師の方々に感謝します。
18.食品膜・分離技術に関する工場見学があれば参加したい。
Page Top
| 「2005年度 食品膜技術講習会-膜の選択からメンテナンスまで-」 |
| プログラムの下に、2005年度食品膜技術講習会に参加された方々の会社・団体名リストと、参加者の意見を掲載しました。 |
主催:食品膜・分離技術研究会(MRC)
共催:化学工学会、日本膜学会、
東京湾岸地域大学間コンソーシアムによる社会人キャリアアップ運営協議会
日時:2005年8月4日(木) 10:00~17:10(交流会17:20~)、5日(金) 9:00~17:00
会場:東京農工大学小金井キャンパス 4号館1F 0411号室(JR中央線・東小金井駅より徒歩10分)
テキスト:『食品膜技術-膜技術利用の手引き-』
(大矢晴彦・渡辺敦夫監修/光琳/定価:\7,000)
参加費(テキスト代込み):MRC会員,及び共催会員 \25,000,非会員 \30,000
(テキスト持参者): 〃 \18,000, 〃 \23,000 |
| <プログラム> |
|
日 時
|
内 容
|
キーワード
|
講 師
|
|
8/4
(木)
|
10:00~12:00
|
実習
|
モジュール、真の阻止率、流速変化法
|
国眼孝雄
(東京農工大)
|
|
|
|
|
|
12:00~13:00
|
昼 食
|
|
13:00~14:45
14:45~14:55
14:55~16:25
16:25~17:10
|
膜技術の基礎Ⅰ
休憩
膜技術の基礎Ⅱ
☆Q&A アワー
|
濃度分極、透過流束、阻止率、物質移動係数、
MF, UF, NF, RO,反射係数、有機膜、セラミック膜、モジュール特性、プロセス設計
|
大西正俊
(森永乳業)
伊東 章
(新潟大学)
|
|
17:20~
|
交 流 会 (講習生相互の交流とMRC役員との意見交換等)
|
|
8/5 (金)
|
9:00~10:20
10:20~10:30
10:30~12:00
12:00~12:20
|
無機膜の性質と無菌化ろ過
休憩
膜の洗浄とメンテナンス
☆Q&A アワー
|
HACCP、生風味食品の創出、無菌性の保証、Fluxの確保、ファウリング、殺菌洗浄、
膜のメンテナンス
|
原田三郎
(NGKフィルテック)
田辺忠裕
(エコラボ)
|
|
12:20~13:00
|
昼 食
|
|
13:00~14:20
14:20~14:35
14:35~16:15
16:15~
|
電気透析の原理と応用例
乳業における膜利用
休憩
全体の復習と食品加工への膜利用、メンブレンバイオリアクター
☆総合討論
|
チーズホエー、
濃縮ジュース、
オリゴ糖の分離、
水飴糖化液の清澄ろ過,
減塩醤油、
無菌化ろ過
|
重松明典
(雪印乳業)
佐藤 武
(味の素)
司会:渡辺敦夫(新潟大学大学院)
|
<講習会参加者の会社・団体名>
| 所属・担当業務 |
業種 |
人数 |
備考 |
| 民間企業 |
食品関連メーカー |
18 |
・正田醤油㈱
・不二製油㈱
・寿高原食品㈱
・森永乳業㈱
・味の素㈱
・明治乳業㈱
・ポッカコーポレーション
・曽田香料㈱
・雪印乳業㈱
・塩野香料㈱
・内外化学製品㈱
・三栄源エフ・エフ・アイ㈱ |
| 膜メーカー |
3 |
・旭化成ケミカルズ㈱
・旭硝子エンジニアリング㈱ |
| 膜装置・エンジニアリング |
4 |
・日本錬水㈱
・㈱ロキテクノ
・㈱サンコー |
| 研究機関 |
|
1 |
・広島県立食品工業技術センター
|
| 合計 |
|
26 |
|
Page Top
<講習会参加者の意見>
※順不同、原文まま (提出23名/参加者26名)
| 質 問 |
評 価 |
人数 |
理由、備考等 |
 |
分かり易かった、
役に立った |
22 |
・膜技術の基礎(本当に基礎の基礎、のところだけですが…)を理解することが出来ました。(正田醤油㈱)
・「膜の洗浄とメンテナンス」プロテアーゼ酵素を用いた洗浄剤が存在することを知ることができ、ためになった。(寿高原食品㈱)
・乳業における膜利用のテーマ(日本錬水㈱)
・食品一般の膜利用の実体が大まかに分かりました。(旭化成ケミカルズ㈱)
・膜の構造、働きについて参考になりました。(森永乳業㈱)
・膜に関する、基礎・応用が理解(一部ではございますが)でき、今後の社会生活で大きなプラスになると期待しています。(森永乳業㈱)
・濃度分極、阻止率についての基礎的な理論を理解することができた。(広島県立食品工業技術センター)
・一部難解な内容もありましたが、どの講師の方も、スライドを使って丁寧に説明していただけました。(食品メーカー)
・基本的な内容から、応用的な内容まで幅広く扱って頂いた点が良かったと思います。(味の素㈱)
・(難しかった)膜素人の私にとっては、専門用語が前提として講義として使われていたので、意味を理解するまでに若干タイムラグがあった。(明治乳業㈱)
・理論的なところはなかなか理解できなかったが、感覚的に膜の考え方を理解することができた。(明治乳業㈱)
・分離について、溶液と混合液でも考え方は同じであると思った。(膜メーカー)
・そもそも阻止率やFluxという言葉も知らずに参加しましたので、これから勉強していく上でのベースを身につけることができました。(ポッカコーポレーション)
・本を読むだけでは、ポイントがつかみにくいが、
慣れた方がかいつまんで説明すると短時間で理解できた。(旭硝子エンジニアリング㈱)
・応用例が豊富であった。(塩野香料㈱)
・膜初心者にも理解できる所が多かった。
理論だけでなく、身近な事が題材となっていたので、入り込みやすかった。(無記名)
・基礎から応用まで教えていただいたのでわかり易かった。(味の素㈱) |
分かりにくかった、
あまり役立たなかった |
0 |
|
| その他 |
1 |
・総じて理解し易かったが、各論については、講義中での理解が難しい所も有った。(不二製油㈱) |
 |
分かり易かった、
役に立った |
15 |
・実際に膜にふれてみるという事は、理解を深める上でとても重要なことと思います。(正田醤油㈱)
・おもしろかった(日本錬水㈱)
・RO膜、UF膜を初めて見ました。
実際に運転して透過液には驚きました。(森永乳業㈱)
・RO,MF等、実際に見ることがなく、ビジュアル的に理解することができました。(森永乳業㈱)
・講座の前に実験装置を見ることで、膜に対するイメージができた。(広島県立食品工業技術センター)
・膜について、理論的にアプローチすることができました。(食品メーカー)
・知識だけでなく、装置を見ることで、イメージが
わきやすくなり、その後の講義内容を理解しやすかったと思います。(味の素㈱)
・実際に動いているところを見ると、膜を利用している者にとっていろいろ役立った。(明治乳業㈱)
・色で見れたので分かり易かった(明治乳業㈱)
・弊社納入の平膜装置が役に立っているので、うれしく思いました。(㈱サンコー)
・セラミック膜で中心部の部分とまわりの部分とで透過液が同じように出てくるときいて、不思議に思った。(膜メーカー)
・セラミック膜、平膜(塩野香料㈱)
・まず、講義の前に実習を行った所が非常によかったと思う。(無記名)
・実際の装置を見るのは初めてだったので、実験の具体的な操作が想像できた。できれば、自分で値をとってJv
を計算など(時間はかかると思いますが)できたら良かったです。(味の素㈱) |
分かりにくかった、
あまり役立たなかった |
5 |
・実物を見ることはできたが、あまり必要ないのでは?(ただし、はじめての方は印象強いかも)(旭硝子エンジニアリング㈱)
・実習は時間的に難しいと思いますので以前のような工場見学などが良いのではないでしょうか(曽田香料㈱) |
| その他 |
2 |
・ROについては、扱った事が無いので良かった。(不二製油㈱)
・ラボテスト装置を、もう少し詳細に見学したかった。(寿高原食品㈱) |
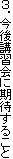 |
・ 出来ましたら、私のようなドシロウトにももう少し踏み込んだところまで理解出るよう、ゆっくりと説明していただければ幸いです。(正田醤油㈱)
・具体的なテーマ(用途)で講習して頂ければ助かります。(日本錬水㈱)
・それぞれの膜の品評も聞きたいです。(旭化成ケミカルズ㈱)
・実習を多くしていただけると、イメージをつかみやすいと思います。(食品メーカー)
・今回同様、実際の実験装置や手順を見る、ということが、初心者には有効ではないかと感じました。(味の素㈱)
・1講義 80~100分ノンストップは初心者にとってキツい。(明治乳業㈱)
・膜を使った新技術(明治乳業㈱)
・実習が多い方がよいと思った。(膜メーカー)
・実際のトラブル解決事例などの紹介など、生産現場サイドの話が聞いてみたいです。(ポッカコーポレーション)
・和気あいあいといった感じを維持して下さい。(旭硝子エンジニアリング㈱)
・今後も講習会は、同様な内容で維持して頂ければ幸いです。(塩野香料㈱)
・まだまだ膜技術に関して、わからない事の方が多いのですが、このような講習会がある事で、膜に興味を持ち、さらには、活用する人が増えるよい機会であると思うので、これからもこのような会をやり続ける事に意味があると感じました。(無記名)
・実習の時間を増やしてほしい。(味の素㈱)
・2日間の開催であれば、1日目を超入門編、2日目を実践編にするなどすれば、
まったくの初心者は2日間出席し、中級者は2日目のみを受講するというように、
出席のし方に自由度が生まれて、より幅広く受講者を集められるのではないでしょうか?(雪印乳業㈱) |
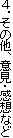 |
・2日間、大変貴重なお時間をいただきありがとうございました。メール等で今後も質問をさせていただきたいのですがよろしいでしょうか?(正田醤油㈱)
・勉強になりました。(日本錬水㈱)
・学術、学問的な内容については理解に困りましたが非常に参考になりました。
営業担当ではありますが今後、活かしていきたいと考えております。(森永乳業㈱)
・営業として参加させて頂きましたが、意識の広がり、他社との交流等、大いにプラスになる部分がございました。引き続き宜しくお願い申し上げます。(森永乳業㈱)
・とっても熱のこもったよい勉強会です。しっかり復習して業務に活かします。
先生方の研究のますますのご発展を祈念します。(明治乳業㈱)
・総合討論での、分極モデルの話(論争?)は、面白かった。(帰って復習します。)(サンコー㈱)
・1つの講義の時間が長いと思った。(膜メーカー)
・食品工業の中での膜の位置づけと、実際にプロセスで使う上でのポイントなどが
感覚的につかめた気がします。(ポッカコーポレーション)
・講義の途中の5分は貴重でした。各界の方のお話を実例含めて聞けてよかった。
次回も別の若手を受講させたい。(旭硝子エンジニアリング㈱) |
「2004年度 食品膜技術講習会-膜の選択からメンテナンスまで-」
主催:食品膜技術懇談会(MRC)
共催:東京湾岸地域大学間コンソーシアムによる社会人キャリアアップ運営協議会
化学工学会、日本膜学会
日時:2004年8月5日(木) 13:00~17:00 、6日(金) 9:00~17:00
会場:東京農工大学工学部 4号館41号室 JR中央線・東小金井駅徒歩10分
テキスト:『食品膜技術-膜技術利用の手引き-』
(大矢晴彦・渡辺敦夫監修/光琳/定価:\7,000) |
|
日 時
|
内 容
|
キーワード
|
講 師
|
|
8/5
(木)
|
午後
|
13:00~14:30
|
◎膜分離の理論
各種膜分離法、
膜材質・膜モジュ
ール特性
|
濃度分極、
透過流束、
阻止率、
物質移動係数
MF, UF, NF, RO
有機膜、
セラミック膜
|
鍋谷浩志(食総研)
大西正俊(森永乳業)
|
|
14:30~14:50
|
休憩
|
|
14:50~16:20
|
透過流束の圧力依存
性濃度依存性
|
| 16:20~17:00 |
実習
Q&A アワー
|
|
8/6 (金)
|
午前
|
9:00~10:30
|
◎膜分離プロセス開
発法、膜による排
水処理
|
HACCP Fluxの確保
滅菌、
殺菌洗浄
膜のメンテナンス
|
原田三郎
(NGKフィルテック)
田辺忠裕
(エコラボ)
|
|
10:30~10:50
|
休憩
|
|
10:50~12:20
|
膜の目詰まりと回復
ファウリング対策
システムの維持管理
|
|
午後
|
12:20~13:20
|
昼 食
|
|
13:20~14:50
|
◎膜分離技術の実例
乳工業・飲料工業
|
チーズホエー
濃縮ジュース
オリゴ糖の分離水飴糖化液の清澄ろ過
減塩醤油
無菌化ろ過
|
重松明典(雪印乳業)
佐藤 武(味の素)
渡辺敦夫(新潟大学)
|
|
14:50~15:10
|
休憩
|
|
15:10~16:40
|
醸造工業
糖質関連工業
|
| 16:40~17:00 |
総合討論
|
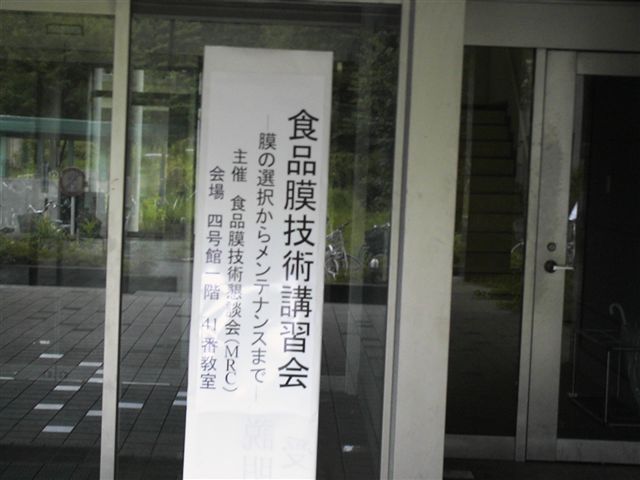

Page Top
2019年1月16, 17日
第11回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/16
(水)
|
10:00~11:00
60分
|
① 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
② 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
ー逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
| 11:00~11:10 |
休憩 |
11:10~12:10
60分 |
③ 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
④ 膜技術の基礎 ― 膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの構造と特性―
|
| 12:10~13:10 |
昼食
(一財)日本食品分析センター紹介と⑫ビデオ講師紹介 |
|
13:10~14:40
90分
|
⑤ 濃度分極と膜ろ過法 |
| 14:40~15:00 |
休憩 |
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー (MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います) |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報が得られます) |
|
1/17
(木)
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
|
渡辺敦夫
|
| 12:00~13:00 |
昼食
⑫ビデオ 研究の進め方 等 |
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備 |
16:00~16:30
30分 |
質問事項記入 & 質疑 (質問がなくなるまで質疑を行います) |
渡辺敦夫:農学博士、 MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
|
MRC第11回 初級者のための食品膜技術講習会(2019年) アンケート集計抜粋
受講者合計17名:昭和化学工業・カゴメ(3名)・クラレ・秋田屋本店(3名)・佐藤食品工業(犬山市)・岩井機械工業・エコラボ(2名)・アサヒホールディング・森永乳業・天野エンザイム・旭化成・江崎グリコ・・・・(アンケート回収数16)
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる1名 ②ちょうど良い時間構成であった13名 ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい2名
充実した時間を過ごせた。来年以降も他の社員に勧めます。程よく休憩を入れて頂き集中できる環境でした。しっかり学習するのであれば2日×2回もしくは2日+アルファーの講義が欲しい。初日の午前中の講義を短く出来るのではないか?
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
意見記入欄 ①たいへん役に立つと思う7名 ②ある程度役に立つ9名
先輩方の書いた論文をしっかり読み、それを超えるために自分に何ができるか考えます。膜の特性など知らなかったことが知識として得ることができた。膜技術の原理原則を理解して膜について考えることが必要と感じた。まだ、ノウハウを持たないレベルでは実践での具体的な情報を得ることができた。食品業界での膜分離に関する基礎・注意点を学べたので食品業界が求める膜の性能を理解したうえで膜開発に取り組めると考えます。膜洗浄・膜選定で製造コスト削減につなげて行きたい。膜の洗浄や透過液の圧力など。今後、膜の選定等の課題に取り組むとき役立つ。社内の技術蓄積の弱さを感じたところであり、今後運転方法についてテストすべき項目を大量に思いついた。お客様の考えられることがイメージできました。処理条件が適当であるか、膜構造や材質も考慮したうえで洗浄条件を適正化できると考えた。関連課題の問題点を解決する手段として膜を検討しており、どの膜を選べば良いかなど参考になった。基礎から応用への展開があって良かった。膜ユーザーが膜をどのように使ってどのような点に問題を抱えているかわかり、今後の膜開発に役立つと思う。膜全体に関する基本的な内容を学ぶことができた。
3.イントロ&受講者自己紹介は役に立ちましたか? ①役に立った16名
意見記入欄 お互いを知れることでその後の交流に役立った。もう少し短い時間でやれるのではないか。
4.交流会は役に立ちましたか? ①役に立った12名
意見記入欄 膜ユーザーがどんな用途に膜を使ってるのか意見を聞けた。膜を使用する側と開発側の意見交換は役に立った。お互いの繋がりに役立ち今後の仕事に役立つ。
5.下記の講義内容は
① 講師紹介および国際情勢・その他 総合学習(我が国の置かれている国際情勢を踏まえ、技術者・研究者のリーダーとしての心構えを講義) ①役に立った11名 ②詳しく知りたい3名、③わかり難かった1名
意見記入欄 先生の考え方が良く分かり興味深かった。社会人として、日本人としてとても為になる話でした。研究者としての心構えまで話をしてもらえるとは思っておらず、ハッとする部分が多くありました。会社の新人として仕事の進め方等の参考になりました。研究員や一人の人間としての考え方が参考になりました。身が引き締まる思いであった。膜とは関係なかったが、詳しく話を聞きたかった。心構えを忘れかけていたので有難かった。内容として大変参考になったが、少々長すぎると感じた。技術者としての創意工夫について参考になったが、国際情勢についてはわからない部分があった。
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎 ①に立った12名、②詳しく知りたい3名、わかり難かった1名
意見記入欄 食品分野で利用される分離技術が分かり勉強になりました。基礎を理解できた。膜以外のクロマトの話も聞けて良かった。プロセス全体を考え目的に合致すれば膜を使うのが良く、何でも膜を使うべきでないことが分かった。用語の説明をしてくれたので講義が分かりやすかった。自分で勉強した上でさらに詳しく知りたいと感じた。
③膜技術と発展の歴史 ①役に立った12名、②詳しく知りたい4名、
意見記入欄 海水淡水化と食品処理での膜技術に求められる技術の違いが理解できた。膜開発の歴史が長いこと、アメリカが進んでいたことが分かった。どの企業がどのように膜を使っているか実例を用いて説明して頂き分かりやすかった。ろ過助剤については知らなかったので良い勉強になりました。どのような課題の中で膜技術が発展してきたかを知ったので、これからの課題解決に役立つと思う。さらに勉強して役立てたい。
④膜の特性とモジュール構造 ①役に立った14名、②詳しく知りたい2名、
意見記入欄 スパイラルモジュール等まだ知らなかった構造を知ることができた。それぞれのモジュール構造の特徴が分かり、今後選定の膜モジュールの選定に役立つと思います(4名)。回転盤型モジュールなどを含めて種々のタイプのモジュールが開発されていることを知ることができた。 今後の洗浄の提案に役立ちます。
⑤濃度分極と膜濾過法 ①役に立った12名、②詳しく知りたい2名、③わかり難かった2名
意見記入欄 真の阻止率に関して意識してなかったのでこれから考慮していきたいと思います。仕組みは理解できましたが、計算についてはついて行けませんでした。原理と数式について理解できました。数式は理解できなかったが、やさしく現象を説明して貰えたので良かったです。もう一度しっかり勉強します。
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (①役に立った13名、②詳しく知りたい3名
意見記入欄 critical fluxの検討を進めていきます。具体的な使用法が参考になりました。運転データーの取り方を参考にモニタリングを進めたい。食品会社における膜モジュールの選別方法について知ることができました。実践に役立つ情報を理解できたので良かった。今後の現地設備確認の役に立つと思いました。ぼんやりと気になっていたこと、わかっていなかったことについて知ることができました。
⑦ファウリング層の基礎的性質 ①役に立った14名、②詳しく知りたい1名、③わかり難かった1名
意見記入欄 社内の膜についても観察を進め、より良い条件を見つけます。内容が難しく量も多くの情報で十分理解できなかったが、重要な課題なので今後しっかり復習します。ダイナミック膜の実例を交えての講義であったのでダイナミック膜について理解することができた。食品系は複雑でありものによって異なった管理を行うことが重要であることが分かった。単一成分での膜の有効性を評価するのでなく実液を用いての評価が重要であることが分かった。ダイナミック膜は有用と感じたので今後研究してみたい。もう一度foulingについて復習してみます。
⑧応用例―その1- ①役に立った12名、②詳しく知りたい2名、③わかり難かった1名
意見記入欄 乳製品業界での実用例とても参考になりました(2名)例が多く消化しきれなかったので復習します。様々の分野で膜が利用されている例を知り勉強になりました。
⑨応用例―その2― ①役に立った11名、②詳しく知りたい3名、③わかり難かった1名
意見記入欄 色々な分野での膜の利用を学べ良かったです(2名)。知識不足の身では応用例が多く理解しきれなかった。製油の精製に膜を利用する試みは知りませんでした。
⑩膜リアクター ①役に立った11名、②詳しく知りたい3名、③わかり難かった1名
意見記入欄 食品膜技術の本を探して購入します。現場で課題になっていたこともあり勉強不足を痛感しました。微生物でも応用範囲があると知り勉強になった。MBRは自分の関連分野であり勉強になりました。排水再利用は興味を持ちました。具体的例示があり参考になりました。排水処理への膜利用はまだ取り組んでいなかったので各工場に情報を伝達したい。ヤオコーにおける遠隔地管理システムなど、膜のビジネスモデルが変わることを実感した。あとでしっかり復習します。
⑪膜の洗浄・殺菌 ①役に立った15名、②詳しく知りたい1名、
意見記入欄 エコラボに相談して改善をはかっていきたいと考えます。膜は洗浄が大切と考えていたので役に立った。膜装置洗浄の基本が学べた。具体的事例があり参考になった(2名)。膜の性質、使用方法をふまえて洗浄方法を検討する重要性が理解できた。膜モジュールの保存方法は膜会社としても参考になった。洗浄方法の最適化等。一番勉強したかったパートです。
⑫ 昼食時のビデオ上映(①役に立った8名、②役に立たなかった3名、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい1名)
⑬その他希望する講義内容
意見記入欄 トラブル事例・改善方法。膜の製法。膜の特徴や種類などについて聞ければありがたい。ダイアフィルトレーションについて詳しく知りたい。実技指導を伴う講義。今回の講義内容を復習したうえでもう一度講義を受けたい。
6.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
意見記入欄 応用例とプロセスについて知ることができました(2名)。ファウリングについての考え方、洗浄法, critical fluxの測定等検討して見るつもりです。基本的な話がとても参考になりました。ファウリング層の基礎的性質。膜モジュールの洗浄と殺菌。酵素でパーシャル分解することで透過性・透過流束が高くなることが参考になりました。ファウランとや洗浄について役立つ情報が得られた。モジュールの構造と特性。膜技術の基礎。膜技術と発展の歴史。膜の特性とモジュール構造。膜導入においては対象によって条件を確立していく必要があることを理解できた。膜は膜屋に任せるのでなく、構造を理解してそれぞれの現象を想像しながら解決策を見つけるべきであることを学ばせていただきました。ファウリングの基礎。応用例(2名)。データーの取り方。
7.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
意見記入欄 今後伸びると思われる植物性ミルクでのアプリケーションはありますか? まずは膜について検討しますが、乾燥についても勉強したいです(2名)。クロマトグラフィー。濃縮技術。排水処理。乳の5倍濃縮する場合の有効な方法について知りたい。UF膜分野。MBR処理技術。NF膜による濃縮技術。膜による無菌化技術。膜の特性。洗浄(2名)。膜以外の分離技術について勉強したいと思った。
8.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
意見記入欄 多くの会社の方と交流ができ良かったです(2名)。グループに分かれてのケーススタディなどあったら良いと思います。非常に情報量が多く当社のレベルからは目からウロコの知見ばかりで、早く入会すればよかったと考えています。30周年記念DVDも購入して初回から文献を読み進めます。他社と情報交換ができ大変刺激になりました(3名)。2日間で学んだ内容を活用し劇的に社内を改善していくつもりです。交流を一つの目的にする研究会の運営が良かったです(3名)。自分の勉強不足なところもあり理解できないことがありましたが、自社で活用できることも多々ありました。休憩も適当にとっていただき講習を集中して受けることができました。今まで自分の狭いジャンルでしか扱ったことがなかったので、今回のような多様な食品への応用や課題について情報を得ることができ、ますます興味がわき更なる可能性があるのではないかと感じました。開催につきご準備いただいた方々にお礼申し上げます。膜の基礎知識を学べたので今後の製造に生かしていきたい。受講者交流において膜洗浄剤を知ることができとても良かったです。こまめに休憩を頂けたので集中して受講できました(3名)。食品業界における膜全般の基礎について幅広く学べた点も良かったです。大変勉強になりました。私の不勉強ですが専門用語がわからず難しかったです。椅子が硬くて、腰が悪いので長時間座りっぱなしでつらかった。

|
|
2018年1月17, 18日
第10回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
|
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/17
(水)
|
10:00~11:00
60分
|
① 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
② 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
ー逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:00~11:10
|
休憩
|
|
11:10~12:10
60分
|
③ 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
④ 膜技術の基礎 ― 膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの構造と特性―
|
|
12:10~13:10
|
昼食
(一財)日本食品分析センター紹介と⑫ビデオ講師紹介
|
|
13:10~14:40
90分
|
⑤ 濃度分極と膜ろ過法
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
⑥
膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~17:00
40分
|
Q&Aアワー (MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います)
|
|
17:00~18:45
|
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報が得られます)
|
|
1/18
(木)
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition) とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食
⑫ビデオ」 研究の進め方 等
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備
|
|
16:00~16:30
30分
|
質問事項記入 & 質疑
|
|
渡辺敦夫:農学博士、 MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
|
|
MRC第10回 初級者のための食品膜技術講習会(2018年) アンケート結果
参加企業:ロキテクノ(株)・キリン(株)・三菱ケミカルアクア・ソリューション(株)・横浜乳業(株)・カゴメ(株)3名・昭和化学工業(株)・宇部興産(株)・高砂香料工業(株)・江崎グリコ(株)・森永乳業(株)・旭化成(株)
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
① 丸2日間では長すぎる1名(集中力が続かなかった) ②ちょうど良い時間構成であった10名
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
①たいへん役に立つと思う10名 ②ある程度役に立つ 3名
3-1 どういう点で役に立つと思いますか?
膜に関する基礎知識が身についた・知っておくべきトピックスについて理解することができた・自身の仕事に関することしか知らなかったがその側面や理論などを学ぶことができた・本当に基礎から応用まで身に着けることができ業務の幅が広がると感じた・膜は初めてだったので知見情報として非常に有用であった・他社事例や社会知識を用いて講義いただけたので社内の問題としてイメージしやすかった・まだ膜を使ったことがないのだが今後使う場合の参考にさせて頂きます・多様な膜を使った方法を吸収できた・現在携わっている以外の分離方法や膜の種類について知ることができた・製品開発のアイデア出しやお客様での課題解決に役立つと思います・膜の選択方法や原理原則が分かった・食品分野の応用例を知ったので参考にしていきたい・実際の仕事(実験)に使えると思った・膜技術だけでなく分離技術の初級レベルの内容について学べた・初級者にとって効率よく膜技術の概要を知ることができました・今後必要に応じて何を調べると良いかという判断に役立つと思います・膜一般についての知見が得られた
4.①-1受講者自己紹介は役に立ちましたか? ①役に立った11名 ②時間の無駄 ③その他2名
自己紹介が交流会の活発化に役立ったと思います3名・バックグランドを知ることは大切・コミュニケーションを取りやすくなった・相手を知る上では役立ったが少し長いと感じた・時間の無駄に近いと感じた
①-2講師紹介とイントロダクションは役に立ちましたか? ①役に立った11名 ②時間の無駄 ③その他2名
膜技術研究の経緯が分かりその後の講義が理解しやすかった・人となりが分かりその後の講義が聞きやすかった・やや長いと感じた・時間の無駄に近いと感じた
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎 ①役に立った9名、②詳しく知りたい2名
擬似移動床クロマトについてもっと知りたい・分画分子量の話が分かりやすかったです・
③膜技術の基礎―膜技術と発展の歴史 ①役に立った11名、②詳しく知りたい2名
食品への膜技術についての紹介が多く非常に勉強になった
④膜技術の基礎―膜の特性とモジュール構造 ①役に立った11名、②詳しく知りたい2名、
モジュールについて特に勉強になった・膜を選択するとき参考になります
⑤濃度分極と膜濾過法 ①役に立った10名、②詳しく知りたい1名、③わかり難かった2名
今回の講義を基に再度勉強します・数学的な話でなかなか短時間では理解しにくかった・大体わかったがついていけない部分があり持ち帰り勉強します
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 ①役に立った11名、②詳しく知りたい2名、
実際に膜を使ったことがないので実際に膜を使うときの参考にさせて頂きます・ 注意すべき点が良くわかりました・詳細に踏み込むと難しい分野だと思いました・
⑦ファウリング層の基礎的性質 ①役に立った10名、②詳しく知りたい3名、
⑧応用例―その1-①役に立った11名、②詳しく知りたい1名、③わかり難かった1名
膜と関連のあるPETボトルの話など幅広く教えて頂き興味深かったです
⑨応用例―その2―①役に立った11名、②詳しく知りたい1名、③わかり難かった1名
現在の課題につながると思いました・
⑩膜リアクター ①役に立った10名、②詳しく知りたい2名、
⑪膜の洗浄 ①役に立った11名、②詳しく知りたい2名、
洗浄液は残留しないのか気になりました・非常に勉強になりました・概要を理解できた・洗浄剤洗浄方法の参考になりました
⑫ 昼食時のビデオ上映 ①役に立った9名、②役に立たなかった、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい2名
参加メンバーと話をしたいため見ていなかった・東レのビデオが分かりやすかった・超臨界流体の話が興味深かった・ 周囲の人と話をしており見ていなかった(2名)・東レのビデオは膜の構造が分かりやすく講習会の前半で上映して頂けるとより有効だと考えます
その他希望する講義内容
クロスフローの使用例は多く学べたがデッドエンドの使用用途の詳細を知りたい・ 膜と膜以外のプロセスで分離を行った際のデーター比較・プラント設計に得意な業者を教えてほしい
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか?
膜技術の基礎―膜特性とモジュール構造、応用例が役立ちました・応用例・具体的利用例・ 膜の特性とモジュール構造・ ファウリング層の基礎的性質(2名)・膜の洗浄・装置の組み立て方・膜の選択方法・ファウリング層における目詰まりについて・他企業の製造工程図は興味深かった・モジュール内の圧力損失を均一化する方法・ 応用例①②・膜の洗浄・装置の組み立て方と運データーの取り方
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか?
無菌化沪過・ 分離技術の近年のトレンド・先端技術の紹介・廃棄物の有効な再利用例があると有り難いです・風味、香りの分離に興味を持っています・
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
今回の講義内容を再度文献調査しさらに詳しく理解できるように今後学んでいきます・2日より長くなると参加させてもらえなくなってしまう可能性があるがもっと詳しく学びたいと思った・沪過助剤、食品分野、膜メーカーなど異業種の人と交流情報が得られ新しい製品作りに生かせると感じた・膜関連について学べる非常によい時間になりました。ありがとうございました・基礎的な原理から応用まで幅広く知ることができとても勉強になりました・今まで社内では経験則のような所もありましたが、理論があることが分かりました・全体を通して先生のご経験をもとにお話しいただきましたので、非常に興味深く、活きた内容を知ることができ良かったです・休憩は90分に1度程度入れて頂きたいと感じました(3名)・乳製品への応用例は全く知識がなかったので大変面白かった・受講生同士の交流ができ、他の業界の状況が分かり良かった・渡辺先生が後輩を育成すべく視点を広く持つための雑学を教えて頂きながらの講義が良かったです・交流会を設定して頂けたのは良かったです・全員に自己紹介の時間を取ったので終了の時間が遅くなってしまったので、できれば交流会の前の質問を2日目に回し早めに切り上げてもらうと嬉しいです・事前にPDFの資料を配布し、印刷して持って来る人、あるいはコンピューターで受講する人と選択できると良いと思います(2名)・交流会は良かったです(3名)・初級者にとってハードルが高い理論式についてやさしく説明して頂き膜分離の評価ポイントについて概要を理解できました・質問の時間を多くとっていただけたことが良かったです(2名)・ 基礎的な部分(膜特性や基礎理論)をもっと厚くしてもらうと有り難いです・
|
| |
|
|
|
2017年1月18, 19日
第9回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/18
(水)
|
10:00~11:00
60分
|
① 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
② 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
ー逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
| 11:00~11:10 |
休憩 |
11:10~12:10
60分 |
③ 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
④ 膜技術の基礎 ― 膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの構造と特性―
|
| 12:10~13:10 |
昼食
(一財)日本食品分析センター紹介と⑫ビデオ講師紹介 |
|
13:10~14:40
90分
|
⑤ 濃度分極と膜ろ過法 |
| 14:40~15:00 |
休憩 |
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー (MRC役員が出席し専門的な質疑ができます。
質問がなくなるまで質疑を行います) |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報が得られます) |
|
1/19
(木)
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
|
渡辺敦夫
|
| 12:00~13:00 |
昼食
⑫ビデオ」 研究の進め方 等 |
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備 |
16:00~16:30
30分 |
質問事項記入 & 質疑(質問がなくなるまで質疑を行います) |
渡辺敦夫:農学博士、 MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
|
MRC第9回 初級者のための食品膜技術講習会(2017年) アンケート結果(抜粋)
回答者9名((株)明治・雪印メグミルク(株)・帝人(株)・ダイセンメンブレン(株)・カネカ(株)・エコラボ(合)・日油(株)・日本クリニック(株)・東洋ろ紙(株))
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(9名) ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい
①2日程度で良いと思うが,講義内容が濃いので時間は足りないと思いました
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う(8名) ②ある程度役に立つ(1名) ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
①いろいろな膜の種類や処理方法が紹介されていたので、今後比較をして行きたいと思います② 膜について基礎から学ぶことができた③膜開発する際のファウリング評価など大変参考になった④技術者の心構えも参考になった⑤ ファウリングの抑制や洗浄法の最適化⑥ 膜技術の基礎が理解できた。⑦膜技術の基本を学ぶことができお客様と同じ目線で話すことで理解度が増すと思います⑧工業的な実例と注意点が分かった⑨現在行っている研究に反映できる内容があった点
3.受講者自己紹介等イントロダクションは役に立ちましたか? (①役に立った(9名) ②時間の無駄 ③その他)
①交流会でいろいろ情報交換ができた② 参加者のことが分かってその後の交流に役立った(2名)③もう少し時間を短くした方が良いと感じました
4.下記の講義内容は
① 膜技術の総合学習 (①役に立った(9名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった)
①技術者としてやるべきことを学んだ②入社後ある程度時間がたつと誰もこのようなことを言ってくれないので良かった③ 膜分離技術は分離技術の一つの分離技術であり、他の方法で分離ができるならその方法を利用するべきであるとの話は参考になった
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、わかり難かった)
①食品については知らないことが多く興味深かった②食品の加工工程を知り開発を進めるために役に立った③膜分離の基礎から教えて頂けたのでとても良かった④ 膜以外の技術についても話を聞きたかった
③膜技術と発展の歴史 (①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
①技術の発展は先人の失敗成功により成り立つことを知り今後の仕事に役立つ②沪過助剤の話はためになりました
④膜の特性とモジュール構造 (①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
①現在膜モジュールの選定を行っており参考になった ②膜の基本を知ることができた
⑤濃度分極と膜濾過法 (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった(1名))
①初心者にも分かり易かった②数式が分からなかった③優しく解説して頂き分かり易かった
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (①役に立った(8名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
①今後の装置設計とデーター取りが重要であることが分かった② critical flux などの基礎事項が理解できた
⑦ファウリング層の基礎的性質 (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった(1名))
①膜分離における最も重要なファクターはファウリングであることが分かった②ファウリングの分類など幅広く解読いただき分かり易かった
⑧応用例―その1-(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
①実際に膜を使った時に出た課題をどう解決したかなどの話があると良い
⑨応用例―その2―(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
①本を買って更に勉強します
⑩膜リアクター (①役に立った(8名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった(1名))
①本を買って更に勉強します②膜の使われ方についてもう少し聞きたかった
⑪膜の洗浄 (①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった)
①内容は役に立ったが資料の字が白抜きでスライドも見難く印刷も見えない(3名)②実用のためには洗浄が重要なことが良く分かった③個人的にはもっと勉強したい
⑫ 昼食時のビデオ上映(①役に立った(9名)、②役に立たなかった、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい)
①基礎および応用に関してよくわかった(2名)②昼ではなく時間を取ってじっくり見たいと思いました
⑬ その他希望する講義内容
①膜と他の処理法との比較・コスト・設置スペース・濃縮倍率②自分で考える時間(演習問題など)③膜装置設計会社に関する情報も提供して欲しい④膜技術で使われる用語とその意味⑤膜技術の理論についても聞きたい
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか(回答例;ファウリング層の基礎的性質)
①膜の洗浄と実用化例(4名)② ファウリング層の基礎的性質が役に立った(6名)③膜特性とモジュールの構造 ④膜技術と発展の歴史⑤膜関連科学の基礎⑤装置の組み立てと運転データーの取り方⑤ファウリング層の基礎的性質
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;乾燥技術・濃縮技術)
①凍結乾燥技術②液クロを利用した食品分離技術③ 蛋白質の濃縮について聞きたい④ 乳の濃縮技術⑤濃縮技術
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
①食品業界で用いられる分離技術が良く分かり興味深かった②MRC役員によるQ&Aアワーと交流会で他業界の話が分かり良かった③膜技術の資料が豊富なためインデックスが付いていると良い④企業での研究開発と学術研究の違いをお話しいただき参考になった ⑤自国の歴史的背景も踏まえた上で自身・自社の研究開発が社会にどのように影響するか考えていきたい⑥膜理論から応用・実用例まで勉強できた⑦他社と交流できたことが良かった(2名)⑧工場見学の機会があればよいと思います⑨研究レベルで止まってしまったプロセスや実用化できなかった理由などが聞けて大変勉強になりました⑩どのようなデーターを取り検討をすればよいか参考になった⑪応用例より基礎事項を知りたかった⑫質問しやすい雰囲気が良かったです(2名)
|
第9回MRC初級者のための食品膜技術講習会の記事が月刊食品工場長3月号に掲載されました。
画面をクリックすればPDFファイルが開きます。
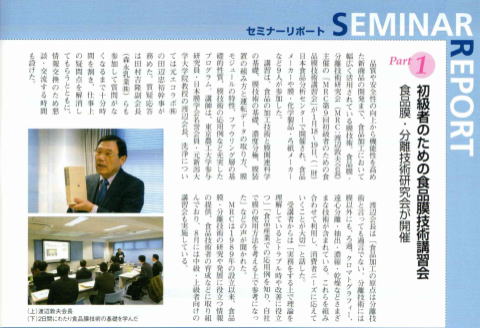 |
2016年1月20, 21日
第8回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/20
(水)
|
10:00~11:00
60分
|
① 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
② 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
ー逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
| 11:00~11:10 |
休憩 |
11:10~12:10
60分 |
③ 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
④ 膜技術の基礎 ― 膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの構造と特性―
|
| 12:10~13:10 |
昼食
(一財)日本食品分析センター紹介と⑫講師紹介 |
|
13:10~14:40
90分
|
⑤ 濃度分極と膜ろ過法 |
| 14:40~15:00 |
休憩 |
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー (MRC役員が出席し専門的な質疑ができます) |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報が得られます) |
|
1/21
(木)
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
|
渡辺敦夫
|
| 12:00~13:00 |
昼食
⑫ビデオ」 研究の進め方 等 |
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備 |
16:00~16:30
30分 |
質問事項記入 & 質疑 |
|
渡辺敦夫:農学博士、 MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
|
MRC第8回 初級者のための食品膜技術講習会(2016年) アンケート回答
受講者: (株)明治(2名)・カゴメ(株)(2名)・森永乳業(1名)・東レ(株)(1名)・高砂香料(株)(2名)・(株)クラレ(1名)・エコラボ(合)(1名)・サントリ―関連会社(1名)・イビデン(株)(1名)
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(9名) ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい(1名)3日にして貴重な話をもっとゆっくり聞きたいと思います。 ④1日だと出席し易い(1名)
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
①たいへん役に立つと思う(8名) ②ある程度役に立つ(4名)
◎役に立った点 ①基本から実例まで学び役に立つ。②実務をする上で理論を理解しているとトラブル時や改善に役立つ。③膜メーカーの立場でなくフラットな立場での講習会で、幅広い知見が得られた。④食品産業での応用例を知ったので自社で膜の使用方法を考えるうえで参考になる。⑤基礎的で幅広い内容の知識を得ることができた。⑥製造現場での長期運用、安定生産に役立つ。⑦研究開発からのスケールアップに役立つ。⑧膜利用の実際例、膜の選択法、洗浄例が学べた。⑨他社との繋がりができた(2名)。⑩基礎知識の整理ができた(2名)。
3.受講者自己紹介等イントロダクションは役に立ちましたか? (①役に立った(10名) ②時間の無駄 ③その他(2名)
①交流会の時、人となりが分かり話やすかった(6名) ②なくても良い。③イントロはもう少し短くても良い。
4.下記の講義内容は役に立ちましたか?
① 膜技術の総合学習 (①役に立った(12名) ②詳しく知りたい、③わかり難かった
①研究に対しての気持ちがより熱くなった。②研究への心構えに共感しました。③
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎(①役に立った(11名)、②詳しく知りたい(1名)、)
③膜技術と発展の歴史 (①役に立った(11名))②詳しく知りたい(1名)
①3Aスタンダード、サニタリー基準等が役に立った
④膜の特性とモジュール構造 (①役に立った(12名)、②詳しく知りたい(2名))
⑤濃度分極と膜濾過法 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(2名))
①数式の理解が難しかった。②濃度分極現象については理解できた。
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(2名))
①実際に実験を行うに当たり必要なポイントが良く分かった(2名)。②膜の選び方の勉強になった。
⑦ファウリング層の基礎的性質 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(2名))
①様々なファウリング対策を勉強できた。
⑧応用例―その1-(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった(1名)
①文字ばかりのスライドで分かりにくかった。②他業種での膜の使われ方がわかり良かった。
⑨応用例―その2―(①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(1名))
①もっと詳しい話を聞きたい。
⑩膜リアクター (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい(3名))
①膜乳化・強制透過化型リアクターについて詳しく知りたい。
⑪膜の洗浄 (①役に立った(9名)、②詳しく知りたい(3名))
①実際にどのような方法で洗えばよいかが分かった。②基本的な勉強ができて良かった。③いろいろな洗剤の特徴が分かった
⑫ 昼食時のビデオ上映(①役に立った(9名)、
その他希望する講義内容
①設備の導入、設計に関して聞きたい。②海外と日本での応用例の違い等について紹介して頂きたい
4.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか?
①応用例。②ファウリング層の基礎的性質(4名)。③装置の組み立て方と運転データーの取りかた。④膜の特性とモジュール構成(2名)。⑤膜・モジュールの洗浄(2名)。⑥濃度分極等分かり易く話してもらい理解できた。⑦食品業界で膜がどのように使われどのように使われなくなったか知ることができた。
5.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか?
①乾燥技術 ②濃縮技術(2名) ③遠心分離 ④機能性成分の分離・抽出・精製 ④
6.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
①他業種との交流ができ良かった。②広範囲の知識をポイントを押さえて網羅的に得ることができた(2名)。③乳業関係の情報が多かったので他分野の話も入れて欲しい。④休憩時間が少なくきつかった。⑤先生の経験を取り入れた説明が理解し易く感じた。⑥資料がカラーであると分かり易い(回答・値段的に無理です)。⑦膜メーカー側の情報があると良い 。⑧実用例の説明があり具体的でよかったと思います。⑨膜全体の勉強をしたかったので受講して良かった。⑩受講者数が多すぎず交流を深めるという点で良かった。
|
| 第7回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
1.日時:2015年1月21日(水)、22日(木) (2日間)
○ 21日 講義; 10時00分より17時00分講義終了後 情報交換・交流会
○ 22日 講義; 10時00分より16時30分まで
2.場所:(一財)日本食品分析センター
新宿駅より小田急線:代々木八幡駅 下車 徒歩5分、あるいは
地下鉄千代田線: 代々木公園駅 下車 代々木上原寄り出口 徒歩5分)
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
TEL 03-3469-7131
|
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/23
(木)
|
10:00~11:00
60分
|
① 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
② 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
-逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
| 11:00~11:10 |
休憩 |
11:10~12:10
60分 |
③ 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
④ 膜技術の基礎 ― 膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの構造と特性―
|
| 12:10~13:10 |
昼食
(一財)日本食品分析センター紹介と⑫講師紹介 |
|
13:10~14:40
90分
|
⑤ 濃度分極と膜ろ過法 |
| 14:40~15:00 |
休憩 |
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報が得られます) |
|
1/24
(金)
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
|
渡辺敦夫
|
| 12:00~13:00 |
昼食
⑫講師 研究の進め方 履歴等 |
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備 |
16:00~16:30
30分 |
質問事項記入 & Q&Aアワー |
|
渡辺敦夫: MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
MRC第7回 初級者のための食品膜技術講習会(2015年)
アンケート回答(回答者11名)
|
| 参加者:サントリ―関連会社(3名)・雪印メグミルク(2名)・明治・キリン・日本錬水・木村化工機・TYK・不二製油 |
|
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか?
① 丸2日間では長すぎる ②ちょうど良い時間構成であった(10名) ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい(1名) (どの程度の日数を希望しますか? ①9時から17時30分に時間を延ばしてほしい
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか?
①たいへん役に立つと思う(9名) ②ある程度役に立つ(2名) ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
◎役に立った点 ①ラボでの実験のやり方実導入の仕方。②膜の実験を行っているが、今までの実験例を理論的に考えられ、データの取り方に役立つ。モチベーションが上がった。③膜の基本的知識や実用例を知ることができ今後の研究開発に役立つ。④今後の研究開発のアイデアがたくさんあった。⑤実用例とそれを示す理論。⑥今後の膜研究の基礎に役立ち興味が広がった(3名)。⑦洗浄の知識と応用例が役立った。
3.受講者自己紹介等イントロダクションは役に立ちましたか? (①役に立った(10名) ②時間の無駄(1名) ③その他)
①参加者の興味・人柄等が分かり親近感を持てた。(3名)②名前と顔が分かり良かった(2名)。③交流会で話やすかった
4.下記の講義内容は役に立ちましたか?
① 膜技術の総合学習 (①役に立った(9名) ②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった(1名)
①研究に対しての気持ちがより熱くなった。②研究への心構えに共感しました。③
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎(①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(1名)、)
①基本が良く分かった(2名)②後半重複するスライドがあったが復習になった。
③膜技術と発展の歴史 (①役に立った(11名))
①膜技術に残された問題、将来の膜技術についても触れて頂けると良い
④膜の特性とモジュール構造 (①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(6名))
①構造や作り方について知らないことが多かったので勉強になった(2名)
⑤濃度分極と膜濾過法 (①役に立った(6名)、②詳しく知りたい(5名))
①真の阻止率の求め方については自習します。②濃度分極について良く分かった。
⑥装置の組み方と運転データの取り方 (①役に立った(9名)、②詳しく知りたい(2名))
①実際に実験を行うに当たり必要なポイントが良く分かった(2名)。②膜の選び方の勉強になった。
⑦ファウリング層の基礎的性質 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(1名))
①様々なファウリング対策を勉強できた。
⑧応用例―その1-(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい(1名)、③わかり難かった(1名)
①文字ばかりのスライドで分かりにくかった。②他業種での膜の使われ方がわかり良かった。
⑨応用例―その2―(①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(1名))
①もっと詳しい話を聞きたい。
⑩膜リアクター (①役に立った(6名)、②詳しく知りたい(3名))
①膜乳化・強制透過化型リアクターについて詳しく知りたい。
⑪膜の洗浄 (①役に立った(5名)、②詳しく知りたい(3名))
①実際にどのような方法で洗えばよいかが分かった。②基本的な勉強ができて良かった。③いろいろな洗剤の特徴が分かった
⑫ 昼食時のビデオ上映(①役に立った(9名)、②役に立たなかった(1名))
その他希望する講義内容
①設備の導入、設計に関して聞きたい。②海外と日本での応用例の違い等について紹介して頂きたい
4.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか?
①応用例。②ファウリング層の基礎的性質・膜の洗浄・ケーク層の原因や対処法について知ることができた(2名)。③膜の構造や特性・使用例の注意等の基礎が良く分かった。④limiting fluxとcritical flux。⑤fouling、濃度分極・物質移動の考え方。
5.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか?
①濃縮・吸着など ②濃縮技術(3名)③実際のデータの取り方を詳しく知りたい。
6.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
①初日の質問時間をもっと長くして貰いたかった。②講義後に追加で質問できるようにしてほしい。③他業種の方と話ができ、交流会は有益であった(2名)。④質問の時間に専門の方が多く参加され、いろいろな回答を頂いたので良かった。⑤実際の食品工場での膜の利用例について講義と参加者から聞くことができ良かった。⑥膜理論も学ぶきっかけになりました。⑦ 質問もしやすい環境でしっかり勉強できました。⑧基本的なことをしっかり教えて頂き、しっかりと膜について理解することができました。⑨2日目は9時30分から講義を開始してもらえると良い。⑩交流会は多くの会社の方々と話ができ良かった。⑪膜の選定法や実験装置の組み方など。⑫初心者だったが今後の検討課題や方向性が分かった |
| 第6回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
1.日時:2014年1月23日(木)、24日(金) (2日間)
23日 講義; 10時00分より17時00分講義終了後 情報交換・交流会
24日 講義; 10時00分より16時30分まで
2.場所:(一財)日本食品分析センター
新宿駅より小田急線:代々木八幡駅 下車 徒歩5分、あるいは
地下鉄千代田線: 代々木公園駅 下車 代々木上原寄り出口 徒歩5分)
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
TEL 03-3469-7131
|
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/23
(木)
|
10:00~11:00
60分
|
① 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
② 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
-逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
| 11:00~11:10 |
休憩 |
11:10~12:10
60分 |
③ 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
④ 濃度分極と膜濾過―真の阻止率・見かけの阻止率、物質移動係数
|
| 12:10~13:10 |
昼食
(一財)日本食品分析センター紹介と⑫講師紹介 |
|
13:10~14:40
90分
|
⑤ 膜の種類とモジュール構造
―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの特性―
|
| 14:40~15:00 |
休憩 |
|
15:00~16:10
70分
|
⑥ 膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
16:20~17:00
40分 |
Q&Aアワー |
| 17:00~18:45 |
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報が得られます) |
|
1/24
(金)
|
10:00~12:00
120分
|
⑦ ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
|
渡辺敦夫
|
| 12:00~13:00 |
昼食
⑫講師 研究の進め方履歴等 |
|
|
13:00~14:00
60分
|
⑪ 膜モジュールの洗浄
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
⑧ 膜技術の応用例―その1―
(1) 無菌化濾過による食品の製造
(2) ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
| 15:00~15:15 |
休憩 |
15:15~16:00
45分 |
⑨ 膜技術の応用例―その2―
(1) 飲料工業への膜利用
(2) 醸造工業への膜利用
(3) 水産工業への膜利用
(4) 食品分野以外への膜利用
⑩ メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備 |
16:00~16:30
30分 |
質問事項記入 & Q&Aアワー |
|
渡辺敦夫: MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
|
MRC第6回初級者のための食品膜技術講習会(2014年)
アンケート 集計・抜粋(回答者11名)
参加企業名
サントリー食品インターナショナル(2名),よつ葉牛乳、昭和化学工業、サンエイ糖化、森永乳業、ロキテクノ、半田研究所、佐藤食品工業、クラレ、キリンビール、日本澱粉工業
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
①ちょうど良い時間構成であった(8名) ②もっと講義を聞きたいので長くして欲しい(1名) ③ 丸2日間では長すぎる(2名)
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う(8名) ②ある程度役に立つ(3名) ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
①営業で技術の話をするときに役立つ ②膜分離・システムの理解に役立った ③膜の開発・評価に役立つ ④膜の基本から応用例まで話を聞けたのでイメージしやすく役に立つと思う ⑤製造ラインの増設を考えているが、膜の選定、基礎実験二役立つ ⑥講習を受け、現在の業務に対するアイデアと改善案など今後の技術開発に役立ちそうなひらめきを受けた ⑦ファウリングを起こさない運転条件、洗浄条件はすぐに役立つと感じた ⑧新技術の開発や改良に役立つ
3.下記の講義内容は
①イントロダクション (①役に立った(8名) ②詳しく知りたい(1名) ③わかり難かった(1名)
①先生や参加者の人柄がわかり交流会で話しやすかった
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎(①役に立った(9名)、②詳しく知りたい、わかり難かった)
①インスタントコーヒーなどの身近なものの製造工程等を例に話をしてくれたので分かり易かった
③膜技術の基礎 (①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
①基礎が良くわかりました ②非対称構造膜の機能が良くわかった
④濃度分極と膜濾過法 (①役に立った(7名)、②詳しく知りたい(2名)③わかり難かった(1名)
①数式が入り少しわかりにくかったが、分かり易い説明であったので理解が深まった(2名)②濃度分極の概要がわかった ③内容が複雑なのでもう少し時間を取ってくれると良い ④濾過の概念から離れられないので、分離膜の機能の理解が難しい
⑤膜の種類とモジュール構造 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい、③わかり難かった)
①膜モジュールの特徴がわかった
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (①役に立った(10名)、②詳しく知りたい(2名)、③わかり難かった)
①ファウリングを起こさない条件の決め方は具体的であり実践してみたい ②今後の膜設備導入時に役に立つ ③過去の評価で抜けていた点を気づかされた
⑦ファウリング層の基礎的性質 (①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(4名)、③わかり難かった)
①実際の運転で役立つところなのでもっと詳しく知りたい ②付着層と目詰まりの測定法について詳しく知りたい ③過去にどういう問題がありどのような対応を取ったか教えてほしい
⑧応用例―その1-(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった(1名)
①先行事例として参考になる ②例が多く興味深かった
⑨応用例―その2―(①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった)
①他社・他業種の話を聞く機会がなかったので参考になりました ②例が多く参考になりました
⑩膜リアクター (①役に立った(8名)、②詳しく知りたい(4名)、③わかり難かった)
①聞いたことのない技術だったので興味深かった(3名)
⑪膜の洗浄 (①役に立った(9名)、②詳しく知りたい(3名)、③わかり難かった)
①膜モジュールの洗浄法についてもっと知りたい(2名)
⑫ 昼食時のビデオ上映(①役に立った(8名)、②役に立たなかった(1名)、③ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい)
4.その他希望する講義内容
①最新の膜の開発状況 ②膜のライフの評価方法 ③実際に問題点を解決した解決方法等 ④実際の設備導入手順 ⑤スケールアップの手順と方法 ⑥製膜方法・乾燥方法 ⑦膜の材質選定方法について詳しく知りたい
5.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
①食品の加工技術と膜関連科学の基礎( ②ファウリング対策と洗浄(2名) ③濃度分極と膜技術の基礎(2名)④膜装置の組み方と運転データーの取り方
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
①膜分離の簡易的実験法 ②濾過全般 ③除菌技術 ④食品改質技術 ⑤ファウリング ⑥メーカー別膜の特徴 ⑦濃縮技術 ⑧乾燥技術
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想を述べてください
①ある程度基礎知識があったので良く理解することができた ②交流会はいろいろな業種の人と交流でき良かった(4名) ③休憩を適当に入れて貰えてよかった ③応用例をたくさん紹介してくれたので参考になった ④交流会に膜会社の人が参加してくれると良かった ⑤自己紹介・交流会非常に良かったです(2名) ⑥たくさんの経験談(雑談)が楽しく、講義に集中できました(2名) ⑦会社を跨いだ横のつながりが大切であることがわかった ⑧膜はもちろんそれ以外の多くのことが吸収できた ⑨食品業界の膜利用の状況が良く理解できた ⑩実際に利用している人とも話ができ役に立った ⑪実例を交えながら説明してくれたのでとても分かり易かった ⑫雑談が面白く楽しみながら勉強できました ⑬2日間楽しく勉強ができました。ありがとうございました(2名)
|
| 第5回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 |
|
|
1.日時:2013年1月23日(水)、24日(木) (2日間)
- 23日 講義; 10時00分より17時00分講義終了後 情報交換・交流会
- 24日 講義; 10時00分より16時30分まで
2.場所:(財)日本食品分析センター
- 新宿駅より小田急線:代々木八幡駅 下車 徒歩5分、あるいは
- 地下鉄千代田線: 代々木公園駅 下車 代々木上原寄り出口 徒歩5分)
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
TEL 03-3469-7131
|
| 第5回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/23
(水)
|
10:00~11:00
60分
|
第1部 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
-逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:00~11:10
|
休憩
|
|
11:10~12:10
60分
|
3. 膜技術の基礎 ―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)―
4. 濃度分極と膜濾過―真の阻止率・見かけの阻止率、物質移動係数
|
|
12:10~13:10
|
昼食
|
|
13:10~14:40
90分
|
5. 膜の種類とモジュール構造
―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの特性―
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
6. 膜装置の組み方と運転データの取り方 ―線速・圧力・温度の影響、limiting
fluxとcritical flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~17:00
40分
|
Q&Aアワー
|
|
17:00~18:45
|
情報交換・交流会(MRC役員が多く出席され豊富な情報得られます)
|
|
|
|
1/24
(木)
|
10:00~12:00
120分
|
7. ファウリング層の基礎的性質 ―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
―MRCニュース目次紹介―
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食
|
|
13:00~14:00
60分
|
(1) 膜装置の洗浄の実際
(2) 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
8. 膜技術の応用の実際
8.1. 無菌化濾過による食品の製造
8.2. ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
8.3. 飲料工業への膜利用
8.4. 醸造工業への膜利用
8.5. 水産工業への膜利用
8.6. 食品分野以外への膜利用
9. メンブレンバイオリアクター ―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備
―食品産業における膜技術用語集―
|
|
16:00~16:10
|
質問事項記入
|
|
16:10~16:30
20分
|
Q&Aアワー
|
渡辺敦夫: MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
|
MRC第5回初級者のための食品膜技術講習会(2013年) アンケート
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
① 丸2日間では長すぎる0名 ②ちょうど良い時間構成であった 18名 ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい1名 (2日の講義を2回)
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う11名 ②ある程度役に立つ 9名 ③余り役立たない ④全く役立たないだろう
どういう点で役に立つと思いますか
①会社の業務で膜を用いているが、膜の経験がなかったので話についていけなかった。しかし、今回の講習で理解が進んだので話についていける。
②膜に関しては新人なので知らないことが多かったが、今回の講習でかなりはっきりわかってきた。
③ゼロベースで活動を始めたので大変勉強になりました。
④食品工学の総合的な観点で理解することが出来た。
⑤膜の洗浄方法でデータの取り方。2名
⑥お客様と会話するとき更に深い意見交換ができると思います。
⑦濃度分極式の導出や係数の取り方などを知りたいので夏の講習会ではぜひ取り上げてください。
⑧運転データの取り方など、実用例も詳しく知りたいです。
⑨専門的な内容なのでなかなか勉強する機会がなかったが、集中的に学べて役に立った。
⑩お客様の問い合わせに対し、今までより説明しやすくなると思います。
3.下記の講義内容で①役に立った、②さらに詳しく知りたい、③わかり難かった、に印をつけてください。④その他の意見の方は意見を記入ください。
①イントロダクション (役に立った17名、 詳しく知りたい、わかり難かった2名、
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎(役に立った17名、詳しく知りたい1名、わかり難かった1名その他1名
③膜技術の基礎 (役に立った18名、わかり難かった点、詳しく知りたい2名、
④濃度分極と膜濾過法 (役に立った12名、詳しく知りたい2名、わかり難かった6名、その他(濃度分極式が理解できなかった )
⑤膜の種類とモジュール構造 (役に立った18名、詳しく知りたい2名、わかり難かった、その他 )
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (役に立った16名、詳しく知りたい3名、わかり難かった①、その他 )
⑦ファウリング層の基礎的性質 (役に立った15名、詳しく知りたい3名、わかり難かった①、その他 ① )
⑧応用例―その1-(役に立った19名、詳しく知りたい①、わかり難かった、
⑨応用例―その2―(役に立った17名、詳しく知りたい①、わかり難かった①、その他①
⑩膜リアクター (役に立った17名、詳しく知りたい①、わかり難かった②、その他② )
⑪膜の洗浄 (役に立った17名、詳しく知りたい3名、わかり難かった、その他 )
⑫ 昼食時のビデオ上映(役に立った15名、役に立たなかった①、ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい1名、その他③①興味深かったです。
⑫その他希望する講義内容(例えば;プロセス設計を詳しく聞きたい) ①UF膜について詳しく知りたい
4.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか(回答例;ファウリング層の基礎的性質)
①食品加工への膜技術の運転条件等の応用例
②濃度分極と膜ろ過法
③ファウリング層と洗浄
④食品の加工技術と膜関連科学の基礎
⑤実務的装置例や計算式はやや難易度が高かったが、今後に役立つと感じました。
⑥膜の基礎知識・洗浄の知識はこれからの研究開発に役立つと思います。
⑦装置の組み方と運転データの取り方。
⑧膜の洗浄。2名
⑨膜技術の応用―その2―
⑩濃度分極
⑪初めて参加であったので全てが役に立った。
⑫膜技術の基礎・膜の種類とモジュール構造・食品の加工技術の基礎
⑬いろいろな業界の例があったのでわかり易かったです。
5.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;乾燥技術)
①抽出技術
②膜の性質についてもっと知りたい。
③耐熱膜について
④膜利用の濃縮技術 2名
⑤ナノろ過技術による食品の改質
⑥濃縮・乾燥技術 2名
⑦UF・NFを知りたい
⑧晶析・膜以外の濾過法・固液分離技術
⑨殺菌技術や充填技術
6.食品加工技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;殺菌技術)
①フレーバーと旨味に関する技術
②洗浄技術
③殺菌 2名
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
①会社での開発業務に生かしていきたい。
②わかりやすかった。
③文系出身で膜に携わって日も浅いので内容が理解できない点もあった。
④1時間の講義の後、5分程度の休憩を入れてほしい。
⑤休憩の回数を増やしてほしい
⑥膜技術の基礎・応用、洗浄技術について学ぶことができ有難うございました。今回学んだことをこれからの研究開発に生かしていきたいと思います。
⑦交流会では有意義な交流ができ、良い機会を頂けたことに感謝致します。
⑧膜の洗浄についての基礎が良く分かった。
⑨今回の講習で学んだことを今後の膜利用の実務に生かしていきたいと思います。
⑩大変勉強になりました。いつも『食品膜技術』の本を読んでおりますが、新しい知見をたくさん得られました。夏も参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
⑪今回の研修会に出席して、膜について新しい知識を身につけることができました。ありがとうございました。
⑫営業を担当していますが、やや難しいと感じました。
⑬基礎とはいえ、十分中身の濃い内容でした。
⑭非常に中身が濃く、消化しきれませんでした。今後も勉強させていただきたいと思います。ありがとうございました。
⑮業界の動向の話ももう少し多めにして頂ければと思いました。専門用語も解説がありわかり易かった。濾過のメカニズムも身近なものに例えて説明してくれたのでわかり易かった。
⑯初心者にもわかり易かった。
⑰昼食休みのビデオ上映は時間を有効に使えてよかった。会社でも昼休みを使って学習時間にあてたら良いです。先生がたくさんの事例や固有名詞を上げられ講義頂いて関心がより高まりました。
⑱内容が難しく90分くらいで休憩を入れていただけると集中力が持続すると思います。知らない業界の事例がたくさんあったのでイメージし易く理解できました。
⑲受講者同士の交流ができ、どのような感度で膜を他の業界の方が使っておられるかわかり、大変面白かったです。
|
|
1.日時:2012年1月18日(水)、19日(木) (2日間)
- 18日 講義; 10時00分より16時55分講義終了後 情報交換・交流会
- 19日 講義; 10時00分より16時30分まで
2.場所:(財)日本食品分析センター
- 新宿駅より小田急線:代々木八幡駅 下車 徒歩5分、あるいは
- 地下鉄千代田線: 代々木公園駅 下車 代々木上原寄り出口 徒歩5分)
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
TEL 03-3469-7131
|
| 第4回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/18
(水)
|
10:00~11:00
60分
|
第1部 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
-逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:00~11:10
|
休憩
|
|
11:10~12:10
60分
|
3. 膜技術の基礎―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)
4. 濃度分極と膜濾過―真の阻止率・見かけの阻止率、物質移動係数
|
|
12:10~13:10
|
昼食
|
|
13:10~14:40
90分
|
5. 膜の種類とモジュール構造
―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの特性―
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
6. 膜装置の組み方と運転データの取り方―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical
flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~16:55
35分
|
Q&Aアワー
|
|
17:00~18:45
|
情報交換・交流会 (MRC役員が多く出席され豊富な情報得られます)
|
|
|
|
1/19
(木)
|
10:00~12:00
120分
|
7. ファウリング層の基礎的性質―透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition)
とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束
―MRCニュース目次紹介―
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食
|
|
13:00~14:00
60分
|
7.2. 膜装置の洗浄の実際
7.3. 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
8. 膜技術の応用の実際
8.1. 無菌化濾過による食品の製造
8.2. ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
8.3. 飲料工業への膜利用
8.4. 醸造工業への膜利用
8.5. 水産工業への膜利用
8.6. 食品分野以外への膜利用
9. メンブレンバイオリアクター
―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備
―食品産業における膜技術用語集―
|
|
16:00~16:10
|
質問事項記入
|
|
16:10~16:30
20分
|
Q&Aアワー
|
渡辺敦夫: MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
MRCの人材育成事業の一環として、『第4回MRC・初級者のための食品膜技術講習会』を開催致します。是非、御社の入社間もない技術者・研究者あるいはこれから新たに膜技術の研究・開発に取り組む技術者・研究者にご参加頂きますようご案内申し上げます。
|
| 記 |
|
|
|
1.日時:2011年1月20日(木)、21日(金) (2日間)
- 20日 講義; 10時00分より16時55分講義終了後 情報交換・交流会
- 21日 講義; 10時00分より16時30分まで
2.場所:(財)日本食品分析センター
- 新宿駅より小田急線:代々木八幡駅 下車 徒歩5分、あるいは
- 地下鉄千代田線: 代々木公園駅 下車 代々木上原寄り出口 徒歩5分)
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
TEL 03-3469-7131
|
| 第3回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム |
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/20
(木)
|
10:00~11:00
60分
|
第1部 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介-イントロダクション-
2. 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
-逆浸透濃縮・真空濃縮・凍結濃縮、浸透圧、分子・粒子の大きさ、物質の質量、超臨界流体抽出―
|
渡辺敦夫
|
|
11:00~11:10
|
休憩
|
|
11:10~12:10
60分
|
3. 膜技術の基礎―膜の構造と濾過、食品膜技術(文献紹介)
4. 濃度分極と膜濾過―真の阻止率・見かけの阻止率、物質移動係数
|
|
12:10~13:10
|
昼食
|
|
13:10~14:40
90分
|
5. 膜の種類とモジュール構造
―膜の作り方、膜の耐熱性・耐薬品性、スパイラル・中空糸・平膜・チューブラーモジュール、各膜モジュールの特性―
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
6. 膜装置の組み方と運転データの取り方―線速・圧力・温度の影響、limiting fluxとcritical
flux ―研究の進め方と報告書の書き方―
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~16:55
35分
|
Q&Aアワー
|
|
17:00~18:45
|
情報交換・交流会
|
|
|
|
1/21
(金)
|
10:00~12:00
120分
|
7. ファウリング層の基礎的性質
7.1. 透過流束の低下と分離性能の変化、fouling (pluggingとdeposition) とdegradation(劣化)、fouling層の性質とfouling防止用モジュール、限界安定透過流束、
―MRCニュース目次紹介―
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食
|
|
13:00~14:00
60分
|
7.2. 膜装置の洗浄の実際
7.3. 膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
8. 膜技術の応用の実際
8.1. 無菌化濾過による食品の製造
8.2. ナノ濾過技術による食品の改質と機能性食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
8.3. 飲料工業への膜利用
8.4. 醸造工業への膜利用
8.5. 水産工業への膜利用
8.6. 食品分野以外への膜利用
9. メンブレンバイオリアクター
―遊離生体触媒型と強制透過型膜リアクター、膜利用型排水処理設備
―食品産業における膜技術用語集―
|
|
16:00~16:10
|
質問事項記入
|
|
16:10~16:30
20分
|
Q&Aアワー
|
渡辺敦夫: MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ |
第2回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会
記
1.日時:2010年1月25日(月)26日(火) (2日間)
- 25日 講義; 10時00分より16時55分講義終了後 情報交換・交流会
- 26日 講義; 10時00分より16時30分まで
2.場所:(財)日本食品分析センター
- 新宿駅より小田急線:代々木八幡駅 下車 徒歩5分、あるいは
- 地下鉄千代田線: 代々木公園駅 下車 代々木上原寄り出口 徒歩5分)
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町52番1号
TEL 03-3469-7131
|
第2回 MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
|
|
日時
|
内容
|
講師
|
|
1/25
(月)
|
10:00~11:00
60分
|
第1部 膜技術および関連技術の総合学習
1. 講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2. 食品の加工技術と膜関連科学の基礎
-浸透圧・分子粒子サイズ等―
分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術
|
渡辺敦夫
|
|
11:00~11:10
|
休憩
|
|
11:10~12:10
60分
|
第2部 膜技術利用の基礎 Ⅰ
1. 膜技術の総論
(ア) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(イ) RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
|
|
12:10~13:10
|
昼食
|
|
13:10~14:40
90分
|
(ウ) 分離膜の製造法と膜材料の特性・評価
2. 膜技術の基礎的理論 ―濃度分極と膜内輸送―
―逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過―
|
|
14:40~15:00
|
休憩
|
|
15:00~16:10
70分
|
第3部 膜技術利用の基礎 Ⅱ
1. 高分子膜とセラミック膜の特性
2. 各種膜モジュールの特性
|
|
16:10~16:20
|
質問事項記入
|
|
16:20~16:55
35分
|
Q&Aアワー
|
|
17:00~18:45
|
情報交換・交流会
|
|
|
|
1/26
(火)
|
10:00~12:00
120分
|
3.
ファウリング層の特性と制御
4. 装置の組み立てと運転データーの取り方
5. 膜装置の日常管理とメンテナンス
(ア) 膜装置の日常管理と衛生管理
|
渡辺敦夫
|
|
12:00~13:00
|
昼食
|
|
13:00~14:00
60分
|
(イ) 膜装置の洗浄の実際
(ウ) 膜装置洗浄用の洗剤
|
田辺忠裕
|
|
14:00~15:00
60分
|
第4部 膜技術の応用の実際
1. 無菌化濾過による食品の製造
2. ナノ濾過技術による食品の製造
|
渡辺敦夫
|
|
15:00~15:15
|
休憩
|
|
15:15~16:00
45分
|
3.
飲料工業への膜利用
4. 醸造工業への膜利用
5. 水産工業への膜利用
6. 食品分野以外への膜利用
7. メンブレンバイオリアクター
|
|
16:00~16:10
|
質問事項記入
|
|
16:10~16:30
20分
|
Q&Aアワー
|
|
渡辺敦夫: MRC会長、日本膜学会名誉会員、(元)新潟大学教授、(元)農水省食総研・研究室長
|
|
田辺忠裕: MRC幹事、元エコラボ(株)、シラサギサニテーションラボ
|
Page Top




Page Top
MRC 第2回 初級者のための食品膜技術講習会 アンケート回答(15名) 概要
1.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
①ちょうど良い時間構成であった 13名
②丸2日間では長すぎる 1名
2.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
①たいへん役に立つと思う 8名
②ある程度役に立った 5名
③余り役立たない
どういう点で役に立つと思いますか
・膜の選定から条件の設定までデーターを確認しながら知ることができ、条件つめ方に非常にためになった。
・膜プラントの設計における周辺機器の選定について役立つ。
・実験を開始する際に何が必要か分かった。
・膜の選定のみならずシステム・モジュールの特性について知ることができた (3名)。
・ファウリングの理解が深まった。・プロセス設計や運転する際の知見が深まった。
・膜に関する用語や食品産業での洗浄のあり方等が分かった (2名)。
3.下記の講義内容の感想を記入してください。
①イントロダクション (役に立った(9名)、その他 面白かった(1名))、
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎 (役に立った(11名)、詳しく知りたい(2名)、わかり難かった(1名))、
③膜技術の基礎 (役に立った (11名)、わかり難かった点(1名)、詳しく知りたい(3名))、
④濃度分極と膜濾過法 (役に立った(8名)、詳しく知りたい(3名)、わかり難かった(4名))、
⑤膜の種類とモジュール構造 (役に立った(9名)、詳しく知りたい(5名)、わかり難かった(1名))、
⑥装置の組み方と運転データーの取り方 (役に立った(11名)、詳しく知りたい(1名)、わかり難かった(2名))、
⑦ファウリング層の基礎的性質 (役に立った(11名)、詳しく知りたい(2名)、わかり難かった(2名))、
⑧-1応用例 (役に立った(12名)、詳しく知りたい、わかり難かった(1名))、
⑧-2応用例 (役に立った(12名)、詳しく知りたい、わかり難かった(1名))、
⑨膜リアクター (役に立った(8名)、詳しく知りたい(2名)、わかり難かった(2名))、
⑩膜の洗浄 (役に立った(14名)、詳しく知りたい(1名))、
⑪昼食時のビデオ上映 (役に立った(8名)、役に立たなかった(2名)、ビデオを上映しないでユックリ食べさせて欲しい(2名))、
⑫その他希望する講義内容
・市販膜・膜メーカーの情報
・プロセス設計・運用面でのノウハウや体験談
・代表的な実用例で膜材質、運転条件、洗浄法など・
4.今回の講習会で特に役に立った講義はどの点ですか
・ファウリング層の基礎的性質 (7名)
・膜の洗浄と殺菌 (4名)
・濃度分極と膜濾過 (3名)
・装置の組み方と運転データーの取り方 (3名)
・膜の応用例・膜の種類とモジュール (3名)
・膜技術の基礎 (2名)
・食品の加工技術と膜関連科学の基礎
・システムの基本設計時の数値やコストなどが具体的に示されていた
5.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
・抽出 (3名)、精製、蒸留、晶析、分離 (2名)、固液分離、清澄化、選択的抽出、乳業での応用例、乾燥、クロマト、廃水処理、
6.食品加工技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか
・殺菌技術 (4名)・乾燥技術・洗浄技術・サニタリー技術・無菌操作
7.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
・応用例をもっと詳しく聞きたい・食品膜技術について体系的に講義を受けられ良かった。応用例が長過ぎる感じがした
・基本について多くの内容があり非常に勉強になった
・装置の組み方から膜モジュールの話まで聞くことができすぐに実験が始まられそうである
・交流会でさまざまな話ができ役立った
・膜設備のフローなどもう少し詳しく聞きたかった
・実際の設備や処理のビデオなどが見られると良い
・膜の種類、使用方法などが分かり良かった
・注意点等良く分かった・さらに本を購入して勉強したい・膜の初級者にとって分かり易い内容であった
・透過流束の回復が上手くいかない時などどのような現象が起こっているか把握できなかったが、ファウリングや洗浄の話などで理解できるようになった
・資料の図、細かい数字が見難い
・洗浄についてもっと聞きたい
・基礎は理解できたので応用を知りたい
・濃度分極の話は分かり易かった
・装置の組み方は参考になった
・プログラム通り講習会が行われ良かった
・一つ一つの内容を詳しく説明してもらえ良かった
Page Top
第1回『MRC・初級者のための食品膜技術講習会』
日時:2009年1月23日(金) (9時30分より17時;17時授業終了後 情報交換・交流会)
場所:川口市川口総合文化センター リリア( KAWAGUCHI LILIA )11階中会議室(京浜東北線 川口駅西口徒歩1分)
〒332-0015 川口市川口3-1-1 TEL:048-258-2000.
MRC・初級者のための食品膜技術講習会 開催趣旨;
食品膜・分離技術研究会(MRC)では、長年に渡り『MRC・食品膜技術講習会 in Tokyo』を開催してきましたが、一部の受講生からは、膜技術についてこれから学ぶ技術者のため膜技術の『いろは』から講義してくれる『初級者のための膜技術講習会』を開催して欲しいとの意見が寄せられていました。
本年初めて、実際に、講習会で講義してみると、既に膜技術についてかなり経験を積んでいる人と、ほとんど膜技術について知らない人が混在して受講している感を受けました。食品産業において膜技術を使いこなすためには、極めて広範な分野の科学技術を理解する必要がある点から、これから膜技術に携わる人を対象に、2009年1月23日に『MRC・初級者のための食品膜技術講習会』を開催することに致しました。2009年度の8月6・7日の2日間には既にある程度膜技術に携わってこられた方を対象に『MRC・中級上級者のための食品膜技術講習会』を開催することに致しております。
今回開催致します『MRC・初級者のための食品膜技術講習会』は、長年にわたり我が国の食品産業における膜技術の研究開発をリードし、また、新潟大学で多くの学生を育ててきた経験を踏まえ、渡辺MRC会長が中心となり全体的な講義をします。また、膜装置の洗浄と洗剤については田辺MRC代表幹事(エコラボ社勤務)が担当します。
テキストには、本講習会用に作成した膜技術の易しい解説書等を使用致します。
是非、多くの方々のご参加をお待ち致します。
MRC・初級者のための食品膜技術講習会 プログラム
| 日時 |
内容 |
講師 |
| 1月23日 |
9:30~10:30
60分
|
◎ 膜技術および関連技術の総合学習
1.講習会ガイダンスと受講者自己紹介
2.分離・濃縮技術(凍結濃縮・蒸発濃縮)としての膜技術 |
農学博士 渡辺敦夫
(MRC会長)
(新技術開発院・院長)
(日本膜学会名誉会員)
(元新潟大学大学院教授) |
| 10:30~10:40 |
休憩 |
| 10:40~12:00
80分
|
◎ 膜技術利用の基礎 Ⅰ
1.膜技術の総論
(ア) クロスフローろ過とデッドエンドろ過
(イ) RO,NF,UF,MF,EDの原理と特徴
(ウ) 分離膜の製造法と膜材料による特性
2.膜技術の基礎的理論―濃度分極と膜内透過-
―― 逆浸透・ナノ濾過・限外濾過・精密濾過 ― |
12:00~13:00
60分 |
昼食 |
13:00~14:15
75分 |
◎ 膜技術利用の基礎 Ⅱ
1.高分子膜とセラミック膜の特性
2.各種膜モジュールの特性
3.ファウリング層の特性と制御 |
14:15~14:25
10分 |
休憩 |
14:25~15:35
70分 |
◎ 膜技術の応用の実際
1. 無菌化濾過による食品の製造
2. 飲料工業への膜利用
3. 醸造工業への膜利用
4. 水産工業への膜利用
5. 食品分野以外への膜利用
6. メンブレンバイオリアクター |
| 15:35~15:40 |
休憩 |
15:40~16:40
60分 |
◎ 膜装置のメンテナンス
1. 膜装置の洗浄の実際
2.膜装置洗浄用の洗剤 |
田辺忠裕
(エコラボ(株))
(MRC代表幹事) |
16:40~16:55
15分 |
総合討論 |
|
17:10~18:40
90分 |
情報交換・交流会 |
|
Page Top
MRC第1回初級者のための食品膜技術講習会 アンケート
1.参加申込者数 16名 (欠席1名) 回答者数 13名
2.本講習会の全体的構成(講習会の長さ)をどのように感じましたか
①丸1日間では長すぎる1名 ②ちょうど良い時間構成であった6名 ③もっと講義を聞きたいので長くして欲しい6名(何日くらいを希望しますか?2日間が6名、
どの課題の講義を期待しますか?ファウリングの原因と対策、膜濾過法と濃縮、応用例 2名、膜のこれからの方向、)
3.本講習会に出席し今後の仕事に役に立つと思いましたか
① 役に立つと思う 13名 ②余り役立たない 0名 ③全く役立たないだろう 0名
①と答えた方 どういう点で役に立つと思いますか 実務経験はあるが基礎的知識を勉強していない、現在使用している膜モジュールの選定理由を社内で説明できる、基礎的知識が重要であることがわかった、将来的に役に立つと考える、抽出プラントなどの設計に生かして生きたい、膜モジュールの洗浄等に生かして行きたい、膜技術導入に向けた検討で役に立つ、エキスの濃縮工程に膜技術を応用するのに役立つ、ファウリングの問題解決に役立つ、膜の基本が理解でき洗浄方法の考え方の基礎になる、トラブルに直面したときの対応に役立つ、基礎を理解できたので今後の研究に役立つ
4.下記の講義内容で①役に立った、②さらに詳しく知りたい、③わかり難かった、に印をつけてください。④その他の意見の方は意見を記入ください。
①イントロダクション (役に立った10名、詳しく知りたい1名、もう少し短く1名)
②食品の加工技術と膜関連科学の基礎 (役に立った11名、詳しく知りたい2名、もう少し短く1名)
③膜技術の基礎 (役に立った9名、詳しく知りたい3名、)
④濃度分極と膜濾過法 (役に立った10名、詳しく知りたい1名、わかり難かった2名、)
⑤膜の種類とモジュール構造 (役に立った10名、詳しく知りたい3名、)
⑥装置の組み方と運転データーの取り方(役に立った10名、詳しく知りたい1名、わかり難かった1名
) ⑦ファウリング層の基礎的性質 (役に立った9名、詳しく知りたい3名、わかり難かった1名)
⑧応用例 (役に立った6名、詳しく知りたい3名、もう少し詳しく聞きたかった2名)
⑨膜装置のメンテナンス (役に立った9名、詳しく知りたい3名、)
その他希望する講義内容(例えば;プロセス設計を詳しく聞きたい)
分離と抽出技術、スケールアップ法、プロセス設計法、
5.今回の講習会で最も役に立った講義はどの点ですか(回答例;ファウリング層の基礎的性質)
膜技術の基礎、クロスフロー濾過の性質、膜技術の基礎***、ファウリング層の基礎的性質***、膜の種類とモジュール構造**、装置のメンテナンス、洗浄法、分離工程のファウリング防止法(限界安定体積透過流束)
6.食品の分離技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;乾燥技術)
分画、機能性成分の単離、乾燥、クロスフローによる濃縮技術、濃縮技術と廃水処理、膜装置のメンテナンス、濃縮乾燥技術、濃縮技術、無菌化濾過、ペプチド分離、殺菌等の技術、超臨界流体抽出、
7.食品加工技術で講習を受けたい分野はどの分野ですか (回答例;殺菌技術)
たんぱく質の変性、加工、膜選定の実務的ステップ、膜装置の利用、洗浄技術と応用、抽出後の濃縮・乾燥技術、脱塩・脱脂工程への応用、濃縮技術、
8.本講習会で改良すべき点、あるいは良かった点、印象に残った点等感想をお書き下さい
各内容をもっと詳しく教えてくれる時間があると良い、理解しやすい内容であった、短時間なのに内容が多すぎた、2日間にしてもっと時間がほしい、2日間にしてもっとゆっくり講義してほしい、関西でも行ってほしい、今まで濾過滅菌と言ってましたが無菌化濾過ということでスッキリしました、
Page Top